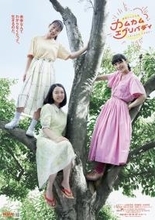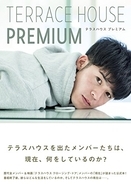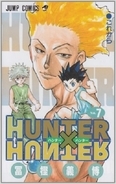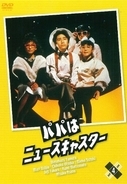私はしばらくのあいだ、鎌田のことを終戦直後に生まれた、いわゆる団塊の世代だと思いこんでいた。しかし彼のプロフィールを調べてみると1937年、それも当時日本の統治下にあった韓国・ソウル生まれとあるではないか。団塊の世代より10歳も上だ。ついでにいえば、早稲田大学卒の鎌田は、小渕恵三や森喜朗といった歴代首相と同窓生にあたる。
私が鎌田をもう少し若いと思っていたのには、やはり「金妻」や「男女7人」といった代表作のイメージによるところが大きい。「金妻」は団塊の世代の妻と夫たち、「男女7人」は放送当時30歳前後(1955年前後生まれ)の男女を描いた群像劇だ。
テレビドラマ史的にトレンディドラマの先駆けとも位置づけられる「金妻」や「男女7人」は、どこが画期的だったのか。それは何よりも、人間関係の描き方だったといえる。これについてエコノミストの吉崎達彦は「金妻」を例に、《ホームドラマにはありがちな社会のタテ関係を排し、登場人物がほとんどヨコ関係で描かれていたことが目新しかった》と書く。
《『金妻』には、口うるさい義理の親やら、借金を申し込んでくる兄弟といった厄介な人々は登場しない。地縁血縁といったしがらみを拒絶するのは、団塊世代が、彼らの生涯を通じて実践してきたことである》(吉崎達彦『1985年』)
こうしたヨコにつながった人間関係は、サークルやコンパのノリで男女が交際する「男女7人」でさらに徹底して描かれたといっていいだろう。鎌田は、こうした戦後世代のヨコ関係をうまく作品に取り込み、視聴率的にも成功を収めた。
鎌田の新作である「母の秘密」でも、主人公となるのは団塊の世代の父親とその息子だ。渡瀬恒彦演じる父・麻倉賢三は、かつての学生運動の活動家であり、運動の沈静化後には出版社を立ち上げ、反体制運動への支援を続けた。それだけに劇中には、内ゲバや三里塚闘争といった単語がセリフに出てきたり、羽田闘争や新宿騒乱など当時のニュース映像、あるいは70年安保の頃に歌声喫茶で学生たちによく歌われたロシア民謡「ともしび」など、学生運動華やかなりし時代を象徴するものが数多く登場する。エンドロールに流れるボブ・ディラン「風に吹かれて」も、まさにあの時代の若者たちの心をとらえた曲だ。
団塊の世代であれば、老親の介護の話が出てきてもおかしくないが、「母の秘密」のなかにはそうした話は一切出てこない。おそらく賢三もまた、血縁や地縁といったしがらみを捨てて都会に出てきたのだろう。出版社が倒産したあと家を売り払い、現在は四国で事業を起こしているが、それも昔の仲間と一緒にである。彼のなかにはどこまでもヨコの関係しかないのだ。
賢三の家には常に仲間が出入りし、日々会合を開いては議論を交わしてきた。彼らに対し、賢三の妻・幸恵(神野三鈴)は甲斐甲斐しく食事をつくるなど世話を続けた。子供のときから、そんなふうに父に家政婦のように仕える母親の姿を見てきた息子の慎介(中村勘九郎)は、いつしか父に強い反発を抱くようになる。
その母がやがて亡くなる。以来、父と子はわだかまりを抱えたまま、別々に暮らすようになった。それがあるとき、父の誘いで2人は秩父札所参りに出かけることになる。慎介は当初迷ったが、妻で現在ともに農業を営む加奈子(ともさかりえ)の後押しもあり、親子水入らずの旅に出たのだ。
旅先でも、慎介はどうして父が自分を誘ったのかまだ訝しんでいた。父がしきりにする昔話も、母や自分に対して手前勝手な見方をしているとしか思えない。そのさなか、慎介は妻の加奈子から電話で、母が入院中に「お父さんが自分のことをどう思っているのか、家庭をどう考えているのか何もわからない」と言っていたことを打ち明けられる。しかも加奈子はその言葉を、義父の賢三に伝えたというのだ。
その後、慎介はついに不満を爆発させ、父とぶつかる。文字通りの体当たりだ。
「あんたのしてきたことは一体何だったんだ。社会を変革してみんなを幸せにするなんて大きなことばかり言って、そばにいる人間だって幸せにしてないじゃないかっ」
「おれはおまえと母さんを幸せにするために闘ってきたんだよ!」
「母さんは父さんのことをどう思ってたんだよ!? 父さんは母さんのことをどう思ってたんだよ!?」。
ある寺社まで来たところで、父がようやく息子を誘った真意を明かす。じつは先に四国八十八カ所を巡礼しているときに、母の「自分のいたらなさを子供に伝える、弱みを見せる、それも親の役割よ」との声を聞いたというのだ。
その帰り、駅で別れる際に、慎介は父を抱きしめる。言葉はないが、彼は父のことを許したのだろう。父はそのまま何も言わず反対側のホームに移動し、列車に乗ろうとする直前、息子に向かって深々と頭を下げるのだった。
父がどういう想いで頭を下げたのかわからないとしつつも、慎介はこう心のなかでつぶやく。「あのとき、父と一つになれたような気がした。
「お父さんにはお父さんの生き方があったんだよ。お母さんにもお母さんの生き方があった。私たちにも私たちの生き方がある。それでいいんじゃない?」
父と母と自分とそれぞれの生き方を認めることによって、ようやく慎介は両親と一つになれたと思えたというのが何とも興味深い。父に自分の誤解を謝るのでも、逆に父を強引に謝らせるというのでもない。互いに認め合い、許し合うことで決着をつけるというのは、ひたすらにヨコの関係を志向してきた団塊世代の父親とその息子らしいともいえる。こうした父子の描き方はやはり、長いあいだ少し上の世代として戦後世代を描き続けてきた鎌田敏夫ならではだったと思う。
余談ながら、「母の秘密」の劇中で渡瀬恒彦が深々と頭を下げる姿に、ふと、映画「セーラー服と機関銃」においてヤクザの若頭に扮した渡瀬が、薬師丸ひろ子演じる女子高生との初対面時に頭を下げるシーンを思い出した。
(近藤正高)