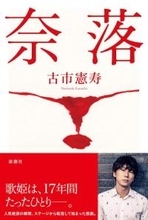この国民的映画には、不思議なことが一つある。
それはノベライズ作品の少なさ。少ないというか、存在をほとんど聞かない。
渥美清の評伝や寅さんの名言集など、関連本は検索するとたくさん見つかる。
ところが小説となると『男はつらいよ 寅さんDVDマガジン』に連載された、監督の山田洋次による「寅さんの少年時代 けっこう毛だらけ」がある程度。
この隙間産業に目を付けた作家がいる。
「楽器」で2011年に新潮新人賞を受賞して、デビューした滝口悠生だ。
1982年生まれ、1995年のシリーズ最終作となる「男はつらいよ 寅次郎紅の花」が公開された時でも、まだ中学生。
そんな若手作家の書いた中篇小説「愛と人生」は本の帯によると、〈山田洋次監督も共感した独創的な‘’寅さん小説‘’〉だという。
独創的な寅さん小説というのも謎だけど、「男はつらいよ」に馴染みのない世代も増えていく中で、今の読者と寅さんをつなぐ要素なんてあるかというのも謎である。
と思ったら、あるじゃないか。美保純だ。
寅さんの実家である団子屋「とらや」。
で、タコ社長の娘・あけみを演じていたのが、朝の連続テレビ小説「あまちゃん」や、バラエティ番組でのぶっちゃけキャラでもお馴染みの女優、美保純なのだ。
映画では脇役だった美保純が、この小説ではヒロイン役となる。
そして主人公はもちろん寅さん、とはならない。
主役となるのは、1987年上映のシリーズ第39作「男はつらいよ 寅次郎物語」に出演していた〈私〉。亡くなった父のテキ屋仲間だった寅さんと一緒に、母親を探す旅に出る少年・佐藤秀吉を演じていた。
舞台はそれから約30年後の世界。
〈私〉と美保純は「寅次郎物語」で一緒になって以来の再会を果たし、伊豆下田を旅していた。旅館に泊まる二人はそこで、「男はつらいよ」に自分たちが出演していた頃を振り返る。
が、おかしい。いろいろと、おかしい。
そもそも、〈私〉は何者なのか?子役の後に何をしていたのかもよくわからないし、なぜ美保純と再会することになったのかもよくわからないまま、物語は進む。
さらにおかしいのは、私も美保純も、映画の出演者なのか作中人物なのか曖昧なこと。
たとえば〈私〉は、出演者として「男はつらいよ」について語ることもあれば、佐藤秀吉として自らの生い立ちや、寅さんとの思い出を語ることもある。
一人の人間の中に、複数の人格と人生が存在する。そんな、科学でもスピリチュアルでも説明し難いことが起きているのだ。
そんな一風変わった設定だけど、テーマとなるのはタイトルにある「愛と人生」というド直球なもの。愛とは、人生とは何か?なんて青臭いことを主人公の〈私〉は自問し、その答えを「男はつらいよ」の中に求める。
〈そんな小難しく考えないといけないものかしら〉
何事も理屈っぽく考えがちな〈私〉に、美保純は言う。
〈あんたは要するに私のお尻のことを考えてるんでしょ。お尻の話をすればいいのよ〉
幼い頃一緒に入った銭湯の女風呂で見て、脳裏に焼き付き、〈私〉が今なお愛してやまない美保純のお尻。それがなんと、物語の重要な鍵を握っているのだから、確かに独創的なこの小説。
シリーズの歴史や配役の変遷、寅さんの名言・名場面、作品のマンネリと渥美清が抱えていたかもしれない屈託。
「男はつらいよ」のあらゆる要素を、愛と人生の意味に結びつけていきながら一つの作品を作り上げる、作者の作家としての腕力は見事なもの。
そして美保純のお尻が、〈私〉と読者を思いもかけない場所へと連れて行く終盤。どこに連れてこられたのか、気づいた瞬間の驚きたるや!この本を読まない人生なんて考えられないと思うに違いないのだから、こうご期待。
(藤井勉)