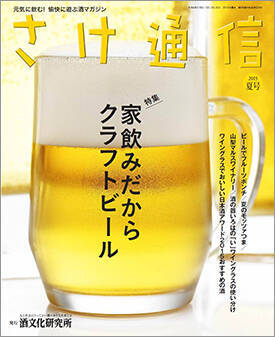
『さけ通信』については、以前ここエキレビ!でも紹介済みだが、簡単に説明しよう。
「酒文化研究所」が発行する、酒にまつわる情報やコラムが掲載された小冊子で、年4回発行、全国の約600店の酒専門店で入手できる。
クラフトビールは家飲みで
さて、最近よく見聞きする「クラフトビール」という言葉だが、本特集の説明を引けば、
飲みやすく万人受けする大手メーカーのビールではなく、「俺が飲みたいビールだけをつくる」という冒険的な小規模メーカーのビール(後略)
ということになる。Craft(手工芸品)という言葉を冠しているように、たくさんは作れないけれど、そのぶんこだわりの詰まった高品質のビール、というわけだ。
クラフトビールは専門店で飲むことができる他、最近では、品揃えのいい酒屋やちょっと気のきいたスーパーなどでも扱っている。日常的にガンガン飲むには少々値が張るが、そこは家飲みの強み、晩酌でなら居酒屋の生ビールくらいの値段で飲むことができる。週末のちょっとした贅沢としては許容だろう(と、自分に言い聞かせて時々買っている)。
本特集には、クラフトビールの選び方や、飲み方の指南の他、ごく簡単にではあるがその美味しさの元となる「モルト(麦芽)」「ホップ」についての解説もある。また、クラフトビールビギナーに向けて、アンカー・ブルーイング社(サンフランシスコ)の「リバティエール」4種を紹介。
やっぱり休肝日は必要?
また、私が毎号楽しみにしている連載が「はらだペコのためして MIX」だ。酒に何かをミックスして美味しい組み合わせを模索するこの実験コーナー、今回のテーマは、特集にちなんで「ビールでフルーツパンチ」である。要するに、ビールにいろいろなフルーツを入れてパンチにして飲む、という趣向だ。パイナップル、グレープフルーツに加えて、最後には生姜にもチャレンジ。さて、その結末はやいかに……。
そして最後に、毎号ちょっと憂鬱になりながらも気になって熟読してしまう、医学ジャーナリスト・松井宏夫の連載コラム「酒飲みの健康学」についても触れておかねばなるまい。「酒と健康」がテーマの本連載、今回のテーマは王道の「休肝日」である。酒飲みにとってはあまり愉快ではない言葉だが、30代も半ばを過ぎ、そろそろ病気の1つもするのではないかとビビっている私にとって避けては通れない話題である。
1975年に誕生した「休肝日」という言葉は、その後どんどん市民権を獲得し、すでに「休肝日は必要」と衆目の一致するところになって久しいが、じつはその必要性について科学的根拠は示されていなかったという。しかし、だ。
ここへきてアルコール性肝疾患を予防するためには、週に3〜5日の休肝日が効果的であることの科学的根拠が示されたのです。(デンマーク、コペンハーゲン大学病院の研究報告による)
やっぱり必要なんじゃないか! しかもけっこう多い。3〜5日ということは、週の半分以上である。真ん中を取って週4日休肝日を設けるとする。365日÷7日とすると、1年間はざっくり52週。4日×52週で計算すると、1年間で208日の休肝日が必要ということになる。年間150日も飲めない日があるということで、こうしてまとまった数字にしてみると、なんだかかなり大変そうだ。あまり直視したくない研究報告である……。
そんなわけで、飲みながら少々反省モードになってしまった。どうか皆さんも、健康に留意しつつ楽しく飲まれますよう。
(辻本力)






























