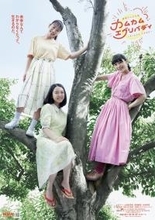といっても、原作から完全に外れたわけではなく、描かれたのはそれを補強するエピソードである。
もう1つは、菊比古と助六の関係である。鹿芝居の成功から芸に開眼し、人気も急上昇の菊比古と、逆に出る杭は打たれるとばかりに、生意気で上を上とも思わない態度が師匠方に疎まれるようになってきた助六、その2人の境遇の違いが明確にされた回でもある。2人が出世していけば真打昇進も夢ではなく、そうなれば前回も書いたとおり八代目有楽亭八雲の名跡を誰が継ぐかという問題も現実のものになってくる。2人が仲良く下宿で酒を酌み交わしていられる日々も、そう長くはないのだろう。
巡業甘いか酸っぱいか
今回の話の中で、菊比古が師匠の八雲から親子会で地方巡業に出ようと誘われる場面があった。東京・大阪・名古屋といった定席のある場所以外でも定期的に落語会が開かれる都市は少なくないが、六代目三遊亭圓生『寄席切絵図』を読むと、戦前には3都市以外にも定席のある町があったことがわかる。
──落語の途中で
「くださいな」
店の方から、女の客の声がした。
「はいはい、何ですかの」
お婆さんは大儀そうに立ち上ると、店の方へ行ってしまった。
お婆さん1人に聞かせていた落語である。そのお婆さんがいなくなっては落語を続けても仕方がない。(中略)私は店へ入って行って、突然、落語の続きをはじめた。
”ちょっと伺いますが、「ひらめ」ってえのはどういうわけで「ひらめ」って云うんです”
買物客はさぞ驚いたに違いない。
前出の『寄席切絵図』には、若き日の圓生が旅先で苦労した話がたくさん出てくる。寄席に食事を出前するのを雑用(ぞうよう)屋というが、そのおかずがまずくて湯豆腐ばかり食っていた話、旅先で金が無くなった落語家が訊ねてきて、圓生の義父である五代目圓生にすがりついてきた話など。
さて、八雲と同行した菊比古は、旅先でどんなことを見聞するのか。
今回の噺
断片的ではあるが、6つの噺が口演、もしくは言及された。
最初の寄席の場面で助六が演じているのが「火焔太鼓」である。荷物を背負った道具屋が侍と会話を交わすのは、市で買ったばかりの太鼓を殿様にご覧に入れるため、屋敷を訪れたからだ。「そんな汚い太鼓を持っていったら、お前さんなんかお咎めを受けて屋敷の松にふん縛られちまう」とおかみさんにさんざん脅かされ、目利きの腕がないことを馬鹿にされたことを思い出して道具屋、憤りがぶり返してきた、という場面なのだ。現在の「火焔太鼓」の形を作ったのは五代目古今亭志ん生で、現在も古今亭一門のお家芸である。助六はこの他、寄席で「らくだ」をかけた、と真打に叱られる場面がある。長い噺なので、おそらくは持ち時間からはみ出してしまったのだろう。こちらは口演はなく、演題だけなので内容は省略する。
そのあと、女郎が客に親のためと称して金を無心しようとする場面を菊比古が演じている。これは「文違い」である。間夫(情人)のため、客を騙して金を作ろうとする女郎を中心にした噺で、登場人物のほとんどが騙し騙されの関係にあるという入り組んだ内容だ。女郎を騙す間夫、その女郎に客が騙され、といった具合に嘘が重なっていくのである。いわゆる廓噺の中でも笑いが少ないネタのため、ふらりと寄席に行っても聴く機会はそれほど無いだろう。販売されている音源の中では十代目金原亭馬生(先代。故人)のものがお薦めである。
菊比古はその他にも「品川心中」、「五人廻し」と廓噺を演じており、得意にしている様子が窺える。助六からいろっぽい噺が向いていると言われ、その気になったか。「品川心中」については前々回に詳しく書いた。
「五人廻し」もまた、廓の慣習を描いた雰囲気のある噺である。吉原では、1人の花魁が1人の客につききりになるのではなく、複数を順番に巡って相手をする見世が当たり前だった。これを「廻し」というのである。目当ての花魁・黄瀬川がまったく廻ってこないので不機嫌になり、店の若い衆に金を返せと凄む客たちをオムニバス形式で描いた噺だ。吉原のことなら何でも知っていると豪語する男、通人ぶった薄気味悪い客、自称江戸っ子の田舎者、役人風を吹かせる無粋な男と、それぞれの演じ分けが楽しい。
もう一席、夜道を帰る菊比古が稽古しながら歩いていたのは、やはり廓噺の「紺屋高尾」だ。藍染職人と絶世の人気を誇る花魁との純愛噺で、成就する恋愛を描いたという意味では珍しい部類に入る落語だろう。もう1つ同型で「幾代餅」という噺があり、故・古今亭志ん朝の十八番だった。
さて、次回はおそらく原作に戻って話が進むことになるだろう。三角関係、そして八雲襲名問題の行方はいかに。
(おまけ)
私も新米落語プロデューサーというか、下足番として会を企画しています。よかったらこちらにも足をお運びください。

3/31(水)午後6時半(開演午後7時)笑福亭羽光単独ライブ#3〜私小説落語家族編