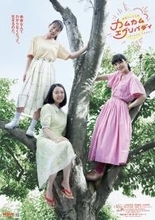王道の料理バトル
卒業達成率1割にも満たない名門料理学校「遠月茶寮料理学園」に転入した下町の定食屋「ゆきひら」の息子である幸平創真。そこで出会ったたくさんの仲間と共に退学を賭けたあらゆる試練に立ち向かっていく。
食戟のソーマと聞くと、試食後の過度なお色気リアクションを思い浮かべる人も多いだろう。美味し過ぎて可愛い女性キャラクターの服が破れたり、イカを食べてイカに身体中をまさぐられるなど、表現方法はまさに自由。しかし、今回は僕が思う食戟のソーマの魅力、キャラクターの豊富さについて考えていきたい。
改めて漫画のバランスって難しい
例えば普通のバトル漫画の場合、初期にメチャクチャ怪力なヤツを登場させると、後に同じタイプのキャラクターを出すのが難しくなる。もし、もっと怪力なヤツが現れてしまうと、初期のキャラが死んでしまう からだ。かといって力の差を明確にしなければ新キャラの凄さも伝わらない。これは野球漫画のメチャクチャ球が速いヤツや、メチャクチャ足が速いヤツにも当てはまる。
そこでよく利用されるのが特殊能力だ。ジョジョのスタンドや、HUNTER×HUNTERの念などがそう。その作品オリジナルのルールを作って、火を操ったり、怪我を回復させたりと、ファンタジー要素を足してキャラクターのパターンを増やしていく。
しかしこれにも難点はある。能力で出来る範囲のライン引きが難しいという所だ。
バカみたいなキャラクターがバカみたいに出てくる
しかし、食戟のソーマはこの問題点を全て、しかも簡単にクリアしている。なぜならば 料理はこの世に実在するし、 ジャンルも数え切れないほど存在するからだ。
肉料理が得意なヤツ、海鮮好きなヤツ、薬膳料理が得意なヤツ、イタリアから来たヤツ、ちゃんこ好きな相撲取り風なヤツ、最先端の調理器具を使うヤツ、とにかく鼻が利くヤツ、ジビエ飼ってるヤツ、何でも燻したがるヤツ、ただただ詳しいヤツ……と、バカみたいにバカみたいなキャラクターが登場するが、どのキャラクターも個性が強く一発で何が得意なのかがわかる。全てリアルに存在するものを誇張しているだけだから、矛盾も発生しづらい。
そして漫画には力関係問題というものがある。例えばバトル漫画で一対一の戦いに勝負がついたら、その二人の格付けは済まされてしまう。例え僅差だったとしても、負けた方は一生勝てないという雰囲気が出てしまう。
しかし、肉料理が得意なヤツが鼻が利くヤツにカレー対決であ負けても、カツ丼対決なら勝てるかもしれない。実力差が見えても勝つチャンスは残されている。つまり、キャラクターが死なないということだ。
漫画は先が読めるほど面白い
主人公の幸平創真は庶民派料理が得意だ。対するヒロインの薙切えりなは高級料理しか認めない。まぁ、展開が読める 。第二ヒロインの田所恵は優しさに溢れる料理を作る。これもえりなに影響を与えそうだ 。キャラクターの対比がしっかりしているから展開も作りやすい。展開が作りやすいということは予想がつきやすい。予想がつきやすいということは、 裏切った時の衝撃も大きい 。
食戟のソーマは本当にわかりやすいアニメだ。なので第2シリーズから観ても追いて行かれることはないだろう。初期に比べてお色気シーンが少なくなっているのは残念だが、それは本筋の面白さが認められてきている証拠。
(沢野奈津夫)