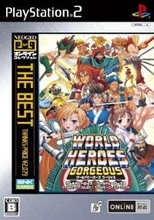現在も「Let’s天才てれびくん」として継続して放送中だが、初期の「天才てれびくん」の放送期間は、1993年4月から1999年4月という、90年代を駆け抜けた形になっている。
「てれび戦士」と呼ばれる子役タレントたちがさまざまなことに挑戦していくというのがメインだが、アニメ、音楽、ゲーム、クイズなど、多様なコンテンツによって構成されていた、充実の番組だった。
その中でも、番組開始当時、革新的だったアニメがある。それが、1993年度に放映された「恐竜惑星」というアニメ作品だ。
実験的だった「恐竜惑星」
これは、「天才てれびくん」の番組内で「バーチャル世界アニメシリーズ」と呼ばれた作品シリーズの第1作。当時のテレビ番組としては珍しく、実写とCGを併用したテレビアニメ作品であり、子どもたちを夢中にさせた。
トランシーバーを頭につけた「萌」というおさげの女の子と、どこかポケモンのようなかわいい恐竜の子どものキャラクター「レイ」という、90年代アニメらしい絵柄が印象的な作品だったが、その構成とストーリーなかなか革新的だったようだ。
ストーリーとしては、てれび戦士の山口美沙がバーチャルワールドに入って恐竜の世界へ行き、そこで「恐竜人類」たちの戦いに巻き込まれていくというもの。
ティラノサウルスの残酷な補食シーンも特徴的で、映画「ジュラシックパーク」をきっかけにした恐竜ブームや、男性視点からの恐竜観に対する一種のアンチテーゼを掲げたともいわれている。
近未来を感じさせた設定
また、主人公の山口美沙はバーチャル大陸内では「萌」というハンドルネームを用いる、という設定もあり、インターネット時代を予見するかのような近未来も感じさせる。
最新の科学考証を取り入れたハードSF的な設定は、SF研究家の金子隆一と本多成正が設定・原画に関わっていることによる。
そして構成も複雑で、当時の「天才テレビくん」の設定世界である「メディアタワー」と、超仮想現実空間のバーチャル大陸を行き来するというものだ(ちなみに、「天才てれびくん」の舞台となるこの「メディアタワー」というものも21世紀の時空間で、人間の言いなりになっていたテレビが反乱を起こすというシュールな世界観だ)。
「メディアタワー」の住人である「アッケラ缶」というCGキャラクターと、実写のてれび戦士の清野努が、アニメキャラクターの萌をナビゲートしていくというスタイルで、同一人物を実写・CGパートでは俳優(主に、てれび戦士など子役)、バーチャル世界のアニメパートでは声優が演じるというキャスト構成も斬新だった。
実写とアニメを巧みに組み合わせたスタイルは、他に類を見ない実験的なものだった。
その後、「バーチャル世界アニメシリーズ」の3部作は「ジーンダイバー」「救命戦士ナノセイバー」と続いたが、90年代後半からは「アリス探偵局」「アリスSOS」「スージーちゃんとマービー」など、純粋なアニメ作品が放送されていくことになる。いずれも未だにファンの多い名作ではあるが、90年代初期の「恐竜惑星」は1年という短い期間ながらさまざまな挑戦がなされた、最も伝説的な作品といえるだろう。
(空町餡子)
※イメージ画像はamazonより恐竜惑星 2 [DVD]