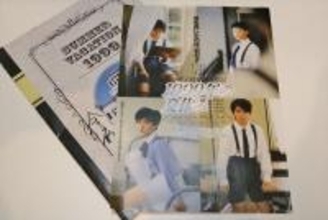東京・武蔵野美術大学内にある美術館で「モダンリビングへの夢―産業工芸試験所の活動から」展が開催中です。展示のタイトルにある産業工芸試験所(以下、産工試)は、ずいぶん固い名称をしていますが、それもそのはず。
展示されているのは、1950年代から60年代を中心に戦後復興期から高度経済成長期にかけて作られた輸出製品を主にした試作品と、その資料として収集された海外の参考品。試作品の中には、素材を独自に扱ったものや、今見ると変わった印象を受ける製品もあるとか。産工試がどのようなデザインを行ったのか、同美術館の敷田弘子さんに解説をお願いしました。

今の北欧雑貨ブームは偶然ではないのかも…?
――まずは産工試が行っていたデザインの研究について教えてください。
「産工試のデザイン研究は日本の伝統的な工芸技術をいかに現代的にアレンジしていくか、という視点でデザインを試みたジャパニーズ・モダンの先駆けでした。今の日本製品には『質がいい』という印象がありますが、昔は安くてかつ粗雑なものも少なくなく、工芸における日本のデザインのレベルも低かったのです。戦前からのそういった流れを変え、外貨を獲得するために、日本製品の質とデザイン性を上げる研究が行われていました」


――「参考品」というのは、どういう趣旨で集められたものなのですか?
「輸出製品を作るための商品分析用の資料です。後に世界的インテリアデザイナーとして知られる剣持勇が海外で買い集めたものも含まれます。戦後だった当時の主な輸出先はアメリカでした。これらの参考品をもとにアメリカの生活様式に適した大きさや形、なぜそのデザインが優れているのかを研究していました」
――主に買い集められたものはアメリカの製品ということですか?
「参考品に多いのは北欧製品です。アメリカでは北欧のものが価格も高く、人気があったのだそうです」
――近年でも、北欧雑貨や家具は人気がありますね。
「使う素材も似ていて趣向も近いため、人気があるのではないでしょうか。


――国の機関では、もうその頃から北欧製品に注目していたんですね。ちなみに、資料として集められた参考品は、今どのくらい価値のあるものなのでしょうか?
「残っているのは、今でもデザイン関係の本に掲載されているようなものばかりです。産工試では国内外のデザイン動向や流行を研究する部署があったので、購入する参考品を選別する彼らの見る目は確かだったのでしょう」
――名品が集まっているんですね。
海外の生活を知らずに作ったために、変わったデザインのものができてしまった時期も…

――試作品は、どのような目的で作られたんですか?
「輸出製品を製作するためのデザインの指標です。けれども参考品のデザインをそのまま取り入れたのではなく、新しい日本のデザインとして昇華しています。デザインについて見識の乏しい職人さんに、海外で喜ばれるかっこいいデザインを啓蒙します。例えばこの花器は富山県高岡市の高い鋳造技術とモダンなデザインを融合していて、かつ積み重ねて高さを変えることができます」
――アメリカで売られている製品のコピーではないということですね。
「アメリカで売られる製品をそのまま真似しても、日本はまったく太刀打ちできないことが分かっていたのではないでしょうか」
――研究が未熟な時期は、日本の輸出製品のデザインはどのようなものだったんですか?
「海外の生活様式を知らないまま、用途が分からないままに作るわけです。例えばサラダボウルを作るときに、日本人には具体的な使い方、使い勝手が分からない。その中で作ってしまうので、おかしな形や装飾がついているものができてしまったこともありました」
――研究によって、産工試が手掛けた製品はどのような変化を遂げたのですか?

「このザルを例にとると、太いテープ状の竹を格子で編んでいるものは、一般的な伝統工芸品には見られません。もともとある伝統的な編み方を研究し、その中からアメリカの生活で好まれるデザインに合う編み方を考え出しています」
――展示されているものは今見てもモダンですよね。ここにあるのは分析と試行を重ねた後の磨かれた結果なんですよね?
「そうですね。
イメージ戦略としてのデザイン
――どんな風に変わっているのですか?
「例えば『高級化』という研究がされていました。高級に見せる技術ですね」
――ストレートというか…すごい言葉ですね。

「日本の製品は海外ですごく安く買いたたかれましたし、不当に低い価格で継続的に販売するダンピングの疑いもかけられていました。あまりにも安い製品の一部は、一定の数を超えると関税を高くする、ということもアメリカはしていました。その対策としての『高級化』です。製品の単価を上げるために、価格に見あったデザインの工夫をしています。こちらのボウルはプラスチック製品ですが、重厚な雰囲気になるように厚い黒地の器に金箔の装飾をしています」
――漆器かと思いました。これプラスチックなんですか!
「当時プラスチックは新素材で未来的なイメージもあり、積極的に研究されていました」
――これがかっこよかったんですね。

「この半磁器は『日本の雰囲気を出すため白にした』と当時の記録にあります。日本をアピールするイメージ戦略としてのデザインになっています」
――なぜ白いかって、日本っぽいイメージにするためだったんですね。素材面から、日本的な演出が見られるものはありますか?

「この皿は、陶器の釉薬でできる模様『そば釉』をまねて作ったプラスチックのお皿です。ここでは2重成型という、プラスチック製品の成型の方法と、模様のつけ方にトライしています」
――とても真面目な取り組みで、だからこそ今見ると少しズレた感じがありますね…。
海外の生活様式を知るために行われた分析が真面目すぎる

「このティーセットは海外のものを集めて、容量を測ってサイズを研究したものを反映していて、カップは250ccとなっています。海外ではポットさえ変えれば兼用している風もある。
――容量を測るなんて、本当に真面目な取り組みですね…。ちなみに今でも使われているような製品って、どんなものがあるんですか?
「小林工業の『ラッキーウッド』というブランドのデラックスシリーズは今でも販売しています。一時期喫茶店行くと、どこでもこのカトラリーだったこともあると聞きました。グッドデザイン賞を受賞しています。
当時、日本では通常ナイフとフォークは使わない食生活をしていました。手に握ったときにどうしたら手になじむかなど、海外の生活様式と機能の分析をして作られました。今でも残っているというのは研究の成果ですよね」

涙ぐましい研究努力がすごい
――展示を見てきて思うのは、敗戦した後日本にアメリカ様式が入ってきて、その後すべてがアメリカ一色になったわけじゃないということです。日本文化を見直す動きとしてジャパニーズ・モダンは一助となったんですね。
「戦後すぐは日本もアメリカ色が濃くなってしまったけれど、そこで、はたと『日本のものはどういうものなのか』と立ち止まったんでしょう。戦後、日本が復興して自立するために、日本の伝統的な要素を残しつつ、海外の動向と切り結べる優れたデザインを模索たデザインだったと思います」
デザイン史の中でも産業工芸試験所の研究がクローズアップされることはこれまで少なく、あまり知られていない分野なのだとか。150点あまりが展示される展覧会も初の試みとなる。この時代ならではの製品の魅力と、産業工芸試験所という機関が行ったアツい研究への思いを感じてみてください。
(石水典子)
展覧会概要
「モダンリビングへの夢―産業工芸試験所の活動から」
会期:2017年5月22日(月)~8月13日(日)
休館日:日曜日、祝日
※6月11日(日)、7月17日(月・祝)、8月13日(日)は特別開館
開館時間:10:00~18:00(土曜日、特別開館日は17:00閉館)
会場:武蔵野美術大学美術館 展示室2
入館料:無料