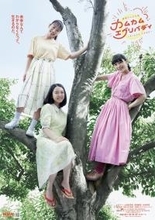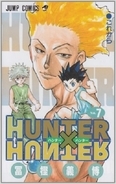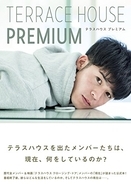地上波TBSでは、1969年8月より松下電器(現パナソニック)の提供による「ナショナル劇場」(のちの「パナソニック ドラマシアター」)の枠で、「水戸黄門」が放送され、2011年まで43シリーズを数えた。この間、黄門役は、東野英治郎を初代に、西村晃、佐野浅夫、石坂浩二、里見浩太朗と引き継がれ、今回抜擢された武田で6代目ということになる。
この記事では、テレビ登場以前より、長らく日本人に親しまれてきた「水戸黄門」の物語について、中国文学研究者の金文京による『水戸黄門「漫遊」考』(講談社学術文庫)という本を主に参照しつつ、史実との関係などからあらためて振り返ってみたい。
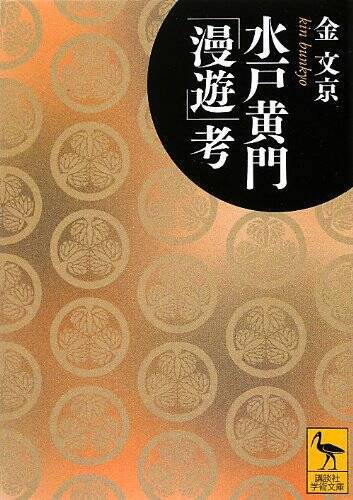
助さんと格さんにもモデルが
徳川光圀は実在の人物ながら、隠居した黄門様が助さんと格さんを従えつつ全国各地を巡り、悪者をこらしめるという「水戸黄門」のお話はフィクションだ。こうした基本的なストーリーは、明治以降、講談『水戸黄門漫遊記』によって世に浸透し、その後、浪曲や小説や映画で繰り返しとりあげられ、さらにテレビ化にいたった。
そもそも実在の光圀の行動範囲は、水戸藩領内、水戸と江戸のあいだ、そしてその祖母(徳川家康の側室・お勝の方)が創建した英勝寺があるためたびたび出かけた鎌倉にかぎられた。一方で、光圀は、ライフワークというべき『大日本史』の編纂にあたり、史料を集める目的で日本全国に使者を派遣した。このことがのちに、光圀自身が全国をまわったという伝説を生んだと考えられる。
助さんこと佐々木助三郎、格さんこと渥美格之進にもモデルがいた。『大日本史』編纂のため、江戸の水戸藩邸内に設けられた史館の総裁であった佐々介三郎(さっさすけさぶろう)と安積覚兵衛(あさかかくべえ)である。とくに佐々は、光圀に代わって、北は岩手、南は熊本まで、史料探索のために各地をまわる任を負った。
助さんと格さんが登場するのは、やはり講談の『黄門漫遊記』からだが、二人が出てくるのは『黄門漫遊記』のうち大阪で演じられていたものにかぎられる。東京で演じられる『黄門漫遊記』でお供するのはまったく別で、俳諧師の松雪庵元起なる人物だった。
東西でそれぞれ別の型の話が演じられた『黄門漫遊記』だが、大正以降は、大阪型が東京型を圧倒し、小説や映画でも、黄門のお供には助さん格さんが定番となった。そのなかで、テレビシリーズの水戸黄門が世をしのぶ仮の職業として名乗る「越後のちりめん問屋」は、東京型の数少ないなごりといえる。
東北と水戸黄門の深い関係
「水戸黄門」が地上波のTBSで放送を終えたのは2011年10月。奇しくもこの年3月には同じくTBSの武田鉄矢主演のドラマ「3年B組金八先生」がファイナルを迎えている。その武田が新たな水戸黄門となって最初に旅するのは東北地方である。いうまでもなく、「水戸黄門」と「金八先生」が一区切りをつけたまさに6年前、東日本大震災で大きな被害を受けた地域だ。武田は今回の出演に際し、《震災で被害をこうむった伝統芸能や工芸品、そして郷土料理などを積極的に取り上げることで、微力ながら復興のお手伝いになればと思っております》とのコメントを寄せている(BS-TBS「水戸黄門」公式サイト)。
じつは講談の「水戸黄門」でも、東北地方は重要な位置を占める。東京型・大阪型ともに、もっとも早い時期の速記本では、黄門が東北へと赴く様子が描かれていた。東京型では先述のとおり、黄門のお供として松雪庵元起が東北を旅するが、元起は蕉風の俳諧師という設定で、あきらかに松尾芭蕉の『奥の細道』を意識したものと考えられる。
明治20年代に大阪で発行された速記本のひとつ『水戸黄門巡遊記』では、黄門と助さん格さんが、現在の福島県楢葉町、相馬市、宮城県山元町、岩沼市など東北の太平洋岸を、さまざまなできごとに遭遇しながら旅する。いずれも先の震災で大きな被害を受けた土地である。
テレビが生んだお約束「水戸黄門の印籠」
前出の『水戸黄門「漫遊」考』では、中国や朝鮮半島にも、時の権力者から命を受けた者が、身分を隠して地方に赴き、悪をこらしめて弱者を救うという「水戸黄門」とよく似た物語があることが紹介されている。
しかもそれらの話では、主人公が身分と権威を証明する品を携帯しており、最後にそれを提示するという。たとえば、朝鮮半島に伝わる『春春伝(しゅんこうでん)』という物語では、馬牌というハンコとしても用いられる品が、主人公の身分を示す。ようするに「水戸黄門」の印籠と同じ役割だ。しかも印籠は、鎌倉・室町時代に中国より伝わった当時は、その名のとおり印判つまりハンコを入れるものだった。はたしてこれは偶然の一致なのか? 著者の金文京はこれについて検証するため、テレビの「水戸黄門」の脚本家にも取材しているのだが、返ってきたのは意外な答えであった。
詳細は本に譲るとして、じつは「水戸黄門」の印籠は、それまでの講談や映画などには出てこず、テレビドラマで初めて使われたものだという。それも初登場は、番組スタートの翌年、1970年1月放送の回で、毎回出てくるようになったのは、もうしばらくあとのようだ。いまでこそ印籠といえば水戸黄門のイメージが強いが、じつはそれはたかだかここ40年のあいだに定着したものにすぎないのだった。
ホームドラマとして企画された「水戸黄門」
1969年にTBSの「ナショナル劇場」で「水戸黄門」の企画が出たとき、局内では「何でいまさら水戸黄門なんだ?」という意見が大勢であったらしい。その前番組は「S・Hは恋のイニシャル」という青春コメディで、視聴者にも好評だったというから、それも無理はないだろう。だが、当時、スポンサー側の松下電器に在籍したプロデューサーの逸見稔は、ホームドラマからの発想で、水戸黄門をわがままだが人間的魅力に富んだおじいちゃん、助さん格さんはそれを支える孫として、まったく新しい作品をつくろうと思い、提案したという。
結果的に、そのもくろみは当たり、「水戸黄門」は40年以上続く長寿シリーズとなる。それが2011年にいったん終了したわけだが、6年を経て今回、BSとはいえ復活をはたした。印籠に象徴されるように“偉大なるマンネリ”ともいうべきこのドラマが、新たなキャストを得て、どんな展開を見せるのだろうか。
(近藤正高)