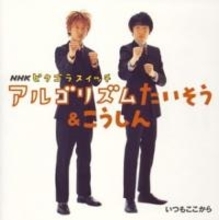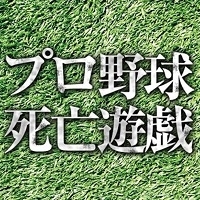春は桜とホームランが元気をくれる。
自分が10数年前に新卒で就職した春、当時ニューヨークメッツの松井稼頭央がデビュー戦初打席初球本塁打をかっ飛ばしたのを鮮明に覚えている。
……と無意味に頑張ってるアピールをしてみたが、この時期はよくフレッシュな新社会人が話題になるが、本当にヤバイのは社会人に慣れてきたノンフレッシュな春だと思う。新人の頃の高揚感も緊張感もない。またなんとなく新年度が始まってしまった。歳を取ったとも思わないが、もう若くはないのは確かだ。気が付けば、歳下の後輩も増えた。時にアドバイスや指導もしなきゃだけど、新卒の彼らとどう接していいのかいまいち分からない。だって、自分が20代前半の頃、昼飯でいきなり説教かます上司が死ぬほど苦手だったから。最近よく見る新社会人へのアドバイスツイートしてる人たちにも、できることなら死ぬまでかかわりたくない。
短気だった現役時代
昨年まで、大谷を指導していた日本ハム・吉井理人投手コーチも、現役時代に「コーチは目先の結果だけを見て好き勝手言って選手の邪魔をしている」と感じていたという。
日米通算121勝129敗62Sの成績を残した選手時代の吉井のイメージといえば、とにかく短気の変わり者。投手交代を告げられると、マウンドを降りる際にボールをボレーキックして2軍落ち。オフのプロ野球界の同学年の集まりも「球界にいる選手はみんな敵」と断固拒否。
そんな異常にキレやすい若者が、引退後は筑波大学大学院で人間総合科学研究科体育学専攻を学び、コーチ業8年間で4度のリーグ優勝といまやロジカルさと熱さを併せ持つ球界屈指の名指導者である。
選手との会話に気を遣い、自分で考えさせるコーチに
今回紹介する『吉井理人 コーチング論 教えないから若手が育つ』(徳間書店)はそのコーチング哲学が詰まった一冊だが、読んでみて「ここまで気を遣っているのか」と驚かされた。例えば、吉井は選手に威圧感を与えないように偉そうな腕組みはNG。話すときは、相手の真正面ではなく斜め前の位置を意識して、選手と同じ高さに降りるのではなく、ちょっと下の位置につくことを前提にする。もちろん投手陣からの愚痴や不満でもまずは耳を傾けて、否定することなく受け入れ話を聞く。ってそのまま週末の合コンの必勝テクニックとして使えそうなスタンスである。
試合中、追い詰められた投手にマウンド上へ声を掛けにいくときは、パニックになった投手の意識が自分自身に向かっている内向きの状態なので、なるべく意識を外に向けさせることを考える。あえて野球の話題ではなく、「お前、出身地どこやったっけ?」とか「出身校どこ?」なんて投げかけ、一瞬意識をずらす。そこで「○○県の意地の見せどころや!」と鼓舞するわけだ。
さらに捕手も若手のときはバッテリーで浮き足立ってしまう。すると、内野を守るベテラン陣に「どうしたらええ?」と投手コーチからアドバイスを求めるケースもあるという。

なぜ吉井はここまで選手の側に立った指導者になろうと思ったのか? それは自身のプロ1年目にいきなりコーチから投球フォームのことを指摘され、大混乱してしまい満足に投げられなくなった苦い過去があるからだ。投げるコツを思い出そうと十代の吉井がたどり着いたのは“自分で考えること”だった。
「人に言われたことだけやっていては、できたとしても一瞬だけで自分のものにはならない。自分で考えて、汗を流して、初めて血肉になる」実体験をもとに吉井コーチは指導する。例えば、グラウンド上のオフィス(練習中のセンターフェンス前)に投手陣たちを集め、前日の一場面について登板した投手を中心に「俺はこう思う」「自分ならこうする」と意見をぶつけ合う。例え物別れに終わっても、その繰り返しが思考を回す訓練になるという。
人からの指示を持つのではなく、自分で考えること。コーチにできるのはその手助けにすぎない。……と書くとど真ん中の実用書と思われがちだが、本書にはもちろん男・吉井が歴代監督たちとぶつかったここでは書けないエピソードの数々、日本ハムが昨年調子の悪かった理由、「投手としての完成度はまだ3割くらい」と話す名投手コーチが一番近くで見て感じた大谷翔平論、それに斎藤佑樹評まで、プロ野球の現場のリアルも豊富に収録されている。
スマダン世代には、一軍に定着していて実績もそこそこありプライドの高い選手は、そこから一流になるか、調子に乗って若手に悪影響を与えるか別れ道となるのが30歳手前くらい説も身にしみるはずだ。
ちなみに監督との口論は選手に見えないところでやるのが鉄則だという。
【プロ野球から学ぶ社会人に役立つ教え】
上司の説教は適当に流して、自分の進む道は自分で考えよう。
(死亡遊戯)