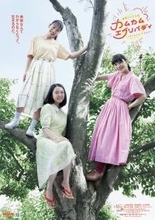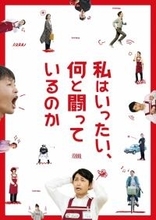放送前の記事につけた「國村隼とイッセー尾形激突」というタイトルどおり、このドラマはまさに俳優同士の激突と呼ぶにふさわしい内容だった。

気鋭のディレクターが手がけた演技派ぞろいの実録ドラマ
このドラマでイッセーが演じたのは、1995年に起こった警察庁長官狙撃事件の“真犯人”を名乗る老スナイパー・中村泰。それに対し國村は、中村を取り調べ、その周辺を洗い出すため奔走する警視庁の刑事部捜査第一課の刑事・原雄一を演じた。
中村は最初の取り調べから、自分は革命家だと言い張り、また長官狙撃事件の関与について肯定も否定もしないと発言。さらには「原さん、残念ながらあなたの経歴に未解決事件がまた加わりそうですね」と、なぜか過去に原の担当した未解決事件のことも知っていて、牽制をかけるようなことを言う。その後の取り調べでも、中村は思わせぶりな供述で、原を翻弄し続ける。両者のやりとりは、これをそのまま舞台化して生で観てみたいと思わせるほど、緊迫感に満ちていた。
國村とイッセーだけでなく、原刑事の上司にあたる刑事一課長役の中村育二や管理官役の遠山俊也、警視庁と合同捜査にあたった愛知県警の刑事役の酒向芳、中村泰の弟役の石丸謙二郎、そしてラスボス的役割を担った警視総監役の小日向文世と、脇を固めるのも演技派ぞろい。さらに、原刑事のもとで捜査にあたる警視庁刑事部の刑事を渋谷兼人、あとになって公安部から捜査チームに加わった刑事の一人を毎熊克哉と、それぞれ気鋭の俳優が演じた。とくに語り手も務めた毎熊は、当初は中村の取り調べに懐疑的だった若手刑事が(そもそも彼の所属する公安部は長官狙撃事件をオウム真理教の犯行として終始、捜査を進めていた)、綿密な捜査で真実を追求する原の姿勢に感銘を受け、しだいに積極的に捜査にかかわっていくさまを好演していた。
このドラマは、現実の事件をもとにした実録物ではあるが、時に大胆に脚色や演出を加えたところもあり、単なる再現ドラマの域を超え、見ごたえ十分であった。なお、脚本・演出を手がけた黒崎博は、これまでに芸術祭受賞作「火の魚」「セカンドバージン」や連続テレビ小説「ひよっこ」などのドラマを手がけた、いま注目されるディレクターのひとりだ。
イッセー尾形を容疑者役に起用した意義
今回のドラマが放送されるにあたり、私が一番気になっていたのは、中村による長官狙撃当日の供述をいかに映像化するのかということだった。制作側もまさにここを大きな山場として、変化球で挑んできた。
場面は取り調べ室から一転、中村役のイッセーがいきなりスタジオでテレビカメラを前に、犯行当日の行動について語りながら再現し始める。やがて場面は、屋外ロケで撮影した映像に切り替わり、彼が犯行におよび逃亡するまでの経緯が、ときおりスタジオ収録の映像を挿入しながら描かれた。
狙撃事件に関する中村の供述にはたしかに真に迫るものがある反面、どうもつくったかのようなところもある。それをこのドラマでは、リアリティのあるロケパートと、中村の妄想を描いたかのような非現実的なスタジオパートと、二つの映像を並べることで表現し、彼がシロかクロか判断は視聴者に委ねたといえる。
それと同時に、この場面からは、なぜ容疑者役にイッセー尾形を起用したかがはっきりとわかった。スタジオのパートではセットは何もなく、イッセーが自転車や傘などの小道具を用いながら、たった一人で演技する。これは彼の本領である一人芝居そのものではないか。ここにこそ今回、イッセーを起用した意義が集約されていたといえる。
中村が犯行当日のことを自供し終えたあと、原は調書を小日向文世扮する警視総監に提出する。しかし公安出身の総監はそれを一読して「ドラマみたいだな」「できすぎてると思わんか」と切り捨てる。中村の供述がまるで信じられない総監は、こんなやつとかかわっている暇があるなら、ほかの未解決事件の捜査をやったほうがいいのではないかとまで言う。それにもかかわらず、原が「では捜査は中止したほうがいいですね」と返すと、「捜査は続けろ」と命令する。
小日向文世の警視総監の貼りついた笑顔が不気味
原はなおも、中村に協力した人物を探し出しては、聞き込みを続ける。中村がアメリカから銃器を密輸するにあたり、協力したと思われるメキシコ系移民の母娘に話を聞くためロサンゼルスにも飛んだ。しかしそこであきらかになったのは、中村がその母娘とじつの家族のように心を通わせていたという意外な事実であった。母娘は、原から中村は狙撃事件の容疑者だと聞かされても、けっして信じようとしない。
中村の共犯者のうち最後まで謎のまま残ったのが、狙撃事件当日の共犯者「ハヤシ」(仮名)だ。この正体さえつかめば、オウム一辺倒で捜査を進める公安部も中村逮捕へと動くはずだった。しかし、あれだけ饒舌な中村もこれだけは頑なに口を割らない。原はそこにかえってハヤシこそ、中村の秘密を握る存在だと見抜く。
だが、時効は刻一刻と近づく。いよいよ手詰まりとなった原に、中村は取り調べで一つの取り引きを持ちかける。それは、自分がオウム真理教と関係があったことにすれば、原は自分を逮捕できるし、公安もメンツが保てるだろうというものだった。
時効を半年後に控え、中村の取り調べが始まって以来6人目の捜査一課長から、原は捜査打ち切りを命じられる。それでも彼はぎりぎりまで捜査を続けるつもりであった。このとき彼はたまたまエレベーターで警視総監と乗り合わせ、念を押されるように「彼(中村)はオウムから指示を受けた事実はないんだろうね」と訊かれる。原が一瞬言葉につまりながらも「ありません」と答えると、総監は「そうか。ならいいんだ」と笑みを浮かべる。その貼りついたような笑顔は、これ以上深追いするなと原に圧力をかけるようでもあり、また、中村から取り引きを持ちかけられたことをまるで見抜いていたかのようにも感じられ、言い知れぬ不気味さを感じた。
このあと、2010年3月、事件は時効を迎え、ついに中村逮捕にはいたらないまま、捜査本部は解散となる。
容疑者Nの供述に真実はあったのか?
ドラマを観ていて私はふと、いまは亡き劇作家・演出家のつかこうへいの代表作『熱海殺人事件』を思い出した。同作では、幼なじみの女子工員を殺してしまったみすぼらしい男を、刑事たちが取り調べを通して自分の理想どおりに事件を書き換えながら、“立派な”殺人犯へと仕立て上げる。
それに対し、このドラマというか事件はまるで逆だ。原たち刑事は、「革命家」を自称し、狙撃事件にもさも大義があったかのように語る自己顕示欲の強い男から、虚飾を剥ぎ取り、単に官憲への私的な恨みから犯行におよんだ者へと引きずりおろすことに全力を挙げる。彼らはそのために思い込みは一切捨て、愚直なまでに地道な捜査を続けながら真実を追求するのだが、結局その努力は報われずに終わった。
原たちのとったやり方は、事件捜査のあるべき姿であることは間違いない。しかし、そのために彼らは、長官狙撃事件はオウムの犯行であるとの前提で捜査を主導する公安部からは圧力をかけられ、そして、犯行を供述しながらも、肝心なことは隠し通した容疑者に対し敗北を喫した。物語を打ち崩し、真実をつかむとはかくも難しいことかと思わせる。
時効成立後、原と面会した中村は、先の取り調べでの「9つの真実に一つの嘘が混じって何がおかしい」という自分の発言を持ち出し、「あれは逆でしたね。この世の中に9つも本当のことなんてありゃしない。9つの嘘に混じって一つの真実があれば十分ですよ」「原さん、あんた、みすみすその一つの真実を逃したんですよ」とぬけぬけと言う。これに原は「あるんですか? あなたに一つの真実が」と言い返すのだが、中村は笑ってごまかすと、そのまま退席するのだった。
「9つの嘘に混じって一つの真実があれば十分」という中村のセリフは、取材をもとにしたものなのか、それともまったくの創作なのかはわからない。だが、これはつくり手から視聴者への問いかけでもあるのだろう。
(近藤正高)