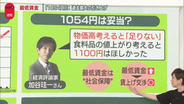2019年2月19日に、20世紀のプロレス界を支えたジャイアント馬場の没後20年を記念した追善興行が東京・両国国技館で開催されるという。
馬場が社長を務めていた全日本プロレスを始め、主要団体のほとんどが参加予定とあって、平成最後のプロレスオールスター興行となりそうだ。
当日の目玉企画の一つが「ブッチャー引退セレモニー」。
御年77歳! “黒い呪術師”アブドーラ・ザ・ブッチャー! プロレスを知らない方にもその名前は轟いているのではないか。
そのブッチャーの長いプロレス人生において、ひときわ異才を放った試合がある。
それは、現・RIZIN統括本部長、高田延彦との異次元対決!
ケレン味たっぷりの悪役レスラーのブッチャーと、格闘技寄りのファイトスタイルの高田。まさに真逆の生き様のぶつかり合いだ。
そして、この対決があったからこそ、格闘技ブームが始まったと言ったら、あなたは信じるだろうか?
「リアル・ファイト」への渇望こそがプロレスラー高田の原点
当時、高田がエース兼社長を務めていたUWFインターナショナル(Uインター)は、プロレスの原点回帰をテーマに打ち出した格闘技志向の強い団体だった。
90年代初頭、高田は「最強」を掲げ、ボクシング世界ヘビー級元王者のトレバー・バービックや元横綱の北尾光司を倒すなど、「平成の格闘王」にふさわしいスター街道を爆進していた。
高田の転機となったのはバービック戦。高田にとって初の「リアル・ファイト」となった世紀の一戦である。
本当の強さを求めて新日本プロレスに入門、さらにUWFを経て、自身の団体で実現したこの試合。高田は「この日のためにプロレスラーをやってきた」と実感したという。それだけ、リアル・ファイトに対する思いは強かったのだ。
この試合での高揚感や緊張感が忘れられない高田は、いつか再びリアル・ファイトが実現するはずと信じて、身を粉にしてプロレスを続け、団体運営に奔走していく。
引退宣言、参院選落選、新日本プロレスに完敗…迫り来る崩壊の足音
しかし、ビッグマッチ以外の集客に難があり、スポンサーがなく、テレビ局も付いていないUインターは徐々に消耗していくことに。
自身の団体を守るため、ファイターとしてよりも社長業を優先しなければならない高田のモチベーションが下がるのは明らかだった。
不協和音を奏でる社内の人間関係に嫌気が差し、突然の引退宣言。さらに、存在意義を見失い、周囲に言われるがままに参院選に出馬と、高田の迷走が始まる。
しかも、トヨタのトラックのCMが内定したなかでの出馬だったため、莫大な違約金を払うことに。そして、選挙は落選……。
高田は身も心も疲れ果て、Uインターの存続も危ぶまれる状況にあった。
そんななか、活路を求めたのが新日本プロレスとの対抗戦だ。
一連の対抗戦は、興行成績も話題性も記録ずくめで大成功だったのだが、結果として「おいしいところ」を持っていったのは新日本。初戦の対武藤敬司戦での高田の敗戦を含め、Uインターは、新日本の歴史と交渉力の前に事実上の完敗だったのである。
強さを求める団体のアイデンティティーは崩壊し、離脱する選手も相次ぐことに。
そこで、崩壊寸前の団体を守るために、なりふり構っている場合ではない高田が選んだのが、ブッチャーとの一戦だったのである。
自身の団体を守るため、禁断のブッチャー戦に臨んだ高田延彦
1996年10月、数あるインディー団体のひとつ、東京プロレスで行われた高田vsブッチャーの一戦。
当時の週刊プロレスには「夢か現(うつつ)か幻か…“究極の異次元対決”」のキャッチコピーが踊ったが、まさにそのとおり。
高田の格闘技寄りのファイトスタイルとはまったく対極にいるコテコテの悪役レスラー、しかも、すでに55歳(!)が相手なのだから、生粋のプロレスファンも仰天のカードだ。
この東京プロレスには、オーナーがバイク便の会社を中心にマルチに事業展開しているとあって、潤沢な資金力があった。
当然、ファイトマネーがよく、さらにUインターの社長にもなってもらい、資金援助もしてもらうという話もあったという。
もっとも、この東京プロレスは多角経営が裏目に出て、最終的には23億円もの借金を抱えたオーナーの失踪により崩壊してしまうのだが……。
ともかく、普段とは違うプロレス団体で試合をすることでUインターのプロモーションになるというメリットもあった。
自身の団体を守るため、高田には断る選択肢はなかったのである。
高田延彦vsアブドーラ・ザ・ブッチャーの試合ダイジェスト
いつものガウンではなく、フード付きのラフなジャンパーで入場した高田。
終始伏し目がちな表情からも乗り気でないのが伝わってくる。
対するブッチャーは、ギラギラと目を輝かしてやる気満々の臨戦態勢。
数多くの名勝負を残してきた名優も寄る年波には勝てず、主戦場だった全日本プロレスの晩年は前座でお茶を濁す程度の扱いだった。
しかし、この試合では看板外国人レスラーとして、往時の勢いの歓迎ムード。観客の大声援を受け、メインイベンターとしての貫禄がよみがえってきた感じだ。
試合開始からしばらくは、間合いを計りながら組み合ってはロープブレイクを繰り返す両雄。
コーナーに押し込んだ高田の喉元に会心の一撃を見舞う。
これを合図に5分近く責め立てるブッチャー。アームブリーカーやドラゴン・スリーパーを受ける高田は依然精彩を欠いたままだ。
ブッチャーは必殺のジャンピング・エルボーをブチ込むが、高田はカウント2でキックアウト。さらに、隠し持っていたフォークを掲げてアピールし、再度エルボーを狙うも、高田に避けられて自爆。そして、これにてブッチャー劇場は閉幕。
ブッチャーに対してゲストとしての最低限の礼を尽くした高田。得意のキックを連発し、最終的には右ミドル4連発からあっけなくカウント3を奪取。
表情を変えることなく淡々と勝ち名乗りを受けると、足早にリングを去ってしまった。
ブッチャー戦の屈辱がヒクソン・グレイシーと闘うきっかけ!?
プロレスの強さを証明するために闘ってきた高田を応援してきたファンにとって、この試合は踏み絵だったかも知れない。
ポリシーを捨てた高田に見切りをつける声も多く、結局、この試合から3カ月を待たずしてUインターは崩壊してしまった。
しかし、この異次元対決こそが後の総合格闘技イベント「PRIDE」へとつながるきっかけだという。
プロ書評家&インタビュアーの吉田豪氏は、自著『聞き出す力』において、金子達仁氏が書き下ろした高田の自伝的ノンフィクション『泣き虫』を引き合いに出して、「Uインターが経営危機になり、やむなくブッチャーと試合をしたがすごい屈辱で、こんなことやってられないってことでヒクソンと闘う決意をした」と語っている。
筆者が『泣き虫』を読む限り、ここまで具体的な記述は見つからなかったが、高田が別のインタビューでこの一戦を「刹那的な気持ち」だったと振り返っているのは事実。
当時の高田は、エンターテインメント性の高いプロレスを批判することが多く、この一戦が自身のポリシーに背くものだったことは想像に難くない。
迷走する高田を支えていたのが、前述のようにリアル・ファイトの実現だ。特に、本物の強さを感じるヒクソン・グレイシーの存在がその思いに拍車をかけたのも事実である。
実際、Uインターでは鈴木健取締役がリング上からヒクソンへの対戦を呼びかけ、No.2の安生洋二がヒクソンの道場に交渉を兼ねた殴り込みをかけている。
しかし、いずれも失敗し、Uインターでの対戦は幻となった経緯があった。
会社のためにブッチャー戦をやらざるを得なかった高田は当時、引退を覚悟しており、プロレスという職業に対しても失望していたようだ。
そんな高田が「プロレスを嫌いなまま辞めたくない」「胸を張って引退したい」、そんな思いから最後のケジメとして選択したのが“究極のリアル・ファイト”伝説のヒクソン・グレイシー戦なのである。
この闘いからPRIDEの歴史は始まり、総合格闘技の大ブームに繋がっていくのはご存知のとおりだ。
高田の過去のインタビューを掘り起こすと、プロレスと格闘技の間を常にさまよい続けていた苦悩と葛藤が痛いほど伝わってくる。
対してブッチャーは、一貫して悪役レスラーをまっとうしているのがよくわかる。
プロレスラーの生き様に、正解などないのかもしれない。
だから、プロレスはおもしろいのである。
(バーグマン田形)