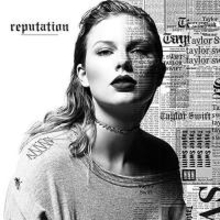国税庁が「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を改訂し、その内容が「複雑過ぎる」「分かりにくい」「めんどくさい」「あほくさい」として大きな話題になっており、テレビのワイドナショーでも「あれは?これは?」と格好のネタになってしまっているようです。
飲食店に関しては店内で飲食した場合には軽減税率は適用されず、テイクアウトした場合には軽減税率が適用されるわけですが、私たちの生活実態は両者を単純に二分できないシチュエーションも少なからず存在します。
たとえば、役務の提供のタイミングと金銭の支払いのタイミングが異なる場合です。国税庁によると、コーヒーの回数券を利用する際には、店内利用の場合に限って差額を支払うか、もしくは回数券販売時点で予めテイクアウト用と店内用の2種類を用意しておくという対応が求められるとしており、お店の側には無駄な行程が発生し、顧客にも回数券利用時には選べないという不便が発生します。
まともに税金払う人が馬鹿を見る仕組みだ
また、イートインの線引きも非常に複雑です。イートインスペースがある場合は顧客に利用するか否かの意思表示を聞く必要があるとのことです。確認する手間が発生するのは当然のこと、本当は店内で食べるつもりでも「テイクアウトします」と虚偽の申告をする人が続出する可能性は十分あります。飲食をしているお客のうち、正確に申告した人と虚偽の申告をした人を見分けるのは至難の業です。
確かに「店内で食べます」と申告した客に対してのみ卓上に置く立札等を渡せば、見分けることは理論上可能です。ですが、立札を持っていないのに飲食をしている客に対して注意するにも人件費が発生するにもかかわらず、回収した20円は一切お店の利益にならないわけですから、お店の側に積極的に注意しようというモチベーションは湧きません。
また、お弁当と飲料を購入したとして、「お弁当はテイクアウトしますが、飲料のみ店内で飲みます」と申告し、立札だけもらって、お弁当も一緒に全部店内で食べてしまうということもできるわけです。これを監視するのはほぼ無理でしょうから、結局のところ立札によるオペレーションも非現実的です。
いくらでも抜け穴があるわけですから、店内で食事をする分にのみ正確に10%の税を徴収するというのはほぼ無理と言えるでしょう。このような抜け穴だらけの税制では、まともに払うほうが馬鹿らしくなってしまいます。ただでさえ日本国民の納税意欲は他国よりも低い傾向にありますが、このような抜け穴だらけの税制を設ければ、ますますそれを低下させる事態になりかねません。
また拙い税制に合わせたくだらない競争が始まる
そして、わずかな価格差を競い合う外食産業は、何とか軽減税率が適用されるよう、様々な仕組みや方法を考えることに没頭し始めることでしょう。
たとえば、パチンコ業界が「三店方式(パチンコ店・景品交換所・景品問屋の3つの業者が名目上分かれていることで、パチンコ玉の現金化という賭博としか思えない行為が違法性に問われない構造)」を採用しているように、今後飲食の提供をする業者と食事スペースを提供する業者と両者を繋ぐ業者に分かれることも考えられます。いかに税制にフィットする仕組みを整えるかという競争軸が新たに加わるわけです。
ですが、本来であれば、そのような競争は必要ありません。アンハイザー・ブッシュ・インベブや中国勢等のビールメーカーが世界市場でしのぎを削る中、日本のビールメーカーは歪んだ税制の抜け穴を探すために「第三のビール」の開発に没頭してしまい、グローバル化が出遅れたことを思い出します。飲食店そのものの優劣という本来の競争の軸とは違う軸に「企業努力」を費やすように仕向ける税制は、明らかなミスリードです。
拙い軽減税率は貧困推進策だ
そもそも、食品に対する軽減税率は、貧困層に対する支援策として導入することが決定したもののはずなのに、線引きを「外食か否か」に設定したことで、逆に貧困層に対して不利な状況を生むケースも多いのではないでしょうか?
たとえば、夫・妻・子のいる世帯と単身世帯とでは、貧困層に多いのは明らかに単身世帯です。高齢者に限ると、単身世帯の相対的貧困率は2人以上の世帯の約2倍にもなります。ですが、単身世帯で自炊をしようとすると、食材が余ってしまうためにかえって食費が高くなってしまう場合も多く、外食で済ませる人は少なくありません。
また、夫が正社員で妻が主婦という家庭よりも、共働き家庭のほうが外食する率は高いと思われますので、「共働きは不利」「妻が主婦をしたほうが食費は安上がり」という状況を新たに作り出しています。女性の経済的自立や政府が進める女性活躍とは真逆の方向に力を加えるものです。所得税における配偶者控除等が作り出している「150万円の壁」と同様、国が経済的に豊かになるはずの共働きを阻害してしまう愚策だと言えます。
さらに、一人親家庭は圧倒的に人手が足りないわけですから、食器の後片付け等をしないで済み、重い食材の持ち帰る手間も無いイートインで食事を済ませることは、大変恩恵があります。食材を持ち帰る体力の少ない高齢者がイートインを頻繁に利用しているケースも少なくありません。
軽減税率はどうあるべきか?
結局のところ、政治的意思決定をした人々が国民生活の実態をよく把握しておらず、「夫と妻2人ともいるけれどちょっと貧しい家庭」「日常の食事は自炊で済ませて外食は非日常を味わうところ」という昔ながらの生活イメージが強いために、このような稚拙な税制ができてしまったのではないでしょうか?
軽減税率自体は私も賛成(むしろ5%に下げても良いと思う)ですが、外食には適用しないという線引き方法はやめるべきだと思います。外食にも原則的に軽減税率を適用しつつ、法人税における交際費等の損金不算入の条件と同様に、「1人当たり 5,000 円超の飲食費」に限定して、軽減税率の適用を除外する方法が良いのではないでしょうか。
もちろんこの方法にも様々な問題が生じると思いますが、少なくとも「貧困層に対する支援策」という本来の目的を達成するには、現行の方法よりも十分効果があるのではないでしょうか。
(勝部元気)