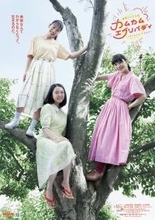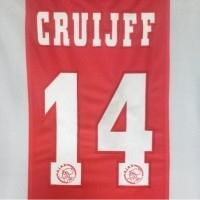2018年1月の放送スタート以降、子供たちだけでなく、大人のアニメファンからも高い支持を集めてきた人気作もいよいよクライマックス!
来週3月30日(土)に放送される第64話で、「キトラルザス決戦編」が終了。

そこでエキレビ!では、アニメの制作現場を牽引してきた池添隆博監督にインタビュー。アニメ化プロジェクトスタート時から、クライマックスまでの制作秘話を、前後編の2部構成で語ってもらった。
緑や赤や青の新幹線があることも知りませんでした
──『新幹線変形ロボ シンカリオン』というプロジェクトは、テレビアニメの放送が始まる以前から、玩具やWEB動画という形で展開されていました。池添監督がテレビアニメの監督としてのオファーを受けた時、『シンカリオン』という題材に対して、特に魅力的だと感じた点を教えてください。
池添 まずは、新幹線がリアルなロボットになるというところですね。昔、小さなロボットになる『ヒカリアン』(『超特急ヒカリアン』『電光超特急ヒカリアン』)という作品はあったのですが、リアルなサイズ感でロボットになるのは、たぶん初めてだったはず。人間と本物の新幹線の大きさの対比も、そのままリアルに描けるところが良いなと思いました。
──監督として関わる以前、新幹線や電車に関する知識や興味は、どのくらいあったのでしょうか?
池添 ほぼゼロでしたね。電車は混むイメージもあったから、移動も車ばかりで、まったく興味が無かったです(笑)。新幹線も小学生の頃に乗って以来、まったく乗ってなかったので、緑や赤や青の新幹線があることも知りませんでしたし、「監督をやろう」と決めてから知ったことは、すごく多かったです。でも、さまざまな新幹線がロボットになったらビジュアルイメージ的にもすごく格好いいと思ったし、企画に対するワクワク感も高まりました。

──池添監督がテレビアニメの制作チームに加わった時点で、作品の方向性や内容などは、どの程度、固まっていたのでしょうか?
池添 ShoPro(小学館集英社プロダクション)さんの方で作られたプロット案と、メインキャラの初期設定的な資料はありました。
──もう少し熱血キャラな感じだったのですか?
池添 はい。ただ、元々は「王道ロボットものをやろう」という話だったので、僕としてはアグレッシブなキャラでもありかなとは思っていました。どちらかと言えば、自分はそちらの作風の方が得意でしたし。でも、企画的には鉄オタを主人公にしたいというオーダーもあったので、そこを重視するなら、いちから考え直そうということになりました。それで、少しおとなしめだけれど、前を向いて進めるような少年像を考えていったんです。どうすれば、アグレッシブではないオタク少年を主人公として成り立たせることができるのかについては、かなり丁寧に考えて描いたつもりです。
鉄道ネタも含めてリアルな形で描けるのは、すごく大きかった
──ロボットアニメの第1話の大きな悩みどころでもある「主人公はなぜロボットに乗るのか」「どうやって乗せるのか」という動機や展開については、キャラクター設定と同時に考えていったのですか?
池添 キャラの設定が深まるのと、本(脚本)が進むのがほぼ同時進行で、いったりきたりしながら作っていった感じですね。あと、作品の世界観というか、どのようなムードの作品にするのかについてもかなりやり取りをしました。最初は(メインスタッフの)誰も、具体的な方向性が見えていなかったかもしれません。
──熱血ものなのか、もっとクールなのか、ギャグなのか、といった方向性ですか?
池添 そうですね。でも、TBSのプロデューサーの那須田(淳)さんが「リアルな人間ドラマを描くなら、少しシリアスに始まっても良いんじゃないか」という判断をされた時、方向性が見えてきました。物語に緊張感を持たせつつも、主人公がお父さんのためにならロボット(シンカリオン)に乗る。

──主人公の父親の速杉ホクトがシンカリオンを生みだした「新幹線超進化研究所」のスタッフであるという設定は、初期プロットやキャラ設定案にも存在したのですか?
池添 結果的に初期プロットはほとんど使っていないと思います。メインスタッフが集まってから、みんなで新たに考えていきました。そうやって作業を進めていく中、すごく心強かったのが、監修としてJR各社さんが入ってくださっているから、作中で実在する駅や車両が使えること。ターゲットとして、新幹線好きな少年にかなり一点集中で作ろうとしていたので、鉄道ネタも含めてリアルな形で描けるのは、すごく大きなことだったんです。
──実在の車両や駅が登場すると、新幹線好きの子供たちに対してのつかみになるし、より楽しんでもらえると思ったということですね。
池添 (主人公機を)「E5はやぶさ」と言えること自体、すごく大きかったですしね。それに、あわよくば子供だけでなく、鉄道ファン(の大人)にも観ていただれば、という感覚で作っていきました。
──実在する新幹線や駅が実名のまま出せる一方で、作中での描写に関しては制限もあるのでしょうか?
池添 かなり自由に作らせていただいていますが、走っている新幹線を壊してはいけない、レールの上で危険なことはしない、といった決まりは多少あります。例えば、第1話の冒頭では、新幹線の線路上に現れた巨大怪物体が、線路から少し移動したところを捕縛フィールドで捕らえるのですが。あれは、線路の上に敵を立たせられないという制約があったので、出てきてすぐに線路から少し離れたところへ移動させたんです(笑)。
──作品全体として「こういう方向にしたい」あるいは、「こういうことはしたくない」といった、監督の中での指針的なものはありましたか?
池添 この作品では「好き」という気持ちをテーマにしていて。
──「選ばれし者」と「選ばれなかった者」の構造をなるべく見せないようにしているのですね。
池添 作品の中で学校のシーンをほとんど描いていないのも、それが理由です。たぶん、ハヤトたちが授業を受けている時にキトラルザスが地上に攻めて来たことは無いはず。だいたい、土、日に来てくれるんです(笑)。
いつの間にかアズサは、みんなの良いお姉さん的なポジションに
──数多くの運転士が登場する中、ハヤトは常に適合率トップの位置にいます。他の運転士たちは、そんなハヤトに対してライバル心や嫉妬心を抱くのではなく、力を認めて信頼し、支えていますよね。その関係性も作品の魅力の一つだと思うのですが、その方向性も当初からイメージしていたのでしょうか? それとも、物語が進み、キャラクターも増える中、自然とそうなっていったのですか?
池添 ハヤトは、あまり周りを引っ張っていくタイプではなくて。本当にオタクというか、純粋な「好き」を持っている子。でも、本来、彼みたいな子は周りに埋もれてしまいがちだと思うんですね。だから、あえて、彼を越えようとする人を描かなかったところはあります。
──そういう構造を描くことで、ハヤトを無理矢理押し上げることも、周りを下げることもせず、自然とハヤトの存在感が増したのですね。
池添 ハヤトのような少し根暗なオタクの子を(主人公として)立てるには、そういう方法しか無いかなという感覚でした。
──ハヤトがオタクとして素晴らしいと思うのは、自分は新幹線が好きだけれど、それ以外のものを好きな人をバカにしたり、否定したりしないところです。「キミはそれが好きなんだね!」とリスペクトしますよね。
池添 絶対に相手の「好き」を拒絶しないし、自分の「好き」を無理矢理に押しつけることもしない。そこは意識的に描いています。まあ「この子は、もしかしたら新幹線のこと好きなのかな?」と気づいたら、少しスイッチを押したり、全力で後押ししたりもするんですけどね(笑)。そこは、できたら一緒に楽しみたいという気持ちがあって、誘っている感じです。
──ハヤトの他にも、非常に多くのキャラクターが登場していますが、その中で特に物語を引っ張ってくれたキャラクターや、最初の想定とは大きく変化したキャラクターがいれば教えてください。
池添 最初は、(男鹿)アキタ、(大門山)ツラヌキの2人が(ハヤトの)周りで動いてあげることにより、ハヤトが目的に向かって進んでいけるという関係性がありました。でも、最近だと(上田)アズサがそういう存在にもなってきましたよね。(シリーズ構成の)下山(健人)さんは「最初から、そうやろうと思っていました」と言うんですけれど、本当かどうかは分かりません(笑)。

──池添監督としては、シンカリオン運転士でもないアズサが物語を引っ張る存在になるのは想定外でしたか?
池添 全然思ってなかったです。下山さんがあえて僕らにも言わないまま、そういう風にアズサを描いてきたのだとしたら、本当にすごいなと思います(笑)。でも今思えば、(キトラルザスの)セイリュウとハヤトの間に立てて、客観的な意見をズバッと言える存在はアズサしかいなかったし。ハヤトに対して一番ハッキリ意見を言えるのも、幼なじみのアズサ。たしかに「そうだよな」と思うような関係性になっているんですよね。
──当初のアズサのキャラクター性や立ち位置については、どのように捉えていたのですか?
池添 おせっかいでもなく、自分を主張したいだけの自分大好きなユーチューバー。鉄道オタクのハヤトをちょっと気持ち悪いとも思っていて。「そんなものよりも私の動画を見て!」という感じの子だったし。シンカリオンの存在を知った後も、それを動画で紹介して再生数を稼ぎたくて(ハヤトたちに)くっついていたんですよね。
──初期のアズサは、オタク男子の一番苦手なタイプ、「この子とは関わりたくないな」と思われる女の子として描かれていた気がします(笑)。
池添 まさに、そうでした。だから、話が進んでいった時、アズサ役の竹達(彩奈)さんからも「アズサ、急にどうしたんですか?」みたいなことを聞かれました(笑)。初期のアフレコでは、さっき話したようなことをすごく強調して欲しいと伝えていたので、戸惑ったのだと思います。
悩んだ末に「もう、改札に閉じ込めて斬ってやれ!」と思った
──ハヤトを中心としたアキタ、ツラヌキの関係性についても、意識した点などを教えてください。
池添 ハヤトに足りない部分を補うという意味で、ああいう性格の二人を置いたんです。アグレッシブで、本来、ロボットアニメの主人公になりそうな性格のツラヌキと、クールに分析するアキタは、どちらもよくあるタイプのキャラクターではありますが、ハヤトをサポートする役割としても、大きな意味を持っている立ち位置かなと思っています。実は、当初は、ツラヌキとアキタの相性をあまり良くない感じにして、もっとバチバチやらせようかとなとも考えていたんです。そこで、特別なオーラを持っているハヤトが間に入り、3人の関係性が繋がるみたいな案もありました。
──アキタ、ツラヌキの後もたくさんの運転士が登場していきますが、それぞれのキャラクターの性格などの設定は、どのように固まっていったのでしょうか? ストーリー上の必要性によって生まれたキャラが多いのですか? それとも、アキタやツラヌキのように、キャラクター配置のバランスなどが大きく影響しているのでしょうか?
池添 基本的には、ロボット(シンカリオン)の個性を膨らませるためのキャラ付けという要素が大きかった気がしますね。例えば、こういう技を出すなら、クールな運転士の方が良いなということで(清洲)リュウジが生まれたり。忍者の技を出すシンカリオンの運転士は、やっぱり忍者にしよう。でも、クールではなく可愛い子にすることでギャップを見せようと思って(月山)シノブが生まれたり。シンカリオンありきで考えていくことが多かったです。
──シンカリオン自体の描き方、アクションシーンで特に意識したことや、演出上のルールなどがあれば教えてください。
池添 基本的に、鉄道をモチーフにした武器しか出ないんですよ。だから、技をどう見せるかは苦労しました。E5の「カイサツソード」も、悩んだ末に「もう、改札に閉じ込めて斬ってやれ!」と思って描いたんです(笑)。クスッと笑われてしまうかもしれないけれど、そのくらい誇張した方が印象的で良いだろうと思いました。あと、現場的なことを言えば、1話ごとに使えるCGシーンの尺が決まっているので。ボリューム感や尺を抑えつつ、限られた条件の中で、どうやってそれぞれの機体の個性を出しつつ戦闘を盛り上げていき。最後に(必殺技の)グランクロスで(敵が)爆散するところまで持っていくか、というのは一番苦労したことかもしれません。

──特にお気に入りだったり、印象に残っている戦闘シーンはありますか?
池添 先ほどの話と重なりますが、やっぱり、第2話で「カイサツソード」をやろうと思った時のことは、いまだに印象に残っていますね(笑)。「カイサツソード」という技の名前自体はアニメ化する前からあったのですが、必殺技としてどう映像で見せるかについてはアニメオリジナルで考えました。あの技が生まれたことは自分の中では大きかったです。
(丸本大輔)
後編に続く