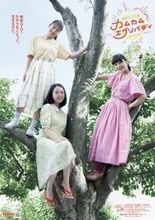インターネットでのトラブルや炎上を描くテレビドラマは、2019年前半だけでも5本放送されている。
ここに挙げたドラマの多くは、ネット民を「炎上やネット私刑、肖像権の侵害、他者を傷つける生放送などのトラブルを起こす存在」として描いた。匿名SNSに隠れて無責任に発信し、熱狂していくネット民の存在によって、主人公をはじめとした現実=リアルの人間が困り、傷つき、苦痛を与えられる。
ネット民は、悪意の塊、トラブルメーカーとしてしかドラマに登場することはできないのだろうか。今期、匿名の悪意を繰り抜いて明確に描き出したのが『デジタル・タトゥー』だった。

ネット民は顔の見えない正体不明の悪意『デジタル・タトゥー』
2019年5月18日からNHK総合で放送されている『デジタル・タトゥー』。ヤメ検弁護士・岩井(高橋克実)と、人気YouTuber・タイガ(瀬戸康史)がバディとなり、インターネット上の誹謗中傷や個人情報の拡散を食い止めていくサスペンスドラマだ。
YouTuberへの殺害予告、痴漢冤罪被害で仕事を失った人、偽装キラキラ港区女子、議員候補の炎上商法、学歴詐称の暴露、生配信者の突撃、ミスコン優勝者へのリベンジポルノと内定取り消し。現実にも十分に起こりうるインターネットを通したトラブルの数々。その裏には、悪意や復讐心に突き動かされる人間がいることが描かれる。
ネットユーザーの炎上へのコメントも、ネガティブなものばかり出てくる。
しかし、ネット民をここまで徹底的に「悪」として描かれると、逆に「そうだろうか」という疑問も湧いてくる。たとえば、第4話の「ミスコン優勝者へのリベンジポルノと内定取り消し」について考えてみたい。
リベンジポルノの被害に遭った早紀(唐田えりか)は、岩井の一人娘だ。キー局の女子アナになるための足がかりとして大学のミスコンに出場し、見事に優勝した。それを「計算高い」と見るか「将来をしっかり考えている」と見るかは、本人の資質ではなく見る側の価値観の違いによるだろう。ある日、早紀が元恋人とラブホテルのベッドで撮ったツーショット写真が流出する。それを、インターネットにアップしたのは友人のミサ(久保田紗友)だった。
昨今の「#MeToo」運動の認知度や、反フェミニズム的な広告などの炎上が多いことを考えると、早紀のリベンジポルノに関してネット世論が被害者バッシングのみに偏るとは思えない。
作中で、「何やってるんだ」と早紀を叱ろうとしていた岩井は、タイガに「早紀ちゃんは被害者だ」とたしなめられる。
『リベンジポルノ―性を拡散される若者たち』(弘文堂)の著者・渡辺真由子はインタビューで《大人が「悪いのは100%加害者なんだ」という認識を持ち、それを子どもに伝えていくことが必要です。

早紀へのリベンジポルノが話題になった時点で、「本人の素行・事情に関係なく、リベンジポルノ自体は悪である」とネットで発信する弁護士やフェミニストが現れてくると考えられる。内定取り消しともなれば被害者を保護すべきとの声はさらに強まり、署名活動などが展開される可能性もあるだろう。その場合、むしろミサに写真を抜かれただけの元恋人・小西(荒井敦史)のほうが、義憤にかられたネット民からの強い非難を浴びる可能性があり心配だ。
このように被害者がネット上で擁護・支援される可能性を『デジタル・タトゥー』は描かない。それは、どうしても悪い言葉ばかり聞こえてしまう炎上やトラブルの被害者から見た世界を、あえて描こうとしているからか。本作が描き出しているのは、多様な意見が交わされる「インターネットの世界」ではなく、あくまで「ネットの炎上被害・トラブルに遭った“現実の”人々」なのだ。
実は誰もが炎上の当事者『向かいのバズる家族』
匿名の悪意を描いた『デジタル・タトゥー』とは対照的に、ネット民のひとりひとりを「あなたの隣人」という見せ方をしたドラマが同時期に放送されていた。2019年4月4日から6月6日まで放送の『向かいのバズる家族』だ。

主人公は、篝(かがり)家の長女でカフェの店長として働くあかり(内田理央)。激怒する客へ謝罪しているあかりの姿が動画に撮られ、それがSNSで賛同・応援の声とともにバズってしまう。
また、あかりの母・緋奈子(高岡早紀)は、料理動画を投稿しはじめYouTuberとして人気に。父・篤史(木下隆行)はプロデュース担当していたドラマがSNSで話題に。そして、弟・薪人(那智)はアルバイトの家庭教師先の生徒・朱里(桜田ひより)と寄り添う写真が「バズる弟、未成年淫行疑惑」とネットにアップされてしまう。
篝一家は、ネット上で「バズる家族」として有名になる。それぞれの「今よりちょっとだけ人生を充実させたい」という素朴な願いが、ネット民を巻き込んで大問題になり、家族の崩壊まで招いてしまった。
写真を勝手にアップされ家族の相関図を作られたり、あかりや緋奈子の元恋人が接触してきたりと、警察沙汰になってもおかしくない事件が篝一家を襲う。それでも『デジタル・タトゥー』ほどの正体不明の恐ろしさを感じない理由は、あかりたちを取り巻くネット民たちの“顔”が見えているからということが大きい。
篤史がプロデュースしているドラマ『少年スナイパー!新平』をいつも批判している「バトルフィーバー」というSNSアカウントが登場する。バトルフィーバーは、ドラマを擁護する「JUSTICE SWORD(ジャスティスソード)」というアカウントといつもSNSで言い争いをしており、スタッフやファンに煙たがられていた。実は、バトルフィーバーの正体はドラマの出来に不満を抱いていた篤史だった。そして、JUSTICE SWORDは篤史を批判から守ろうとした薪人だったというオチだ。
緋奈子のファンの伊勢谷(永野宗典)と迫滝(前田公輝)は、あかりのカフェで働く従業員だ。きゃりーぱみゅぱみゅ(本人)も、緋奈子の動画を楽しんでいた。あかりのファン・穂村真斗(黒羽麻璃央)は人気俳優。バズったり炎上したりを繰り返すあかりを励ますコメントをし続けてくれていた「トゥナイトスター」は、あかりの祖父・清史(小野武彦)だった。お互いに正体がわかり、匿名の仮面がどんどんはがれていくストーリーは、怖さはありつつも不思議な快感、気持ち良さも感じられた。
炎上やバズに関わるネット民たちを「正体不明で制御できない厄災」のように描いたのが『デジタル・タトゥー』だとすると、「実は誰もが当事者のひとり」と視聴者に引き寄せて描いたのが『向かいのバズる家族』だった。
ネット民ひとりひとりに光が当てられた『電車男』
ネット民は、匿名で顔も見えない不明の存在という面も、自分自身や隣人という近しい存在という面も持っている。ドラマを制作するときには、その切り取り方によって悪意の群集にも輪郭があるひとりの人間としても描くことができる。ネット民の描き方という点でいうと、2019年の『デジタル・タトゥー』と『向かいのバズる家族』は対照的な作品だった。
さかのぼれば、「ネット民」を初めてドラマで大々的に取り上げたのは、2005年7月期に放送された『電車男』(フジテレビ系)だ。主人公のオタク青年・山田(=電車男)が、電車で酔っ払いに絡まれていた美しい女性・沙織(エルメス)を助けることから、物語が始まる。

年齢=彼女いない暦の電車男は、どうすればエルメスと仲良くなれるかわからない。そこで、いつも見ていたインターネット上の巨大掲示板「Aちゃんねる」の「毒男スレ(独身男性が毒づくスレ)」で、お礼の電話の仕方やデートで行く店、着ていく服装などを相談する。
浮かれて調子に乗ったり、自信のなさから急に弱気になったりする恋愛初心者の電車男を、Aちゃんねるの住人たちはインターネットの向こうから優しく、ときに厳しく助言しながら見守っていく。電車男役を演じたのは伊藤淳史、エルメス役は伊東美咲だった。
パソコンの向こう側、インターネット上で電車男を励ますネット民たちは、電車男にとっては「顔の見えない匿名の相手」だ。しかし、ドラマ上ではそうは描かれていない。登場するときには居住地のテロップが出る。ひとりひとりの部屋も、一目見れば彼らがどんなオタクか、あるいはどんな生活をしているかがわかるように作りこまれている。
たとえば、小栗旬が演じた「Aちゃんねる」毒男掲示板の管理人・皆本宗孝は、東京都港区在住。宗孝は、AA(アスキーアート)職人でもあり、山田が初めて沙織に電話をかけるときに電車のAAで背中を押した。やや薄暗い部屋で、たくさんのモニタに囲まれて過ごしている宗孝。その孤独な様子から、過去に友人に裏切られ人間不信になったという背景が徐々に見えてくる。
愛知県南知多町に住む引きこもりの青年・浅野真平(山崎樹範)。掲示板上ではイキイキと発言しているのに、廊下に食べ終わったご飯のおぼんを出すときの居心地の悪そうな動作に、胸が苦しくなる。
『電車男』もまた、インターネット上の匿名の熱狂を描いたドラマだった。仮にいまの時代で似た現象が起これば「バズ」と呼ばれるのかもしれない。
匿名掲示板という一種の閉鎖的な空間が舞台の『電車男』では、掲示板の「住人」という形でネット民ひとりひとりにも光が当てられていた。何者なのかわからない不明の存在ではないから、『電車男』に登場するネット民は怪しさや恐怖を感じずにいられる。パソコンにかじりついている人は暗くて怖いという偏見もあった2005年に、こうした形で『電車男』がお茶の間に放送された意義は大きかった。
ドラマで描かれる「ネット民」のゆくえ
日常的にSNSを利用していて自分を「ネット民」と自覚している筆者からすると、正直、自分たちを『電車男』や『向かいのバズる家族』のようにひとりの人間として描いてもらえたほうが嬉しく感じる。考え、主張を持って発信している意見を、取るに足りない匿名の何かとして忌避されるのは悲しい。
しかし、「バズや炎上に関わっている人には何か意見や主張があるわけではない」という見方もある。安田浩一・著『ネット私刑(リンチ)』(扶桑社)では、ネット私刑の参加者へ取材をしている。個人を名指しして「殺そう」「売国奴」などと中傷を繰り返したり、個人情報を晒し上げた参加者たちは、自分のしたことの理由について「特別な理由なんてありませんでした」「ただ面白かった」と語る(p.127)。そんな加害者たちについて、被害者は「罪の自覚もない攻撃が一番たちが悪い」と恐れた(p.146)。

自覚なくバズや炎上、ネット私刑に関わってしまう人がいることを考えると、『デジタル・タトゥー』のようなネットの恐怖を切り取る作品にも啓蒙的な意義があるだろう。一方で、これからは「正体不明の群集」と「ひとりの人間」の溝を埋めていくような作品も、もっと必要になっていくのではないか。
『向かいのバズる家族』は6月6日に最終回を迎えているが、『デジタル・タトゥー』は今夜、6月15日よる9時から最終回放送予定だ。消そうと思っても完全には消せないインターネットの悪意と決着をつける方法はあるのか。匿名のネット民たちは、最後にどう描かれるのか。答えが示されることを期待して、放送を待ちたい。
(むらたえりか)