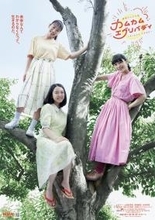複数のクリエイターがルールを共有しながらつくった各エピソード
ファンには周知のとおり、このドラマは、総武警察署の時効管理課に勤務する霧山修一朗(オダギリジョー)が、未解決のまま時効を迎えた事件を「趣味」で捜査するというものだ。霧山は一通り謎を解くと、容疑者に会って直接説明したうえで自白を引き出し、最後は相手に「誰にも言いませんよ」カードなるものを渡して、事件の真相について一切他人には漏らさないと約束する。捜査にはたいてい交通課の三日月しずか(麻生久美子)が付き添い、霧山が自分の解いた謎を説明するときには必ず外すメガネを預かる役目も担う。
1話完結型のこのドラマでは、三木聡をはじめ、園子温、岩松了、ケラリーノ・サンドロヴィッチなど演劇や映画の世界で活躍する気鋭のクリエイターが各話を競作している。いずれ劣らぬ個性派ぞろいながら、シリーズ全体ではしっかり統一感がとれている。それというのも、全編を通して先述の「誰にも言いませんよ」カードなどのルールが設けられているうえ、霧山と三日月の周囲には強烈なキャラクターたちが配置されるなど「時効警察」ワールドともいうべき世界観が存在するからだろう。クリエイターたちもルールと世界観に沿いながら各話を手がけているが、よく見ていくと各人の個性もうかがえる。
このドラマはもともと、プロデューサーの横地郁英(「時効警察」新シリーズではゼネラルプロデューサー)が「サトラレ」などいくつかの作品で組んだオダギリジョーから、「ぜひ、三木聡さんとドラマをやってみたい」と提案されて始まったという(『新・調査情報』2006年5・6月号)。それだけに、「誰にも言いませんよ」カードをはじめ、このドラマの基本設定は三木がつくったといっても過言ではない。
三木は第1シリーズでは第1話と第2話および最終話の第9話の脚本・監督を務めている。
第3話と第7話は、劇中で時効管理課の熊本課長役としてレギュラー出演している岩松了が脚本を(第3話では監督も)担当。いずれの回でも、人間の感情の機微が事件にかかわってくるのが、岩松ならではというべきか。第7話(監督は塚本連平)では、1968年の府中三億円強奪事件をそっくり模倣した「平成三億円事件」なる事件が登場、時効成立後に、葉月里緒奈演じる女性が自分が真犯人だと時効管理課へ電話してきて、手記を書くために必要なので遺留品を返すよう霧山に求める。真犯人が自分で名乗り出てくるあたり、シリーズの基本設定をちょっと崩した形になっている。
デビュー直後の吉高由里子も出演
基本設定を崩したといえば、園子温の脚本・監督による第6話(園にとっては第4話に続く担当回)では、霧山が趣味で時効事件を捜査するというドラマの大前提がひっくり返される。冒頭、テレビで殺人被害者の遺族が「なぜ時効なんてものがあるのか」と訴えるのを見た霧山は、自分の趣味に疑問を抱き、「誰にも言いませんよ」カードを部屋に放り投げてしまう。とりあげられる事件もまだ時効を迎えておらず、森口瑤子演じる容疑者はあとしばらくすれば逃げ切れるという設定だ。しかし彼女は、高校生の娘を介して霧山と出会ってしまい、彼も行きがかり事件を捜査するはめになる。
ちなみに森口の娘役を演じる女の子に見覚えがあると思ったら、声を聞いて吉高由里子だと気づいた。当時17歳だった吉高にとって、これがドラマデビュー作であり、前後して出演した映画「紀子の食卓」も、同じく2006年に公開されている。こちらも監督は園子温だった。
ケラリーノ・サンドロヴィッチ(KERA)が脚本・監督(脚本は山田あかねとの共作)を務めた第8話も、三木聡の担当回に匹敵するほど小ネタ「多め」となっている。なかでも、犬山イヌコ演じるおばちゃんが営む食堂「多め亭」(どんなメニューも多めの量で出てくるほか、おばちゃんの言動も何かにつけて多めという店)は、本筋とはほぼ関係ないが、KERAの本領発揮といえる。事件を捜査する過程でも、喫茶店のマスターのある持病による習慣や、クリーニング屋のロシア人のある行動が真相解明の重要なカギを握っていたりと、いちいちトリッキーで「そんなわけあるかい!」とツッコみたくなる。はたまた霧山のそっくりさんが登場したりと、やりたい放題の回であった。
時効廃止という大変化をどう処理する?
第1シリーズでとりあげられた事件は一部を除き15年で時効を迎えた。放送時の2006年からさかのぼれば1991年と、バブル崩壊の年にあたる。たとえば、第3話の事件は、湾岸戦争の勃発を報じる朝刊が駅の売店に並んだ日(1991年1月18日。戦争勃発自体は前日)に起こった。ほかの回でも、当時のディスコのニュース映像が出てきて、リアルタイムで見ていた私は、平成あるいは90年代がノスタルジーの対象になり始めたのかもしれない、と思った記憶がある。
なお、「時効警察」旧シリーズが放送された2006年〜2007年は、地上波テレビがアナログからデジタルへと移行しようかという時期だった。そのなかで本作は、デジタル化に対応してハイビジョンで撮影されている。したがって画面のアスペクト比は16:9だが、事件発生当時の回想シーンではアナログテレビと同じ4:3に変わる(画調もビデオテープで撮影したような感じになっている)。いまでは結構あちこちで見る手法だが、当時は新鮮だった。
警察物・事件物ではあるが、あくまでコメディなのが「時効警察」の信条である。プロデューサーの横地郁英は第1シリーズ放送直後のインタビューで、「誰にも言いませんよ」カードを渡すくだりなどは、ある種、コントの一環だとわかるようなニュアンスにしたと語っていた。ただし、同性愛を扱ったある回では「エクスキューズ・コメント」を用意するなど、細部は繊細に組み立てたともいう(『新・調査情報』前掲号)。たしかに当該回にはそれと思われるエクスキューズ(セリフ)があったものの、それでもいまの倫理観に照らすと、ちょっと差別的に感じられる描写もなきにしもあらずであった。
時代の流れに関していえば、旧シリーズ放送後には、2010年4月27日の刑法および刑事訴訟法の改正により、人を死亡させた事件で死刑にあたるものについては公訴時効が廃止され、無期の懲役・禁錮刑にあたる罪については時効期間が従来の15年から30年へと延長された。これは本作の根本にもかかわる大きな変化だろう。その背景の一つには、被害者遺族の感情を考慮すれば、時効などあるべきではないという世論の高まりがあった(そう考えると、第1シリーズの6話の冒頭のくだりはそれを反映していたともいえる)。ただし、今夜放送のスペシャルでとりあげられる事件は、1995年に発生し、9年前に殺人の時効が廃止される前日に時効を迎えたという設定になっているという(公式サイト参照)。
ちなみに第1シリーズに出てきた事件はほとんどが殺人だが、先述のとおり、いずれも15年で時効を迎えていた。2006年の時点で、その2年前の法改正により死刑にあたる罪は時効期間が15年から25年に、無期の懲役または禁錮にあたる罪については10年から15年に延長されていたので、ドラマに出てくる殺人事件は後者に相当するということだろう。したがって、新シリーズで同じ罪にあたる事件が出てくる場合、時効期間はさらに倍に延びたことになる。このあたり、新シリーズではどう処理されるのか、気になるところではある。
(近藤正高)