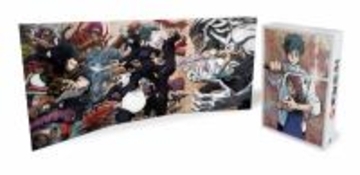船上と岸で一目会い、焦がれ死に
第1話で互いにひとめ惚れをしたお露(上白石萌音)と新三郎(中村七之助)。主治医である山本志丈(谷原章介)はお露の父・飯島平左衛門(高嶋政宏)が許さないとして互いに会うことを禁じていたが、また会いたいと思うあまり体の弱ったお露を前に、二人を一目だけ会わせる手引きをする。釣り人に扮して船でお露の目の前に現れる新三郎。互いに名前を呼び合い、一瞬の逢瀬が叶うが、お露はそのまま「焦がれ死に」してしまう。
お露が身を寄せる「柳島」というのは今でいう浅草から亀戸にかけての地名だという。浅草寺からほど近くにいまも「柳島橋」という橋が残っているが、ここは横十間川と北十間川、二つの川が交わる場所にある。歌川広重の「江戸名所図会」にも描かれているが、川に囲まれたこの場所だからこそ「釣り人に扮して会う」というシチュエーションができたのだろう。原作では新三郎が自ら釣りを口実に柳島に出かけ、その際覚えのある家を訪ねたところお露に一目会うことが叶う。しかし平左衛門にも遭遇してしまい、首を切られる……ところではっと目が覚めると夢だったが、お露に渡された香箱だけは手元にある、という、すでに怪奇な要素が混じったもの。けれどドラマでは、思うようにならない「船上と岸で一目だけ」という形になったわけだ。
ゾンビメイクという新解釈
あっけなく死んでしまったお露を目の当たりにし、侍女・お米(戸田菜穂)もすぐに後を追う。そして最も有名な「カランコロンと下駄の音が鳴り響く」シーンがやってくる。お露は死んだと聞かされていた新三郎のもとへ、牡丹の描かれた灯籠をもったお米を従えてお露が訪ねてくる。
最初はお露の顔の半分が醜いものになっていて、やがて全身がゾンビのようになっている、という表現。ちなみに新三郎を演じる七之助は、かつて歌舞伎でお露を演じたことが何度かあり、そのうち2007年に歌舞伎座で上演されたものは「シネマ歌舞伎」にもなっている。ここではお露が骸骨になっているという表現だった。ただ、確かに死んでけっこうすぐに新三郎の元にいくことを思うと白骨化する前だろうし、生きている男と交われるほど「実態ある」状態はそりゃ骨よりゾンビだろうし、ドラマの方がリアリティ(?)あるのかも。

今回特殊メイクにクレジットされていたのは中田彰輝。映画『来る』などのほか、『髑髏城の七人』など、劇団☆新感線のメイクも担当しているそう。そう言われると最初のお露の顔半分メイク、醜さと同時に美しさも感じられるのが、新感線のビジュアルに通じるな、と納得できる。
なお、新三郎の家は谷中で、お露の墓は新播随院、こちらも谷中。つまりあんなに会いたくても会えなかった谷中と浅草の距離が、墓に入ったことでぐっと縮まったということになる。
さて、1話では「彼女なりの思いもあるのかもしれないな」と思えたお国(尾野真千子)の行動だが、お露が死んで高笑い、源次郎(柄本佑)にはなにかと平左衛門を殺すようけしかける……と、なかなかに露骨な悪女ぶりを見せる。平左衛門に仕える孝助(若葉竜也)に企みを知られてしまうが、孝助は忠義心があるあまり、直接平左衛門に真実を伝えられず、「とにかくいのちだいじに」的なあやふやな忠告をするばかり。こちらの物語は3話で大きく動くことになりそうだ。
いよいよ第3話は「お札はがし」の名場面。そうそう、このドラマ、冒頭で今をときめく講談師・神田松之丞が登場し、雰囲気たっぷりに語りをきかせている。「お札はがし」の場面は松之丞が実際に高座にかけたことがあるネタ。ネタおろしの際にはTwitter上で「『お札はがし』難しいよー」とつぶやいていた。この、講談をする側にとっては激ムズ(らしい)場面がどう描かれるのか。第3話は今夜。
(釣木文恵)
令和元年版 怪談牡丹灯籠
出演:尾野真千子、柄本佑、若葉竜也、中村七之助、上白石萌音、高嶋政宏、戸田菜穂、谷原章介、ほか
脚本・演出:源孝志
プロデューサー:川崎直子、石崎宏哉
制作統括:千野博彦、伊藤純、八木康夫
語り部:神田松之丞
原作:三遊亭圓朝『怪談 牡丹灯籠』
音楽:阿部海太郎
制作:NHKエンタープライズ