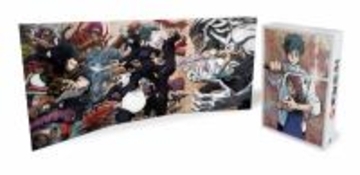「配信中毒」バックナンバーはこちらから
今回紹介するのは、ネットフリックスにて配信中の『ボクらを作ったオモチャたち』である。先日からシーズン3が配信され、それはもう、おれはこのドキュメンタリーを噛み締めるようにして見た。
待ってたよ!! シーズン3は亀とスーパー戦隊とポニーとプロレス!!
タイトルからわかる通り、このシリーズは一世を風靡したオモチャ(基本的にはアメリカでよく売れたものが取材対象)がどのようにして生まれ、どのような経緯を辿って今に至るかを関係者に取材して解き明かすドキュメンタリーだ。なので、登場するのは派手なセレブやスポーツ選手ではなく、基本的にオモチャ会社で仕事をしていたデザイナーや営業の人、コレクターとか研究者とか、そういう地味目の人たちである。
しかしこれがめっぽう面白い。最新シーズンであるシーズン3で取り上げるのはタートルズ、パワーレンジャー、マイリトルポニー、そしてプロレス玩具である。一気に得た大金と権利ビジネスに関する行き違いから、クリエイター2人が決定的な決別(そして再生)へと至る過程が当事者の口から語られるタートルズ回。日米のコンテンツビジネスの大きな違いから、日本からは見えにくい海外における東映の裏面史を照射するパワーレンジャー回(「石ノ森章太郎は日本のスタン・リーである」という見立てのハマり具合よ!)。男社会のオモチャ業界で女性デザイナーたちがいかに試行錯誤したか、そしてそれが通った時にいかに爆発的ヒットを生み出したかが語られるマイリトルポニー回。どれも面白すぎて悲鳴をあげたくなる内容だ。
わけてもシビれるのは、WWF(現在のWWE)を中心とした、プロレス玩具の歴史を取り上げた回である。プロレスラーは実在の人物であるが、同時にフィクション的なギミックやルックスを用い、試合には作為と演出と偶然とガチが入り乱れる。虚実がぐちゃぐちゃに入り混じった存在である。それをさらにオモチャにするとはどういうことか。実在の人間のどこが面白いかを抽出し立体化する作業は、どのような経緯で行われてきたのかが語られる。
「プロレスラーをフィギュアにする」という事業に関わってきた会社は多種多様である。なぜ多種多様になったのかは本編を見て確認してもらうとして、その各社がハルク・ホーガンやブルーザー・ブロディのようなキャラクターをどのように立体化したか、実際の玩具をずらずらと並べて見せられると唸ってしまう。ある会社はゴムでできたガワの中に針金を入れて自由にポーズが取れる(はずの)大型フィギュアを発売し、また別の会社はずっと小さくて関節が入ったコレクションサイズのフィギュアを売る。虚実が入り混じった存在であるプロレスラーをどのように演出して面白く(面白くなければ売れないのだ!)商品化するか、という入れ子細工のような作業を、実際に作業に関わった当事者が振り返る。面白くないわけがない。
「いかにインタビューとテーマを面白く見せるか」に全振りした、編集の妙味
『ボクらを作ったオモチャたち』シリーズ全体に通して言えることなのだが、このドキュメンタリーシリーズで見るべきは抜群の編集のうまさである。というのも、上でおれは面白い面白いと書いたものの、普通オモチャの話を面白がるのは一部のオモチャおじさんくらいなのだ。アメリカ人ならば「ああ、オレも昔持ってたな〜」とノスタルジーに引っ張られることもあるかもしれないが、ここは日本である。子供の頃にヒーマンのフィギュアで遊んだ人というのは、日本ではやはり少数派だろう。
にも関わらず、この番組は誰が見ても面白く見られるように作ってある。インタビューにしたって業界から引退したおっさんたちが「あの時は大変だった」みたいな話をしているだけなので、そのまま真面目なトーンで放り出したら退屈で見られたものではない。なので、『ボクらを作ったオモチャたち』は途中でナレーションによるツッコミを入れ、1カットの長さを10数秒単位でバチバチ切り、おっさんがボケッとしているだけの顔をスパスパ挟んでテンポを作り出す。
さらに言えば、シーズンごとのネタ選定やその打順の組み立ても抜群である。シーズン1の第1話では「服を布でなく樹脂で作った」「大量にコレクションできる」現代的アクションフィギュアの先駆けとしてケナーによる『スター・ウォーズ』のフィギュアを取り上げ、返す刀で人形遊びの一大ブランドであり近代的着せ替え人形の原点であるマテルのバービーへと遡り、残り2話で『スター・ウォーズ』の対抗馬として80年代に花開いたアクションフィギュアの雄であるヒーマンとG.I.ジョーを取り上げてシーズンを締める……。各話が独立しながらも、通して見ると「プラスチックでできたアクションフィギュアとは」というもっと大きなテーマが把握できるようになっている。惚れ惚れするような編集の技である。
シーズン2では『スター・ウォーズ』の対抗馬であり、ずっと長い歴史を持っていたはずの『スター・トレック』のオモチャがその長い歴史ゆえに迷走した経緯を取り上げ、さらにトランスフォーマー、レゴ、ハローキティという非アメリカ製玩具・キャラクターがいかにして世界的ヒットを飛ばしたかを紹介。こちらはこちらでアクションフィギュア以外のオモチャの多様性、国際性(特にトランスフォーマー回は戦後日本とアメリカの玩具業界の関わり合いを見事に説明しきった名作である)を我々に伝えてくる。シビれる構成だ。
シーズン3は「シーズンを通してのテーマ性」みたいな部分がやや薄まった感があるが、そのかわり今までのシーズンの蓄積がものを言い出した感がある。例えばプロレス玩具回では同じ筋肉ムキムキのフィギュアであるヒーマンの回を見ていればより楽しめるし、マイリトルポニー回をより楽しもうと思ったらシーズン1のバービー回を見るべきである。オモチャは単体で存在しているのではなく、あるヒット作が他のヒット作に相互に影響を与え合いながら成立しているという点が、シリーズを重ねることでよりクリアに見えてきたのだ。
オモチャという普通の大人ならさほど興味が湧かない(何度も書くが、いきなりオモチャの話をされて喜ぶのはマニアだけなのである)題材を前にして、これほど面白く重層的なドキュメンタリーを作ることができたという点は、ネットフリックス取材班のパワーを改めて思い知らされた感がある。

(文と作図/しげる タイトルデザイン/まつもとりえこ)