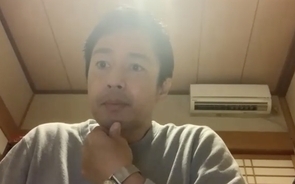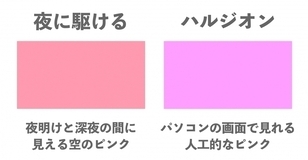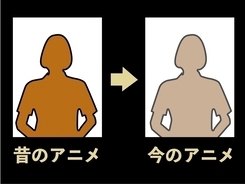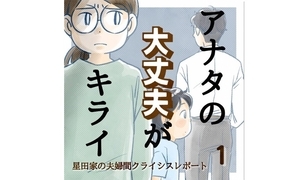お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が8月に刊行した『言い訳 関東芸人はなぜM-1で勝てないのか』(集英社新書)が、お笑いファンや読書家の間で評判を呼んでいる。漫才の祭典『M-1グランプリ』で活躍した芸人たちのネタを、プロフェッショナルの目線から精緻に分析。
3度『M-1』の決勝に進出したものの、ついにチャンピオンの座には届かなかったナイツ。2018年にM-1審査員を務めた塙は、著書『言い訳』の中で同大会を「漫才師の聖地」と表現した。そんな彼が、『M-1』の魅力や頂点に立つために必要なもの、そして12月22日に迫った決勝戦に向けての展望を語ってくれた。
『M-1』人気の理由はルールにあり

――塙さんのご著書『言い訳』では、これまで『M-1グランプリ』で活躍してきた芸人の特徴はもちろん、ナイツの漫才についても細かく分析しています。“タネ明かし”をすることで見ている側のハードルが上がってしまうかも、と気になりませんでしたか?
僕自身はまったく気にならないですね。それ以上に、「この漫才はどういう漫才ですか?」とか「どういう風にネタを作っているんですか?」とか、そういう質問に答えるのに疲れてきたんですよ。「あとはこの本読んどいてください」なら楽じゃないですか。ハードルが上がったら、それはそれで面白いですし。
――このくらいで「笑いがとれなくなるかも」とは考えない、と。
ここまで真剣にお笑いを語って突き抜けてしまえば、議論するネタにもなるじゃないですか。ちょっと恥ずかしいですけどね。“令和の漫才バイブル”ってコピーは、さすがにイジりたくなる(笑)。
――そうだったんですか?
あらためて『M-1』の人気を実感しましたね。芸人だから『M-1』が好きなのかと思っていましたけど、「実はみんな好きだったんだな」ということがこの本を出してよくわかりました。あと、ナイツの漫才を評価してくれる人がたくさんいるとわかったのも嬉しかったです。土屋に印税ぜんぶあげたいなと思いますよ。すべて土屋のおかげですからね。
――(笑)。たしかに、近年の『M-1』はお笑いの枠を超えて、国民的な行事のような盛り上がりを感じます。ここまでの人気コンテンツになった最大の要因はどこにあると思われますか?
やっぱり同じルールだからでしょうね。『キングオブコント』や『R-1ぐらんぷり』って、統一感がないじゃないですか。出場者ごとにセットも違かったりするし、披露するネタもまったく噛み合っていない。
――現状の『R-1』を“世紀の凡戦”と評された猪木・アリ戦にたとえるなど、比喩表現を駆使してわかりやすくお笑いを解説しているのも『言い訳』の魅力のひとつです。とりわけ『M-1』を短距離走と表現し、ナイツは長距離向きだと明かすくだりは印象的でした。
ナイツとしては持ち時間が長ければ長いほど自信があるんですよ。『M-1』の尺は4分ですけど、僕らは10分でも20分でも30分でもネタをやれますから。でも、やっぱりテレビですからね。あまりに長いネタは見ている人の集中力がもたない。最近のネタ番組はどんどん短くなっていきますもんね。『爆笑レッドカーペット』なんて90秒でしたし。
でもね、90秒のネタでウケる芸人は10分のネタをやらせても面白いし、10分かけて面白くないやつは90秒でウケるわけがない。
“平場”で感じる関西芸人の強さ

――お笑い界の西高東低という現状も『言い訳』の大きなテーマのひとつです。塙さん自身が東西の格差を感じるのは、具体的にどんなシチュエーションなのでしょうか。
漫才のネタ以上に、いわゆる“平場”と呼ばれる状況や日常会話の中で、関西の芸人の強さを感じますね。たとえば、なんばグランド花月に出させてもらって大阪吉本の芸人と打ち上げに行くと、やっぱりめちゃくちゃ楽しいんですよ。こっちがボケたらツッコんでくれるし、とにかくみんなボケたがる。東京の芸人は飲み会でもあまり話しかけてこないし、元々の気質が全然違いますね。そういうときに、やっぱり関西人のほうがお笑いを愛しているな、と思うんです。
――ミキの昴生さんが楽屋で気持ちよくツッコんでくれる、というエピソードも明かしていましたね。
関西の芸人には、基本的にそういう精神があるじゃないですか。どんな場面であっても「おもろく生きたい」「おもろいヤツが一番じゃ」みたいな精神が、全体として明らかに関東よりも強いと思う。文化としてそこがまったくブレていないし、ハートも強いやつが多い。
――「面白い」を一番に置く価値観自体が、明らかに関西のほうが強い、と。
関東は「下ネタはやめておこう」とか「それは言わないほうがいい」とか、周囲が止めたがる文化だから「面白い」に振り切るのは難しいんでしょうね。東京の事務所ってネタ見せをすごくやらせますけど、あれも実は弊害だと思うんです。芸人にアドバイスをするなら、失敗した舞台を見て、終わったあとに言えばいいじゃないですか。やる前からストップをかけるのはおかしいですよね。実際にお客さんの前でやらなければ、ネタのどの部分がウケて、どうスベるのかもわからないですから。
勝つために必要な“うねり”とは

――これまで『M-1』の決勝に3度進出し、審査員も務めた塙さんから見て、「これが『M-1』史上最大風速だった」と感じた瞬間はありますか?
2005年のブラックマヨネーズか、2007年のサンドウィッチマンか、難しいところですね。個人的にはやっぱり、無名の存在だったサンドウィッチマンが敗者復活戦から駆け上がった2007年かなぁ。『言い訳』にも書いてありますけど、敗者復活戦で負けた悔しさ以上に「関東芸人の代表として、ぶちかましてきてください!」と熱い気持ちになりました。
――島田紳助さんが100点を出した、2009年の笑い飯の『鳥人(とりじん)』はいかがですか?
あのときの決勝戦、僕たちはトップバッターで暫定1位だったんですけど、「100点出ちゃったの? まだパンクブーブーもNON STYLEもいるのに? もう無理だよ無理」みたいな雰囲気でしたね(笑)。紳助さんの100点は、ネタがものすごく面白かったことはもちろん、笑い飯の『M-1』への貢献度も含めての演出だと思いますよ。僕も審査員をやりましたけど、とても“100”ってボタンは押せないですもん。
――昨年、はじめて審査員の立場から『M-1』に参加した塙さんですが、どういった基準で採点をしていたのでしょうか?
まず決勝に進出したすべての芸人のネタを、事前に10本か20本くらい見ていきました。「この人たちはこれくらいの実力があるんだな」とおおまかに基礎点を決めておいて、当日のウケ量や完成度を加味する形ですね。あらかじめ基準を決めておかないと、みんな面白いからベースが高くなって、点差がつかなくなっちゃうんですよ。
――『M-1』に勝つためには、客席を爆発させるほどの“うねり”のような笑いが必要だと説いた塙さん。実際、昨年優勝した霜降り明星は会場をうねらせていましたね。
うねりましたね。やっぱり“初めて見る感”というか、粗品のツッコミの新鮮さがプラスに働きました。最近のお客さんは頭がいいので、「この粗品って人がこういうツッコミを連発して笑いをとる」という漫才の構造がスッと理解できる。つかみでわざわざ説明しなくても、続けていくうちにどんどん盛り上がって楽しくなっていくわけです。そこを先に説明しちゃうと、お客さんの楽しみを削るようなものなんですよ。
――他のお笑いコンテストとは比較にならないほど、審査員の採点や発言にも注目が集まる『M-1』。審査員ごとの判断基準の違いも見どころのひとつです。
オール巨人師匠は、「稽古をちゃんとしている芸人を高くする」とおっしゃっていました。僕が『言い訳』で語った内容とは逆の価値観ですね。もちろん、どっちの基準もあっていいと思います。僕が巨人師匠と同い年になったら、若手に対して「絶対に稽古はしたほうがいい」とか言ってそうだし(笑)。やっぱり僕らよりも100倍も漫才をやっている人の言葉は重みが違う。だから「巨人師匠が言う稽古とは?」と僕も考えますよね。『言い訳』を渡した後にも言われましたから。「本読んだけど、稽古はせなあかんで」と。
――たとえばナイツの場合は、ものすごい数の舞台に立ってネタをやることが稽古の代わりになっていると考えることもできますよね。
それもあるかもしれませんね。『M-1』で勝つことに特化して考えると、「面白いネタができました」という段階からさらに練習をすることで、「もうちょっとここを……」と不安になっていじってしまうわけですよ。せっかくいいネタができたのなら、本番に向けてその鮮度をなるべくキープしたほうがいいんじゃないか、というのが僕の考え方です。対して巨人師匠はもっと根源的に、「普段からちゃんと稽古をしていない漫才師はダメだぞ」という話をしているんじゃないかと思います。
『M-1』で勝つ芸人は、ネタが絶対的に優れている

――あらためて、塙さんが思う『M-1』の素晴らしさってどういったところなんでしょうか?
やっぱり司会の今田さんが凄いんじゃないですか。
――そこですか!
いや、でも本当にすごいですよ、今田さんは。ふざけすぎないくらいに面白くしてくれていて、なおかつ時間調整もめちゃくちゃ上手い。上戸彩さんとのコンビはもう完璧じゃないですか。ただ上戸さんがいることで「オスカーのタレントさんをイジってはいけない、という縛りができるのでは?」という危惧はありますね(笑)。
――(笑)。イジるという話なら、それこそ今年は吉本の芸人さんの事件というか、不祥事が相次ぎましたけど……。
今年はだからもう、裏番組で『謹慎-1グランプリ』をやってほしいですね。闇営業問題の芸人さんたちと、チュートリアルの徳井さんにも出てもらって。
――『言い訳』でも、塙さんはチュートリアルを絶賛していますね。
よく「お前にしかできないネタをやれ」と教わりますけど、チュートリアルの『チリンチリン』は誰がやっても面白いと思うんですよ。徳井さんがやるのが一番面白いだけで。『M-1』で勝つ芸人は、まず絶対的にネタが優れている。「自分にしかできないネタを作る」じゃなくて、みんなが真似できるほど面白いネタを作らなきゃ『M-1』では勝てないでしょうね。
――塙さんは『M-1』を目指す芸人に「とにかくネタを作れ」と説いています。
やっぱりちゃんとネタを作っている芸人に勝ち上がってきてほしい。予選の動画を見ていても、「ちょっと手を抜いているな」とわかるんですよ。ネタを作ったうえで力を抜くならいいけど、同じネタをずっと使い回しているやつもいる。そういう芸人には「予選ではウケても、準決勝になったら絶対落ちるぞ」と言いたくなります。まあ、とびきりのネタを温存する戦略なのかもしれませんけどね。
――そこは妥協してほしくない、と。
結局、僕も巨人師匠と同じことを言っているのかもしれません(笑)。「とにかく汗かけ!」みたいな。巨人師匠の「稽古しろ」というのが「ネタを作れ」に変わっただけですから。
――12月22日に迫った『M-1』の決勝に向けて、副読本としての『言い訳』にますます注目が集まっています。単刀直入に、塙さんが考える今年の優勝候補やダークホースを教えていただけますか?
大番狂わせは起きない大会なので、基本は去年とそこまで変わらないんじゃないかな。和牛、かまいたちあたりは絶対に面白く仕上げてくるでしょうし……。個人的に注目しているのは、熊本出身のからし蓮根。今年の『ytv漫才新人賞』で優勝したコンビです。もし決勝までたどり着いたら、勢いそのままに上位に食い込んでくるかもしれませんね。
(※インタビューはM-1準決勝の結果発表前に実施)
書籍情報

塙宣之『言い訳 関東芸人はなぜM-1で勝てないのか』(集英社新書)聞き手:中村計
https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0987-b/
2018年、M-1審査員として名を轟かせた芸人が漫才を徹底解剖。
M-1チャンピオンになれなかった塙だからこそ分かる歴代王者のストロングポイント、M-1必勝法とは? 「ツッコミ全盛時代」「関東芸人の強み」「フリートーク」などのトピックから「ヤホー漫才」誕生秘話まで、”絶対漫才感”の持ち主が存分に吠える。どうしてウケるのかだけを40年以上考え続けてきた、「笑い脳」に侵された男がたどりついた現代漫才論とは? 漫才師の聖典とも呼ばれるDVD『紳竜の研究』に続く令和時代の漫才バイブル、ここに誕生!

はなわ・のぶゆき
1978年3月27日、千葉県生まれ。漫才協会副会長。2001年、お笑いコンビ「ナイツ」を土屋伸之と結成。2008年度以降、3年連続で『M-1グランプリ』決勝に進出する。2018年の同大会では審査員に抜擢された。漫才新人大賞大賞、お笑いホープ大賞大賞、NHK新人演芸大賞大賞、第9・10回ビートたけしのエンターテイメント賞 日本芸能大賞、浅草芸能大賞新人賞・奨励賞、第68回文化庁芸術祭大衆芸能部門優秀賞、第67回芸術選奨大衆芸能部門文部科学大臣新人賞など、受賞多数。