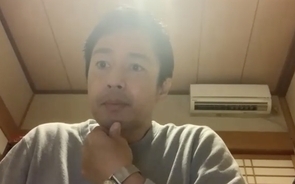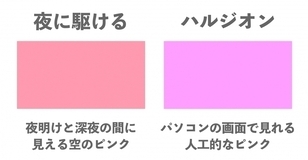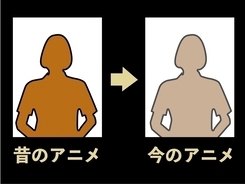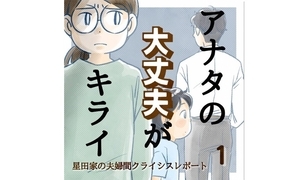いまや宣伝には必要不可欠なツールとなったSNS。音楽業界でも広く使われるようになり、たくさんのアーティストが告知やファンとのコミュニケーションに活用している。
しかし、SNSは良い側面ばかりではない。運用も本格的にやろうと思うと煩雑で、気をつけるべき点も多い。
アーティストがSNSを使う際にはどういう点に気をつけるべきなのか。今回は、主にインディーズアーティストがSNSを活用するときのポイントについて、元Spotify社員で、現在は音楽専業のデータ分析・デジタルプロモーションの会社arne代表である松島功さんにお伺いした。
SNSの運用するときに気をつけること

――簡単に思えるSNSや動画サービスの運用ですが、実際には手間もかかり、分析などのスキルも必要です。
そうですね。これはアーティストだけでやるのは難しくて、少ない人数でもいいからチームを作るべきだと思います。
役割分担も必要で、コンテンツ制作が得意な人は投稿を、分析が得意な人は数字のチェックを、といった形で担当もわりふった方がいいですね。
――「これだけはやっておくべき」というSNSはありますか?
これは難しくて、ひとつに絞るのは危険なので、やるなら全部やった方がいいと思います。
ただ、メンバーが複数いるアーティストなどだとYouTubeのコミュニティ機能がおすすめです。

TwitterやInstagramだと、公式アカウントに加えてメンバーごとにアカウントがあってフォロワーが別れてしまったりするんですね。
でも、YouTubeだとグループとしてバンドとしての1つのアカウントをフォローしてくれるので、フォロワーが集めやすいんです。なのでアーティストによってはYouTube登録者がどのSNSより多いアーティストもいます。
――いくつかのSNSを一度に運用する場合、それぞれのためにコンテンツを作るのと、同じ内容を投稿するのならどちらがよいのでしょうか?
それぞれ出し分ける方が理想的です。大変なのは承知の上ですが。
手間をかけずに運用する方法としては、集中的に投下する時期をずらすという方法があります。NiziUなどがやっていますが、YouTube投稿が多い時期、TikTok投稿が多い時期など、SNSごとに期間を分けて集中的に投稿するという方法があります。非常に計算されたプランニングのように見えますね。

それからテーマで分けるという方法もありますね。Instagramはしっかり撮った写真を出して、YouTubeのコミュニティ投稿では素の写真を出すといった方法です。
あとは「毎週月曜日は自分の曲を宣伝する」「火曜はほかのアーティストを紹介する」「水曜はオフショットの写真を出す」とか、出す内容を決めて運用するのも、比較的手間がはぶけて続けやすいと思います。
――アーティストがSNSを運用する上で、よくやってしまうミスなどはありますか?
有名なアーティストでもよくやってしまうのが「プロフィールから楽曲に飛べない」といたケースですね。これについてはきちんと設定できているケースの方が少ないかもしれません。
今って、どこで知ってもらえるかがわからないから、知ってもらった人に確実に楽曲にたどり着いてもらうことが大事なんですね。
たとえば新しいアーティストを知ったら最初にGoogleじゃなくてYouTubeで検索する人もいるし、Instagramで検索する人もいる。アーティストのサイトにいくとも限らないので、少なくともそれぞれのSNSのプロフィールからきっちり音楽に飛べるようにする必要があります。
――簡単そうで、意外と見落としてしまうポイントですね。
例えばYouTubeだと、概要欄のかなり下まで行かないとストリーミングのリンクがなかったりするんですね。
これだとすごくもったいないので、ストリーミングのような大事な情報は、概要の上の方に入れて欲しいと思います。
――なんとなく始めてしまうことも多いSNSですが、たくさんのポイントやコツがあるんですね。
アーティストのデジタル分析はどういう方法が最適か

――実際に運用するときは、どういう数字を見るのがよいのでしょうか?
ストリーミングの場合だと、共通して重要なのは「再生回数」と「再生している人数」ですね。
ただ「再生回数」は気にしすぎない方がよいです。もちろん重要なんですが、「再生回数を増やせているか」どうかよりも「きちんとファンが増えているか」を気にした方がいいですね。だから「自分の曲を聴いてくれる人が増えているか」をチェックするようにしてください。
――ほかに気にすべき数字はありますか?
ファン1人あたりの平均再生数ですかね。ファンが1日に何回自分の曲を聴いてくれているかという数字です。
もちろん最初の頃は1回だけでも良いんですけど、いま人気のアーティストってある瞬間からそれが4〜5回に一気に増えているんですね。
――1日あたりの再生数を見るとファンの熱量が上がっているかどうかチェックできるんですね。SNSの場合はどういう数字が重要でしょうか。
SNSの場合は、ストリーミングサービスの数字と合わせて見た方がいいですね。
SNSで「自分の曲を聴いてください」とYouTubeのリンクを投稿して、次の日はApple Musicのリンクを投稿して……という風に出し分けて、再生数が増えているかチェックしていくのも良いと思います。
――どれくらいの頻度でチェックするのがよいのでしょうか?
場合によりますが、シンプルなのは曜日を決めて、週一で決めた数字をチェックし続けるというものですね。
――気になるのが、SNSのフォロワーが増えたからといって音楽が聞かれるとは限らないのではないかと思うのですが……。
そういうアーティストももちろんいます。「有名になりたい」とかではなくて、最終的に自分の音楽を聴いて欲しいなら、再生に繋がるように投稿する必要がありますね。
――SNSを運用するとき、似ているアーティストを参考にして運用している人も多いと思うのですが、自分と似ているアーティストを探すのにオススメの方法はありますか?
たとえばSpotifyやYouTubeのアルゴリズムを使うのがおすすめですね。Spotifyで自分の曲と一緒に似ていると思うアーティストをまとめてプレイリストにすると、その下に似ているアーティストをどんどん出してくれるんですね。
それから、YouTubeの再生リストも参考になります。YouTubeの再生リストは音楽ファンが実際に使っているものなので、自分の楽曲が入っているプレイリストにいる他のアーティストはファンに似ていると思われている可能性が高いですね
あとは有料ですがChartmetricやSoundchartsと呼ばれるアナリティクスツールもあるので、それを使うことで似ているアーティストを探しつつ、並行して他アーティストを分析していくこともできます。

――曲が似ているアーティストと、ファンの規模や人気の度合いが似ているアーティストが異なる場合もあります。
そうですね。なので、何組か似ているアーティストを選ぶのがいいと思います。
SNSだったらこのアーティストを参考にする、クリエイティブはこのアーティストを参考にする、宣伝はこのアーティストを参考にする、といったように、いくつも参考にするアーティストを見つけておくのがいいですね。
SNSが苦手なアーティストはどうすればいいのか
――昨今はSNSを通じて人気に火がついたアーティストも多いですが、SNSが得意でないアーティストには不利な状況とも言えます。そういうアーティストはどう宣伝すればよいのでしょうか?
これは本当に難しくて、いまは器用なアーティストが有利な時代でもあるんですね。でも、結局は「自分に合ったデジタルの場所」を見つけるしかないと思います。
たとえばTwitterやInstagramのような日常の投稿が苦手なら、noteで楽曲の紹介を書くというやり方があります。CDにブックレットを付けない代わりに、noteでアルバム全曲紹介を書くというやり方ですね。
Instagramストーリーに画像ではなくテキストをいれて、ミュージックスタンプをつけて、その投稿をハイライトでまとめて。

あとは、オープンな場で発信するのが苦手なら、ファンテックと呼ばれるファンクラブ系のサービス多数出てきていますし、そういうサービスを使ってファンだけに向けて発信していくのも良いと思います。昔ながらの「本を出す」というやり方もありますし、自分が楽しんでできる発信方法を見つけるしかないですね。
――SNSだと誹謗中傷といった問題も必ずついてきます。
SNSって基本的にはアーティストにとって良い存在だと思うんですけど、SNSを通じてメンタルヘルスが不健全になると、そもそも創作活動ができなくなってしまう。
誹謗中傷をエネルギーに変えられる人ならいいんですが、そうでない場合は自分の創作、自分自身の存在を守るためにも、まずは自分の身体を優先した方が良いと思います。
――SNSもストリーミング配信も、「皆がやっているから始める」だけではなく、自分にあった付き合い方を学んでいくべきなんですね。実践的で具体的なお話をどうもありがとうございました!
■まいしろ
社会の荒波から逃げ回ってる意識低めのエンタメ系マーケターです。音楽の分析記事・エンタメ業界のことをよく書きます。
Twitter:https://twitter.com/_maishilo_
note:https://note.mu/maishilo
Soundcharts

フランスのスタートアップテックカンパニーSoundcharts社の音楽アナリティクスツール「Soundcharts」日本語版サイトが8月1日よりオープン、並びに日本のコミュニケーション窓口を開設している。
【Soundcharts 日本語版サイト】
https://soundcharts.com/ja
Soundchartsとは?

Soundchartsは、ストリーミングリスナー、ラジオでのエアプレイ、オンラインメディアでの言及、プレイリスト、チャートをグローバルにモニターし、リアルタイムであらゆるアーティストの分析を提供する唯一のSaaSプラットフォーム。全世界中で毎日5億ポイントのデータを処理している。
Web上でアーティスト名、プレイリスト名を検索することでそのアーティストのリスナー数、チャート状況(Apple、Spotify、YouTube、Shazam、iTunes、Deezer)、プレイリスト状況(Spotify/Apple)などを把握することが出来るツールです。一部の国と地域のチャート情報ではTikTokチャート、Instagram Musicチャートも表示。
海外ではユニバーサルミュージック、ワーナーミュージック、ULTRA、Atlantic、BMG、Believe Digital、ソニーATVミュージックパブリッシングなどが利用している。
Soundcharts活用方法

・チャートを見やすく表示
国、ジャンル、サービスごと、その他のパラメータに基づいて、曲・アーティストのチャートを表示。更新頻度と、ランキング数(トップ100、1000、100000)が選択可能。
・リリース後のデータ分析
リアルタイムにリリースされた楽曲を分析できます。週ごと、国やラジオ局ごとのラジオ再生時間など、楽曲のライフサイクルを把握できる。
・広告/PRのチャンス
あなたの楽曲を再生しているラジオ局を確認。世界中のラジオ局もモニターしています。またオンラインメディア上でリリース前後でそのアーティストについて誰がどんなことに言及しているかを、ソース(公式メディアか音楽メディアか)ごとに確認することが可能。ベストなPRタイミングを発見できる。
・オーディエンスを確認
オーディエンスがどこにいるのかを特定。トップの国や都市をSpotify、YouTube、Instagram別に表示、ファンベースがどこにあるのか、年齢、性別など。InstagramAnalyticsの箇所ではさらなるエンゲージメント数を確認。
・Instagramインサイト情報
性別や年齢別にデモグラフィックデータが閲覧可能。最もパフォーマンスが良かった投稿や、使っているハッシュタグのランキングを確認。「いいね」数、コメント数の平均値、フォロワーのうちどれぐらいが熱心なアクションをしているかの数字を表示。
・新たな海外マーケットを特定
あなたのアーティストが海外でチャートインするたびにメール通知を受信することが可能。247カ国をカバーしているため、新たなマーケットでの動きを特定できる。
・現地のパートナーを特定
1,700以上の海外ラジオ局を確認でき、20,000以上のオンラインメディア(音楽、ニュース、ブログ)での言及を閲覧できるため、新たな海外マーケットを発見し、組むべきローカルパートナーを見つけることも可能。
・狙うべきプレイリストを見つける
Spotify、AppleMusic、Deezerプレイリストの履歴にアクセス。プレイリストのフォロワー数、曲のポジションの変遷など確認可能。公式プレイリスト、メジャーレーベル作成のプレイリスト、それ以外の一般的なサードパーティープレイリストでフォロワー順にフィルターをして閲覧することも可能。
・API
追加のプランとしてデータチームのためにSoundchartsAPIの提供プランも。
価格表
毎月(Monthly)ではなく年間(Annually)契約されているユーザー様が1名いる場合、他のチームメンバーでのディスカウントは相談可能。
https://soundcharts.com/pricing

<まずは無料体験から>
Soundcharts:https://soundcharts.com/
Soundcharts 日本語版サイト:https://soundcharts.com/ja
音楽と美容が好きな人。 2020年、音楽専業のデータ分析・デジタルプロモーション・マーケティング会社arneを設立。インディペンデントのアーティストサービス、レコード会社のデジタル事業サポートにつとめる。