ザ・ビートルズのシングル史には、ビートルズ旋風が始まった曲『プリーズ・プリーズ・ミー』、旋風が終えんを迎えた曲『レット・イット・ビー』、その他にも画期的な曲がたくさんあるが、中でも最も重要な曲は、実はこれまで、ビートルズの最高傑作としてはあまり語られてこなかった曲なのである。
いまだに「ただの軽いブルージーな曲だよ」と作者のポール・マッカートニーが謙虚に語る、50年前の1966年の4月中旬に録音され、同年5月30日にリリースされた『ペイパーバック・ライター』こそ、おそらくはビートルズが物事をこれまでにないほどラジカルに変えていこうとする寸前だったことを物語るシングルなのである。
1965年12月に発売されたばかりの『ラバー・ソウル』は、聴衆の耳に衝撃を与え、翌春になってもまだチャートを席巻していた。この何にも似ていないビートルズのアルバム、予想も期待もできなかった作品は、はっきりと新時代の到来を告げていた。ビートルズ中期が始まっていたのである。
フォーク・ミュージックをリズム&ブルースとブレンドするなど、誰も思いつかなかったことだったが、ごく簡単に言ってしまえばビートルズは、マリファナの歪んだトリップ感に素朴なグルーヴを付け足して、これをやってのけたのだ。最も自然なオーガニック・サウンドであり、最も都会的なオーガニック・サウンドでもあった。中期のビートルズ旋風はレベルをワンランク上げてスタートしようとしていたのだ。
この後『リボルバー』が次期ビートルズの完成形になるのだが、その前にあったのが、あなたを『ラバー・ソウル』の世界から、全くの新宇宙に誘う、名刺代わりの気の利いた1曲、『ペイパーバック・ライター』だったのだ。
基本的には作家志望の男についてのショート・ストーリーなのだが、それでも『ペイパーバック・ライター』には出だしからして、どこか別世界を思わせるところがある。曲はポール・マッカートニーの声で始まるが、ほどなくジョン・レノンとジョージ・ハリスンが豊かな対位法で参加し、曲タイトルがキュビスト的な音のかけらに分断されていく。ハリソンのディストーションのかかったギターによるホットでノイジーなリフが始まると、リンゴ・スターの質実なバスドラムの強打が後に続き、ここにさらにマッカートニーの5弦ベースの早弾きがエネルギーを注入し、Aメロへとなだれ込んでいく。
ベース・ギターがこんな音で鳴ったこともこれまでにはなかったことだ。
「ベースの音がこれほどまでの興奮で愛聴されたのは『ペイパーバック・ライター』が初めてのことだった」と、エメリックはマーク・ルイソンの著作『ザ・ビートルズ レコーディング・セッションズ完全版』の中で述べている。「まず手始めに、ポールが新しいベースを持ち込んだ。リッケンバッカーだ。それから我々は、ラウドスピーカーをマイク代わりに使って、さらに音をブーストさせた」
マッカートニーがその時点で比類なき多彩なベース奏法の技術を持っていたこともけしてマイナスにはならなかった。人を素直には褒めようとしないレノンも、マッカートニーは「史上最も革新的なベース・プレイヤーの1人」だと評したほどである。そして、そんな革新が、エネルギッシュで過剰でホットなバンドの枠組みに組み込まれていたのである。
「『ペイパーバック・ライター』は初期の作品と比べてもヘヴィーなサウンドになっている。ヴォーカルワークもとてもよくできていた」とプロデューサーのジョージ・マーティンは語っている。「そんな風に仕上がるようになってきていたということだと思う。この頃には彼らの曲作りで、リズムが最も重要になってきていた」
ビートルズにとってスタジオそのものが1つの重要な楽器になっていた。そしてこの曲は、ビートルズがスタジオという楽器の演奏方法を学んでいて、すでに熟練の味を出している初期の作品なのである。
「ATOCは大きな箱に点滅するランプが付いているもので、まるで一つ目巨人のキュクロプスににらまれているようだった」と『ザ・ビートルズ レコーディング・セッションズ完全版』で説明しているのは、『ペイパーバック・ライター』マスターディスクの録音を担当したトニー・クラークだ。しかしこの"巨人"が『ペイパーバック・ライター』を、あり得ないほどにベースの音圧を高めつつも、レコードプレイヤーの針が飛ばない曲に仕立てたのだった。
歌詞もまた、新しかった。最初のAメロの部分は手紙の形式を取っており、語り手は何年もかけて書いた原稿を売り込もうとしている。我々はだいたいいつも、ビートルズのジョーク王兼言葉の魔術師といえばレノンだと考えているが、この曲のマッカートニーはなかなか健闘している。原稿はリアという名前の男の小説に基づいているという。リアというのは、シェイクスピアのリア王と、スペイン語の"leer"という動詞(読むという意味だ)をもじっている。マッカートニー流のだじゃれだ。
この頃のマッカートニーは、バンドの目利き役として、劇場や映画館に通い、本を読み、対談を楽しみ、カルチャーをあさっていたのだ。
「念頭に置いていたのはペンギン・ブックスのペーパーバックだよ。典型的なやつだね」とマッカートニーはバリー・マイルズの著書『ポール・マッカートニー:メニー・イヤーズ・フロム・ナウ』で語っている。
マッカートニーはこんな風に芸術家気取りでもありながら、一般受けもするのだ。つまり『ペイパーバック・ライター』は他のビートルズの曲と同じく、アヴァンギャルドにもポピュリストにも同じように受け入れられている。
この曲にはまた、ちょっとしたおふざけの余裕もある。当時のイギリスのバンドは 訳知り風のバッキング・ヴォーカルを付けることに凝っていた。ビートルズは『ガール』で「tit tit tit(小娘、小娘、小娘)」と繰り返し歌っているし、当時クラシックのミュージシャンを雇えなかったザ・フーは『クイック・ワン』で、チェロの音が鳴るべきところで「チェロ」という言葉を繰り返していた。そして『ペイパーバック・ライター』では、3度目のAメロでマッカートニーの後ろの男たちが「フレール・ジャック」(訳注:フランスの民謡)と歌っている。
子どもが一緒に歌うようなメロディを、この世のものとは思えぬ演奏の背景にしのばせ、『三文文士』といったもう少しきちんとした小説から取ることもできたはずの出版の夢物語をあわせると、そこにはとても奇妙ですばらしい世界の衝突が起きるのである。
本当にたくさんのことが起きていながら、すべてが見事に調和している。『ペイパーバック・ライター』で、ビートルズは聴く者を宇宙の外に誘っているようである。あるいは少なくとも、平凡な日常からは連れ出そうとしている。




















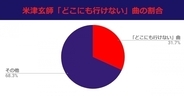







![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








