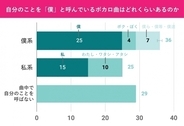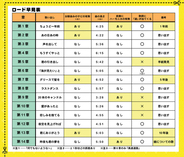クインシー・ジョーンズとの交流から生まれたという彼女のオリジナル曲「The Back」を除けば、収録された楽曲は全てカバー。
今回は本作屈指の「大ネタ」であるボン・ジョヴィの「Livin On A Prayer」をリクエストした、シシド・カフカと桑原の対談が実現。シシドはなぜこのロック名曲を選んだのか、桑原はどのような気持ちでアレンジに取り組んだのか。カバー曲に関してのエピソードはもちろん、ジャンルは違えど同じミュージシャンとして抱える葛藤、課題などについて率直に語り合ってもらった。
【画像を見る】桑原あい×シシド・カフカ 撮り下ろし写真(記事未掲載カットあり:全12点)
─もともとお二人は、どんなふうに知り合ったのですか?
桑原:私は元FRIED PRIDEのshihoさんとよく一緒にライブをしていて。あるときshihoさんから、「今日、カフカさん来てるからあいちゃん挨拶したら?」と言われてお会いしたのが最初です。横浜のMotion Blueでしたよね?
シシド:そう。shihoさんが「カフカさん、あいちゃんのピアノ絶対好きだから」って誘ってくれたんです。それでライブを観て、「なんだこれは!」と(笑)。とにかく力強いんですよ。

Photo by Mitsuru Nishimura
桑原:私がカフカさんを最初に認識したのは、確か図書館(チェコのストラホフ修道院図書館)でドラムを叩いている(プリッツの)CMだったと思うんですけど、そのイメージがずっと離れなくて。お会いした瞬間、「あ、あのシシド・カフカさんだ」って。
シシド:あははは!
桑原:だから、最初にお会いした時は何を話したらいいんだろう……ってなっちゃいました。その後も何度かお話しさせてもらっているんですけど、プライベートなことは聞いたことがなくて。いまだに「朝ご飯とか何を食べてるんだろう、納豆とか食べるのかな?」と思っています。
シシド:納豆は今朝食べてきました(笑)。

Photo by Mitsuru Nishimura
─(笑)そんなカフカさんに、今回はご自身のアルバム『Opera』で1曲リクエストをお願いしたんですよね?
桑原:はい。
シシド:そうだったんだ! 私、ボン・ジョヴィの話をしたことも忘れていました(笑)。
桑原:いい曲ですよね。
シシド:自分は作曲も編曲もしないので、ピアノでカバーするのにどんな曲がいいのかが全くわからなかったんです。3曲くらい候補を挙げたんですけど、中でもボン・ジョヴィは、あいちゃんの力強いピアノにハマるんじゃないかな、ガンガンに弾き倒してくれるんじゃないかなと思って選びました。
桑原:カフカさんの選曲と、山崎育三郎さんの選曲(GReeeeN「星影のエール」)がトップ2で難しかったです(笑)。どちらも自分だったら絶対に選ばない。だって「ソロ・ピアノ・アルバムを作りましょう」「カバーをやりましょう」ときて、「じゃあボン・ジョヴィ」とはならないじゃないですか(笑)。ものすごく挑戦しがいがあったし、やっていて楽しかったんですよね。リリースから1カ月が経ちますが、この曲の反響めちゃめちゃありますし。
シシド:本当ですか? それは良かった(笑)。
─レコーディングは、東京オペラシティ リサイタルホールで行ったそうですね。
桑原:(「Livin On~」は)プレッシャーが凄くて「弾きたくないよ~!」とわあわあ言いながら取り組んでいました(笑)。とにかく最初が肝なんです。左手でリフをキープしながら右手でメロディを弾くんですけど、この部分はmp(メゾピアノ)とp(ピアノ)の間くらいの強さで弾きたかったんです。そうすると、イントロは左手でppp(ピアニッシッシモ)くらいで弾かないといけなくて。しかも機械的には弾きたくなかったから、そのピアニシモの中で抑揚をつけつつ、右手でメロディを立てるっていう。
ピアノって、弱い打鍵で弾くのが一番難しいし体力使うんですよ。逆にff(フォルテッシモ)くらいの方が楽なんですよね。なので、レコーディングの時にテイクを重ねてしまうと弾けなくなっていくし、さらに邪念とかも入ってきそうだったので(笑)、とにかく早めにOKテイクを出さねばというプレッシャーがすごかった。その代わり、テーマを抜けてアドリブに入ったら「ウェーイ!」って弾けました。
「Livin On A Prayer」をピアノで編み直す過程
─実際にカバーする時は、どんなところにこだわりましたか?
桑原:実際にボン・ジョヴィのオリジナル版を聴いてみたら「これぞバンドサウンド!」みたいな感じで。ベースラインも特徴的だし「ピアノ1本に落とし込むにはどうしたらいいんだろう?」って。あのベースラインをそのままピアノで弾くと、ボン・ジョヴィさんに申し訳ないくらい、めちゃくちゃダサくなっちゃうんですよ(笑)。とはいえ、あのベースラインを使わないと「Livin On A Prayer」にはならない。「どうしよう……?」と思っていたときに、16分音符の連打で始まり、ちょっとずつ崩しながらアドリブのところでようやくあのフレーズが出てくるという流れにしたんです。そこのアレンジを思いついたときに「出来る!」と思いましたね。
シシド:それでああいう始まり方だったんですね。
桑原:メロディラインは、原曲を聞いた時から「きれいだな」と思ったし、ピアノで弾いてみても「歌える」旋律だったので。とにかくグルーヴとベースライン、ここを押さえるのが大事なポイントでした。
シシド:「こういう感じできたか!」と思いましたね(笑)。あいちゃんの持つ「力強さ」と「繊細さ」がギュッと凝縮されたアレンジだなと。さっきも話したように、結構ガシガシ弾く感じでくるのかなと勝手に想像していたので、意表を突かれましたし、この曲の新しい魅力を発見しましたね。
桑原:本当ですか?
シシド:うん、めっちゃお酒が進む。
桑原:あははは! やった、褒め言葉だ(笑)。

Photo by Mitsuru Nishimura
─おっしゃるように、あの曲はベースラインがすごく印象的で。その崩すバランスが絶妙だなと思いました。
桑原:編曲って、「曲を編む」って書くじゃないですか。この言葉を作った人すごいなと思うんですよ。私が編曲をする時は、どの曲も原曲が持っている「歌」の部分は絶対に壊したくないというのがあって。でも、楽曲を「編み直す」という感覚で、自分の視点をどこに持っていくか、どの角度から曲を見るかを意識しながらやるようにしているんですよね。
─編集にも「編む」という字が入っているけど、今のお話を聞いて編曲は編集にも似ているなと思いました。桑原さんが「Livin On A Prayer」のどこに感動して、どこを聴かせようとしているのかが伝わってくるような「編み方」だなと。
桑原:ああ、確かに「ここの部分は思い切って切っちゃおう」「ここは際立たせよう」みたいな感覚は編集っぽいかも。原曲をただそのままやればいいというものじゃないですし。ほんと、やっていて楽しかったですね。
楽器との向き合い方、人生の岐路
シシド:このアルバム『Opera』は、あいちゃんのいろいろな面が見える作品ですよね。艶やかな曲もあれば、華やかな曲もあって。もちろん力強さもあったし、一発録りで仕上げていったということにも驚きました。ピアノも打楽器じゃないですか。しかも使っているのは指先で、ドラムとは体力の使い方も神経の研ぎ澄ませ方も全く違うでしょうから、そういうことを想像しながら「やっぱり、この人凄まじいな!」と思って聴いていました。
桑原:わあ、アーティスト目線の感想だ、嬉しい。そんなふうに初めて言われました。
シシド:ピアノって持ち運べないじゃないですか。きっと場所によって相性の良いピアノが置いてあったり、そうじゃなかったりもするんでしょうね?
桑原:そうなんです。あまり言いたくないけど、「ピアノ、かわいそうだなあ」って思っちゃうくらいメンテナンスが行き届いてないところも正直たくさんあるんですよ。でも、観にきてくださるお客さんのことを思うと、ピアノのせいにはできない、ピアニストの中には、ピアノのせいにしちゃう人もいるんですけどね(笑)。でも私は「そこにあるピアノをいかに好きになるか?」を大事にしていて。だからこそ、すごく相性の良いピアノに出会えるとものすごく嬉しいんですよね。
シシド:なるほどね。
桑原:それって、いろんな場所でいろんな人に会う感覚に似ているかも知れないです。世の中にはいろんな人がいて「ちょっとこの人、合わないな」と思ってもいいところを見つけたり、「この人、よく分からないな」と思う人のことを短時間でどれだけ知って、どれだけ良い部分を引き出せるかを考えたり。人と対話している感じに似ています。
シシド:ドラムもそういうところありますね。誰かがものすごくいい音で叩いているドラムを、私が叩いてみたら全然鳴らなかったりして。「ああ、私まだこの子とちゃんと対話ができてないな」って思う。そしたらそのドラマーが「俺も、このドラムとツアーを一周回ってようやくちゃんと鳴るようになったんだよね」って言っていて。
それってチューニング以外の要素もあるんですよね。叩く場所なのか、力加減なのか、その両方なのかも知れない。レコーディングの終盤になって、ようやくちゃんと鳴る時もあります。その場合はイチから再び録り直すことになるんだけど。
桑原:そうなりますよね(笑)。ポン、と叩いたときの鳴りが全然違う時もあるから、録り直さないと全体のバランスがおかしくなっちゃう。

Photo by Mitsuru Nishimura
─楽器に対しての愛情をすごく感じるのですが、それって人との付き合い方にも影響していますか?
桑原:どんなことでも、想像力が大事なのだなと思います。弾く人やメンテナンスの状態で、同じピアノでも全く違ってくるように、人もそれぞれ性格や価値観が全然違うから、自分の価値観を押し付けるのは絶対に違う。たとえ家族であっても他人ですし。やっぱり、「私はこう思っているんだけど」という余白をちゃんと残すようにはしたいです。何に対しても、誰に対しても、頭ごなしには絶対に否定したくないという気持ちはありますね。
実を言うと、昔の私はすごく怒りっぽくて。姉二人によく「昔だったら、こんなことがあったら絶対キレてたよね」なんて言われるんです(笑)。今思うとその頃の自分はすごく疲れていたんですよね。メンバーに対しても「なんでこれ弾けないの?」とか「なんで、ここ練習してこなかったん?」みたいに言ってたんです。「自分の音楽はこうあるべき」みたいな価値観に縛られていて、それを他人にも押し付けていたんですよね。でも、それって自分にも返ってくるので、疲れ果ててしまって曲が書けなくなったりして。

Photo by Mitsuru Nishimura
─そんなことがあったんですね。
桑原:そこからいろんな人と出会ったりしていく中で、すごく価値観が変わったんです。ピアノに対しても優しくなりました。それまではピアノともめちゃくちゃ喧嘩していましたからね。「この子をどうやって鳴らそう?」じゃなくて「私がこんなに頑張ってるんだから、ちゃんと鳴れよ!」って(笑)。でも、人に対してもピアノに対しても向き合い方が変わったら、本当に気持ちが楽になりました。レコーディングの時は、メンバーを信じると決めたし。
そうやって、自分を変化させてくれてありがとうという考え方に変わりました。そういう意味でも、人に対して、音楽に対して、ピアノに対しての考え方は、全部一緒に変化していっている気がします。カフカさんは、そういうターニングポイントみたいなものはありましたか?
カフカ:そうだなあ……髪を切った時ですかね。
桑原:え、それはいつですか?(笑)
シシド:2015年だったかな。とにかくそれまでの自分が、四角四面の考え方をしていたというか。あいちゃんじゃないけど、「こうじゃなきゃダメだ」みたいなこだわりがすごく強くて。慣れない事柄に対していつも憤りを感じていたし、自分に対しても憤りを感じていたんですよね。そういうのを手放したくなって。それで髪を切ったらものすごく心が楽になって、失恋して髪を切る人の気持ちも分かりましたね。
そこからいろんなことに対し、力を抜いて俯瞰で見ることの大切さ。「できないなら仕方ない、じゃあどうする?」というふうに発想を転換させたい。「やりたいこと」「できること」「向いていること」は全部違うし、それに対して納得できていなかった自分もいたのですが、そこに対してちゃんと「受け入れる」ことも出来るようになっていきましたね。本当に楽になったし、そこからよく笑うようにもなりました(笑)。
桑原:なるほど、髪の毛って大事ですよね。
シシド:そう、大事。でも実は髪をまた伸ばそうとしているので、性格もまた固くなっていくかもしれない!(笑)
二人が語る「スランプ」と「挑戦」
─以前のインタビューで桑原さんは、「非日常ではなく、日常に感じるちょっとした心の揺れなどを曲にしていく方が、人に寄り添える音楽が書ける」というふうに気持ちを切り替えた時期があったと聞きました。
桑原:そうなんです。「自分自身、こう生きていたい」みたいなアーティスト像を掲げていると、超苦しくないですか?
シシド:苦しかったです。
桑原:私、それこそマイケル・ジャクソンみたいな、生活感が全くない人が真のアーティストだと思ってしまっていて。そういう理想を追い求めすぎてしまっていた時期があったんですよね。曲を書くときには3週間くらい人に会わず、日の光が入らない場所でひたすら作業するみたいな。
シシド:ええ!? そこまで自分を追い込むのはすごいね。
桑原:そうやって出てくるものこそ「芸術」だと思っていたんです。時期が5年くらいあって。でも、あるときプツンと曲が書けなくなってしまって。

Photo by Mitsuru Nishimura
─そんなときにクインシー・ジョーンズと出会ったのが、今作に収録されたオリジナル曲「The Back」を作るきっかけになったとか。
桑原:モントルージャズフェスのコンペティションに、日本人代表で出演が決まった時があったんですけど(2015年)、ちょうどスランプ真っ只中だったので、スイスまで行くかどうするか迷っていたんですよ。自信もないし「1位を獲って帰らないと、みんなに見放されるんじゃないか?」とまで思い詰めていて(笑)。そういう精神状態なので、向こうでもずっと泣いてたんですよね。で、出番10分前くらいに舞台袖に行ったらそこにクインシーがいたんですよ。「演奏を見にきたよ」って言ってくれたんです。
その時点で「うわあ、クインシーだ!」ってなるわけですよ。メンタル崩壊してるので、号泣してしまったんですよね。そしたらクインシーが、「賞なんてどうでもいいから今の君の演奏をしてきなさい」って。その言葉に勇気づけられて、ステージ上で思い切り即興したら持ち時間をオーバーしちゃって、結局コンペは失格したんです(笑)。でもクインシーからは、今の演奏はすごくジャズだったし音楽だったしゴージャスだった。あなたに足りないものは何もない。生きるだけだ」と言ってもらえて。
シシド:わあ、クインシーにそんなこと言ってもらえたら嬉しいよね。
桑原:それで少し話をして、帰っていくクインシーの背中を見ているときに「今、曲を書かないと後悔する!」と思ったんです。それで帰りの飛行機の中で書いたのがこの曲なんですよね。そのおかげでスランプからも抜け出すことができて。
シシド:そうだったんだ。だからタイトルが「The Back」(背中)なんだね。
桑原:そうなんです。今でもその時の背中を、映像として鮮明に覚えているんですよね。クインシーに会っていなかったら音楽辞めていたかも、と思うくらい落ち込んでいたから、本当に彼には感謝しています。カフカさんは、そういうスランプってありましたか?
シシド:スランプしかないです。
桑原:ええー?
シシド:(笑)私は作詞をするんですけど、パパッと書けたことなんてほとんどないですし、それこそいつも苦しみながら書いていますね。出来上がったものに対しても「自分に才能がある」とは思えなくて。ただ、自分はドラム&ボーカルという形にはもはや囚われてはいなくて、何かしらの形で「音楽」をずっと続けてはいくのだろうなと思っているのですが。
─ハンドサインを学びにアルゼンチンへ留学してサンティアゴ・バスケスに師事したのも、その考えのもと?
シシド:それこそ縁もあったし興味もあって、そういう行動を起こしたというのもあるけど、納得できるレベルまで到達できているか?と言われたら、まだ探っている途中ですし。そういった意味では、達成感みたいなものはまだ一つもないかも知れない。ずっと納得できるものを探して回っているのかも知れないですね。もちろん、「叩いて歌う」ということに対するアイデンティティは感じていますし、そこは細く長く続けていきたいことだとは思いますが。
「el tempo」はシシド・カフカがコンダクターとして100種以上のハンド・サインを駆使し、バンドの即興演奏をディレクションするプロジェクト。動画は2020年10月に開催されたブルーノート東京公演のダイジェスト。
桑原:最近はどんなことに挑戦していますか?
シシド:コロナ禍に「時間ができた、これはチャンスだ」と思って作曲を始めてみました。やってみると、やっぱり難しくて。「まずは和音とか理解するところからだな」と思って、YouTubeで調べて鍵盤の押さえ方から始めていますね(笑)。
桑原:ほんとですか? すごい……。
シシド:また忙しくなってきて、最近は疎かになりがちなんですけど、でもちゃんと続けていきたいことの一つです。
桑原:いつでも弾きますよ!
シシド:本当に? 嬉しい。でもその前にあいちゃんをel tempoに呼びたいんだよね。
桑原:私、el tempoめちゃめちゃ興味があったんですよ。ぜひ誘ってください!

桑原あい
『Opera』
発売中
https://jazz.lnk.to/AiKuwabara_OperaPR