
『72年間のTOKYO、鈴木慶一の記憶』宗像明将・著 株式会社blueprint・刊
生い立ちと音楽の目覚め
ー『72年間のTOKYO、鈴木慶一の記憶』によると、慶一さんは大家族のなかで育ったそうですね。社長をしていて一家の大黒柱だった厳格な祖父。役者の父親、社交的な母親、そして、親戚達とひとつ屋根の下で暮らしている様子は、まるでイタリア映画みたいです。大人たちに囲まれて育ったことが、慶一さんに影響を与えているのでしょうか。
慶一:いつも言ってるけどそうだね。年上のいとこからいろんなことを教わったから、同世代の子供達よりも先に文学とか映画とか音楽に触れる機会が多かった。小学校に入るくらいに親戚の叔母さんに連れられて『二十四時間の情事』を観に行ったりしてね。
ーそういえば、ムーンライダーズに「24時間の情事」という曲がありますね。
慶一:あの映画に原爆のシーンが出てくるんだよ。そこで実際の映像が使われていて、それが子供心に衝撃でね。30歳過ぎるまで、もう一度観られなかった。叔母さんが(主演をしていた)岡田英次のファンだったから観に行ったんだけど驚いていたと思うな。
ーあと、お祖父さんが新しいもの好きで、新しい電化製品が出るとすぐに買われていたとか。テクノロジーに対する興味は、慶一さんに通じるところがあると思いました。ムーンライダーズもいち早くシンセやコンピューターを音楽に取り入れていましたし。
慶一:ラジオ、テレビ、ステレオ、テープレコーダー、そういうものが、いち早く家にあったことは大きいね。ずっと、家でそういうものをいじっていて。子供の頃から宅録をしてたから、ギターを弾くようになってもバンドをやろうとは思わなかったんだ。私が中1の頃、弟(ムーンライダーズのメンバーの鈴木博文)が、転地療養で全寮制の養護学園に2年半くらい行くんだよ。
ー母親から買ってもらったギターも弾き放題。
慶一:エレキギターにフォークギター。あと、ハイハットだけ買ってもらったりね。よく買ってくれたと思うよ。エレキなんて、当時は大卒の初任給くらいしたんじゃないかな。そういう点では恵まれていたね。お袋は私が音楽をやったらいいんじゃないかと思っていたのかもしれない。
ーご両親が劇団で知り合ったということもあって、芸能ごとに理解がある家庭だったのでしょうか。
慶一:そうだね。
鈴木慶一が見た日本語ロック黎明期
ー宅録で曲作りをしていた少年時代。そして、高校卒業後にあがた森魚さんとの運命的な出会いをして、あがたさんが自主制作をした『蓄音盤』を手伝ったことをきっかけに音楽の道に進んでいく。
慶一:家で宅録の研究をしていたことが『蓄音盤』で役に立つわけだ。
ーあがたさんと一緒に都心に頻繁に出るようになったことも大きな変化だったそうですね。『72年間のTOKYO、鈴木慶一の記憶』によると、渋谷や新宿といった都心と慶一さんが生まれ育った羽田とでは文化圏が随分違っていたとか。
慶一:家から都心に出るまで1時間くらいかかるから、滅多に出かけることはなかった。お袋の実家が武蔵野の方にあって、お袋と一緒に実家に行った帰りに一度だけ新宿に寄ったことがあるんだ。68年くらいだったと思う。アングラ・ブームで新宿が大変なことになっているって聞いていたから、新宿で途中下車したんだよ。
ー『72年間のTOKYO、鈴木慶一の記憶』に書かれている、慶一さんから見た当時の音楽シーンがとても興味深かったです。頭脳警察、遠藤賢司といったアーティストが日本語でロックをやろうとしていた。それを目の当たりにした慶一さんは「早く自分も日本語ロックを書かないと」と焦ってはちみつぱいを結成する。日本語で歌う、ということが重要だったんですね。
慶一:69~70年くらいに頭脳警察やエンケンをテレビで見て衝撃を受けたんだ。あがたくんも斉藤哲夫さんも日本語だった。そして、はっぴいえんどが出てくる。関西フォークが出てきたのも大きいね。
ーロックにどんな言葉を乗せるのか、何を歌うのか、というのは大きな問題だったわけですね。
慶一:歌詞で何を扱うのか、ということはサウンド以上に考えたね。(はちみつぱいの1stアルバム)『センチメンタル通り』が完成する直前まで歌詞をいじっていた。ビートルズにしろ、(ボブ・)ディランにしろ、ザ・バンドにしろ、曲を聴くだけではなく、歌詞を何度も読んでた。ロビー・ロバートソン(ザ・バンド)のストーリーテリングには本当にやられたね。本にも出てくる(マザーズ・オブ・インヴェンションの)『フリーク・アウト!』は聴くまで3日かかったけど、その間、ずっと歌詞カードを読んでたんだよ。日本のアーティストで歌詞に影響を受けたのは、友部正人、松本隆、高田渡の3人だな。
ー当時、自分が書く歌詞で意識していたことは何ですか?
慶一:はちみつぱいを結成した時、すでにはっぴいえんどは活動していて、(松本)隆さんは山手線の内側の風景を描いていた。私は羽田で、あがたくんは京急の上大岡に住んでいた。
ーはっぴいえんどに対抗心を燃やしていたわけですね。
慶一:絶対違うことをやろうって思ってたね。サウンドも、歌詞も。もうすでに出来上がった音楽をなぞってもしかたがない。巨大な存在感だったし。最初から大きく違ったのは酒だよ。彼らは酒は飲まないけど、俺たちは酒浸りだった。
ー『センチメンタル通り』のジャケットが物語ってますね(笑)。
慶一:あれは本当に酔いつぶれてるからね(笑)。
ムーンライダーズが変化し続けてきた理由
ーはちみつぱい解散後、76年に慶一さんはソロ・アルバム『火の玉ボーイ』を発表します。同じ年にあがたさんは『日本少年』、細野さんは『泰安洋行』を発表。それぞれ傑作ですが、共通するのはコンセプチュアルな作品であること。架空の世界を描き、そこにいろんな音楽性を織りまぜることでオリジナルな世界観を模索しています。
慶一:その架空さというのが当時の最先端だったのかもね。それまではアメリカの音楽をなぞってきたわけじゃない? 「日本のグレイトフルデッド」とかさ。そうじゃなくて、自分たちで面白い世界を作ろうと思うようになった。
ー自分たちで面白い世界を作る、という延長線上にムーンライダーズがあったわけですね。ムーンライダーズは、ブリティッシュ・ロック、モダン・ポップ、プログレ、パンク、ニュー・ウェイヴなど、作品ごとにその時代の最先端の音楽を取り入れて変化していきます。常に新しいサウンドを取り入れる、というのはバンドを結成した時に心掛けていたことなのでしょうか。
慶一:バンドを結成する時に決めていたのは、作詞も作曲もできる、そして、歌も歌えるメンバーがいっぱいいるバンドにしたいということだった。そういう人たちを集めてみたら、みんな演奏が器用でどんなサウンドも弾くことができた。変化に柔軟に対応することができたんだ。
ーテクノが注目を集めた時、慶一さんと同世代のアーティストの間では意見が分かれました。シンセの音色を軽薄に感じて嫌うミュージシャンのほうが多かった。そんななかで、ムーンライダーズのメンバーは誰一人反対せずに、新しいサウンドに飛び込んでいく。全然違うタイプの曲を書くメンバーが集まっていながら、この足並みの揃い方は見事ですね。
慶一:次々と新しいものに興味をもち、それを器用にこなせるのが6人の資質だった。私個人のことでいうと、生まれ育った羽田の東糀谷という場所は、時代とともにどんどん風景が変わっていくんだよ。子供の頃は田んぼもあったんだけど、それが工場だらけになり、工場がなくなるとアパート。今ではマンションが建ち並んでいる。時代に蹂躙される土地で、住民はその変化を受け入れている。そうでない人たちは引っ越す。
ー常に変化する場所、というのは実に東京的ですね。はっぴいえんどは東京の原風景をノスタルジックに歌いましたが、ムーンライダーズは東京のごとく変化していった。
慶一:過剰な変化だよね。いま、渋谷が再開発で変わったことに文句を言う人がいるけど、私は全然平気。道がわかりにくくなったけど、それは把握すればいいだけだから。
ー変化し続けるから完成しない。完成しないから常に新しい、というのが、ムーンライダーズの音楽なのかもしれません。
慶一:メンバーの誰もムーンライダーズのサウンドを完成させようとは思ってなかったんじゃいかな。1曲1曲、アルバム1枚ごとの完成度は目指すけど、重要なのは「今を作る」ことだった。自分たちが面白いと思うものを作り続ける。そういう場所を確保するために活動を続けていた。
ーそんなムーンライダーズの活動を振り返ると、慶一さんが好きな詩人、ジャン・コクトーが残した「美よりも速く走れ」という言葉を思い出します。
慶一:コクトーは名言を残したね。だからこそ、コクトーは映画も作るし、舞台もやるし、詩人では収まらない。
ー常に新しい美を追求していたコクトーは「いかなる革命も、3日目から堕落が始まる」とも言っています。ムーンライダーズは作品ごとに革命を企てるバンドでした。
慶一:新しいものを取り入れる、というのは自然にやっていたことだったけど、前のアルバムとは違うものを作ろう、という気持ちはメンバー全員が口に出さず意識していたと思うな。
レジェンドよりも、ひねくれ者でありたい
ーそんな攻めの姿勢を崩さずに、よく半世紀近くもバンドが続けられたと思います。『72年間のTOKYO、鈴木慶一の記憶』には2011年に無期限活動休止を宣言した経緯も書かれていますが、東日本大震災という大事件に遭遇しながらも、新しい作品を生み出すことに限界がきてしまった?
慶一:毎回、新しいコンセプトでアルバムを作ることに疲れ果てたんだろうね。もうこれ以上、何も出ないぞ、と。ミーティングで無期限活動休止の話をした時に誰も反対しなかった。無理をしながらアルバムを作ることに嫌気がしていたのかもしれない。そこで次のアルバム(『Ciao!』)のコンセプトを「最後のアルバム」にすると決めたことで急にみんな元気が出たんだよ。
ー創作に疲れ果てながらも、元気になるきっかけが創作というのもムーンライダーズらしいですね。『72年間のTOKYO、鈴木慶一の記憶』のなかで、慶一さんは「はちみつぱいは自分がリーダーじゃなくて、みんなのバンドだ」とおっしゃっていますが、恐らくムーンライダーズもそうですよね。慶一さんにとってバンドというのはどういう集団なのでしょうか。
慶一:これは岡田君(ムーンライダーズの岡田徹)が言っていたことなんだけど、バンドっていうのは互助会なんだよ。小さく固まって、お互いに助け合う。いろんな人が集まって巨大になるとろくなことがない。一度、ムーンライダーズを会社化したことがあったけど、それで多額の借金を抱え込んだりして大変なことになってしまった。今はその都度集まる小さな会社だ。
ー借金の件は本に赤裸々に語られていましたね。小さな会社、あるいは町工場、そんな親しみやすいサイズ感が今のムーンライダーズにはあっているような気がします。
慶一:曲を作っている時に、メンバーがお互いにアイデアを出し合う。そのことで曲のクオリティがワンランク上がるんだよ。そういう瞬間にワクワクさせられる。それがあるからバンドを続けていられるんだ。仲間から良いアイデアをもらえるっていうのは最高の楽しみだね。
ームーンライダーズは22年に11年ぶりの新作『it's the moooonriders』を発表して再始動。今年、No Lie-Senseは活動10周年を記念して新作『Twisted Globe』とベスト盤『Slightly Better Than No Lie-Sense』を発表しました。これまでに慶一さんは、THE BEATNIKS、P.K.O、Controversial Sparkなど様々なユニットやバンドを結成。その一方で、映画や舞台の音楽、CM音楽もやれてきて、とにかく膨大な仕事量です。いろんな仕事をやること、その振り幅が慶一さんにとって大切なのでしょうか。
慶一:そうだね。その振り幅を広くするのか、狭くするのかは、その都度考えている。ムーンライダーズをやっているだけで安定した日々を送れていたら、また違っていたかもしれない。でも、それはそれで早いうちにバンドを解散していたかもしれないな。ヒット曲がないことを逆手にとって、いろんなことをやってきたから。
ーもし、ロック一筋で半世紀やっていたら、日本のロック界のレジェンドになっていたかもしれませんね。
慶一:レジェンドなんて言われるのはごめんだね(笑)。
ーそういう性格だから、メインストリームから逸脱し続け、ひねくれ続けて今に至る(笑)。『It's the moooonriders』に収録された「私は愚民」を聴いて、慶一さんはレジェンドになるより、「丘の上の愚か者(Fool on the Hill)」でいることを選んだんだと思いました。
慶一:そうそう。バカだったからよかったんだよ(笑)。バカな奴がバカなことをやるのをレコード会社が許してくれた。ヒット曲は出さないかもしれないけど、なんか面白いこと、新しいことをやってる奴がいる。そういう奴を、そういうバンドを、ひとつくらいレーベルに置いといた方が良いじゃないか、と思ってくれる人がいたことに感謝しないとね。

『72年間のTOKYO、鈴木慶一の記憶』
発売中
詳細:https://blueprint.co.jp/lp/suzuki-keiichi-no-kioku/
著者:宗像明将
価格:3,300円(税込価格/本体3,000円)
出版社:株式会社blueprint
判型/頁数:四六判ソフトカバー/336頁
ISBN:978-4-909852-47-2
<目次>
1章:1951年ー1974年
■東京都大田区東糀谷、大家族暮らし
■母親が見抜いた音楽の才能
■「日本語のロック」への目覚め
■あがた森魚、はっぴいえんどとの出会いが変える運命
■バックバンドから独立したバンド、はちみつぱいへ
■混乱したライヴ現場での頭脳警察との遭遇
■風都市の終焉と、はちみつぱい解散
2章:1975年ー1983年
■ムーンライダーズの「最初の日」
■『火の玉ボーイ』鈴木慶一の曖昧なソロの船出
■椎名和夫の脱退、白井良明の加入
■ムーンライダーズとYMO
■鈴木慶一とCM音楽
■『カメラ=万年筆』で幕を閉じる日本クラウン期
■高橋幸宏とのTHE BEATNIKS、ロンドンで受けた刺激
■『マニア・マニエラ』屈指の傑作にして発売中止
■『青空百景』のポップ路線と、広がる若手との接点
3章:1984年ー1990年
■『アマチュア・アカデミー』以降の数百時間に及ぶREC
■ムーンライダーズ10周年~『DON'T TRUST OVER THIRTY』
■ムーンライダーズ約5年にわたる沈黙へ 消耗する神経
■メトロトロン・レコード設立~KERAとの初コラボレーション
■鈴木慶一、はちみつぱいとの「決着」
■鈴木慶一と『MOTHER』
■鈴木慶一と映画音楽
4章:1991年ー1999年
■ムーンライダーズを復活へと導いた岡田徹のバンド愛
■40代にして初の公式ソロアルバム『SUZUKI白書』
■鈴木慶一と90年代前半の雑誌/テレビ
■『A.O.R.』と大瀧詠一が残した言葉
■ムーンライダーズ・オフィスを巡る借金問題
■兄弟ユニットTHE SUZUKI~『MOTHER2 ギーグの逆襲』
■移籍を繰り返してもつきまとう『マニア・マニエラ』の亡霊
■鈴木慶一と岩井俊二、Piggy 6 Oh! Oh!
■ムーンライダーズ20周年 ファンハウス時代の音楽性の多様さ
■鈴木慶一と演劇
■先行リミックス、無料配信……作品発表スタイルの模索
5章:2000年ー2008年
■宅録の進化がムーンライダーズに与えた影響
■『Dire Morons TRIBUNE』以降のバンド内での役割
■鈴木慶一と北野武、映画音楽仕事の充実
■新事務所、moonriders divisionの誕生
■夏秋文尚の合流~『MOON OVER the ROSEBUD』
■鈴木慶一とcero、曽我部恵一
6章:2009年ー2021年
■高まり続ける映像やサウンドへのこだわり
■ムーンライダーズと「東京」
■鈴木慶一と『アウトレイジ』
■激動の2011年、ムーンライダーズの無期限活動休止
■Controversial Spark、No Lie-Sense始動
■かしぶち哲郎との別れ
■『龍三と七人の子分たち』~ムジカ・ピッコリーノ
■鈴木慶一45周年 はちみつぱい・ムーンライダーズ再集結
■中国映画、アニメ映画音楽への挑戦
■コロナ禍に迎えた鈴木慶一音楽活動50周年
7章:2022年ー2023年
■新体制での『It's the moooonriders』
■鈴木慶一とPANTA
■鈴木慶一と高橋幸宏
■岡田徹との別れ
■バンドキャリア半世紀近くに取り組んだインプロ作品
■鈴木慶一と大滝詠一
■一つずつ叶えていく「死ぬまでにやりたいことシリーズ」
8章:鈴木慶一について知っている七の事柄
鈴木慶一年表(1951年ー2023年)
参考文献
あとがき



















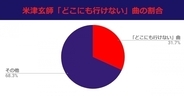


![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








