ただ、少なからず判明していることもある。どうやらこのデュオにとって、「次に何が起こるかわからない」というのは重要なファクターであるようだ。NY・ブルックリン在住のマルチ奏者でありポップユニットのブランチ・ブランチ・ブランチをはじめ多数のプロジェクトに関わってきたザック・フィリップスと、ベルギー・ブリュッセル在住のボーカリストであるマ・クレマン。我々は二人の引き起こす化学反応に振り回され、いつの間にか魅了されてしまう。
それぞれのローカルシーンとも密接に関わり、2021年に最初のアルバム『Gods Trashmen Sent to Right the Mess』をリリース。その翌年にはステレオラブのツアーに招かれるなど、同業からの評価も高い。また最新作『Rong Weicknes』では、3パターンのライブ録音からなるコラージュによってアレンジを行うという「live in triplicate」なる手法を取り入れるなど、悪戯っぽい野心も保たれたままだ。
そんな「次に何が起こるかわからない」デュオが8月27日(水)と28日(木)に初の来日公演を開催。会場はなんとブルーノート東京だ。当日はかねてより親交のあるMaher Shalal Hash Bazの工藤冬里を招くなど、ますます予測不能。今回はザックとマの二人にインタビューを敢行、即興的な側面からデュオの身体に流れる哲学に迫った。
出会いは完全なるアクシデント
―まず最初に、このプロジェクトが始動した経緯を教えてください。
ザック:完全なるアクシデントだったんだよ、たまたま出会ったんだ。でも僕たちは偶然の出来事を受け入れて、その上にさらなる偶然を重ねていった。今もそうさ、僕たちはアクシデントを含んだ計画ばかり立てている。
マ:本当にそう、言えてるね。
ザック:例えば「Hit Me Now」なんかは、マと出会ってから10日以内に録った曲なんだ。僕らが最初に録音したテイクのひとつだね。そんな感じで、本当に偶然始まったプロジェクトなんだ。
「Hit Me Now」(『Gods Trashmen Sent to Right the Mess』収録)
―その時のお互いの印象は覚えていますか?
マ:うーん。私は一緒にいて楽しかったけど、自分たちが何をしているのか全くわかってなかった(笑)。
―(笑)。
マ:私は「音楽を作る」って行為をしたことがなかったから、リハーサルから録音まで何もかもが初めての体験で、とにかく新鮮だった。
ザック:僕はシンガーと曲を作り上げていくのが好きなんだ。
しかも、それって単なる「歌の上手さ」に関係したことじゃなくて、彼女が作品全体に宿らせるエートスに拠るものなんだ。結局、誰かの演奏を聴いたときに「何をやっているか」ということではなく、「なぜそれをやっているのか」とか「なぜそれが重要なのか」っていうのを伝達できるかが大切なんだよね。
―ザックはニューヨークのブルックリンが拠点ですよね。どのようにして周囲のコミュニティと関わってきたんですか?
ザック:僕はブリュッセルにいたこともあるし、その前はバーモントのブラトルボロにいて……あそこは「都市」とは言えないかもね(苦笑)。それでブルックリンには12年くらい住んでいるよ。
ニューヨークは東京みたいに大きな街だから、色んなことが毎日のように起きている。ただその中でも、DIYコミュニティは微々たる存在なんだ。僕らは今でも地元のリソースに頼ってるし、整頓されてないやり方で活動できているのはコミュニティに支えられているおかげなんだ。「公式っぽく」動き出したのは本当に最近だね。根本的には、ファイベル・イズ・グロークはローカルの一員であり、同時に様々な場所からの影響が入り混じった「トランス・ローカル」でもある。
マ:そうそう。
―マはファイベル・イズ・グロークを始める前からブリュッセルのシーンとは繋がりがあったんですか?
マ:いや、誰とも関わってなかった。本当に、全く音楽活動をやってなくて。ファイベル・イズ・グロークを始めてから地元のコミュニティと繋がりができたんだよね。
ザック:そうそう。今のマはララ・ハンバート(Lara Humbert)とかアリス・ジョージ・ペレスとか素晴らしいミュージシャンと一緒に活動をしているし、他にも沢山のプロジェクトに囲まれているよね。
―ではシンガーとして活動する上で、どのような人物から影響を受け取って今の活動に至ったのでしょうか?
マ:ここ数年で一番大きかったのは、ルース・ガルバスのライブを観たこと。自分の中の何かが永遠に変わったと思う。ライブ中に彼女はリスキーな歌い方をするんだけど、そのリスクが「危険」には感じられず、むしろ楽曲を探求しているような余裕さえある。しかも彼女が歌うのを止めるのは完璧に「そこしかない」っていうタイミングで、そこで演奏が終わるんだよね。真の意味での「遊び人」だと思う。
ザック:今の話で思い出したんだけど、前にMaher Shalal Hash Bazの(工藤)冬里の昔のインタビューについてマと話したことがあるんだよね。彼はそこで「ミュージシャンを料理の材料のように扱うべきじゃない」と語っていた。つまり、自分がコックと見立てた場合、ミュージシャンを器や具材のように扱うのは避けるべきだと。
―ほう。
ザック:このアイデアは他者との接し方のみならず、演奏を行う自分たちの内面にも通じてることなんじゃないのかな。ルース・ガルバスは声を単なる「楽器」として使っているんじゃなくて、自分の全てを出てくるものに落とし込んでいる。それが「歌っているもの」なんだ。これはマにも言えることなんだけど、表現行為が断片的じゃなくて包括的なんだよね。
重要なのは誤解、混乱、サプライズ
―さらに興味深い点として、あなたたちはオンラインで楽曲制作を進めるのではなく、ブリュッセルもしくはブリュッセルにお互いが赴いた際に楽曲制作を行うとお聞きしました。ある意味でアナログな制作スタイルですが、その利点はなんですか?
マ:ファイベル・イズ・グロークにとっては、そのやり方が最適だと思う。というのも、私たちはとにかく会話をしながら制作をしていて、お互いの言葉に対する反応から曲が生まれることがほとんどだから、オンラインでは成立しないんだよね。もちろん誤解はしょっちゅう生まれるんだけど(笑)、そのアクシデントが音楽を書くきっかけになるんだよね。
ザック:例えばオンラインで制作してたら、「こういうのが良さそう」とか「こういうのが好きかも」みたいなアイデアを起点に作ることになると思うんだよね。ファイベル・イズ・グロークに当てはめると、僕がマの好きそうなものを用意して、それに対してマが僕の好みに合う要素を重ねて……みたいな。でも、僕たちがやりたいのはそういうことじゃない。オフラインの制作はもっとダイナミックで、偶然や誤解を歓迎しつつ、それらを創造的に使うことができる。そしてそのことに没入できる。それがすごく刺激的なんだ。何日もぶっ続けで一つの音楽に集中していると、個人としての境界線をちょっと超えてしまうときもあって(笑)。
マ:そうそう(笑)。だから楽しいんだよね。
ザック:二人で尋常じゃない混乱を共有するんだ、それが楽しい(笑)。
―ファイベル・イズ・グロークはその即興性から、ジャズ・プロジェクトとして解釈されることもありますよね。そういったジャンルを熱心に追っていたことはありますか?
マ:ジャズに触れたのは最近で、一緒に曲を書き始めるまで聞いたことはなかったかな。
ザック:僕もジャズを積極的に聞くようになったのはここ数年だよ。ファイベル・イズ・グロークに参加してくれるメンバーを通じてコンテンポラリー・ジャズに触れるようになったんだ。最近だとポール・コーニッシュの新しいアルバムが良かったね。彼はLAのピアニストで、ノウワーなんかとも一緒に演奏してたりするんだ。ファイベル・イズ・グロークにも参加してくれたトム・ギルとも共演している。
ジャズ・ミュージシャンと共演するたびに思うんだけど、彼らはハーモニーや理論を用いた即興演奏のエキスパートなんだ。知識があって、色んなアプローチを即座に試せて、しかも自分なりの個性を音楽に反映できる。そういう演奏家を求めているなら、ジャズ・ミュージシャンと組むのが一番良いに決まってる。彼らは本当に努力してるし、みんな自分の楽器とものすごく深い関係を築いてるんだ。
―なるほど。
ザック:でも、ジャズそのものが僕らの直接的な影響源かというと、そうでもない。例えばジョニ・ミッチェルは完全に独学で自分のサウンドを構築して、そのアプローチもすごく独特なんだけど、同時にものすごく明確なスタイルを持ってる。彼女は一時期ジャズ・ミュージシャンを自分のバンドに起用していて、それに見事にフィットしていたよね。バンドは彼女に新しい何かを教えたはずだし、彼女もまたバンドにとって興味深いフレームワークを提供していたように思える。僕らとジャズの関係もそういうものでありたいね。
―個人的に、「即興演奏」と聞くと浮かぶイメージはプレイヤー同士が腕を競い合ってバトルするような構図なんです(笑)。ファイベル・イズ・グロークからはそれとは真逆の軽快さを感じます。どういった要素が独特の雰囲気を生んでいるとお考えですか?
ザック:真っ先に浮かんだのは「遊び心(Playful)」っていう言葉かな。
マ:あとは「楽しんでる(Enjoying)」ってこととか。素っ気なく聞こえたらごめんね(笑)。
ザック:そもそも、ユーモアのない音楽っていうのがピンとこないんだよね。それが二人の共通点のひとつだと思う。君が言ってくれたような競争的なマインドセットは、往々にしてシリアスな音楽を生みだす傾向があるよね。もちろん、僕たちだって自分たちの音楽には本気で向き合ってはいる。でも、僕らには「軽やかさ(Levity)」が必要なんだ。それは空気のようなもので、欠かすことはできない。
僕たちにとって重要なのは偶然であり、誤解であり、混乱であり、そしてサプライズなんだ。面白いものが生まれたときも「自分たちは天才なんだ」とは思わない。ただ「うまくいったな」とか「ラッキーだったね」って思うだけ。曲作りやレコーディングに入るときも先入観を持たずに「この曲をどうしたいのか?」とか「一緒に演奏するミュージシャンは何を求めてるのか?」みたいな問いかけから始めるようにしてるんだよね。そこに競争みたいなものが入り込む余地は全くない。そもそも、人生はそんなことをするには短すぎる。
―例えば最新作『Rong Weicknes』では「live in triplicate」というライブ演奏のコラージュからなる手法を取っていましたし、その前の作品も一発録音ですよね。ライブにおいてアクシデントを呼び込むために即興を取り入れるのはまだしも、それを録音物として固定するためには一定の審美眼が必要だと思うんです。どういうテイクを「良し」とするのか、その基準はなんですか?
ザック:それは直感的に判断しているんだ。「これだ!」っていうのは、自然とわかるんだよね。僕たちはもっと新しいことをやりたいから、オーバーダブをもっと積極的に試してみたり、『Rong Weicknes』のようにバンド演奏の上にさらにバンド演奏を重ねて録るようなやり方をまた探るかもしれない。ただまぁ、ギリギリまでどうなるかわかんないだろうけど(笑)。
マ:それはそう(笑)。「live in triplicate」もレコーディングの直前に決まったよね。ザックがエンジニアに「こういうことできる?」って聞いたら、ちょうどスタジオにそれを試せる空きチャンネルがひとつだけあって、それで「じゃあやろう」って。
ザック:『Rong Weicknes』の制作は本当にチャレンジングだった。仕上げの段階ではかなり細かく編集していて、その部分に関しては録音・ミックス・マスタリングを手がけたエンジニアのスティーブ・ヴィーリーの貢献が大きいと思うよ。
―収録曲の中でも「As Above So Below」はMVも含めとりわけ印象的でした。どういったプロセスから生まれた曲だったのでしょうか?
ザック:確かこの部屋(ブルックリンの自宅)で書いたんだよ。ドラムマシンとループを使ってね。
マ:そうだそうだ! 昨日ちょうどアナトールとシルヴァン(※)と一緒に、あの曲のデモを聴いたところだった。
※アナトール・ダミアン(Ba)とシルヴァン・ハーネン(Gt)、Fievel来日公演のバンドメンバー
ザック:Drumdropsからサンプリングして、それをAudacity(オーディオソフト)に貼り付けてピアノでセッションしたんだ。最初にサビがそれで出来たから、後から他のセクションを作っていったんだ。僕たちにとっては珍しい作り方だったね。
マ:うん。パズルみたいにパーツを動かしながら「これがサビにふさわしいかも」とか「このメロディーは使わないな」とか、そんな感じ。
ザック:「As Above So Below」と「Transparent」はそういう作り方だったね。そのときに「これは新しい手法だな」って思ったんだ。普段はセッションで直線的に作っていくから、「As Above So Below」をきっかけにパーツを動かすやり方を試すようになったんだ。
奇才デュオがブルーノート東京で演奏する意味
―また「Love Weapon」はブランチ・ブランチ・ブランチのバージョンよりも少しテンポを落として、より腰を据えて聞けるようなアレンジに変更されていますね。ある意味で二つのプロジェクトの違いを表すような差異だと思うのですが、どういった経緯で再び録音することになったのでしょうか?
ザック:そうだね……「Love Weapon」をファイベル・イズ・グロークで最初に一緒に演奏したのは2019年だった。でも、そのときは録音が上手くいかなかったんだ。ブランチ・ブランチ・ブランチは僕と親友のサラ・スミスでやっていたバンドなんだけど、あの頃の音楽って「自分のものだ」っていう感覚があまりないんだよね。かなり前に作ったものだし、今はちょっと距離を置いて外から見ているような感じ。そもそも2010年に書いた曲だしね。だから15年分の年月が堆積していると思うし、それを再解釈できたからファイベル・イズ・グロークでもカバーしたんだ。
―ありがとうございます。最後にブルーノート東京での来日公演についても教えてください。「ブルーノート」と聞くと伝統的なジャズの殿堂というイメージを抱きがちですが、偶然や驚きを受け入れるスタンスの二人がそのような舞台に立つというのが興味深くて。
マ:うん、私たちも同じように考えてた(笑)。
―(笑)。
ザック:ブルーノートで演奏するのは本当に光栄だし、名誉なこと。それに、2025年だからこそ、こういうことが起こりえたんだと思うんだ。つまり、ブルーノートのような歴史ある場所や機関にも、文化を横断する理解が育ってきている。ジャンルの境界だって明確じゃないよね。結局、僕たちは「音楽」という同じ井戸から水を汲んでいるだけなんだ。
ブルーノートからの招聘は「君たちの音楽にはジャズの系譜に通じる統合的な要素が感じられる。それをウチの空間で探求してほしい」っていう、そんな手を差し伸べてもらったように感じているよ。ありがたいことだし、その期待に応えられるよう頑張りたい。それで実際どうなるかは……もちろんまだわからない(笑)。
―(笑)。セットリストもまだ決めていないんですか?
マ:新曲を披露することになると思う、それが一番楽しみかな。もちろん昔の曲もやる予定。
ザック:カバーはしないんだっけ?
マ:今回はそうだね。私たちのライブではちょっと珍しいかも。
ザック:でもさ、マに聴いてほしいルー・リードの曲があってさ……。後で共有するけど、それをやるのはアリかもね。
それはさておき、今回は6人編成での来日になるよ。僕とマに加えて、ずっと一緒にやってるドラマーのギャスパー・シックス、ギタリストのシルヴァン・ハーネン、それから『Flaming Swords』とか未発表のセッションでも演奏しているベーシストのアナトール・ダミアン、そして管楽器奏者のアンドレ・サカルソトも参加する。しかも(工藤)冬里も一緒に演奏してくれる予定で、もしかするとMaher Shalal Hash Bazのメンバーも加わるかも。冬里もルー・リードをカバーしたらすごく喜ぶと思うな……うん、良いアイデアかも。
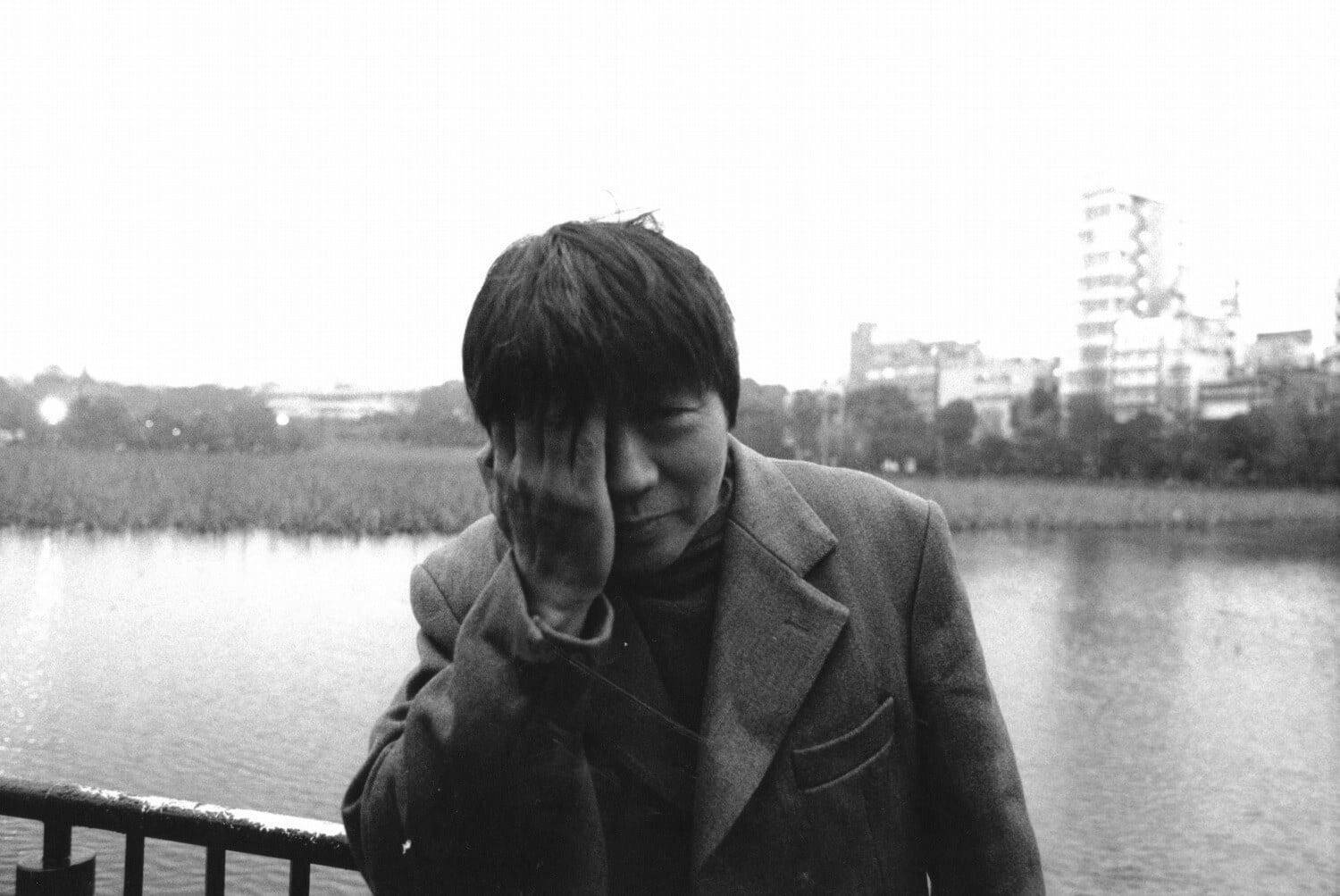
工藤冬里 [Maher Shalal Hash Baz]
ファイベル・イズ・グローク来日公演
2025年8月27日(水)・28日(木)ブルーノート東京
1stステージ:Open 17:00 / Start 18:00
2ndステージ:Open 19:45 / Start 20:30
ミュージックチャージ:¥8,800(税込)
公演詳細・チケット購入:https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/fievel-is-glauque/
〈メンバー〉
ザック・フィリップス(p,key)
マ・クレマン(vo)
ギャスパー・シックス(ds)
アナトール・ダミアン(b)
シルヴァン・ハーネン(g)
アンドレ・サカルソト(sax,fl)
Guest:工藤冬里 [Maher Shalal Hash Baz] ※8.27のみ
※ゲストの工藤冬里は両日出演予定でしたが、アーティスト都合により8.27 wed.のみの出演となりました。













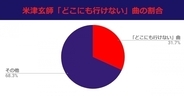





![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)








