生涯現役、笑いの点と点が繋がる特別対談
『笑点』で視聴者を笑わせ続けてきた落語家・林家木久扇(86歳)。坂上二郎とのコンビ「コント55号」で日本中を笑いの渦に巻き込んだコメディアン・萩本欽一(82歳)。奇しくも芸歴64年目のレジェンドが初の対談。
木久扇が落語の世界に足を踏み入れたのと、萩本がコメディアンとしての第一歩を踏み出したのは、奇しくも同じ年だった。それから64年、お互いに相手を意識し続けてきたが、じっくり話すのは初めてである。笑いというフィールドで闘ってきた同志であり、競い合ってきたライバルでもある2人が、積年の思いをぶつけ合う。(1回目/全4回)
──これまでに、お二人が番組で共演したことは?
木久扇:50年近く前になりますが、木久蔵時代に『欽ドン』に呼んでもらいました。
萩本:ちょっと待って、先生はやめて。私が後輩なんだから。こっちは「仙人」って呼びたくなっちゃう。
木久扇:では、欽ちゃんで。
萩本:覚えてます。しばらくしてから「なに?」って。
木久扇:そんな調子で、何度も「やり直し」と言われて、6回やりました。最後は、片岡千恵蔵さんの口調で「スモウでテレビがケツかいてやがるぜぃ」って言ったら、欽ちゃんがあ然としたんです。大ウケでしたね。
萩本:たぶん6回とも放送したと思う。あの番組は、お笑いのプロの人に来てもらうことは珍しかったけど、飛ぶ鳥を落とす勢いの木久蔵さんに、ぜひ出てほしかったんですよね。
木久扇:もう一回、NHKの番組でご一緒した記憶があります。
萩本:そっちは覚えてない。そう言ったってことは、仲良くなりたかったのかな。
バカとマヌケは似てるようで違う?

木久扇:バカとマヌケは、ちょっと違う気がしますね。
萩本:私の中では、全然違います。マヌケっていうのは、庭の草木に水をやっている途中に雨が降ってきても、そのままのんびり水をやり続けるみたいなこと。「もうやらなくていいや」とは思わない。
木久扇:ぼくが考えるバカは、孫に「今月分だよ」って、封筒にお金を入れてお小遣いをあげて、また次の日も同じ封筒を用意して、「あれ、もうあげたっけな?」と思いながら、またあげちゃうようなことかな。
萩本:バカって、言葉の響きが強いじゃない。「このバカ」と言われると、すごく怒られてる気がする。
──あまりにも深いお話で違いをつかみ切れませんでしたが、どちらも「人生を楽に生きる秘訣」ということですね。
木久扇:そうなんです。たぶんマヌケも同じだと思いますけど、勝ち負けとか自己嫌悪とか恨みつらみとか、そういうこととは無縁でいられます。
萩本:マヌケも、そのへんとは無縁ですね。あと、マヌケだと周囲の人に「こいつ、なんか助けてやりたい」と思ってもらえる。私はマヌケだったおかげで、劇場をクビにならずにコメディアンになれました。
──今日、こうしてお二人に対談してもらうにあたって、それぞれの笑いに対する強い思いがぶつかって、バチバチ火花が散ったらどうしようと、少しビクビクしていました。
萩本:そういうことで火花を散らすのは、お利口さんがやることです。バカとマヌケの私たちが話しても、ぶつかりようがない。だけど、あらためて聞いてみようかな。木久扇師匠、あなたは笑いをどういうものだと考えますか?
木久扇:たとえば、椅子が2つあるとしますよね。片方は木だけでできている椅子で、片方はクッションがついている贅沢な椅子で、「どうぞ」と勧められてどっちに座りたいかといえば、ふかふかのほうがいい。そのスプリングの役が笑いだと思うんです。人生の座り心地をよくしてくれるというか。
萩本:うわー、ちゃんとした答えが返ってきちゃった。私は、笑いっていうのは、生活の中で一番いらないものだと思ってる。笑いがなくても、生きていくうえでは何も困らない。でも、「あったほうがいいかもね」ってところに、自分の笑いがあるって考えてます。
木久扇:「あったほうがいいかもね」って、ちょっと遠慮がちなところがいいですね。
萩本:「あったほうがいいよ」って自信を持って勧めるのは、違う気がする。まして「ないとダメ」なんて、恥ずかしくて口が裂けても言えません。
落語とコメディ、うらやましい点

木久扇:落語は、登場人物の役を全部自分がやっちゃう。楽といえば楽なんですけど、自分の力量を超えた展開にはなりません。その点、コメディは相手役がありますよね。欽ちゃんの場合は、坂上二郎さんとコント55号を結成したことで、笑いの枠が大きく広がった。そういうのは、いいなと思いますね。
萩本:二郎さんは、いちばん組みたくない人だったんです。浅草の舞台で何度か一緒になって、とにかくツッコミがしつこい。二郎さんに一緒にやろうと言われて、「試しに一回か二回やってみる感じでどう」なんて逃げ腰で言ってた。だけど、ウケたもんだからそのままコンビになっちゃったんです。
木久扇:むしろ二郎さんに、見る目があったってことですね。
萩本:落語でうらやましいのは、やっぱり歴史の積み重ねがあるところかな。着物の人が高座で話し始めると、誰もが「さぁ笑おう」っていう心構えになる。コメディだと、新しいことをすればするほど、見てる人が「さぁ笑おう」にたどり着くまでに時間がかかっちゃう。
──萩本さんは『笑点』をよくご覧になっているとか。
萩本:そう、木久扇さんのボケが見たくてね。13年前に二郎さんが亡くなって、芸を見せてくれるボケの人がいなくなったなと寂しく思ってたら、『笑点』にいたんですよ。
木久扇:そんなふうにおっしゃっていただいて恐縮です。
まだまだバカやマヌケの大切さを伝えていかないといけない

萩本:実際の師匠のお気持ちはわからないけど、円楽さん(六代目三遊亭円楽)がいなくなってからは、ちゃんといじってもらってない。だから、ちょっと寂しそうに見えたかな。自分だったらこうツッコむのにって、もどかしい場面がよくあった。俺を出してくんないかなぁと思ってたけど、声がかかんないからさ。
木久扇:そういうわけではないですけど、だんだんしんどくなってきちゃって。バカだからやめ時がわからなくて長くやっちゃいましたけど、おかみさん(妻)が「そろそろいいんじゃない」と言ってくれたんです。
萩本:師匠が『笑点』から卒業したら、学校のイジメが今以上に増えちゃうかもしれない。だって、バカのすごさを示してくれている人がいなくなったら、誰かの欠点やダメなところは「バカにしていい」としか思わなくなるでしょ。
木久扇:となると、ぼくも欽ちゃんも、まだまだバカやマヌケの大切さを伝えていかないといけませんね。
萩本:半年ぐらいしたら、司会で復帰してほしいな。いよいよ体がしんどくなったら、横に布団敷いて寝てるだけでもいいから。お前らは座布団だけど、俺は布団だって。
木久扇:ハハハ、いいですね。寝転がって、「面白くないよ」なんてブツブツ言ってる。
萩本:私も3週間に一回ぐらいずつ、舞台の右から左にすーっと歩いていく。師匠に手を振ったりなんかしながら。
木久扇:欽ちゃんがいつ登場するかわからなくて、視聴率が上がっちゃうかもしれない。
萩本:お互い、まだまだ暴れましょう。跳んだりはねたりはしなくていいけど。
(1回目/全4回)
Kikuou Hayashiya
1937年、東京・日本橋生まれ。高校卒業後、食品会社を経て、漫画家・清水崑の書生となる。1960年、三代目桂三木助に入門し、翌年、八代目林家正蔵門下へ。1982年「全国ラーメン党」を結成。3月末、約55年務めた『笑点』の大喜利レギュラーメンバーを”卒業”する
Kinichi Hagimoto
1941年、東京・下谷生まれ。高校卒業後、浅草の東洋劇場に。1966年に坂上二郎と「コント55号」を結成。1980年代には『欽ちゃんのどこまでやるの!』など、手がけた番組が軒並み高視聴率を叩き出し「視聴率100%男」と呼ばれた。多くの番組で司会者としても活躍
取材・文/石原壮一郎 撮影/ヤナガワゴーッ!
―[インタビュー連載『エッジな人々』]―


















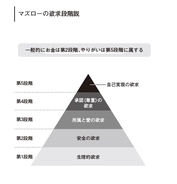






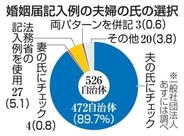



![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)

![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークアイボリー/ホワイト RYST5040H(AIV/WH2) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41bUm2zOxIL._SL500_.jpg)






