
今夏の甲子園大会では送りバントの数はここ15年間で最多となった。しかし、プロ野球解説者の宮本慎也氏は、今では送りバントをしない方が得点確率は上がると解説している。
宮本慎也氏の最新刊『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』より一部抜粋・再構成してお届けする。
送りバントは本当に手堅い作戦?
序盤に大量得点を狙う場合、どうしても気になってしまうのが「送りバント」の有効性ではないでしょうか。「序盤に大量得点を狙うのが正しい」としても、「先取点を取って優位に試合を進めたい」という考えも大きなウエートを占めるからです。
先取点のメリットはあります。特にチームの監督は、先取点が入るといろいろな戦術を実行しやすくなります。1点ビハインドや同点でスチールやエンドランをかけて失敗すると目立ちますが、リードしている状況なら目立ちにくいものです。
1点を先制すれば、大胆な戦術を実行しやすくなり、そこから大量得点を狙っていけるという考え方もできるでしょう。
観ているファンの目線に立ってください。勝っている状況なら積極的に動いても楽しめますが、負けている状況で動いて失敗するとダメージを大きく感じ「余計なことをするな」と思うのではないでしょうか。
ではここで、無死一塁という状況に限定し、送りバントをして得点が入る確率と送りバントをしないで得点が入る確率を調べてみました。日本球界全体の平均で、2022年の記録から3年前までを遡ってみたデータがあります。
今では送りバントをしない方が得点確率は上がることをご存じの方が多いでしょう。
「大量得点を狙う」も「先取点が欲しい」も、送りバントをしない方が確率は上がります。
その理由を推測してみました。送りバントをすると一塁が空きます。そうなると、相手バッテリーは「歩かせてもいい」と考える状況ができます。特に僅差の試合で終盤にもなれば、そういう攻めが多くなります。「カウントが悪くなれば、無理をして勝負しない」となるわけです。厳しいコースだけを狙って勝負できるわけですから、バッターにとっては厄介です。
送りバントはそれほど効率のいい戦術ではない
では、ここで2020年から2024年までの5年間のペナントレースで、アウトカウントに関係なく、一塁に走者が出ている場合と二塁に走者が出ている場合。
さらに一、三塁に走者が出ている場合と二、三塁に走者が出ている場合とで、バッターの打率とOPSを出してみました。
OPSとは「On-base plus slugging」の略で出塁率と長打率を足し合わせた値。打席当たりの総合的な打撃貢献度を表し、数値が高いほど、打席当たりでのチームの得点増に貢献する打者と評価されます。
さて、データを見ると予想通りの結果ですが、皆さんの予想はいかがだったでしょう?走者が一塁と二塁で比べると、すべての打率は走者が二塁(一塁が空いているケース)の方が低くなります。OPSは2020年だけ、一塁に走者がいるときの方が高いですが、それ以外の年は打率と逆です。やはり一塁が空いていればバッテリーに「歩かせてもいい」という意識が働き、打率は低くなりますが、四球による出塁率が高くなり、OPSは上がるということです。
データを見ても一、三塁と二、三塁を比べると2021年以外の年は、一塁に走者がいる一、三塁の方の打率が高くなっています。OPSも2023年以外は、一塁が空いている二、三塁が高くなっています。送りバントで相手チームに1アウトをやり、わざわざヒットが出にくい状況をつくっているわけです。四球で出れば再び一塁が走者で埋まり、打率は上がりますが、送りバントはそれほど効率のいい戦術ではないということが分かるでしょう。
一塁が空いている状況で強打者を打席に迎えると、「中途半端になるのが一番よくない。ベンチから勝負なら勝負、歩かせるなら歩かせると指示を明確にした方がいい」と解説する人がいます。
完全に否定するつもりはありません。
もちろん、ピッチャーのタイプや状況、バッターの調子や格などによっても違います。プロのピッチャーでもストライクが投げられなくなる場合はあります。それでも完全にボールゾーンに投げろというのであれば、今の私にも投げられるし、その辺にいる人でもボールゾーンには投げられます。
落合博満もバレンティンも一塁が空いた状況を嫌がった
プロのピッチャーならば、どうしてもストライクゾーンで勝負したくない場合や、際どいところに投げて甘くなる確率がありそうな場合は、ボールゾーンにバッターが思わず手を出してしまうボールを投げればいいのです。プロというより、1軍のマウンドに上がるピッチャーであれば、それぐらいのことはできるレベルは持っていて当たり前だと思っています。
先ほど述べたように、特に強打者は一塁が空いている状況で臭いところを突いて勝負されるのは厄介だという話をしました。日本球界で三冠王を三度獲得した落合博満さんも、走者一塁から盗塁して一塁が空いた状況で勝負されるのを嫌がっていたと聞いています。ヤクルトで60ホーマーを記録したウラディミール・バレンティンも嫌がっていました。それだけ「歩かせてもいい」と開き直って投げてくるピッチャーは嫌なものなのです。
私なりに「それでも送りバントをした方がいい」という状況も考えてみました。
ひとつは、明らかにヒットも打てないし、四球も選べそうもないバッターに無死一塁で打席が回ってきたときです。セ・リーグはDH制がないため、絶対ではありませんが、投手に打席が回ってきたときなどは、送りバントをさせた方がいいと思います。
もうひとつは、僅差の得点差で試合終盤に無死一塁になったときです。このケースでは、守る側も極度のプレッシャーがかかります。当然、送りバントが成功すれば走者は得点圏に進みます。僅差の試合終盤ならば、そのプレッシャーは強く、得点が入らなくても「疲れさせる」というメリットがあります。
「そんなことでプロが疲れるの?」と言う人がいるでしょう。しかしこのような状況では、私でも自分のところに「打球が飛んでくるな」と思います。それが積み重なれば、疲労感はたまっていきます。長いペナントレースでは、蓄積疲労でケガをする確率が上がります。
特に効果があるのは、短期決戦です。日本シリーズだけでも疲れますが、クライマックスシリーズがあります。メジャーでも短期決戦のポストシーズンでは、送りバントや進塁打などの自己犠牲を伴う戦術が多くなります。「相手が嫌がることをしろ」というのは、勝つために必要です。
「送りバントをしていなかったら、もっと打てていたのに」に対して宮本の回答は?
確率からいうと、無死一塁からの送りバントは「手堅い作戦」ではないのです。しかし、時と場合によっては完全否定することもできないということが分かってもらえたと思います。
個人的な「送りバント」の話をします。自慢するつもりはまったくないのですが、私は通算408犠打で歴代3位の“送りバント男”でした。1シーズン67犠打の日本記録も持っています。2000本安打を達成している選手の中で、300犠打以上している選手はいません。
テレビや雑誌、イベントなどで私を紹介する場面でも、犠打記録が披露されます。いわば送りバントは私の「代名詞」のようなものです。しかし正直に言うと「恥ずかしい」という気持ちになってしまうのです。
私の中で「送りバント」は、プロで生き残るために仕方なくやっていたものです。打てないから送りバントのサインを出されると思っていました。とはいえ、いい加減にやっていたわけではありません。生き残るために必死にやっていたことだけは付け加えておきます。
みんなからは「送りバントをしていなかったら、もっと打てていたのにな」と労われることもありますが、それは違うと思っています。当時、小技がうまくなければレギュラーにはなれなかったし、多くの試合には出られなかったでしょう。
野球教室などで子供たちに「宮本さんのようなプレーヤーになりたい」と言われることがあります。親御さんから聞いたのでしょうが、そんなときは「そんなスケールの小さなプレーヤーを目指すな。ホームランバッターを目指しなさい」と言い続けています。幼いときから自分の限界を決めていたら、もっと高いレベルの野球にはついていけなくなるからです。
送りバントはしない方がいい。送りバントは打てない選手がやるもの。こう言うと「お前が言うな!」という突っ込みがあるでしょう。そんな突っ込みは、この先も私が死ぬまで潔く、甘んじて受け止めようと思っています。
文/宮本慎也
『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』(PHP研究所)
宮本慎也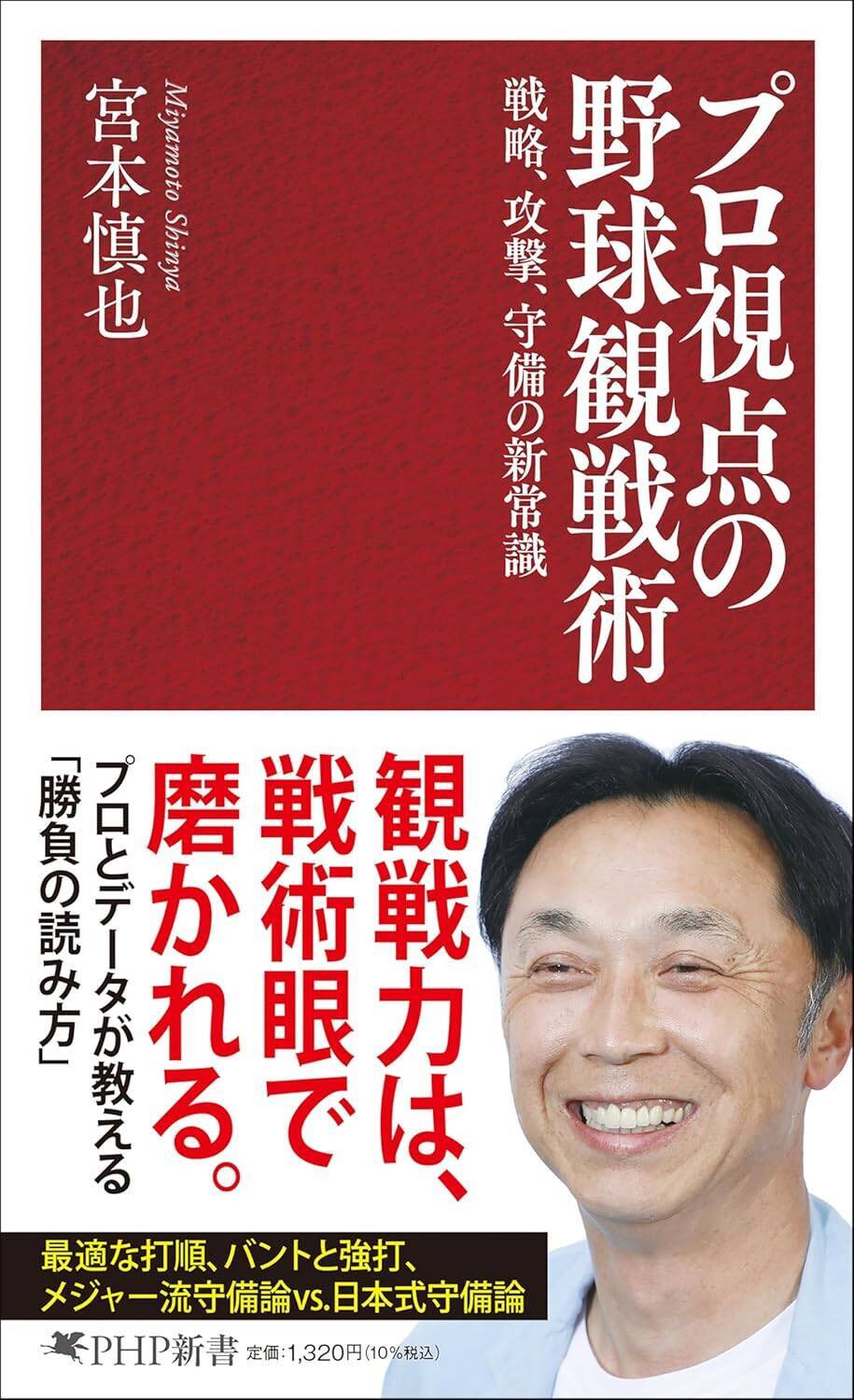
著者は、通算2133安打・408犠打を記録し、10度のゴールデングラブ賞を受賞。堅実な守備と高い戦術理解度で長年チームを支え、WBC(2006)では世界一メンバー、2008年北京五輪では日本代表主将を務めた。現役引退後はNHKの野球解説者として活動しながら、学生野球の指導にも力を注いでいる。
こうした豊富な実績と経験に、現代のデータ分析を融合させ、本書では「戦略としての野球」に本格的に切り込む。著者は、個々のプレー技術を論じるだけではなく、チーム全体をどう設計し、どのような方針で試合に臨むかという“戦略”と、実際の試合中にどんな判断を下すかという“戦術”の両面を精緻に考察している。
たとえば、バントや打順の構成における旧来の常識は、もはや「思考停止」と言わざるを得ない。著者は、試合展開に応じたバントの是非、最強打者の打順の合理性、得点を奪うための起用と配置など、試合の局面ごとの具体的な戦術判断についても、理論と実例をもとに詳しく解説している。
そして、日本野球が世界と戦う上で進むべき方向性として、従来の「緻密な野球」ではなく、「パワーベースボール」をまずは志向すべきと説く。打力・身体能力を活かす選手育成、柔軟なポジション編成、徹底したデータ活用を通じて、国際舞台でも勝てる新たなチームづくりが求められている、と説く
技術論にとどまらず、大局的な戦略と実際の試合での戦術を見通す本書は、ファンのみならず、選手、指導者にとっても必読の内容である。「観戦力は戦術眼で磨かれる」――。データとプロの経験が導く「勝負の読み方」は、野球という競技の理解を一段と深めてくれるだろう。新たな観戦の地平を切り拓く、新時代の野球論の決定版である。

























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


