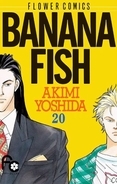「わたしを離さないで」第8話は、カズオ・イシグロの原作『わたしを離さないで』第19章の1部にあたる短い箇所を拡げた回だった。
過去の行き違いについて、互いを許す雰囲気が生まれたのが前回第7話だった。第8話ではさらに美和の気持ちが掘り下げられた。その結果生まれた穏やかな日々と、恭子との別れを描くが主眼となった回だったのである。冒頭に引用したのは、そうした時間について恭子が触れた言葉だ(話し相手になるのは、別の提供者である加藤。演じる柄本佑は2004年の「世界の中心で、愛を叫ぶ」以来12年ぶりの綾瀬との共演になる。
どこをとっても無駄がない
回る走馬灯というべきか、貼り雑ぜ屏風というべきか。
今回使われたのは、コラージュの技法である。過去7話分のカットを抜き出し、恭子と美和の会話の合間合間に挿入していく後半部の展開は圧巻であった。「陽光学苑編」で子供時代の恭子(鈴木梨央・演)が変顔をしてみせた場面のように、まさかあれも使われるのか、というようなピースが次々に登場し、視聴者の頭の中にイメージを形作っていく。
ピースの中でも特に意表をつかれたのは土井友彦(原作のトミー。三浦春馬・演)が、美和が大事なことを言った瞬間におならをしたことだ。「陽光学苑編」で美術の時間に友彦が、「これは現代アートです」と言い張っておならをして見せた場面にこれは対応している。原作にはないおならのエピソードがわざわざ挿入されたのはそのためだったか、と感服したものである。親の叱言と茄子の花は千に一つも無駄がないと言うが、ドラマの構成の緊密さを実感した瞬間だった。
もう1つ。第8話の最後に恭子がついに友彦と結ばれる場面があった。このときのカットは恭子の位置が上である。第4話でブラウン・コテージの先輩・浩介(井上芳雄・演)と同様のことがあったときには、恭子が下だった。この違いはおそらく、恭子の意思を反映したものなのではないか。恭子が主体的に行動することを決めた後の場面だから、受け身の姿勢ではないのだ。
表情って大事
前々回に書いたように、ドラマ版「わたしを離さないで」が原作と大きく異なるのは、キャラクターに重きが置かれている点である。役者の演技にプロットと同等の価値があり、ストーリーを前に推進させる働きをする。物語の鍵を握っていたのは美和なので、彼女を演じる水川あさみはあえて視聴者に憎まれるような演技を多用していた。前回、恭子との会話の後で浮かべた微笑もそうなのだが、今回はそれ以上に過去回では見せなかった表情を出していた。美和だけではなく、前半で陽光学苑の跡地を訪れた3人が、なんということのない話題を口にしながら笑う場面も、その表情が強く印象に残ったのである。
第6話が放送された時点で、恭子が子供時代の自分にそっくりな少女に出会うことが予告されていた。少女がどんな存在なのかは視聴者も薄々感づいていたのではないかと思うが、あの表情は予測していなかったのではないか。
「みんなおとなしすぎる。話しかける大人がいないと、こうなるのかな」
陽光学苑の跡地はHOMEと呼ばれる施設に変わっていた。建物の荒廃ぶりもそうだが、いちばん驚かされたのは、そこで暮らす子供たちがみな無表情だったことだ。鈴木梨央の演じる少女も凍った表情の中に怯えのようなものを浮かべていた(少女たちを乗せて走り去った車がどこへ向かったのかはわからないが、おそらくは考えたくもない未来が待っているのだろう)。そこが一切の人格が認められない場所であるということを、彼女の表情が物語っていた。
再び陽光学苑へ
すでに陽光学苑はこの世になく、子供たちを統率する存在だった神川恵美子(原作のエミリ先生。麻生佑未・演)も老いの隠せない姿になっていた。次回、第9話では恭子たちが彼女と再会することになるのだろう。
ドラマが始まったばかりのとき、陽光学苑はたまらなく偽善的な雰囲気をまとった場所に見えた。「心を表現する」「あなたたちは天使なのです」といった言葉の数々が、醜い現実を覆い隠すものと聞こえたからだ。そこに現実への批評性も感じた。ところが第8話で、そうした虚飾の部分には別の意味が見え始めた。美和の提供を通じて、価値の逆転が生じたのである。となれば第9話以降も、思わぬ展開が待っているのではないか。陽光学苑の謎がいよいよ明かされようとしている。
(杉江松恋)