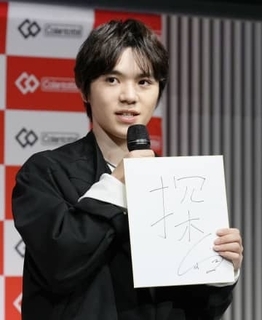1996年3月にプレイステーション用ソフトとして発売された初代『バイオハザード』。
洋館に閉じ込められた主人公が迫り来るゾンビと戦い抜くのが目的であり、「サバイバルホラー」という新ジャンルを開拓した、ゲーム史に残るエポック・メイキングな作品である。
ハリウッドでの映画化だけでも偉業なのに、シリーズ化して新作が出るたび世界的な大ヒットを記録。アミューズメントパークでのアトラクションも定番化している。
ゲームを遊ばない層にもその認知は絶大だろう。
斬新な設定から多くのフォロワーが登場
そもそも、それまでの映画やゲームにおけるゾンビはザコキャラ的位置づけが基本。そして、「なぜゾンビになったのか?」は重要ではなかった。
しかし、このゲームでのゾンビは「T-ウィルス」によって変異した生物兵器であり、舞台となる洋館はその実験場だったという設定は画期的だった。
このゲームの大ヒットを受け、ゾンビの地位は向上(?)。
90年代後期以降、映画やゲーム、漫画の世界にゾンビを題材としたものが、まさに「T-ウィルス」のように爆発的に拡散したのである。
ホラー映画の世界に迷い込んだような臨場感を体験
この『バイオハザード』を初めてプレイした時の衝撃は忘れられない。
とにかく怖い! 怖すぎる!
随所に、「初見殺しの罠」が散りばめられており、曲がり角の先に……扉の向こうに……何かがいる!?という不安をあおられまくり。
ゾンビ犬が窓をブチ破って登場したときには、本気で声を上げて驚いたものである。
倒したゾンビが画面から消えることなく、横たわったままなのも斬新だった。「再び起き上がるのでは……」と思わずにはいられないのだ。
純日本製なのに、キャラクターたちはあえて英語で会話し、映画のような日本語字幕が流れる点も画期的。まさにハリウッドのホラー映画を観ているような感覚だ。
銃を撃つと薬莢(やっきょう)が飛び出し、床に落ちて音がするまでを再現するなど、ディテールにもこだわり抜いており、BGMや効果音も「静」と「動」の緩急が実に巧み。
もはや、映画を観ているどころか、映画の世界にさまよい込んだかのような臨場感である。
しかし、これだけのクオリティを誇りながらも、開発当時はまったく期待されていなかったという。
やむを得ず生まれた「ラジコン操作法」が生んだ恐怖と緊張感
製作元のカプコンでは、1991年に登場したアーケードゲーム『ストリートファイター2』がメガヒット。これを受け、1990年代中期も新作のリリースや、家庭用ゲーム機への移植が中枢を担う一大プロジェクトとなっていた。
必然的にベテランクリエイターたちはそちらに集中。なので、『バイオハザード』には新人クリエイターが集結し、プレステ用オリジナルゲームの実験作のひとつとして開発が始まっている。
経験不足のまま挑むカプコン初のハード、しかも初の3Dゲームだ。技術的にも困難をきわめたという。
そのため、本来はプレイヤーの目から見た「主観視点」を予定していたが、グラフィックを含めたハードの制約から「三人称視点の固定カメラ型」になった。
しかし、これこそが『バイオハザード』大ヒットの分岐点だろう。
固定カメラ視点だからこそ、ゾンビが死角から現れるショック演出が生まれ、また、ラジコンのような独自の操作法にせざるを得なかったのである。
この操作法に戸惑った方は多かったはず。なにしろ、主人公キャラは右ボタンで時計回りに回転、左ボタンで反時計回りに回転する。オールドゲーマーにはファミコンの『バンゲリングベイ』で味わったようなもどかしさだ。
逃げたいのに逃げられない。銃を当てたいのに当たらない。
しかし、思うように操作できない不自由さがプレイヤーを焦らせ、より恐怖を倍増させる。まさに、ゲームの要となる独自の操作法となった。
また、プログラムの読み込みに必要なロード時間を、ドアを開ける際にした点もナイス。
主観視点のアニメーション演出になっており、プレイヤーは待ち時間を感じるどころか、不気味に開くドアの先に待ち受ける恐怖をあおられるわけだ。
マイナス要因をプラスに転換させる逆転の発想が、独自のゲーム性を生んだのである。
『バイオハザード』の原点はホラー映画モチーフのファミコンソフトにあり

『バイオハザード』は、1989年12月にファミコンで発売された『スウィートホーム』がベースとなっていることをご存知だろうか。
同年1月に公開された同名のホラー映画がモチーフになっているのだが、これが当時としては珠玉のクオリティ。
ジャンルとしては、呪われた洋館からの脱出を目的としたRPGになる。そして、日本製ホラーゲームの元祖といえるだろう。
演出やBGMなど、随所におどろおどろしさが満載。死んだ仲間は絶対に生き返らないし、回復アイテムも非常に少ない。キャラクターは武器以外の道具は2つしか持てないなど、シビアなゲーム性も緊張感と絶望感をあおりまくった。
映画の世界観が上手に盛り込まれているうえに、映画よりもむしろ怖い仕上がりと、もっぱらの評判だった名作だ。
ゲームの目的はもちろん、回復やアイテムの保持数に制限があることや、プレイヤーキャラのショッキングな死亡シーン、ドアが開く際の演出など、類似点は多く、確かにルーツとなっていることがうかがえる。
当然、ファミコンのスペックではできないことも多く、グラフィック面を含め、製作陣はこの『スウィートホーム』でやりきれなかったことを『バイオハザード』にぶつけたという。
このゲームといえば、CMが凄まじかったことも思い出される。
ゲーム画面とともに、映画でのショッキングな場面がてんこ盛りであり、屈指のトラウマシーンである「下半身を失った古舘伊知郎(カメラマン役)が床を這いずり回る姿」まで流してしまう始末。子どもに向けた口調の明るいナレーションと凄惨な場面のギャップが、逆にものすごく怖かったものだ。
加山雄三&鈴木史朗のオールドゲーマーも熱狂!
初代『バイオハザード』の斬新なゲーム内容は多くの著名人のファンも生んでいる。
バイオの話題で必ず名前が上がる芸能人といえば、加山雄三とフリーアナウンサーの鈴木史朗が筆頭だろう。
2人とも『スペースインベーダー』時代からの古参ゲーマーであるが、特にバイオがお気に入りで、シリーズはもれなくやり込むほどのどハマりっぷり。
加山は専用の大型モニターまで購入し、地方公演の合間の息抜きに楽しんでいるなど、初代当時から大ファンであることを公言。クリアタイムが早いどころか、ナイフのみでクリアという達人レベルの腕前を誇るから凄い。
鈴木は『さんまのSUPERからくりTV』の忘年会でプレステを貰い、続いて娘さんから初代バイオをプレゼントされたことがきっかけだとか。
こちらも、腕もやり込み度も相当なもの。
「ゲームで前後左右に気を配るでしょ。だから車の運転が上達したんです」と、バイオのやりすぎで反射神経がよくなったと語る。
ジョジョの荒木先生もハマっていたッ!
また、『ジョジョの奇妙な冒険』の荒木飛呂彦先生も当時ハマっていた模様。少年ジャンプの作者コメントでは、何度かバイオの話題を出している。
「鳥嶋編集長から『バイオハザード』の攻略本をもらったが、見なきゃよかった!」(1996年37・38合併号)
「『バイオハザード2』ついに発売されるそうですが本当にうれしい。首を長くして待っていました!!」(1998年4・5合併号)
ホラー映画も大好きとあってツボだったのだろう。腕前も気になるところだ。
NHK『爆笑オンエアバトル』では、「間違いない!」でブレイク中の長井秀和が『バイオハザード』のプレイヤーキャラの独特な動きをネタにしたことも。自慢のパントマイムを生かした芸で、その再現度はピカイチだった。
後に、次長課長の井上聡も同じようなネタをしていたが、プレイした方にとっては爆笑必至。究極の「あるあるネタ」である。
発売直後は20~30万本ほどのセールスだった初代『バイオハザード』だが、口コミで徐々に人気が拡大。熱狂は徐々に社会現象化し、100万本を達成したのはおよそ1年後のことだった。
その後、シリーズを重ねるにつれて圧倒的な進化を遂げたわけだが、初代で受けた衝撃を超えたことはいまだにない。
まだソフトをお持ちの方!
久しぶりに、皆さんも「ハザッて」みたら?(加山雄三の伝説の名言)
(バーグマン田形)