東日本大震災から11年となる3月11日を前に被災地に取材に赴いたニッポン放送・飯田浩司アナウンサーが、3月10日のニッポン放送『飯田浩司のOK! Cozy up!』の中で、この時機に読むにふさわしいものとして1冊の書籍を紹介した。
『探訪 ローカル番組の作り手たち』(隈元信一/はる書房)
飯田)思えば2011年の3月11日に震災があり、原発の事故があり、私は2012年のお正月からニュース番組のキャスターを務めるようになりました。
『ザ・ボイス そこまで言うか!』(ニッポン放送 2012年1月~2018年3月)という番組でした。やはり、震災を契機にしていろいろと言論の空間も変わってきたということもあって、いろいろな意見が聞きたいよね、というところで始まったニュース番組でした。しかし、やっていくなかで、やはり現場に入って現場でお話を聞いてこないと東京の感覚だけではわからないことがたくさんありました。特に、東日本大震災はあれだけ多くのところで甚大な被害がありました。その復興というのは、東京から見ていてもわからないことがたくさんあるということは、やっていても思ったことですし、実際に取材に入れば入るほど現地の人たちの気持ちというのに本当に届いているのか、それを聞けているのかということを常に自問自答しながらやってきました。
そのようななかで今回も取材をしてきたのですが、取材の前後で『探訪』という本に出会いました。
サブタイトルに『ローカル番組の作り手たち』と書いてあります。これはもともと朝日新聞の論説委員をされていた隈元信一さんという方が書いた本なのですが、この方は東京本社学芸部などを経ていらっしゃって、放送業界に関しての執筆が非常に多いのです。ラジオ・テレビ欄の中に番組の紹介をするコラムがあったりしますが、そのようなところを中心にずっと放送業界を長く見てきた方です。
といっても、東京の放送局だけに向き合ってきたわけではありません。本当に新聞の方がすごいと思うのは、「足で稼ぐ」と言うではないですか、もう全国津々浦々いろいろな現場に行って、しかもローカル局だけではなく、災害でできた臨時FM局であったり、そこから派生したコミュニティFM局だったり、ケーブルテレビ局の番組制作の現場も歩いていろいろな論考を書いていらっしゃいます。そのなかの論考をまとめたような形で1冊の本が出来上がっています。
北は北海道から南は沖縄まで、様々な放送局やそこで頑張っている取材者の方々や制作者の方がたくさんいるのだな、と思いました。
東日本大震災についても、勿論東北の局を中心に書かれているのですが、あのとき全国から人が入ったのだなということが読んでいてわかります。たとえば熊本放送局の制作者の方の話が出てくるのですが、テレビ熊本に熊本(竜太)さんという方がいらっしゃって、この方が2011年の3月11日に東京にたまたま出張があって羽田に着いた瞬間に地震が起きました。そして、「手の空いている人で系列で行ける人は行ってくれ」と言われて、そのまま東北に向かったという方です。そこから石巻に毎年通ってドキュメンタリーを撮り続けているのですが、2016年の熊本地震では自身も被災者になってしまったわけです。そうすると、当事者になって本当に他人事じゃない状態になったことで、番組に変な“励まし”を入れたり、「前を向いて頑張っています」なんていう肉付けをしたりする気がなくなったそうです。
“ありのまま”というものを出していくことをするのだと。どうしても東京の感覚だと番組の締めで「復興は道半ばです」とやるか、あるいは「とにかく前を向いています」とかになると思います。しかし、そのおそらく両方の真ん中付近のどこかに本来の姿というのがあって、でも東京からテレビが来た、ラジオが来たとなると、現地の人たちも「このような画が求められているのかな?」とか「このようなコメントが求められているのかな?」というようなアジャストが効いたりだとか……そこに真実はあるのかな?などと、読んでいて本当にそのようなことを思わせられました。
この隈元さんという方は旅する記者のような人です。作家で、日本ペンクラブの前会長の吉岡忍さんという方が帯を書いていらっしゃいますが、「隈元信一は、つなぐ人だ。人を、地域を、放送をつないできた。
そこから生まれる発見、感動、強さを、誰よりも知っている」と書いています。また「隈元出版基金」呼びかけ人で、この本を出された原動力にもなった石田彰さんという方が「あとがきにかえて」という形で書かれています。もともとTBSラジオの永六輔さんの『永六輔の誰かとどこかで』という番組を長らく携わってきた方で、制作者と取材する側ということで隈元さんと話されてきた方です。やはり、永さんもそうですし、永さんのその生き方というものに非常に影響を与えた方々もそうなのですが、「スタジオでものを考えるのではなく、電波の届く先へ行って、見たり聞いたりしたことを、スタジオに持って帰って話しなさい」ということをおっしゃっています。永さんもTBSの番組以外はもうずっと旅を続けられてきて現場を見てきたという、その尊さのようなものが非常に貫かれている本でもあります。
『探訪 ローカル番組の作り手たち』(隈元信一/はる書房)です。
震災でいろいろな特集が(メディアで)組まれるタイミングでもありますが、この時機に一度ご覧いただくと非常に参考になるなと思いました。
radikoのタイムフリーを聴く:https://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20220310060000















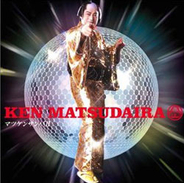



![【Amazon.co.jp限定】ゴジラ70周年記念 怪獣王シリーズ ゴジラ(2023)ゴールドカラーver.[完全生産限定] ※この商品にはBlu-ray&DVDはつきません(フィギュアのみ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51yxeR5I4oL._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ARIEL -エリアル- Blu-ray Archive BOX 地球最強の女神再臨セット (購入特典:”巧緻を極めた原作絵師 鈴木雅久”の原作絵キャンバスアート) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51TWZjmwxKL._SL500_.jpg)
(Amazon限定グッズ:ムービーモンスターシリーズ (クモオーグ、コウモリオーグ、ハチオーグ、サソリオーグ、カマキリ・カメレオン(K.K)オーグ)+Special 収納 BOX(Amazon ver.)付き)(メーカー特典:クリアしおり(ランダム 全 3 種)付き) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/316mitukrDL._SL500_.jpg)







![[山善] 32V型 ハイビジョン 液晶テレビ (裏番組録画 外付けHDD録画 対応) QRT-32W2K](https://m.media-amazon.com/images/I/516WFLybmIL._SL500_.jpg)