「死とはいったい何か?」「悔いなく死ぬためには、死をどう考えればよいのか?」——人生100年時代に、死は遠い先のことであり、まるで他人事のように思える。メメント・モリ(自分もいつか死ぬことをわすれるな)。
■自殺幇助の是非
加藤:自殺について考えてみます。シェリー・ケーガン(イェール大学哲学教授)は生死の様相を、P機能とB機能として説明します。
呉:医療が技術的にも制度的にも進んでしまって。
加藤:そのおかげで、死ぬまでに、P機能とB機能で時間差が生じてきた。そのとまどいが、認知症なんだと思います。それに、技術や制度の急激な変化のなかで、驚くような速さで死や葬送の価値観も変わりました。代々このようであったという尺度をあてられても、もはや全く納得できません。先代と同じ墓に入りたくない、夫婦でも墓を別にしたい、そもそも墓は不要だ、等々。費用の問題も大きい。
呉:はい。
加藤:日本尊厳死協会の資料(2017年)がありますので、ここで引用しておきます。
終末医療における事前指示書(リビング・ウィル Living Will)
この指示書は、私の精神が健全な状態にある時に私の考えで書いたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄するか、または撤回する旨の文書を作成しない限り有効であります。
□私の傷病が、現在の医学では不治の状態であり、既に死が迫っていると診断された場合には、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。
□ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和医療を行ってください。
□私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は生命維持措置を取りやめてください。
以上、私の要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げるとともに、その方々が私の要望に従ってくださった行為一切の責任は私自身にあることを付記いたします。
自署 氏名 押印 住所 生年月日 日付
「尊厳死の宣言書」の登録について
入会希望者は宣言書に署名、押印して協会に送って下さい。協会は登録番号を付けて保管し、その代わりコピー二通をあなたに返送します。そのコピーの一通を本人が持ち、もう一通を近親者など信頼できる人に所持してもらって下さい。必要が生じたときにどちらかのコピーを医師に示して下さい。
呉:日本尊厳死協会は「われわれの主張しているのは安楽死ではない」と言っている。尊厳死と安楽死を、彼らは一応、分けている。尊厳死の場合は、死が目前に迫っていて、ほかに救う手立てがない場合で、安楽死は、まだ手前の段階。まだ自由に動くけれども、もう先は生きていても仕方がないというのが安楽死なんだよね。尊厳死協会は、そこを非常に厳しく主張している。一緒にしてくれるなと。
加藤:それと、医師の立場を守るためなんです。この宣誓書は、後で遺族と揉めたときに「本人が、判断能力のあるうちに自分でそう決めたのです」という証拠になる。
呉:これは両親を看取った体験からも、今、自分が高齢になっている現実からも、切実な問題なんだ。
加藤:日本では積極的安楽死は違法ですが、延命治療をやめるという消極的な安楽死は可能ということですね。
呉:現在、日本でも要件がそろうと安楽死は認められる方向になっている。絶対に助からないことがわかっていて、死が眼前に迫っていて、医師の立ち合いがあるとかね。ということは、実際にすでに行われている可能性がある。いちいち報告する義務はないわけだから。家族と当人が医師に懇請すれば、やる可能性がある。
——ただ、そのハードルは高いですね。だって、もうすぐ死ぬ人間は、安楽死したいという主張をできないわけですから。だから、その要件に当てはまらないかもしれない。
呉:そうそう。だから、いわゆる安楽死より、死が迫っている時に、ということなんだよね。もう自分は70まで生きた、80まで生きた、これからいいこともないし、現に体が弱ってきて苦痛も大きいという段階で、やれるかどうかという問題なんだよね。
加藤:死にたい人を手助けする自殺幇助という方法も、最近は選択肢に入ってきました。
尊厳死に関する意識が最も進んでいるといわれているのはスイスで、すでに自殺幇助団体が優良企業として発展しているそうです。このあたりは最近盛んにあちこちで報告されています。読みやすい本としては、脚本家の橋田壽賀子(1925~)の『安楽死で死なせて下さい』(文春新書)があります。自分の意思で誰にも迷惑をかけずにきれいに死んでいきたい、つまりP機能が先に衰えきってしまう前に、自らB機能を絶ちたいという願いが、スイスで叶えられるのです。これは高齢者に限らず、NHK特集で放映された、若い日本の女性の例も知られています。彼女は不治の病から、自分でスイスの自殺幇助団体に申し出て、姉たちに付き添われてスイスに向かい、静かに亡くなりました。もちろん、最後まで丁寧に意思確認がなされた上でのことですが、死の瞬間まで放映されたことは心に残る出来事でした。
呉:橋田は、俺のおふくろと同い年なんだね。おふくろは4年前に91歳で死んだけど、橋田にとっては切実な問題です。
加藤:ケーガンは、死を悪いことと考えることは、先入観、固定観念であると語ります。確かに歴史を振り返れば、死は常に悪いこととされてきたわけではない。むしろ「死を想え(メメント・モリ)」や、人間はいずれ必ず死ぬ存在なんだから、今を頑張れよという励ましの言葉として使われることもある。「決死」の覚悟でやりなさい、という日本語もある。生を再起動するために、死をもってくるのは日常的なことだった。そして、死を想う気持ちがさらに積極性を持ち、あげくに「前向きに死んでいきたい」という願いに至ることもあったわけです。それでケーガンは、死への希求や自殺について考察を進めてゆくのですが、先ほどのP機能とB機能つまり心身の死の時間差について、変な話を付け加えておきましょう。
加藤:エドガー・アラン・ポー(1809~49/作家)の『ヴァルドマアル氏の病症の真相』に、こういう話があります。
催眠術師の「私」は「臨終の人間に催眠術をかけたらどうなるだろう」という疑問を抱いていた。
劇症の肺結核に冒され余命いくばくもない友人のヴァルドマアル氏が奇特にも「私」の知的好奇心を満たすべく、臨終に際して「私」に催眠術を施術することを許可してくれる。施術は成功し、瀕死の男は臨終の床で眠りにつき、眠ったまま息をひきとる。ところがそれから数分ののち、ヴァルドマアル氏は「眠り」から覚めてしまう。深い洞穴から聞こえてくるような、くぐもった声で、彼は「さっきまで私は眠っていたが、いまは死んでいる」とうめく。催眠術の眠りのせいで、彼は死の瞬間を逸してしまったのである。
ヴァルドマアル氏はそれから7カ月死んでいながら、死んでいない宙吊り状態におかれる。「私」は、ついに彼にかけた催眠術を解くことを決意する。術が解け始めると、再び、あの地獄の底から響くような声がうめく。「早く、眠らせてくれ、でなければ、早く目を覚まさせてくれ」
そして術が解け切った瞬間、ヴァルドマアル氏の身体は「いまわしい腐敗物の、液体に近い塊」と化して崩れ去る。SF話のようですが、たぶんポーは本当に実験したのでしょう。
呉:いかにもポーらしい作品だね。
加藤:なかなか体が腐らない人を、キリスト教では聖人として崇めたわけで、ある種の宗教的な熱狂やエクスタシーの中で、心と身体の死期が一致せず、不思議に見える現象が生じていたのかもしれません。
心身の死について、スウィフト(1667~1745/作家)もまた思考実験を試みていました。彼の『ガリバー旅行記』に登場するラグナグ国は、不老不死ではなく、人々は老いるが、なかなか死なないという超高齢社会の国です。ガリバーはそれを知って長命を大いに寿ぐのですが、その国の人々は複雑な表情で「とんでもない」と言う。超高齢化が、どれほど醜悪で大変な社会となり果ててしまうかを、ガリバーに訴えるのです。まだまだ寿命が短くて、長寿が疑いようのない美徳だった時代に、皮肉なスウィフトは未来を予言していました。
(呉智英×加藤博子著『死と向き合う言葉:先賢たちに死生観に学ぶ』の本文一部抜粋)
【著者略歴】
呉智英(くれ・ともふさ/ごちえい)
評論家。1946年生まれ。愛知県出身。早稲田大学法学部卒業。評論の対象は、社会、文化、言葉、マンガなど。日本マンガ学会発足時から14年間理事を務めた(そのうち会長を四期)。東京理科大学、愛知県立大学などで非常勤講師を務めた。著作に『封建主義 その論理と情熱』『読書家の新技術』『大衆食堂の人々』『現代マンガの全体像』『マンガ狂につける薬』『危険な思想家』『犬儒派だもの』『現代人の論語』『吉本隆明という共同幻想』『つぎはぎ仏教入門』『真実の名古屋論』『日本衆愚社会』ほか他数。
加藤博子(かとう・ひろこ)
文学者。1958年生まれ。新潟県出身。文学博士(名古屋大学)。専門はドイツ・ロマン派の思想。大学教員を経て、現在は幾つかの大学で非常勤講師として、美学、文学を教えている。また各地のカルチャーセンターで哲学講座を開催し、特に高齢の方々に、さまざまな想いを言葉にする快感を伝えている。閉じられた空間で、くつろいで気持ちを解きほぐすことのできる、「こころの温泉」として人気が高い。さらに最近は「知の訪問介護」と称して各家庭や御近所に出向き、文学や歴史、哲学などを講じて、日常を離れた会話の楽しさを提供している。著作に『五感の哲学——人生を豊かに生き切るために』。


















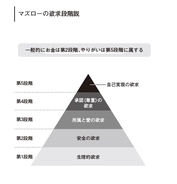






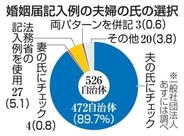



![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 05月号[スタジオジブリの建築・アート]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WAGDJN3-L._SL500_.jpg)

![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークアイボリー/ホワイト RYST5040H(AIV/WH2) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41bUm2zOxIL._SL500_.jpg)






