先日、ドキュメンタリー映画『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』が公開された。
1969年5月13日、作家の三島由紀夫と東大全共闘の学生が開いた討論会の様子を当時の関係者、現代の文学者、ジャーナリストなどの証言を織り交ぜながら紹介したもの。
映画のトレーラーを見ると、小説家の平野啓一郎は「社会を変えていくのは言葉なんですよね」、評論家の内田樹は「この1000人を説得しようと思っているんですよね」と熱く語っている。
東大全共闘の芥正彦は「言葉が力があった時代の最後だとは思っている」、瀬戸内寂聴は「あんな目、見た事ない」と述べていた。
この討論会の内容を前から知っていたこともあるが、正直、見られたものではなかった。この映画が宣伝で謳っているような「伝説の大討論」でも「言葉と言葉の殴り合い」でもない。大人と子供が相撲をとっているようなものだ。はっきり言ってくだらない。
映画のトレーラーには三島は「単身乗り込んだ」とあるが、実際には三島はこの討論会の書籍化を新潮社に持ちかけており、録音機を抱えた編集者とカメラマンが同行。翌月、書籍化された。教壇に立つ三島の背後から会場全体を映し出した新潮社のカメラマンによる写真は、この討論会の「ショー」としての本質を見事に表していた。
三島は保守主義者だったが、死ぬ前の数年間は右翼に転向した。念のため言っておくが、保守と右翼は水と油である。保守は理想を警戒するが、右翼は理想主義者である。結局、この討論会も含めて、先述した小説家や評論家が言うのとは逆に、三島は「言葉に溺れて」いったのだと思う。
当時も今も、三島はあまり理解されていない。
お隣韓国でも、三島に関するアホな記事が多い。
「デイリー新潮」によると、駐韓大使の冨田浩司が、三島由紀夫の娘婿にあたる人物であるとして、ネガティブな報道をしているらしい。政権寄りの報道姿勢で知られるソウル新聞は「極右作家の娘婿」という見出しで報じた。保守系メディアの中央日報は、三島は「安倍首相の憲法改正の試みの端緒になった」とこじつけたという。
これはアホすぎ。安倍の憲法観と三島の憲法観は真逆。三島が生きていたら、安倍の改憲は全否定していたはず。
安倍は改憲派が積み重ねてきたロジックを完全に破壊した。本来なら「改憲派」が率先して自衛隊を愚弄する安倍の改憲を批判しなくてはいけないのに。要するに改憲を唱えてきた連中の多くがやってきたことは「ままごと」ということだ。
情弱のネトウヨ向け月刊誌はどうでもいい。害はあるが、バカがバカに向けて確信犯的に作っているので、何を言ってもムダである。悪質なのは、危機を感知する能力を持ちながら、黙っていた保守である。
ついに日本政府が「北方領土」という言葉を使うなと言い出した。すでに二〇一九年版の外交青書で「北方四島は日本に帰属する」との表現が削除されていたが、安倍と周辺の一味は売国どころか、上納金と一緒に国土をプーチンに献上してしまった。「ロシアに叱られないようにする」ことが行動基準の国。
絶望し、憤死、諌死(かんし)した三島だが、あの時代のほうがまだマシだった。
《私はこれからの日本に大して希望をつなぐことができない。このまま行ったら日本はなくなってしまうのではないかという感を日増しに深くする。日本はなくなって、その代わりに、無機質な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済大国が極東の一角に残るのであろう。それでもいいと思っている人たちと、私は口をきく気にもなれなくなっているのである》(「果たし得ていない約束」)
日本はすでに経済大国ですらない。貧困で抜け目しかない、頭が空っぽな国が残った。バカがバカを担いできた当然の結果である。




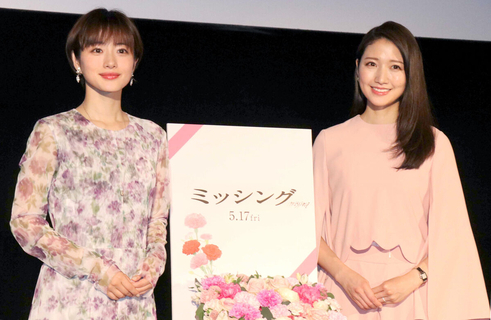



























![[山善] テーブル ミニ 折りたたみ サイドテーブル 幅50×奥行48×高さ70cm ハイタイプ 傷・汚れ・水分・熱に強い天板(メラミン加工) なめらかな表面 角が丸い アンティークアイボリー/ホワイト RYST5040H(AIV/WH2) 在宅勤務](https://m.media-amazon.com/images/I/41bUm2zOxIL._SL500_.jpg)







