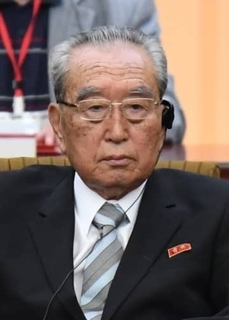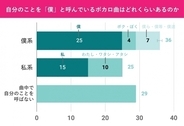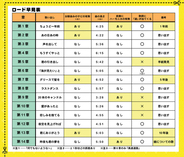Text by 原里実
Text by ノイ村
2021年3月に発売されたベストアルバム『SZ10TH』以来、約2年4か月ぶりとなるSexy Zoneのアルバム『ザ・ハイライト』が2022年6月1日にリリースされる。
デビュー10周年を機にレーベルを移籍して以来、初のオリジナルアルバムとなる今作には、JQ(Nulbarich)、岡崎体育、STUTS、butaji、iriといった個性豊かな顔ぶれが楽曲提供アーティストとして名を連ねる。
デビュー当時、平均年齢14.4歳という歴代最年少で活動をスタートしたSexy Zone。11年目の彼らは現在、何を見据え、どこに向かおうとしているのか? アルバムのテーマやタイトル決定、提供アーティストの人選などにもメンバーみずからが携わったという渾身の一枚を、音楽面から紐解く。

Sexy Zone
左から:菊池風磨、松島聡、佐藤勝利、中島健人(マリウス葉は現在休養中)
どこからどう見たって1970年代から1980年代を席巻した伝説の某音楽番組としか思えないロゴや、敢えてカタカナ表記で記載された「セクシーゾーン」という文字列、そしてNight Tempoの作品群のアートワークを手がけていることで知られるtree13氏によるジャケットに至るまで——いまのSexy Zoneがいったい何をしようとしているのかは6月1日にリリースされる最新アルバム『ザ・ハイライト』のジャケットを見れば一目で察知することができる。
本作のリードトラックの一つ“THE FINEST”を聴くと、その直感は確信へと変わるだろう。JQが作詞・作曲・編曲に関わっている同楽曲は、彼が所属するNulbarich直系のソウル / ファンクを軸としたメロウなポップソングであり、目を閉じれば東京の夜の街を彩る綺羅びやかなネオンサインが浮かんでくるほどにゴージャスで贅沢な名曲だ。ミュージックビデオも『シティハンター』など1980年代のテレビアニメを彷彿とさせる仕上がりとなっており、画面のざらつきや4:3の画角などに至るまで、徹底的にこだわってつくり上げられている。
というわけで、本作の制作にあたって、数年前から国内外で活発となっているシティポップ・ムーブメントが参照されていることに間違いはないだろう。その背景を推測するうえで、近年のSexy Zoneの活動におけるスタンスの変化、つまりは海外進出という目的を挙げることもできるかもしれない。
彼らは2020年8月にレーベルを移籍して以来、全英語詞の“RIGHT NEXT TO YOU”(2021年)の発表や、(主にシングルのカップリング曲を活用した)海外のトレンドを大胆に取り込んだ楽曲制作など、海外進出を見据え、着々と準備を整える動きが見られていた。例えば、シングル『NOT FOUND』に収録されていた“Arms Around Me”はまさにシティポップ的なサウンドであり、同楽曲を聴くことによって“THE FINEST”における彼らの進化をより深く実感することができる。
シティポップといえば、The Weekndが今年初旬にリリースしたアルバム『Dawn FM』の収録曲“Out of Time”のなかで、亜蘭知子の“Midnight Pretenders”(1983年)をサンプリングしたことも大きな話題となっており、韓国のK-POPシーンにおいてもYUKIKAやTOMORROW X TOGETHERといったアーティストがシティポップを参照して人気を博している。Sexy Zoneが海外進出を意識するうえで選択肢の一つとして挙げたとしても、まったくおかしなことではないだろう。
とはいえ、実際に全編を通して聴いてみると、『ザ・ハイライト』はいわゆるシティポップ・アルバムというわけではない。例えば、アルバム冒頭を飾り、本作のもう一つのリード・トラックでもある“Forever Gold”は、ヴァン・ヘイレンの名曲“Jump”を彷彿とさせる、眩しいシンセサイザーのメロディーが印象的な、非常にスケールの大きいスタジアムポップだ。
ミュージックビデオも、学園生活とテレビショーを舞台に、アメリカの1980年代のポップカルチャーをモチーフとしたものとなっており、二つのリードトラックを用いてそれぞれ日本と海外の二つの1980年代を参照しているという構造になっている。この二面性こそが、本作の最大のポイントなのではないだろうか。
その構造は、アルバムを通して聴くことでより浮き彫りになっていく。1980年代のスタジアムロック的な“Forever Gold”のあとにはジャスティン・ビーバーの“Sorry”を彷彿とさせる爽やかな“Desideria”が続き、同じく1980年代のシティポップ的な“THE FINEST”のあとには秦基博が手がける王道中の王道のJ-POPバラード“夏のハイドレンジア”が待っている。
以降も、淡い恋を描いた、オールドスクールなヒップホップの力強いビートと、ラップやハーモニーを織り交ぜた軽やかでキャッチーな歌唱のコントラストが楽しい“Iris”から、夏の恋の盛り上がりのピークとハウスミュージックの高揚感がシンクロするダンスチューンの“SUMMER FEVER”へ切り替わるなど、本作の前半では曲ごとに表情を切り替えながら、時代・場所・音楽性に対して、どちらか片方に注力するのではなく、どちらも完璧に乗りこなしていく。
この流れは壮大なバラードの“Story”によってクライマックスを迎えるが、本作が7曲目の本楽曲でいったん区切りとなっているのは、カセットテープ文化へのオマージュだろうか。
前半の時点でもその構造の妙に魅了されるが、後半パートにおいて、『ザ・ハイライト』はさらに衝撃的な展開を迎える。ヘヴィに唸るベース・ラインと強靭なビートに乗せて文句も評論も批判も同調圧力もすべてを嘲笑う挑発的な“Eliminator”から、PSY“江南スタイル”を彷彿とさせる2010年代前半のEDMムーブメント直系のブチ上げ系エレクトロに乗せて「え、ここまで歌っていいの!?」と心配になるほどに過激でセクシャルなリリックを歌い上げる、本作最強のパーティーチューン“Freak your body”へと雪崩れ込むのだ。
だが、本当に衝撃的なのはこの二曲からメタパロディーネタに定評のある岡崎体育が手がけた“休みの日くらい休ませて”へと突入することだろう。
本作の持つ構造は、続けて鳴り響く、現在の彼らを最も象徴している楽曲の一つ“LET’S MUSIC”の持つ強靭なメッセージ性に、あらためて大きな説得力を与える。J-POP、ジャズ、R&B、ヒップホップ、ハウス、ロックンロール、ダブステップ、トラップ、ラブバラードなど、時代もジャンルも場所もすべてを超えて音楽を愛して、人々のために最高のエンターテイメントとして提供すること、それがいまの彼らであり、彼らなりの海外進出戦略、つまりより多くの人々を楽しませるための姿勢である。
AかBかの二択を迫るのではなくどちらも最高、もっと言えばどちらも楽しめることが最高だと示すことに全力を注いでいるのだ。これまでの作品群でもそういった姿勢を感じさせる瞬間はあったが、今作はそれが最も明確に表れた一枚、まさに「全曲がハイライトである」と感じさせる仕上がりとなっているのだ。
ここまで徹底的に「LET’S MUSIC」を体現した『ザ・ハイライト』だが、12曲目以降、本作は意外な方向へと向かいながらフィナーレを迎えていく。夜から朝へと変わっていく時間を描くうえでこれ以上ない人選ともいえるSTUTSがbutajiとともに手がけた“Summer Ride”は80年代的な綺羅びやかさに想いを馳せた“THE FINEST”とは異なり、あくまで現代の都市の夜を描いたポップミュージックである。幻想に夢を見るのではなく、意識を研ぎ澄ますかのような力強いビートのなかで、どうしようもないやるせなさと寂しさに浸るための楽曲だ。
これは1990年代生まれの筆者の個人的な考えだが、近年の80年代ポップスやシティポップのリバイバルの中心にいるのは、(国内外ともに)リアルタイムで経験していない人々であり、ある種の桃源郷として、現代にはない何かを感じて、当時の文化を参照しているように感じている。もはやファンタジーとしか思えないバブル時代の熱狂はその一つの象徴だろう(関連記事:シティポップの世界的ブームの背景 かれらの日本という国への目線)。
Sexy Zoneもまた、メンバー全員が1990年代以降の生まれであり、ミュージックビデオやアートワーク、ファッションを通して「自分たちなりの1980年代」を全力で楽しんだ、その試みはエンターテイメント性に満ちた11曲目までで確実に成功している。
その予兆は、続く“Dream”によって容赦のない事実として突きつけられる。始まりこそドリーミーなアコースティックポップだが、荒い質感のビートと、どこか諦念を感じさせ、時折感情が零れ落ちるような歌声が、曖昧な時間のままにしていた“Summer Ride”の先にあるバッドエンドを示している。
本楽曲を手がけたiriもまた現代の夜の景色を描く最高の書き手の一人であり、一つの恋が終わろうとしている瞬間を鮮やかに描ききっている。それまでの華やかさやアイドル性に満ちたエンターテイメントぶりが嘘のような、やるせなさに満ちた、エモーショナルな瞬間がここにはある。
だが、本作は悲哀では終わらない。最後を飾るのは綺羅びやかでムーディーなイントロが象徴的な、80年代シティポップ直系の“Ringa Ringa Ring”であり、想いを寄せる相手との電話を巡るドキドキを描いた愛らしいラブソングだ。どれほどつらい夜を迎えようが、どれだけ弱々しい姿を見せようが、それでもなお最後はハッピーエンドという美しい夢を見せてアルバムは幕を閉じる。
そして、これこそがSexy Zoneの在り方なのだろう。「シティポップ」というモチーフを現在と過去のスタイルで使い分けることによって、さまざまな音楽性を表現するだけではなく、複雑な感情をも見事に表現している。アルバムを一枚通して聴き終わる頃には、最初は単なるシティポップへのオマージュのように感じられた本作のアートワークが、また違ったイメージとして見えてくるのではないだろうか。
作品全体のイメージをレトロに揃えることで新鮮な印象を与えつつ、複数の角度で当時の音楽を参照することによって全方位的な音楽への愛情をさらに拡大させた『ザ・ハイライト』は、これまで以上に幅広い音楽性や表情を楽しむことができる純粋に優れたポップアルバムであり、キャリア屈指の名盤と言って良い会心の仕上がりだ。
だが、それ以上に本作は“LET’S MUSIC”に象徴されるSexy Zoneにとっての音楽との向き合い方をこれまで以上に明確に具現化したものであり、さらに言えば、日本か海外か、昔かいまか、アイドルか社会人か、現実か幻想か、そして強さか弱さかといったさまざまな二面性に対して「どちらも肯定する」ことに全力で向き合った作品であり、それこそがいまのSexy Zoneらしさなのではないだろうか。