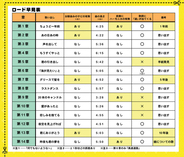Text by 山元翔一
Text by 原雅明
Text by 柳智之
多種多様なジャンルにわたっていながら、貫徹されたビジョンとサウンドを誇るジャズレーベル「ECM Records」。かつて「ECM」でプロデュース業を学び、2020年に「Red Hook Records」を立ち上げたサン・チョンこそが本稿の主役である。
エレクトロニックミュージックの最重要レーベル「Warp Records」をお気に入りのひとつに挙げるサン・チョン、およびその主宰レーベル「Red Hook」は、徹底した「音」の探索を通じて、時代と社会を真に映し出す「リアルミュージック」に手を伸ばしている。「ECM」がそうであり続けるように。
その「Red Hook」からリリースされた最新作『Refract』を題材に、サン・チョンいわく「混乱状態に陥っている」という音楽がいま向かうべき先はどこなのか、音楽ジャーナリスト/ライターの原雅明とともに話を聞いた。

サン・チョン
1982年5月18日、サンフランシスコ生まれ。父親は国際的に活躍する指揮者・ピアニスト、チョン・ミョンフン。2001年、NYに移住。
—ジェイソン・モラン、マーカス・ギルモア、BlankFor.msという組み合わせが実現した経緯から教えてください。
サン:まず、『Two Centuries』(※)をつくっているときにBlankFor.msの話題になったんです。
ほかのプロダクションでもそうで、僕はいいと思ったら自分からアプローチして話を進めていくっていうパターンなんですけど、これも同様だった。
BlankFor.msの実の名前はタイラー・ギルモアといって、タイラーと僕らとは共通項がいろいろありました。彼は僕と同じNEC(ニューイングランド音楽院)で学んでいて、ジェイソンはNECで教鞭を執っているんです。
サン:それで実際に6か月間、プリプロダクションをやりはじめてみたら「やっぱりドラマーもいたほうがいいよね」という話になり、マーカスにも声をかけて参加してもらうことになって『Refract』を制作しました。
—タイラー・ギルモアは、NECでジャズを学んでいたのですか?
サン:ジャズ・コンポジション(ジャズ作曲)を学んでいましたよ。
—ということは、『Refract』をつくるにあたっては、3人にジャズという共通言語があったということですね。
サン:そうですね。エレクトロニックミュージックの音楽家のなかでも、伝統的な音楽の素養を持っている人と、もっと「耳と音のみ」に頼って音楽制作をする人がいます。
後者の人たちが悪い、ということでは決してないので誤解しないでほしいのですが、やはり素養がある人たちは、和声をはじめとした何層もある音楽的知識に根づいたコミュニケーションができる。
—ジャズという共通言語があったとはいえ、ジャズとエレクトロニックミュージックでは曲のテクスチャーも違いますし、つくり方も違うと思うのですが、そこでの難しさはなかったのでしょうか?
サン:僕はいつも「音」に絶大な信頼を置くような人たち、スタイリスティックなものよりも「音」に軸足のある人たちと仕事をすることを大事にしています。ジャズとかロックのようなジャンル性が大事なのではなくて、音を聴いて反応して、独自の音楽の世界を構築する人たちです。
たとえば、ビル・フリゼール(※)もそう。ビルにボサノバとかロックをやってもらったら、ジャンルとしての「ボサノバ」「ロック」ではなくて、その音の世界に反応して自分の音楽づくりをはじめると思う。ビルはもう巨匠といっていい領域に入ってきたので、「すべて超越した世界」をお互い尊重しあいながらつくれるというところがいいと思っています。
—あなたも関わっていた「ECM」(※)はジャンルの境目にあるような、マージナルな音楽をつくりだしていましたが、「Red Hook」はそうした「ECM」の意志も受け継ぎつつ、さらなる可能性を探っているように感じます。そもそもそうした指向性はどこから生まれてきたのでしょうか?
サン:ぴったりの答えがなかなかないんですが、僕がレコードをつくるときに大事なのは、やはり「物語を語ること」なんです。
物語性があるものというのは、ジャンルを超越して本当におもしろいものが出てくる可能性がすごく高い。一方で伝統的なジャズは、みなさんもうかなり聴き込んできているわけですが、そういった状況でも若い人たちに新しいものを提示できたら、という思いもあります。
—いま、日本でもジャズを学んだ若いミュージシャンが目立ってきていて、みんなすごくうまいんです。ただ、ジャズという枠組みが以前よりも大きく、重くもなってきたように感じていて、少しその枠組みから飛び出た表現が出て来にくいのかなと感じることもあります。
サン:まさに同じことがNYで起きています。スタンダード化されてきているというか。それから、やっぱり教育システムができあがって、学校が幅を利かせています。あとYouTubeで誰でも簡単にすごい演奏に触れられるから、それを真似すればいい、というところもある。だから、テクニック的に非常に卓越した人なら、山といるという状態なんです。
実は一昨日、同じ話を父(※)ともしました。父も、音楽家の数が山といて、いまは本当にうまい人がいっぱいいると言っていた。父はピアノも弾くけど、自分よりもテクニックがある人はもう溢れるほどいっぱいいるってね。でも、父の音楽にある深遠さや豊かさとか、そういうものをみんなが持っているかというと、また別問題だと思う。
音楽が物語を語れるかどうか、十分なエネルギー、熱量があるかどうか、音楽とちゃんと結びあい一体化しているか。テクニックと音楽性のバランスがすごく問われるんじゃないか、と父とも話しました。
サン:一生懸命にテクニックを磨くことで、本物の「リアルミュージック」を犠牲にしてしまう。そういった現実にも、いま若い人は直面しているんじゃないかな。だからその意味で、ジャズも近年では「クラシック音楽」化しているところが感じられる。「自分の音」の確立を目指すのではなくて、マスターの音をコピーするような、そういう流れが見られますね。
だからこそ、僕は「マスター」と言われる巨匠と仕事するのが大好きなんです。巨匠たちは、見事に自分の感情を直接的に出してみせてくれる。ハートとスピリットが音楽とすごく近い。それらが一体化するような音を出してくれる。
そして僕は、そこに若手を投入するわけです。そうするととても正直に音楽づくりをすることができるんです。巨匠を前にしたら、若い音楽家は見せびらかす必要などまったくない。だから、すごく正直に、真摯に、音楽づくりに取り組めるのです。
—「音楽の深遠さ」に必要なものは何だと、あなたは考えますか?
サン:それが何かを言葉にするのは、あなた方にしてほしいことだと思うのですが、僕の仕事は、それを見つけて、認識して、レコーディングし、届けることだと思っています。僕の父はクラシックだけど、それがジャズであろうと、エレクトロニックミュージックだろうとね。
あくまで僕の思うこと、という前提で言わせてもらうと、昔のほうが、もっとそれぞれの個性や、ひとつの音の持つ意味、その向こうにあるものを追い求めることをとても大事にしていた。いまはどうしてもテクニック偏重になりかねないところがあります。
YouTubeなどで安易にアクセスできるようになったことによって、ちょっと混乱状態に陥っているような感じがしますね。さらには、学校に行けば「コルトレーン風に弾く」とか、簡単に教えられて身につけられてしまうわけだから。
—『Two Centuries』も『Refract』もテイラー・デュプリーがマスタリングを手がけています。これも「Red Hook」の作品を魅力的にしている理由のひとつだと思いますが、彼を起用した理由を教えてください。
サン:彼はご存じのようにエレクトロニックミュージックでも卓越したテクニックを持った人で、この音楽に対する優れた感性を持っている人です。右に出る者がいないほど卓越したものを持っている。そして、何よりもいい人で、本当に仕事がしやすいんです。
とってもシンプルな理由だけど、非常に大事な理由で、最初に『Two Centuries』でやったときに本当にうまくいって、また仕事したいと思わせてくれた。そんな素晴らしい人なんです。
—デュプリーは「12k」というレーベルを主宰しています。坂本龍一は「12k」と自身の音楽の「静かで非常に焦点が絞られている」ところに共通点を見出したのではないか、とデュプリーはインタビューで語っています(*1)。この特徴は「Red Hook」の一貫した音楽性にもあてはまると思うのですが、いかがでしょうか?
サン:以前も、あなたのインタビューで話しましたが(*2)、僕が自分のレーベルをつくるときに構築した「ソニック・アイデンティティ」は、やはり「焦点が絞られている」という意味であり、「Red Hook」から出した4枚からそう感じてもらえているなら、すごく嬉しいです。
「12k」との比較で言えば、僕のほうがもう少しエクスペリメンタルかもしれない。というのは、テイラーのほうがアンビバレンスなところもあるし、彼は独学で自分の音の世界を構築してきた人なんですよね。
そういったところから比べると、僕のほうがもうちょっとアブストラクトな部分もあるし、そして音のなかに分け入って探索(エクスプロール)していくところが僕の特徴かもしれないです。
—「12k」やデュプリーの音楽は、単なるアンビエントではなくて、あなたの言うアブストラクトなところもあるし、デュプリーと坂本龍一のデュオ演奏にはジャズの即興性にも近いものを感じました。あと、音響構築というか、サウンド全体に気を遣っている側面があります。そして、それは「Red Hook」や「ECM」の音楽にも強く感じるところです。ジャズミュージシャンにも、演奏だけでなく、そういった側面に対する意識が変わってきたような流れは感じますか?
サン:すごくいい質問なんだけど、これの答えは、いわゆる音楽のエキスパート、そういった録音された音楽に関する深く広い知識を持った人、あなた方のような人がきっといっぱいご存じだと思う。だから、確実な答えはないけど、ただ、その種の人たちが増えているのは、感覚的にはありますね。
—「Red Hook」では、ピアニストのキット・ダウンズ、サックス奏者のヘイデン・チスホルムと、バルカン半島のアカペラボーカルクインテットPJEVによる『Medna Roso』(2023年)で、民族音楽、伝統的な音楽への視点が顕れていました。こうしたサウンドの扱いに関しても、エレクトロニックミュージックの扱いとつながるものを感じられます。
サン:たしかに共通項はあるかもしれない。キットが弾くオルガンは過去を遡ればエレクトロニックミュージックの元になった最初の楽器ということもできるわけですよね。そういった楽器から、探索して分け入っていくのがいつもの僕のやり方です。
だから、『Medna Roso』ではアカペラの女性たちのコーラスと、オルガン、サックスを結びつけるという新たな組み合わせによって、新しい別の次元のものを聴いてもらいたいというふうに思ったわけなんです。新たな「音の探索(ソニック・エクスプロレーション)」をしていく流れのなかで僕は、民族音楽にもアプローチしています。
『Medna Roso』は、リハなしで臨んだ1時間のコンサートの録音です。彼女、彼たちは互いに聴き合う能力が非常に高いアーティストたちで、その前提、素地があったから、民族音楽というのはまた別に置いといても、できたのだと思う。だから、僕たちにとって一番大事なのは、その音に分け入り、探索し、実験して入っていくようなところなんです。
—「ソニック・アイデンティティ」「ソニック・エクスプロレーション」におけるソニック=「音」という言葉が印象的ですが、音楽との対比でどうとらえているのでしょうか?
サン:「音」にはじまり、そして探索の旅路を通して「音楽」に到達するという、そういったものだと思います。だから、非常に重要なツールとしての「音」があるわけです。
まず、その元のツールがよくなければいい音楽には到達しないので、音楽の旅もできない。だから「音」を非常に気にかけて大事にしていきます。そこには、やはりテクニック的なものも入れば、感性的なもの、いろいろな要素が入ってくるのです。
—音の探索、探求ということは、先ほどの深遠さにつながる話でもありますね。マニュアル化、システム化された演奏の習得から脱して、その音をいま鳴らす意味や理由、そのリズムがどこから来たか由来を問うてみることなど、現代においては避けられている部分があるように思いますか?
サン:個性、意味、理由、由来、そういったものをみんなが問うてないわけじゃない。でも、それに対する問いかけが「十分ではない」と僕は思います。
昔はそういうことにもっと焦点がしっかりと向けられていた。いまの人たちがそれを問題視してないわけじゃ全然ないと思う。でも十分ではない。だから、この問題はみんながもうちょっと正面から話しあうべき課題のひとつじゃないかと思います。
サン:ひとたび確立されてしまった音楽を進化させようと思ったら、やはり過去を学ぶことも重要です。過去を学んだうえで進化させていく。
たとえばラップはすごく感情が前面に出ますよね。ラップにおいては、ある意味ではすごく深いところの感情が、それも「いま」という時代と非常に深く結びつきながら表現されている。
そういった意味では、ジャズよりも現代性があって、いまという感情との結びつきは強いかもしれない。僕はラップの録音はしないけど、ラップが社会を映し出した音楽であることはすごく重要なことだと思っています。いまジャズミュージシャンは、厳しい挑戦の時期を迎えているのかもしれないですね。
—僕は以前、ジェイソン・モランにインタビューした際(*3)、彼の口からはジャズミュージシャンより、お気に入りのヒップホップのプロデューサーの話が多く出てきたんですが、そのとき、ラップがいまを映し出していることはとても重要だと言っていて、あなたの話と重なりました。
サン:ジャズは、カッティングエッジのところに立つ部分はつねにある。そういったなかで、自分が焦点を合わせるところを見失っちゃいけないんですよね。ジャズの場合、「伝統」というものがあるだけに難しいとも思うけど、伝統とのバランスのなかで、カッティングエッジであることは問われていると思う。
音楽家が世代やジャンルに縛りつけられることなく集まって、あらゆる区分を超えて音にフォーカスする。それによって、その音楽には自ずともっと純粋な現代性が映し出されるんじゃないかと僕は思います。
—あなたの「探索」が向かっている先にあるものを教えてください。
サン:探索したいことはたくさんあるんだけど、こういったもののセールスは決して容易じゃない(笑)。僕は「Libellule Editions」という新しいレーベルもスタートさせたんですが、そっちはインディーミュージック的なものを扱っていこうと考えています。
第一弾はBon Iverのショーン・キャリーとトランペット奏者のジョン・レイモンドのアルバム『Shadowlands』で、やっぱり聴きやすいのか、ストリーミングの数字を見ても違いがわかると思います。
—「Libellule Editions」では、ほかにどんなリリースを予定していますか?
サン:アーロン・パークスのLittle Bigの音源を出す予定です。12月にNYで録音して2024年リリースの予定なんですが、「Libellule Editions」では自分が聴いて育った音楽であり、より多くの人に親しみのあるインディーミュージックを扱っていきますよ。