右肩上がりの成長の背景には、数々の人気アーティストの存在はもちろん、藤倉尚社長の画期的な経営手腕があった。
○■社員時代に担当したアーティストの数々
――まず、簡単な経歴から教えていただいてもよろしいでしょうか?
大学を卒業して、まず入社したのはワインなどのお酒を扱う会社でした。もともと就活中に音楽会社も受けていたのですが、行きたい会社には採用してもらえなかったんですよ。
だけど、配属先の福岡でイベントに出展していたとき、ゲストで来ていた新人歌手の周りで働くスタッフたちの姿を見て、「ああ、やっぱり自分がやりたいのはこの仕事なんだな」と気づきました。
その日を境に、やっぱり音楽業界で世の中の人を楽しませたいと思い、ポリドール・レコードに転職したんです。今のユニバーサル ミュージックジャパンの前身の会社ですね。
ーーユニバーサル ミュージック入社後は、どんな仕事をされていたんですか?
ほぼすべての仕事を経験しました。レコードショップにCDを仕入れてもらうための営業の仕事もしましたし、ZARDやWANDS、大黒摩季などの販促もしました。GLAYも手掛けていて、当時はちょうど『HOWEVER』や『誘惑』『Winter, again』などがヒットしていた時代で、北海道でミュージックビデオの撮影に立ち会ったりもしていました。
他にもアーティストのプランニングや制作の仕事もしましたね。アーティストでいえば、松田聖子やAI、徳永英明なども担当しました。
その後はユニバーサルシグマというレーベルの代表や邦楽全体の統括を経て、2014年にユニバーサル ミュージックの社長に就任してからは会社全体を見ています。
○■ユニバーサル ミュージックは”コロナ禍によって大きく進化した”
ーーコロナ禍で音楽業界も大きく変化したと思いますが、ユニバーサル ミュージックにはどういった変化があったのでしょうか?
今になって振り返れば、コロナ禍によって大きく進化できたと思います。もちろん、最初は大変でした。
当初は「新型コロナウイルスはライブハウスから広まったんだ」という話が広がって、音楽のような不要不急のものは必要ないという風潮もありましたし、もちろんライブ活動などもできません。コロナ後の1~2年は、ライブ事業の収益はそれ以前の10分の1くらいまで落ち込んでしまいました。
ーー業界全体が大打撃を受けていたんですね。
そうですね。
アーティストたちも、ライブ活動ができないぶんのエネルギーを作品づくりに注ぐことができましたし、結果として例年より新作のリリース数は増えました。レコーディングスタジオに集まることも難しかったので、在宅で録音したり、韓国のアーティストとオンラインで録音したこともありましたし、数年後にきたであろう未来を一足飛びで経験することができました。
また、コロナ禍ではアーティストの探し方も変わりました。
ーーユニバーサル ミュージックが9年間過去最高業績を出し続けている要因も、そのあたりにあるのでしょうか?
やはり結局は“人”ですね。いい社員、いいアーティストに出会えたからということに尽きると思います。
ーー2018年には全スタッフを「正社員化」され、話題になりました。「正社員化」に至った背景をお聞かせください。
そもそも音楽業界は、社員もアーティストとともに結果を出すことに対してヒリヒリしているべきだ、と考えられていた時代がありました。2000年代初頭、“能力主義”が謳われていた頃ですね。アーティストもアスリートも、結果を出し続けなければ契約は更新できませんから、社員もそうあるべきだという考え方です。
しかし、音楽業界も時代とともに変化しました。たとえば、CDの売上は発売日をピークに、3週間で90%くらいの結果は出てしまうのですが、ストリーミングサービスはリリース日からだんだんと視聴回数が増えて、3年後にピークを迎えることもあります。つまり、長期的な視点で結果を見なければならないので、社員もアーティストも1年契約で短期的に評価するのはおかしいという話になってきます。
ーー時代の変化によって、結果が出るタイミングが変わったということですね。
私が契約社員として働いていたときも、「自分はこの仕事を長くしたいのにな」「ヒットを出し続けないと先輩たちも卒業しちゃうのか」と不安でしたし、いつ会社を去ることになるかわからないので、他の会社にもいい顔をしながら過ごさないといけないかなと思ったりもしました。でも、それってすごく不健全じゃないですか。
それに、契約社員だと結果を出している人間ほど競合からの引き抜きも多くなりますし、それは会社としても大きな損失です。株主にはこういったことを1年くらいかけて丁寧に説明し、正社員化することを理解してもらいました。
もちろん、正社員化したあとも結果を求めて会社を成長させ続けることが大前提ですし、そのために降格制度も導入しました。といっても、マーケットがほぼ横ばいの中、この10年間は右肩上がりで成長しているので、社員もアーティストもそれまでと変わらずに頑張ってくれていると言えます。
○■「日本の音楽を世界中に届ける」かつての夢が現実的な目標に
ーー最後に、今後会社として取り組みたいことや、未来の展望などについてお聞かせください。
やはり今後も新しい才能、共に歩んでいける才能を探し続けていきたいと考えています。国や人種は問いません。日本のアーティストも、もっといろんな国で聴かれる状況になってほしいとも思っています。
アメリカでも、インドでも、中国でも、北米でも、日本のアーティストの曲は通用するはずです。社長に就任したときは、これを夢として語っていましたが、今はもう目の前の目標として迫っています。
外資系企業はクールで能力主義というイメージがあるかもしれませんが、世界中の60を超える地域に仲間がいるのが我々の強みでもあります。日本の人口は1億2000万人で、今後はますます少子化も進んでいきますが、世界には大きなマーケットが広がっています。
もちろん、他の言語圏も国境を超えてきますから、競争は激化します。しかしそれは、オリンピックなどと一緒で、すごく健全な競争じゃないですか。フェアなルールのもと、日本のアーティストの作品がグローバルで輝けたら嬉しいですね。
(撮影/曳野若菜)

















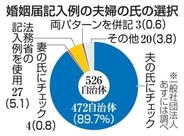







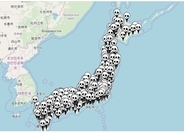



![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)








