2013年7月21日、山口県周南市の限界集落で起きた連続殺人放火事件。集落の住人だった当時63歳の男が近隣に住む高齢者5人を殺害し、被害者宅を放火するという忌まわしい事件は「現代の八つ墓村」などと騒がれ、「犯人の男は村八分にされていた」などといった噂がネット上でまことしやかに語られた。
そんな事件の真相に迫ったルポ『つけびの村』(晶文社)が話題になっている。ノンフィクションライターの高橋ユキ氏は複数回にわたって現地取材を行うも、掲載媒体が見つからず、“最後の手段”とnoteで有料記事としてアップしたところ大反響を呼び、大幅な加筆を加えて出版された。「事件ノンフィクションの定型」とは一線を画す手法で、高橋氏がたどり着いた事件の真相とは――。
***
――今年9月に刊行された『つけびの村』が扱っている山口連続殺人放火事件は、2013年に起きた事件です。本書によれば、高橋さんが取材を始めたのは17年とのことですが、なぜこの時期だったんでしょうか?
高橋 ある月刊誌からの依頼で最初の取材をしたんですが、特に何かがあったタイミングではなかったですね。
――夜這いの風習があったことが今回の事件の因縁につながっている、という話ですよね。正直、わりと眉唾な話に聞こえると思うのですが、それを元に現地に取材に行くというのがまずすごいな、と。
高橋 さすがに月刊誌でも珍しい依頼だと思います。戦中に夜這いがあったかどうかの証言を今さら取ってくるって、かなり難しいですからね。
――結局、その月刊誌では掲載できなくて実話誌に載せてもらったということでしたが、取材費は月刊誌のほうから出たんですか?
高橋 そうですね。それはありがたかったです。どんどん休刊になっていますが、事件モノをやるには、月刊誌の存在はすごく大切でした。大きいテーマで継続的に取材をして、自分なりに結論をつけて最終的に本にするという流れが立ち行かなくなっていると感じます。

――犯人がつかまって裁判にまで至っている、世間的にはひとまず「終わった」事件を追いかけるのも、ネットメディアではなかなかやれないことだと思いました。
高橋 私も普段、ネットメディアで事件モノを書かせてもらうときは、判決があったり控訴・上告があったりしたタイミングで編集さんに話をします。それくらいしか書けるチャンスがないんですね。この事件は今年7月に最高裁で判決があったので、個人的にはやっと一区切りがついたタイミングだったかな、と。
――本書の結末も、最高裁の死刑判決について高橋さん自身が考え続けるところで終わります。保見光成 (ほみ・こうせい)死刑囚は妄想性障害と判断されていて、妄想の世界を生きている人に贖罪は可能なのか、というしこりを感じていることが率直に書かれていて、これは裁判傍聴を続けてきた高橋さんならではじゃないかと思いました。
高橋 個人的に「どうなんだろうな」と思っていることを書きました。解釈はさまざまにあって、「妄想性障害であっても完全責任能力が認定されたんだから死刑になるのが当然だ」と思う人もいれば、「この状態で死刑にするのは人権的にどうなのか」と思う人もいるので、読んだ人にも考えてもらえるといいな、と。今でもまだ自分の考えはまとまっていないですね。本にも書いた通り、私は当事者でもないし遺族でもないので、どうあるのが一番いいのかはまだわかりません。
――その「当事者でもないし遺族でもない」というところで終わるのが、この本のすごいところだと思います。あとがきで「いま、普通の“事件ノンフィクション”には、一種の定型が出来上がってしまったように感じている」と書かれていましたよね。
高橋 売れる本はどこが読者を惹きつけているか知りたくて、Amazonで殺人関連のノンフィクションをランキング上位から順に買って読んだんですが、そういうパターンが多いかな、と感じます。もちろん、私はそうしたノンフィクションも好きです。でも、読者として読んでいて「これはさすがに想像じゃないか?」「ちょっとついていけないかも」と複雑な思いを抱くときもあったので、定型をあまり意識しないで書いてみようと思いました。
――とはいえ最初は、そのスタンダードなスタイルにはめ込むように取材を重ねていた、とも書かれていました。
高橋 そうなんです。
――「コープの寄り合い」で生まれていた噂の中身に迫っていくところは、特に引き込まれました。でもその後、後半では一転して村のお祭りの話が続きます。あの構成には、どういった意図があったのですか?
高橋 お祭りの話、長かったですよね、すみません(笑)。最初に原稿をnoteで公開したとき、「異様な村」「怖い村」ととらえている反応が多くて、それがちょっとひっかかったんです。確かに事件は起きたけど、同じように噂話ばかりしている集落は全国でほかにもあるはずで、私が住んでいた地元もそうでした。かつてはこの村も栄えていたときがあって、いろんな人が住んでいて地元を愛していたんだけれど、人口が少なくなったせいで噂が娯楽としての強度をだんだん増していったんだということがわかるように、栄えていた時期のことをきちんと入れたいと思ったんです。
それに、ネットの一部では「村八分」説(編注:犯人が村民から村八分に遭っており、嫌がらせを受けていたことが犯行理由とする説)が今も根強く残っていて、住んでいる人たちは事件で怖い目に遭ったのにそんなことを言われ続けるのは気の毒だな、という思いもかなりありました。
――一方で、住人の方々の家を訪れたり加害者のお姉さんたちのもとを訪ねたり、口が重いであろう当事者の方々を直撃されてますよね。私は経験がないのですが、直撃取材は怖くないんでしょうか?
高橋 私は週刊誌でも仕事をしているんですが、週刊誌記者ってわりと直撃が多いですよね。先輩記者には“猛者”と呼ばれるような人もいますが、みんな「ピンポンするのは気が重いな」って言うんです。私もすごく怖いです。でも、先輩記者たちが気が重いというのであれば、私も怖くて当然だ! と思ってピンポンを押しました。相手の方の生活を乱すことになるので罪悪感はあるし、冷たく対応されたら悲しいけど、当然だなと思ってしょんぼりします。普通の人と同じように怖いんですよ(笑)。
――加害者のお姉さん3人の取材はすべて断られてしまいますが、加害者側も残された人たちは大変な思いをするんだと、そのぶん強く感じました。
高橋 都会だったら事件が風化する速度は速そうですが、田舎だと「あの人は今どこそこに住んでる」「騒ぎになって逃げた」とか、みんながよく知ってるんですよね。これが当人だったらつらいだろうな、と取材をしていても思いました。
――濃淡の差はありますが、娯楽としての噂というのは、どこにでも存在しますよね。SNSで日々起こっていることもそうだといえますし。
高橋 そうなんですよね。SNS上で、会ったこともない人をすごく批判したり、何か決めつけてかかったりするのも、似たようなマインドだと思います。この事件についても、「村八分」説をいまだに強固に信じている人がすごくいて、人は信じたいものしか信じないんだな、というのは強く感じます。逆に今は「なんでこの人はここまでこの説を信じているんだろう? どんな事情があるのか?」っていうほうが、だんだん興味が湧いてきていますね。
――先ほどのノンフィクションの定型の話に通じるのかもしれませんが、わかりやすく一本筋が通って聞こえるストーリーを消費したいという感覚があるのかな、と思いました。
かつてのノンフィクションでは、犯人が異常な事件を起こした理由を生まれ育ちに帰結させて読者を納得させている部分があったのかなと思うんですが、実際はそれだけではないですよね。保見死刑囚も、生まれや育ちは村のほかの人とさほど変わりはないんです。ただ妄想性障害がひどくなってしまったという事情がある。でも、病気であるという結論は、読者は納得しづらいと思うんです。こんなに不条理な事件が起こったのに理由は病気か、って。その感覚もよくわかるので、『つけびの村』はそこがモヤモヤする人もいるかもしれません。ほかの書き手の方だったら、別の結論のつけ方をしたのかもしれない――と、想像はめぐらせます。でもやっぱり事件の取材をすると、こういう場合もあるんだということを、きちんと出したかったんです。
(取材・文=斎藤岬)
●たかはし・ゆき
1974年生まれ、福岡県出身。2005年、女性4人で構成された裁判傍聴グループ「霞っ子クラブ」を結成。殺人等の刑事事件を中心とした裁判傍聴記を、雑誌、書籍等に発表。現在はフリーライターとして、裁判傍聴のほか、さまざまなメディアで活躍中。著書に、『霞っ子クラブ 娘たちの裁判傍聴記』(新潮社)『霞っ子クラブの裁判傍聴入門』(宝島社)『あなたが猟奇殺人犯を裁く日』(扶桑社)(以上、霞っ子クラブ名義)、『木嶋佳苗 法廷証言』(宝島社、神林広恵氏との共著)『木嶋佳苗 危険な愛の奥義』(徳間書店)『暴走老人・犯罪劇場』(洋泉社)ほか。Web「東洋経済オンライン」「Wezzy」「サイゾーウーマン」等にて連載中。



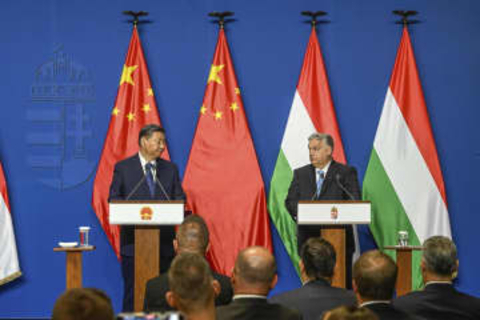


























![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)
![[医食同源ドットコム] iSDG 不織布マスクPREMIUM 50枚入り (個包装) (ふつう)](https://m.media-amazon.com/images/I/51XlQaY1QuL._SL500_.jpg)
![[医食同源ドットコム] iSDG KUCHIRAKU MASK (クチラクマスク) ホワイト 30枚入 ダイヤモンド型 くちばし型 メイクが付きにくい](https://m.media-amazon.com/images/I/51S5YMnLMNL._SL500_.jpg)








