今春、電車内で痴漢を疑われた男性が相次いで線路に逃げる事件が社会問題となった。逃走した男性が死亡し、犯人特定にいたらなかったケースもあるが、被害者にとって、痴漢はいつまでも癒えない傷となって残る。
■加害者は、ごく普通の家庭を持ったIQの高い会社員が多い
――斉藤先生の著書には、痴漢加害者は大卒で、ごく普通の家庭を持った会社員が多いとありました。三浦先生が今まで弁護のために接してこられた痴漢加害者も、そのような印象でしたか?
三浦義隆氏(以下、三浦) 犯罪者全般を見ると、言い方は悪いですが、窃盗や傷害などの加害者は、貧困の方や身寄りのない方、成育歴の悪い方が多いです。しかし、強姦に至らないような痴漢や盗撮といった性犯罪は、斉藤先生のおっしゃる通り、社会的地位もあって収入も普通以上にある、妻子もいるという人が目立って多いです。
斉藤章佳氏(以下、斉藤) 比較的、知的レベルが高いですよね。痴漢加害者は、我々が通常依存症治療の中で接する人より、社会的地位やIQが高い人が多いです。
三浦 痴漢をやっているか、やっていないかは別として、逃走してしまうケースが非常に多いのは、失うものが大きいからという側面が強いと思います。
斉藤 実際に、我々のクリニックに来られる人の中にも逃げた経験のある人がいます。捕まった後の自分の人生を、一瞬のうちに考えるようです。もし捕まったら、仕事と家庭を一気に失ってしまう可能性があるのは、通常のサラリーマンだったら想像できることです。
三浦 痴漢をやっていて、最終的には自白に至ったケースでも、初回接見に行ったときに否認するパターンはかなり多いですね。やはり、「認めてしまえば人生おしまいだ」という意識があって、証拠からは争っても筋が悪いのではないかと思われる案件でも、当初は否認するケースがよくあります。
――やっていても、やっていなくても、逃げる人が多いということですか?
三浦 それはどちらもあると思います。やっていなければ逃げなくていいじゃないか、という理屈もありますが、現実的な不利益を考えると、必ずしも得策ではないという面が、かつてはあったわけです。否認していると勾留されてしまう「人質司法」が以前はありましたが、今は若干改善されてきて、特に痴漢については、最終的な処分がどうなるかはともかく、否認していても20日間勾留されるなんてことはそうそうありません。ですから、そこで逃げてしまうのは得策ではないと、ブログやメディア出演の際に繰り返しお話ししてきました。
ただ、『それでもボクはやってない』(2007年公開)という映画の影響が大きいんですよ。あの映画は、刑事弁護をやっている弁護士から見て、当時の現実としては非常にリアルなものが描かれていたと思うんです。
斉藤 仮に、痴漢をしたという前提で、人間は瞬間的に失うものの大きさを比較するわけです。もし、常習化していて自分でやめられないと本人が自覚している場合、初犯だと裁判になったときに執行猶予がつくかもしれませんが、件数が多いとか悪質な場合は実刑の可能性もある。薬物事犯などは初犯の場合、だいたいの量刑がイチロクサン(懲役1年6カ月執行猶予3年)と決まっています。痴漢の場合も、初犯の量刑相場はある程度決まっているのですが、初犯の裁判の判決段階で、執行猶予判決と同時に義務として治療プログラムへつながるような制度が作れれば、というのが私の見解です。
しかし、このシステムの場合、気をつけないといけないのが、常習化した痴漢行為の治療が、本人の行為責任を軽くするために利用されるというリスクもあるため、その治療導入の入り口部分は厳密に精査して、治療可能性も含めたリスクアセスメントと、取り組む意思があるのかを確認した上で治療へ導入するシステムがあればと、常々考えています。
三浦 厳罰を科すという、行為に対しての責任をきっちり取らせることと、本人の行動を改善することは、なかなか両立しにくい面があると思うんですよね。覚せい剤もそうですが、依存の絡むような犯罪については、実刑を科したところで本人の更生にはつながらないというか、むしろ更生の道を狭めてしまっているのではないかと、普段、弁護活動をやっていてもなかなか忸怩たるものがあるわけです。
刑罰の意義というのは、本人を矯正することだけではなく、社会一般へのアナウンス効果もあります。社会全体の人が犯罪を犯さないよう、あらかじめ「こういう行為に対しては、こういう罰が科されますよ」と告知しておいて、実際にやった人にはきっちり責任を取ってもらう。
覚せい剤の件で言えば、被害者のいない犯罪ですから、安易に実刑にせず、もっと治療寄りになってもいいと思います。
――斉藤先生の著書から、例えば「女性が痴漢されたがっていて誘っている」といった加害者の「認知の歪み」が痴漢の原因のように感じられたのですが、弁護する側の三浦先生から見ても、認知の歪みを感じ取れますか?
三浦 長期的に治療する観点から関わっているわけではありませんが、斉藤先生が先程おっしゃった通り、知的レベルも高い人が多いですから、どちらかというと認知の歪みをあけすけに言ってしまうより、模範解答的なものが出てくる傾向にあるように思っています。ただし、斉藤先生のご著書にもありましたが、やはり被害者に対する謝罪の言葉がなかなか出てきにくいと感じることはあります。
斉藤 ここが治療の中でも非常に難しいところで、まず重要なのが問題行動(痴漢行為)をやめさせることです。治療では本人の内面の変容よりも、再犯させないことが最優先事項です。問題行動は、さまざまな治療教育的なプログラムを受けて再発防止スキルを身につけて、うまく回避・対処できるようになってきます。
――具体的には、どのようなアプローチでしょうか?
斉藤 考え方としては、「今日一日」再発しないためのリスクマネジメントを毎日積み重ねることで、年単位で内面が少しずつ連動するように変容していきます。例えば、問題行動につながりやすい発想や認知の歪みが出てきたときに、昔ならそこが引き金(トリガー)となって行動化していたものを、プログラムで学んだ対処方法でうまく回避して「こういう考えが出てくるのは危ない。警告のサインで、前と同じ悪循環のパターンだ」と、自分の中でうまく対話(セルフトーク)できるようになるんです。この積み重ねで、1年ではそう大きく変わりませんが、3年ほどたつと少しずつ話し方や人との接し方、女性への考え方が変化してくる。
世間が期待する変容(反省や贖罪)と、実際目の前にいる人が変わっていく順番が違うのは、世間との大きなズレのひとつかもしれないです。裁判の中で反省を求めることもありますが、いきなり内面を変えていくのは難しいと思います。従って、著書にも書きましたが、裁判で読み上げる被告人の「謝罪文」が上滑りして聞こえるのは、そのためかもしれません。
三浦 裁判所も検察庁もそうなのですが、通り一遍の反省というものではなくて、行動変容につながるような手立てを具体的に打っている、というところをもっと重視していくべきだとは思います。刑事弁護人がそのような動きをとっていて、裁判所が応えてくれることもあるのですが、裁判官によってまちまちという現状があります。また、ご著書にもありましたが、私も加害者による謝罪文や反省文はあまり意味がないと思っていて、書かせないことが多いです。反省文を裁判所に出しても、実際にはほとんど重要視しませんからね。ただ、示談交渉をする際に、被害者ご本人から求められるケースは時々あるので、その場合は書かせて出しています。
(姫野ケイ)
(後編に続く)

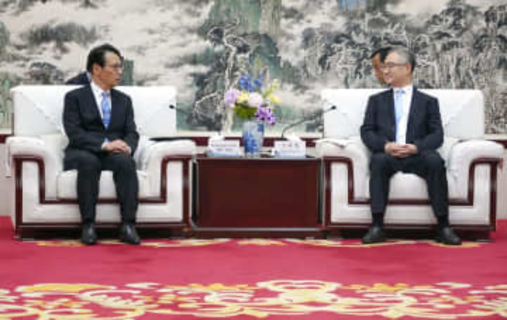































![[山善] 40型 液晶 テレビ フルハイビジョン Wチューナー (裏番組録画 外付けHDD録画 対応) QRTN-40W2K](https://m.media-amazon.com/images/I/51NPC4ZvImL._SL500_.jpg)
