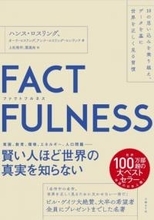震災から2ヵ月半、いま俺たちが聞くべきは、戦争を体験し、そこを力強く生き抜いてきた加藤さんのことばなんじゃないだろうか、そう思い、取材依頼の電話をかけた。
(取材日:4月22日)
天井に穴があいた
加藤 計画停電はありましたか?
ーーそれが一度もなかったんですよ。都内なんですけど。
加藤 あら……ない? ぜひ経験して欲しかったのに! あたり一帯、真っ暗になる。そんな思いをするいい機会だったのにねえ。残念だわあ。
ーーす、すみません。
加藤 「我に七難八苦を与え給え!」
ーーえ?
加藤 毛利と戦っていた山中鹿之介は三日月に向かってこう祈っていたのです。
ーーし、鹿之介?
加藤 毛利元就は知っているわよね? 出雲地方の戦国大名で毛利に亡ぼされた。尼子勝久の重臣で、こういう字を書くの尼子家再興に力を尽くす。あ、ペンを貸してくださる?(紙に名前を書き出す)。
ーーへえ。
加藤 歳はあなたぐらい、いやもっと若いかも。若い人は苦労を乗り越えなければ駄目。それが鍛えるということになるんですよ。
――若い時の苦労は買ってでもしろと親からも言われたことがあります。
加藤 でしょう? おっしゃる通り。でも、「わざわざ苦労を呼び寄せるなんて変わった人ね」なんて言う人もいる。
――あ、はい。
加藤 (お茶を入れてきて)ありがとう。あのね、いまの若い人たちは、物も豊かで社会の仕組みがある程度できあがっている状態から出発しているでしょう。自分ができること、しなくてはいけないことがあまりないのではないかと感じているのではないかしら。
――自分がやらなくても、他の誰かが動いてくれるような?
加藤 天井がなくなってしまったでしょう。
――えっ?
加藤 今まで気付かなかったでしょうけど、あなたたちは大人のつくったシステムに守られていて、この平和がずっと続くと思っていた。頭上には、大人たちの作った天井があった。その安心の天井に、今回の震災で穴があいたんでしょ? 私たちの若いときには、そんなものなかったの。日本は戦後、一日にお芋二、三本からがんばって、世界第三位の経済大国になったんですよ。いま、その天井のあちこちに穴があいて、経済が危なくなるんじゃないか、自分たちも何かしなくてはと思うようになってきたと思うんですよ。街中や電車で見かける子供たちの顔を見ると、そういう気持ちになっているような気がするんです。自分から被災地に向けてメッセージを書いたり、義援金を集めたりしているでしょう。
――たしかに僕も以前より気付くようにはなったかもしれないです。レジの横の募金箱に小銭を入れたり。
加藤 小さな一歩ですよね。でも、それが大事。いまの若い人たちの天井は壊れてしまった。私たちが若いときは大人たちは天井をつくる余裕がなかったから、ぽっかりと大きな穴から空が見えていたの。天井をつくるどころか、戦争に行って、死ぬ。戦闘機が飛んできたり爆撃されたり……日本の空はめちゃくちゃだったんですよ。女学生だった私たちは、よくもあんな強い相手と戦争をして、それに勝てるという判断をどうしてしたのかという気持ちでいっぱいでした。
みんな立ち上がって働き出した
――戦時中からずっと思っていたんですか?
加藤 はい。大東亜戦争がはじまったときから、クラスでは「この戦争は間違っている」「負ける」とそっと言う生徒たちもいました。私たちの女学校は、かなりリベラルな雰囲気でした。敵国語禁止の時代に、米英やフランスの歌を歌ったりして。でも、女学校三年(中三)のときに勤労動員になると、私たちはお国のために工場で一所懸命働いていたんですよ。だけど、そのことと戦争に勝てると思っているかどうかはまた別ですよね。
――無理だとは思っていたけど、労働に駆り出されたらそこはきちんと。
加藤 それはもちろん、別のことですからね。英語を勉強してはいけないと言われていましたけど、隠れて勉強をしていましたからね。
――以前インタビューで伺いました。夜、友だちの少女たちで集まって、英語ができる方のところへ行き勉強会を開いていた。
加藤 その勉強会に行くのだってうかうかしていられないんですよ。いつ、爆撃されたり、戦闘機が飛んできて機銃掃射をしてくるかわからない。人が逃げ込めるように、どこの線路の脇にも防空壕が掘ってあるんです。
――線路脇にまで。
加藤 クラスメイトの話なんですけど、京王線で家へ向かっているときに突然空襲警報が鳴って、戦闘機が襲ってきたんですって。防空壕に逃げこみながら彼女は「私はここで死んでしまうかもしれない。お母様は私がここに死んでいるとはわからないだろうな」と思ったんですって。機銃掃射が終わって外に出てみると、電車の車体がボコボコ。
――車中にいれば殺されていた。
加藤 そういう現実も、ついこのあいだまであったんですよ。戦争が終わって戦闘機は飛んでこなくなり、家の電気を点けられるようになった。「今夜からパジャマに着替えて眠れる」この1文からどういう情景をイメージなさるか聞いたのを覚えていらっしゃる?
――はい。毎晩のように警戒警報や空襲警報が鳴って、すぐ庭にある防空壕に飛び込まないといけないからですよね。
加藤 そう、いままでズボンにゲートルをまき、すぐ逃げられる格好で寝ていたのが、やっとパジャマに着替えて安心することができる。あのときは答えがわからなくて、あなたは、一日中パジャマを着ていることもありますとかおっしゃっていたけど(笑)、震災があった3月11日、布団に入って熟睡できた? できなかったでしょう?
――できませんでした。実家が茨城なので被災しているとニュースで報道されていたんですけど、電話がつながらないので安否がずっとわからなくて……。余震もなんどもあって、心配で布団に入ることすらできなかったです。
加藤 そう。大変だったわね。あのころも日本は敗戦で一時的に駄目になっていたけれど、みんな立ち上がって働き出したんですよ。
――その立ち上がることがいまこそ必要。
加藤 そういうこと。
自分たちの足で立たなくてはいけない
――どうして日本は立ち上がることができたんでしょうか。
加藤 負けたままでいいはずがない! という気持ちが強かったんです。あのころの東京近辺の大人たちは関東大震災を経験しているんですよ。日本人は非常に我慢強くて前向きなところがありますから、東京はめちゃめちゃになったけれど、新しく設計しなおして素晴らしい都市にしたんですよ。あのときだってできたんだし、今度もまたできるとみんなが思っていました。
――負けたままというのは、戦争に対して?
加藤 そう。戦争に負け、占領されているから、その場で偉いのは進駐軍になりますよね。そうしたとたん、このあいだまで「鬼畜米英」と言っていた多くの大人たちの態度がころっと変わったことに対して、すごく腹が立ちました。電車も進駐軍専用車両なんてのがあるんですよ。横須賀線なんて普段は混みすぎて椅子の上にまで立つくらい。ガラス窓も今よりガラスがもろいから、ギュウっと押すと割れちゃって、血まみれになっている人もいました。
――うわー……。
加藤 専用車両を見るとガラガラで、進駐軍は売春婦を連れて座っているわけですよ。当時はパンパンって言っていましたね。あるとき、こちらの車内はもう満員なのに入り口の方から人々が押してくる。なんだと思ったら、ふたりのアメリカ兵が入ってきて乗客をビール瓶で殴っていたのだそうです。見えないけれど、前の方の人たちが叫んでいた。
――ええ、ええー!?
加藤 次の駅に着いたらふたりを押し出そうと、まわりの日本人たちに、なんで大人しく殴られているんだ! って言おうと思って。私は、押してくる人々を押し分けて、逆に前へ進もうとしました。強く押し返され、結局はできなかったけれど。戦争に敗けて、強いはずだった男性たちも萎縮してしまったのですね。
――すごいですね。それはおいくつのとき?
加藤 高一でした。ほんとうにくやしくて、そういうのを見るたびに怒っていましたね。
――その当時の大人への不信感はかなり大きいですね。
加藤 かなりありました。今の若い人たちは、大人たちがこの社会を作ったから、偉いと思っているんじゃないでしょうか。今回、それが少しでも崩れたのは、いいことだったと思うんですよ。
――「大人なんかあてにできない」が加藤さんのいままでの原動力になっているんですよね。
加藤 そうなんです。ただ、日本を見事に復興させたのは、そういう大人たちなんですよ。だから表面だけ見ていてはいけないのかもしれない。あなた、一度被災地にいって瓦礫の山の中を歩いていらっしゃい。
――え。
加藤 昭和20年3月10日の空襲によって、東京の下町では10万人も死にました。私はその場にはいませんでした。家が山の手なので、2階から町中に火の手が上がっているのが見えたんですよ。あそこで逃げ回っている人たちがいるのかと思って……。
――それは……。
加藤 話を聴いたりテレビで観るのと、自分で現場に行って体験するのは全然違うんです。そんな遠いところではないでしょう? 瓦礫の下にはまだ遺体が埋まっているかもしれない。自分の眼で見て、考えるのは非常に大切なことですよ。戦争で亡くなった人たちや、今回の被災者たち、肉親を失った方たち、お気の毒だと思います。でも、もしかしたらこれは若い人たちにとって、こういうことが起きる。自分たちの足でもって立たなくてはいけない、というメッセージなのかもしれない。
――僕たちが受け取るべき教えなんですね。
加藤 今までにも地震が来ると言われていたり、原発も大丈夫だと言っていたけれどこの有様でしょう。こうなるということがわかったのは、ものすごい警告であると同時に教えでもあるんです。これからは経済的にも下りますからね。それを立て直すのは現代の山中鹿之介。若い人たちにかかっているんですよ。
(加藤レイズナ)
part2