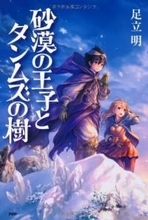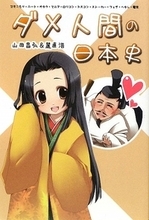例えば、菓子折りに賄賂を忍ばせて商人と役人が悪い笑顔を浮かべるシーン。
この3つのシーンは誰でも目にしたことがあるはずだ。もはや定番ともいえるほど繰り返し使われているのは、これらを登場させることで物語の状況を、みている私たちに伝えてくれるかららしい。このような物語中の“食べ物が出てくるシーン”とその意味を探っているのが『ゴロツキはいつも食卓を襲う』という本だ。
この本によると、賄賂を菓子折りに忍ばせるのは、甘いお菓子には“抗いがたい誘惑、我慢できない欲望”といったアイコン付けがされているから。張り込み中の刑事の食事があんぱんと牛乳なのは、携帯食として張り込みの緊迫感が演出できるから。さらに鑑賞者が食べたことのある、つつましく、ささやかなものを相棒刑事と一緒に食べることでより二人の関係性が近くなるからだ。失恋した女性がケーキなどの好物をやけ食いするのは、好物を思いっきり食べることで喪失感を埋め、失恋の痛手を吹っ切ったということを伝えてくれるから。
確かに私たちは無意識のうちに、このようなニュアンスを受け取っている気がする。「もっと詳しく知りたい!」と著者の福田里香さんにお話を伺った。
「物語に食べ物をうまく登場させると、登場人物の性格や感情、置かれた状況を、鑑賞者へ伝達するのにきわめてスムーズに働くようで、これらの現象は3つの原則にまとめられると考えています。
福田さんはこれを“フード三原則”と呼んでいる。今までみてきた、読んできた物語を思い
出してみると、どれも当てはまっている気がする。
「登場人物が口を開けておいしそうに食べ物を飲み込めば、私たちは親近感を持ちます。その人物が腹の底を見せたからです。何も食べない人物は訝しく感じます。腹の底が見えないからです。また、おいしそうな目玉焼きに吸い差しの煙草をじゅっと突っ込むなどと食べ物を粗末に扱えば、確実に善人には見えませんよね」
先日みた映画で、主人公がヒッチハイクで出会った男と楽しくご飯を食べているシーンがあった。得体の知れない男なのになぜか安心して、親しみを持つことができたのは、フードシーンをみたからかもしれない。その男が食べることで相手に腹の底を見せてるから、この人は敵ではないんだと感じとったからかもしれない。そういう風に、フードシーンに注目して物語を楽しむのも面白そうだ。
「食べ物は、物語の演出上、感情の機微を伝えるための優秀な装置として機能し、キャラクターの特性をひと目で表すためのアイコン的な役割も果たしています。まずは自分の好きな作品を、フード目線でもう一度鑑賞してみてください。
外に出るのが億劫になる梅雨の季節。物語に触れることが多くなりそうだが、その際は、ちょっとフードシーンに注目してもらいたい。
(上村逸美/boox)