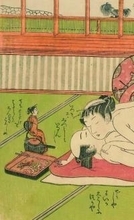そんな忍者の概念を打ち破る企画展「THE NINJA -忍者ってナンジャ!?-」が、開催中だ。監修を担当した三重大学人文学部・山田雄司教授に、知っているようで意外と知らない、忍者の秘密を聞いた。

実際の忍者は戦わなかった? 意外にも地道なその作戦
――忍者といえば、ひそかに暗躍する姿が思い浮かびます。実際はどうだったのでしょうか?
敵の屋根裏や床下に忍び込んで盗み聞くのではなく、普通の人に紛れ込んで情報を得るほうが多かったです。忍者に大切な能力は、「臨機応変な適応力」、「見聞きしたことを覚える記憶力」、「コミュニケーション力」とされ、特に相手から情報を聞き出すためのコミュニケーション力は重要視されました。

――忍者はどんな忍術を使って活躍してきたのでしょうか?
忍者は命令を受けると「ははっ!」と、すぐさま敵国に乗り込むと考える人も多いでしょう。しかし、敵城の壁が高くて忍び込めないときは、遠くから穴を掘って忍び込んだり、壁に塩水を毎日吹きかけて腐らせたり、すごく地道な計画を行っていました。
また、忍者は体力以外にも、儒教、薬草、火薬、天文学などあらゆる知識を持っていました。その知識を得るために、地道にコツコツ研究を重ねていたのです。

――三重大学で忍者について教えている山田教授、特に学生たちが驚くことは何ですか?
多くの学生たち「忍者は戦わない」ということに驚きます。どうしても敵と戦うイメージがあるようです。しかし、戦ってしまえば死ぬ確率が高くなり、情報を伝えられなくなってしまいますよね。
実際には無意味な戦いを避けるために、任務を遂行することもありました。敵国の軍事力の情報を得て戦を中止したり、敵国の政策で良いものは自国で生かしたりと、平和的に利用されることもあったんです。

忍者が愛されるのには理由があった
――忍者が、これまでたくさんの人に愛され続けていますが、それは何故だと思いますか?
技や術の面だけでなく、忍者の「しのぶ心」や「耐える姿」が日本人の心にマッチしたからこそ、長いこと愛されてきたと思います。日本でもこれらが美徳とされてきました。そうした精神が、現在まで続く日本の土壌を培ってきたのだと思います。

忍者に関する資料や文献には、信憑性に欠ける物や、資料自体を手に入れるのが難しい物があり、研究は一筋縄ではいかないという。それでも山田教授が、忍者の真実の姿を追い求めるのには理由がある。
――忍者の魅力はどんなところでしょうか?
忍者というのは、時代によっては疎外された者として扱われたり、スーパーマンとして活躍したり、学校で忍術を学んだり、いろいろな描かれ方をしています。海外では、忍者はSF風のものも含め、現代で活躍するキャラクターとして描かれているんですよ。時代に合わせた忍者像が作られているのが面白い。

忍者は正体が謎に包まれているからこそ、多面的な描かれ方ができるコンテンツとして魅力的だという。

――科学的観点から忍者を研究した今回の企画展「The NINJA -忍者ってナンジャ!?-」。新たに分かってきたことはありますか?
忍者が行う「印を結ぶ」という行動は集中力を高めたり、解いたりすることができるんです。ただのパフォーマンスではなく、理にかなっていることだとわかってきました。

山田教授、実は印を結ぶのが苦手だとか……。「指が硬いので忍者失格ですね」と笑う。また、気持ちを落ち着かせるため、忍者の呼吸法などを普段の生活に取り入れているとのこと。

忍者のように、地道に取り組む姿勢を身に着けて
忍者は心・技・体を鍛えるために地道に鍛錬していたので、この企画展で子供たちにもコツコツと地道に取りくむということを体感してほしいと山田教授は語った。歴史の裏で鮮やかに活躍していたように思える忍者たち。実は、大変な努力を日々重ねていたのだ。


企画展「The NINJA -忍者ってナンジャ!?-」は、日本科学未来館で7月2日(土)から10月10日(月・祝)まで開催。私たちの知らない忍者に、この夏出会える。
(唐沢未夢/イベニア)