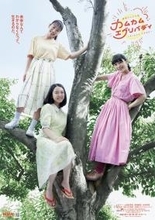第12週「お笑い大阪 春の陣」第72回 12月23日(土)放送より。
脚本:吉田智子 演出:本木一博 高橋優香子

71話はこんな話
オチャラケ派の芸人・総勢150人もが北村笑店に寝返った。文鳥(笹野高史)も北村笑店に加勢して、寺ギン(兵藤大樹)もいよいよ年貢の納め時に・・・。
てんの株急上昇
風太(濱田岳)を先頭に練り歩いてくるたくさんの芸人たち。大人数のエキストラが投入されて、画面の密度がぐっと上がった。
藤吉(松坂桃李)はその様を「戦でもはじめるのか」と例える。
あとから、真打ち登場とばかりに現れた文鳥は「大阪 春の陣」と。
余談だが、濱田岳は「信長協奏曲」(14年フジテレビ)で徳川家康を演じていた。
芸人をもの扱いする寺ギンVS家族だという北村笑店
芸人流出を食い止めるため、彼らに借金返済を迫る寺ギンに、てんは、へそくりから2500円を肩代わりすると大英断を下す。
2511円50銭を壺にへそくりしていた妻を、藤吉が「でかした、てん!」と大絶賛。やっと褒めてくれましたねって感じだ。
文鳥は、てんがカレーうどんを作ってくれた6年前と同じ着物を着ていることに気づく。
寄席が繁盛しているなかで、贅沢しないでやってきたてん。「始末、才覚、算用」の北村家の家訓を守っていたのだ。
寺ギンはおとぎ話のワルモノ
「芸人さんみんな家族やと思ってます」「(困った)家族にお薬をあげるのは当たり前」と言うてんに、文鳥は、落語「貧乏花見」(長屋で肩寄せいあいながらおもしろおかしく暮らしている人たちの話)を例に上げ、「ここなら、貧乏でも毎日笑って暮らせそう」と伝統派53名を北村笑店に出すと言い出す。
希望に満ちたすてきな劇伴がかかるなか、寺ギンだけ圧倒的に分が悪い。
「そんな殺生な」とあたふたする寺ギンは、すっかり牙がもがれ、かわいらしい感じになっていた(たぶん、兵藤大樹にはこっちのほうが似合っている)。
てんはあくまで懐広く「いっしょに、仲良うやり直しませんか」「笑いは作る人がわろてんと、お客さんも笑わない」とこわい顔ばかりしている寺ギンを諭す。
反省した寺ギンは、寄席と芸人を全部、藤吉に託し、お坊さんに戻り、諸国行脚の旅に出る。
おとぎ話のワルモノ退治の構造である。
おとぎ話と思えば、キャラクターを細かく描写せず、いい者、悪者と簡単に色分けてあるだけで十分だ。
とはいえ、最初は純粋に笑いを追求していた寺ギンが、次第に金の亡者になってしまった課程をもう少し丁寧に描いてほしかった。
番頭になった風太
オチャラケ派との戦いは終わり、平和が戻ってきた。
芸人たちのクーデターを率いたとはいえ、寺ギンの下で働いていた風太は、どこかへ去っていこうとする。
てんは引き止め、風太を北村笑店の番頭に迎えたいと言う。
番頭
番頭
番頭
何度も繰り返す風太。京都の藤岡家の手代止まりだったため「いっぺんだけでも番頭さんって呼ばれてみたかった」と感無量なのだ。暖簾分けしてもらって、番頭通り越して当主になれたはずが、どういう発想なんだろうか。商人にとって「番頭」ブランドはそれほど重要なことなのか。
なにはともあれ、北村笑店は200人以上の芸人を抱え、日本演芸史上初、寄席のチェーン店化をすることに。千日前に規模の大きな南地風鳥亭がオープンした日は、団吾(波岡一喜)と文鳥が口上をつとめた。
団真(北村有起哉)もきっとこの寄席チェーン店の何処かで落語をやっているに違いない。
これだけ、影も形もなくなっているのは、まさか、台詞で名前を出すだけでもギャラが支払われるというシビアな契約でもあるのかと、ひと妄想。
(木俣冬)