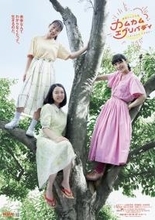第16週「笑いの新時代」第90回 1月19日(金)放送より。
脚本:吉田智子 演出:川野秀昭

90話はこんな話
団吾(波岡一喜)がラジオに出ることを止めようと、風太(濱田岳)はラジオ局で待ち伏せるが、放送ははじまり、団吾はしっかり出演していた。
落語の使い方はうまい
話の構成が甘いにもかかわらず、視聴率は20%を保ち続け、ドラマに口うるさい層をやきもきさせている「わろてんか」。ここのところ、週平均視聴率は2週続けて20%を切っており、このまま下がっていくのか持ち直すのか気になるところではあるが、ながらく辛抱して見続けていると、ごくたまにキラリ流れ星をみつけて、報われる瞬間がある。
さて。
89話で団吾は「死神です」と藤吉(松坂桃李)の見舞いにやって来た。
師匠が風太をまんまと巻いて京都のスタジオで行ったラジオ初出演の演目は「死神」。貧しい男の元に死神が現れて、寿命が見える能力を授ける。おかげで金持ちになった男が、あるときその力を悪用してしまう、というようなお話。
この落語の使い方がうまかった。
16週の藤吉の生死にまつわるエピソードのみならず、ドラマの最初からの興味だった、藤吉がいつ死ぬのか問題と、「死神」の内容がうまくかかっていたのだ。
「わろてんか」における藤吉の寿命を、最終的に、主人公が死ぬのか、死なないのか・・・とやきもきする趣向になっている「死神」のように描いたということだろう。
起死回生
藤吉の寿命があとどれくらいかはさておき、一度は三途の川を渡ろうとしながらも戻ってきた藤吉は、助かった命を大事に、新たなことをやっていこうと考える。
時代は、団吾が言うように、写真やラジオなど新しいものが生まれ、移り変わっている。
寄席のメンバーたちは、風太を筆頭とするラジオ反対派と、賛成派に分かれていたが、東京に行っていた万丈目(藤井隆)は、そこで新たな芸を見て刺激を受け、自分ももっと芸を磨いていこうと考える。
隼也(大八木凱斗)は、一番の冒険は、お父ちゃんの後を次いで、お父ちゃんを超えることだと決意し、そのためには大学に行くという。
みんな、それぞれ、前を向きはじめた。
死んだ気になってがんばる。死と再生。
1月17日をはさんだこの時期に、こういったエピソードを描くのは、制作者たちはやっぱり忘れていないのだと思う。
「べっぴんさん」でも明示はしたくないが思いはあるとプロデューサーは言っていた。答を明示したくない朝ドラ『べっぴんさん』であえて語らなかったことを三鬼Pに言葉にしてもらいました
その心は「わろてんか」にもあるのではないだろうか。
まだ91話が残っているが、落語に詳しい後藤高久プロデューサーと、いい元ネタさえあればそれをキレイにまとめることができる吉田智子(「君の膵臓を食べたい」で今年度の日本アカデミー賞優秀脚本賞受賞)の能力が最大限に発揮された会心の週だったと思う。
ピンチをチャンスに
「死神」は、主人公が、途中、ピンチをチャンスにして助かるところがある。
1月19日の「わろてんか」の放送のあと、「あさイチ」に松坂桃李が出演した。
このとき、有働由美子が、松坂桃李の出演作のひとつ「パディントン」で声を震わすテクニックについて話題をふり、松坂はそれをその場で実演した。
これには驚いた。
なぜなら、「わろてんか」で松坂の発声が震えているという意見がネットであがっていたことを、テクニックであると暗に反論したかにも思えたからだ(私は「わろてんか」における松坂の発声を問題に思ったことはない。
落語「時うどん」を語る場面についても、台本になかったが急に演出家に足され、笹野高史の落語シーンの撮影を見て叩き込んだと説明した(文鳥を、団吾と間違えてしまったが、これは生放送ならではのご愛嬌)。
話題にすることで、さらに傷に塩を塗りかねないことを、あえて言葉にした、その勇気を讃えたい。
落語では、「もうじき死ぬよ」といわれた主人公は必死で寿命を伸ばそうと奮闘する。
はたして藤吉はどうなるのか。
(木俣冬)