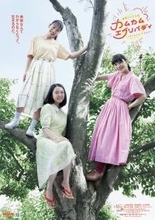第2回「立派なお侍」1月14日放送 演出:野田雄介

1月20日放送の「土曜スタジオパーク」で、林真理子先生は「直木賞作家」の肩書についで「大河作家(原作者)」の肩書を得たことを誇らしく語っていた。
直木賞作家にして大河作家(原作者)は過去、どんな作家がいるか調べてみると、
司馬遼太郎、海音寺潮五郎、城山三郎、永井路子、山崎豊子、杉本苑子、新田次郎、陳舜臣、高橋克彦、宮尾登美子、と錚々たる作家たちであった。
林真理子先生、すごい。
だが、直木賞受賞作「最終便に間に合えば」「京都まで」の「京都まで」は京都が舞台で、「西郷どん!」も京都からはじまっている。彼女にとっては京都がラッキースポットなのではないか。
林真理子先生の原作「西郷どん!」は、上巻で安政3年、篤姫の婚儀まで進んでしまう。けっこう駆け足な展開(たくさんの資料を読み込んで勉強したことを短くわかりやすくまとめるほうが大変だと思う)なので、脚本の中園ミホ先生は、一足飛びの足跡を、一話一話、丹念に広げていかないとならない。
はじめのほうは、西郷が翔ぶための、土台を着々作っているようで、「失敗する西郷さん」の「失敗」を描く。
2話では、1846年、18歳になった吉之助(鈴木亮平)が、大きな挫折を味わうエピソードだった。
泣く、西郷さん
1846年、18歳の吉之助は、藩(薩摩)の農政と年貢の調整を行う「郡方書役助」(こおりかたかきやすたすけ)という役目に就いていた。
農民から上納米を集める仕事だが、その年、長雨と冷夏で稲がやられてしまい、上納米を納めることが難しい。
吉之助は農民に同情し、上納のシステム変更を提案したり、借金のかたに売られそうになる娘・ふき(柿原りんか)を助けようとしたり奮闘するが、力及ばず、己の非力さを痛感する。
1話に続き、伝えたいことをシンプル、かつ丁寧に描いて、誰にでもわかりやすい。
まずは、吉之助の周辺の人々の、貧しい生活を描く。白いごはんを食べたことのない農民の子どもたち、貧しいのに子だくさんの西郷家(ドラマでは書いてないが、原作で書かれているところも面白い)、取れ高に応じて上納米の分量を変える検見取りのほうがいいかと思えば、隠し田を作っている農民には嬉しくないなど、いろいろ事情が込み入っていて、正義を貫くことは簡単ではなかった。
出だしは、賄賂をもらっている役人(おかやまはじめ)を出し抜いてふきを助けることに成功したり、検見取りを提案したり、吉之助の行動が弱い者を救っているように見え、「立派なお侍さん」と呼ばれ、自尊心がくすぐられる。
自分は立派なお侍さんなんかではないという現実に打ちのめされる吉之助の、最後の泣きは迫真だった。
視聴率は、1話に続いて2話も15%台と低かったが、鈴木亮平には誠実さがあるから、次第に多くの視聴者に愛されていくのではないかと思う。
「西郷どん」は何を描くか
まだ何者でもない少年(小吉)に「強くなれ」「か弱き者の声を聞き、民のために尽くせる者こそが真の侍になる」と鼓舞し、彼の人生に大きな影響を及ぼした島津斉彬(渡辺謙)と、幼馴染にして、ひじょうに優秀な青年・大久保正助(のちの利通〈瑛太〉)が配置されている。
瑛太の活躍は、これから楽しみにすることにして・・・やっぱり渡辺謙(斉彬)。
この人はこの人で、悩みを抱えていた。
父・島津斉興(鹿賀丈史)は斉彬よりも、弟の久光(青木崇高)のほうを、跡継ぎにしようとしている。
そのことを、藩の者たちは「(側室)由良(小柳ルミ子)のいいなり」と揶揄していた。
時代的にも、土地柄的にも、男尊女卑がまかり通る地域ではあるが、「好きな女には抗えない」などという
台詞も出てきて、女が意外と政治に関与していることを暗に書いているのが面白い。
女を知る者、知らぬ者で、青年たちは大騒ぎ。美味しそうな鯛をだめにしてしまう。
それを女の糸(黒木華)に「食べ物を粗末にする人間がお国の将来を語るなんておこがましか」と叱られて、男は女に形無しという印象を醸す。
とはいえ、決して、男性と女性、どちらが優れているかというような比較をするわけではなく、男だからこう、女だからこうと規定することのナンセンスさが描かれているように思うだけだ。
大事なのは誰もがちゃんと生きられることだから。
1月20日放送の「土曜スタジオパーク」には、時代考証の磯田道史も登場し、林真理子の原作には、国家とは何かが描かれていると語っていた。「死にたくない」という思いが集まったのが国家で、「死なせない」のが政治家の役割だと。つまり、国家とは国民すべてが生きられるためのものであるということだ。一部の人だけが生き残るためのものではないという、まさに、いまの日本が直面している命題だ。
西郷どん、がんばって。
「チェスト」、流行るかなあ。
中園ファミリー
「西郷どん」で夫婦役となる鈴木亮平に黒木華は、早朝再放送している朝ドラ「花子とアン」(14年)で、主人公の花子の夫と妹役で出ている。2話で泣かせてくれたふきは、やがて大人になって高梨臨(浦和レッズの槙野選手と結婚を発表して話題の)が演じるという。彼女は、花子の親友・醍醐さんを演じていた。
鈴木、黒木、子役の柿原が並ぶと、鈴木、黒木、高梨と脳内変換が行われて、「花子とアン」に意識がいってしまう。
昔から、自分の作品を的確に表現してもらうために、作家や監督が同じ俳優を起用することはよくあることなので、それはそれで楽しいものだ。
「国家」とか「ファミリー」とか、集団をどう規定するかは、興味深い問題である。
(木俣冬)