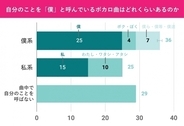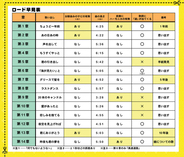真ん中に投げれる球を持っていながら、守備範囲は広くしようって考えている人とやるほうが音楽は楽しい。刺激的だしね(森重樹一)
自分の中で決めちゃうと、その時点で狭まっちゃうから、おもしろくないんですよね(千聖)
2017年8月の千聖ソロデビュー20周年記念イベントへ出演してもらったことをきっかけに、今では食事にもよく出掛ける間柄のPENICILLINの千聖とZIGGYの森重樹一。
(取材・文/長谷川幸信)
――6月6日発売の千聖とCrack6のスプリットシングルで、ボーナストラックの「MONSTERS OF ROCK NIGHT SHOW!」の作詞を手掛け、ヴォーカルの一人としても参加しているのが森重樹一さんです。
千聖:コラボレーションですね。
――モノマネ番組における、ご本人登場みたいなサプライズ感ですよね(笑)。
千聖:それに近い状態(笑)。森重さんが一緒にZIGGYの「EASTSIDE WESTSIDE」をやってくれるってだけで、高校生のときの自分に言ってあげたい気分でした。なにしろ高校の文化祭でやった曲だから。その後、自分の誕生日パーティにも来てくださったし。
森重:そうそう(笑)。
千聖:横浜に同級生がオーナーをやっている店があって、僕の誕生会をそこでやることになったんです。それで森重さんをお誘いして。断られるかと思ったら、まさかの“いいよ”って返事で(笑)。
森重:楽しかったよね。
千聖:あと忘年会も一緒にやって(笑)。音楽がきっかけなんですけど、イベント以降は食事ばっかりで(笑)。
森重:芝居も一緒に観に行かせてもらったじゃない。
千聖:ああ、そうだ! 高嶋政宏さんのお芝居に。最近、高嶋さんとも仲良くさせていただいてるので「森重さんと一緒に観に行く」って事前に伝えたら、高嶋さんも相当驚いて(笑)。
森重:だからイベントに誘ってもらってから、いろんなプロセスがあって、今回のコラボレーションの話があってという。

――いわゆる“お仕事”というノリのコラボレーションではなくて?
森重:バンドマンってそういうノリじゃないから。一緒に音を出すのが楽しいから。
千聖:いつかセッション的なことをさせていただければって、じつは昨年からお話もさせてもらってたんですね。高嶋さんのお芝居を観に行ったときも、別れ際に「良かったら、曲を作らせてくださいよ」って森重さんに言ったんですよ(笑)。そしたら「いいよ」って。
森重:そうそう、機会があったら一緒にやろうぜって。バンドマンのスタンスってそこにあるように思っていてさ。
千聖:それと同時に、“あのとき”の気分に戻れたりもするし、今の自分とオーバーラップもできるし。まるでタイムスリップするように当時と今を行ったり来たりする感じで。今回のシングルもそういう感覚でセッションできたんですよ。
――その“あのとき”というのは、ZIGGYに初めて触れた高校時代ですか?
千聖:そうです。インクスティック芝浦のライブ写真が、当時の音楽雑誌によく載ってたんですよ。真正面から撮られていたライブ写真。
森重:あっ、あれね(笑)。スティーヴン・タイラー(エアロスミス)と同じ服を着てたやつだね、懐かしい。
千聖:そっか、言われてみれば、同じような(笑)。ZIGGYの森重さんと言えば、あのライブ写真のイメージが強くて。高校生の自分的には、まずはヴィジュアル的にカッコいいバンドがいるな、スゲーなと。それがZIGGYだったんですよ。でも音楽性、大事じゃないですか。ルックス好みでも、聴いた感じが違ったら、あれ~ってことになっちゃいがちです。ZIGGYは、その当時の洋楽にはないものがあって、それでも洋楽的な香りもするロックンロールだったので、新しいなと思ったんですよ。あまりにもアメリカとかイギリスっぽい音楽だと、それならその国のバンドでいいじゃないか?ってことにもなるじゃないですか。でもZIGGYの場合、自分たちがプロデュースしている感じが、すごくカッコいいなと思ったんです。生意気ながらそう感じたんですよ(笑)。
森重:でも、バンドのありようは自然だったと思う。先輩のバンド達には影響も受けたりしたけど、そのまま真似したり、洋楽をそのままやっても、まったく意味がないでしょ。もちろん、いい意味でアイデアを盗んだりするよ。自分のテリトリーや土俵に引きずり込んで、初めて自分のものにする感覚っていうかさ。俺が18~19歳でバンドを始めた当時の話なんだけど、ラウドネスがデビューして以降、ジャパメタのボーカルはハイトーンで歌うことを義務つけられたような感じだったんだ。でも、みんな、声がひっくり返ったような歌い方でね。ハイトーンでちゃんと歌えるのは一握りだけ。それなのに出もしないハイトーンで必死の形相で歌っていて、俺はバッカじゃないの? ナンセンスだなと思ったわけ。自分の歌えない音域で歌っているのはいいわけがない。俺は自分のキーに合わせた曲を作るって、まず最初に思ったのはそれだったよ。ZIGGYはそれをやろうと思った。
千聖:やっぱセルフ・プロデュースですよね。自分に合ったプロデュースしないと意味がないっていう。
森重:そうそう。そういうふうに音楽を続けていかないと、楽しくもないし、長続きもしないじゃん。辛そうな顔してハイトーンで歌ってもねぇ……。
千聖:客観的に見るとね…(笑)。
森重:ホントだよ(笑)。だいたいブームに乗っかってやっているものは、借り物のままで、どう考えたって身についてない。俺にはそう見えたから。やっぱモノにしている人たちを一生懸命に知ろうとしたよ。それが当時のルージュとか村八分というバンドで、むしろメタルではない表現で音楽をやっている人たち。日本人で日本語を使っているって、超カッコいいじゃんと思ったから。もちろんエアロスミスやニューヨーク・ドールズは最高だけど、まんま持ってきてもどうにもならないから、自分たちなりの日本人であるというアイデンティティを踏まえてやらなきゃ意味ないよねって思ったね。
千聖:森重さんたちは日本の土壌にあるロックもミックスして、すごく入りやすい入り口があるうえに、自分たちに合ったスタイルを綺麗にプロデュースしていましたよね。後に「GLORIA」がいわゆるトレンディドラマの主題歌にもなったじゃないですか。それって当時のバンドたちのスタイルにはなかったというか。あの時代以前、そういう話自体あまりなかったのかもしれませんが、たとえ来ても、俺らのイメージに合わないって断る可能性もあるわけです。でもZIGGYはあの曲を提供し、それによってさらに曲が独り歩きしていったわけじゃないですか。そういう現象を起こしたのも、森重さんたちの頭の柔らかさも相当、効いてたんだなと。それは当時、素人の学生だった自分にもわかりましたね。俺たちだって、そういうやり方もありじゃないかって。

撮影/コザイリサ
――ヒット曲がきっかけでアルバムを聴くと、じつはマニアックなこともふんだんにやっていたりするのがZIGGYなんですよね。
千聖:そうそう。マニアックさをうまくブレンドさせていて、それもプロデュースだと思うんですよ。だからすごいんですよ。
森重:そういう前例を作っていける時代だったんだよ、まだ。当時の音楽雑誌の人たちもすごくおもしろがってくれて、協力してくれてね。前例がなかったから。だって日本のバンドは売れねえんだから、どうやっても売れない時代だったからね。ZIGGYでデビューする前、爆風スランプのインタビューを雑誌で読んだんだけど、給料が3万だって書いてあって。どうすんだよ、大学まで出た大の大人が給料3万って! ふざけんな、冗談じゃねえよ、と思うでしょ。でも、それでもやるんだよ。大学の卒業間近には就職勧誘の資料とか山ほど届いたよ。
千聖:ちょうどバブルのころですよね?
森重:そういう時代に3万しかもらえねえ仕事でも、俺はやりてえって。それを選べたのは、自分の環境も含めて、すごく感謝しているし。いわゆるバンドで成功して億万長者になりてえって思うヤツなんて、一人もいないんだから。バンドマンなんて金にもなんねえし、ある種、世の中から白い目で見られる存在なんだから(笑)。そんな感じで始めたから続いたんだと思うよ。上を見ればセレブリティみたいなミュージシャンだっているよ。じゃあオマエらは何を作ってるんだよって話だよ。俺は毎年、アルバムを作ってさ、毎回、ツアーやってさ、新しい曲が出来ればどんどん録っていきたい、と思ってやってるよ。一生のキャリアで5~6枚しかアルバム作らないで終わっていくようなバンドより、クソみたいなアルバムかもしれないけど、20枚でも30枚でも作り続けるほうが、よっぽどカッコいいって。ZIGGYはそういうスタンスのバンドだったと、俺は思ってる。
千聖:あとZIGGYの魅力は、音楽的に想像をしてない、おもしろいことをするんですよね。「Jealousy」とか、今までのZIGGYとはまるで違う湿度の高い感じの方向性なんだけど、それはそれで森重さんのものになっちゃうんだなって。ボーカリストとしての存在感、可能性、要はなんでもZIGGYに持っていけちゃうんだっていう力強さを、あの曲から感じたんです。あの曲って、ちょうど僕がソロでデビューする直前だったんですよ。発売前の関係者向けのテープってあるじゃないですか?
森重:アドバンス・テープだね。
千聖:それを徳間ジャパンのオフィスで見つけてね、これもらって良いですか?って言って、持って帰って聴いてました(笑)。いまだに実家にあるし。そういう思い出もある曲だったりするんです(笑)。ともかくボーカリストとしての柔軟性とか、モノにできちゃうところとか、すごくボーダーレスな感じがしてカッコよかった。何に対しても逃げてないし、受け入れるけど、自分のものにして、しっかりアートとして繰り広げているから。
――だからZIGGYはロックンロールに限定されない幅広いファンから支持もされましたね?
森重:ガチでロックンロールを標榜している人たち、例えばフィフティーズ・スタイルの人たちにとってのZIGGYは全然、ロックンロールじゃないと思う。でもLAで育ったヤツからネイティブ英語を教えてもらっていたとき、要はアメリカ人のロックンロールの解釈は広いものなんだ、と体験上、語ってくれて。ジューダス・プリーストもオジー・オズボーンもロックンロールなんですよ、と。最高だなと思ったよ。だってロックンロールは、選ばれた限られた人間がやるものじゃなくて、トラックのドライバーもレストランのウェイトレスも、みんな、楽しめるのがロックンロールなんだよなって思ってね。だったらZIGGYはロックンロールにいていいなと思えたんだよね。
あと俺にとってのロックンロールは、幼少期に聴いていたフィンガー5かもしれないしさ、ジュリーや西城秀樹さんかもしれないんだよ。そういうものがワクワクするものとして俺の中にあってさ。だからZIGGYがどんなに歌謡曲っぽいことをやろうが、例えば「Jealousy」も、ローリング・ストーンズがディスコスタイルの曲をやったときのことを考えれば、全然ありでしょって。自分ではそう思えた。今でもそういうところはある。こうじゃなきゃダメだ、ああじゃないとダメだと言うヤツと音楽やるのは、俺はそんなに楽しくないの。こういうのもありですよねって言いながら音楽やってるヤツのほうが好きだし。真ん中に投げれる球を持っていながら、だけど守備範囲は広くしようよって考えている人とやるほうが、音楽は楽しいもん。刺激的だしね。
千聖:それは同じ考えです。自分の中で決めちゃうと、その時点で狭まっちゃうから、おもしろくないんですよね。
――【PENICILLIN千聖 & ZIGGY森重樹一】スペシャル対談後編へ
★【PENICILLIN千聖&ZIGGY森重樹一】直筆サイン入りポラロイド写真を3名様にプレゼント!
※応募締め切り:8月1日(水)