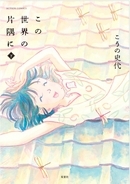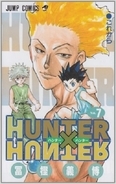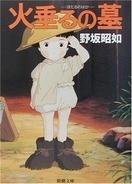歴代の自民党総裁で連続3回以上選出されたのは、これまで池田勇人(任期:1960〜64年)と、安倍首相の大叔父(祖父・岸信介の実弟)にあたる佐藤栄作(任期:1964〜72年)の二人しかいない。このうち佐藤は4選をはたし、首相の連続在任期間では憲政史上最長となる7年8ヵ月を務めた。
池田と佐藤が総裁を務めたのは、高度成長期の1960年代から70年代初めだが、その後、1977年に総裁任期に関する党則が改正されて、1期が3年から2年へと短縮され、80年には連続3選が禁止された。それが、小泉純一郎総裁のもとで2002年に1期が2年から再び3年に延長され、さらに昨年の党大会での党則改正により、連続3選も再度認められた。
もし、今回の総裁選で安倍総裁が3選すれば、佐藤栄作が1968年に3選して以来、じつに半世紀ぶりということになる。しかし、総裁選の様相は、佐藤の時代とくらべれば大きく変わっている。この記事ではその変化を、過去のケースをあげながら見ていきたい。
決選投票で敗れた岸信介、勝利した孫の安倍晋三
自民党は1955年、鳩山一郎率いる民主党と、吉田茂の流れを汲む緒方竹虎率いる自由党の保守合同により結成された。それに際して、総裁は党大会で公選することが党則に定められる。それまでの保守政党の党首は、前党首を含む長老を中心とする話し合いによって選出していただけに、公選制の導入は画期的であった。ここには、人事をめぐる旧民主・自由両党の対立を解決するという目的に加え、最大野党だった社会党に対抗できる党組織の建設を目指して、党内民主主義を実現するというねらいがあったという(中北浩爾『自民党──「一強」の実像』中公新書)。

ただし、結党時には総裁は置かず、ひとまず4名の代行委員制がとられた。
この総裁選では、岸信介・石橋湛山・石井光次郎が争い、第1回投票では岸が1位となるも過半数に達せず、2位の石橋との決選投票にもつれ込む。このとき石橋と石井が2・3位連合を組んだ結果、わずか7票差で石橋が総裁に選出された(石橋:258票、岸:251票)。なお、総裁選での逆転劇は、このときと、自民党が野党だった2012年の総裁選において1回目の投票で1位につけた石破茂が、2位の安倍晋三に決選投票で敗れたとき(安倍:108票、石破:89票)の2度しかない。
さて、56年12月の総裁選は、自民党内に派閥が確立されるきっかけとなった。このとき各派閥のあいだでは、巨額の政治資金とポストの空手形が飛び交う熾烈な動員合戦が繰り広げられる。それまで派閥は多分に流動的なもので、なかには複数の派閥に重複して所属する者さえいたが、このときの総裁選を境に、そうした者はほとんどいなくなり、無派閥議員も大幅に減って、派閥が強固なものとなった。
自民党の派閥を確立させたのは、このほか、衆議院の中選挙区制によるところも大きい。中選挙区制とは一つの選挙区から2〜6名の議員を選出する選挙制度だが、自民党は、政権を維持するべく衆議院での過半数の獲得を目指したため、各選挙区で複数の公認候補を立てざるをえなかった。同じ党の候補どうしで争うとなると、選挙運動では党組織に頼ることができない。そこで各候補者は派閥に支援を求め、派閥もまた勢力拡大のため、あらゆる手段を使って自派の候補者を後押しした。
総裁選を通じて党内に基盤を築いた田中角栄
こうして、いわゆる55年体制下の自民党では派閥が「党中党」ともいうべき存在となり、派閥間では激しい権力闘争が展開される。それだけに総裁選も、各派閥の領袖どうしで争われる時期が長く続いた。
1964年7月の総裁選では、現職の池田勇人に対し、佐藤栄作と藤山愛一郎が事前に2・3位連合の約束を交わした上で挑んだ。各陣営のあいだでは、中間派の議員の取り込むため空前の現金が飛び交うことになる。結局、このときは池田がぎりぎりで過半数を得て3選された。だが、彼はその翌月、のどに異常が発見され、10月の東京オリンピック閉幕のあと病気のため首相辞任を発表、後任総裁には3ヵ月前に争ったばかりの佐藤を指名した。
佐藤は、首相となるのと前後して党内の有力者があいついで亡くなったこともあり、総裁の地位を盤石のものとした。先述のとおり1968年11月の総裁選では3選を果たす。このとき、三木武夫が外務大臣を辞して出馬、池田から派閥を引き継いだ前尾繁三郎も立候補している。前尾は出馬に消極的だったが、派閥の領袖が出なければ集団の士気・団結にかかわるため、名乗りをあげざるをえなかった。結果は、佐藤が249票、三木が107票、前尾は95票と最下位に終わる。
このあと、1970年11月の総裁選では佐藤に対し三木がただ一人挑んだ。党内では総裁選前より佐藤の4選を支持する声が強く、佐藤の圧勝に終わる。
はたして田中は佐藤政権末期に福田に追いつき、追い越すことに成功する。1972年7月の佐藤退陣後の総裁選には、田中・福田・大平正芳・三木のいわゆる「三角大福」が立候補し、第1回投票で1位となった田中が2位の福田を決選投票でも破って、総理総裁の座を射止めた。田中はその後、1974年に金脈問題により首相を辞任、76年にはロッキード事件で逮捕されるも、なおも党内最大派閥を率いて強い影響力を保持し続ける。
1977年には、総裁選の投票権を一般党員にまで拡大した予備選挙が導入され、その上位2名が国会議員による本選挙に進むことになった(それまで投票権を持っていたのは党所属の国会議員と各都道府県連選出の代議員だけだった)。だが、1978年と1982年に行なわれた予備選挙では、それぞれ田中の支持を取りつけた大平正芳と中曽根康弘が圧勝し、2位以下に終わった候補者が本選挙を辞退する。これを受けて1981年には候補者が3名以下の場合には予備選挙は行わないことになり、89年には予備選挙が廃止された。
小泉政権を境に弱くなった派閥、強まる総裁の権限
しかし、森喜朗の任期途中での辞任にともなう2001年4月の総裁選では、各都道府県連が一般党員による予備選挙を行なうことが認められた。
従来、内閣や党三役の人事は派閥の力関係に応じて行われていたが、小泉はそれをとらず、派閥の弱体化を図った。小泉政権以降、派閥の力はしだいに弱まっていく。ここには、1994年に中選挙区制に代わって小選挙区比例代表並列制が導入されたことも大きく影響していた。
小選挙区制では、当選に必要な得票率が中選挙区制よりも上昇したため、党の公認なくして当選することが困難になった。その結果、公認権を握る党執行部、そのトップたる総裁の権限は強まったのである。その効果は、小泉政権下の2005年に行なわれた郵政総選挙などにおいて造反を抑え込むうえでおおいに発揮された。
冒頭にあげた総裁の任期延長、連続3選の解禁も、総裁の権限強化が背景にある。このほか、小泉政権以降、総裁選のさまざまな規定が改正され、一般党員の参加の拡大も進められた。
2012年の総裁選では、先述のとおり第1回投票で1位となった石破茂が、国会議員のみによる決選投票で安倍晋三に敗れた。これを受けて、翌年の党大会では、決選投票にも第1回投票の地方票が加味されることになる。なお、党員による地方票は2002年に300票にまで倍増されていたが、2014年の党大会ではさらに国会議員票と同数に増やすことが決まった。
いまだに地方支持層が厚いとされる石破にとって、こうした一連の改革は、今回の総裁選で追い風となるのだろうか。彼はまた先の総裁選での敗北を教訓に、無派閥議員を集めて「無派閥連絡会」を発足、さらに2015年にはこれを前身に水月会(石破派)を結成している。国会議員票を集めるためには、依然として派閥を持つことは有効なのだ。
もっとも、ここまで書いてきたように、かつて以上に総裁の権限は強まっているうえ、しかも安倍首相は国政選挙では負け知らずで、党内をがっちり押さえている。予想どおり3選は固いのか。ちなみに安倍がこのまま3選して首相を続投すれば、2020年8月24日、東京でオリンピックのあとパラリンピックが開幕する前日、佐藤栄作の政権最長不倒記録(2,798日)を上回ることになる。
【参考文献】中北浩爾『自民党──「一強」の実像』(中公新書)、北岡伸一『自民党──政権党の38年』(読売新聞社)、伊藤昌哉『自民党戦国史 上』(朝日文庫)、竹中治堅『首相支配──日本政治の変貌』(中公新書)
(近藤正高)