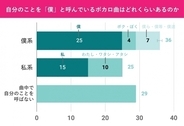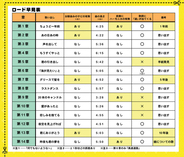J-ROCK&POPの礎を築き、今なおシーンを牽引し続けているアーティストにスポットを当てる企画『Key Person』。第23回目は来年で結成50周年を迎えるTHE ALFEEが登場! やりたいことをやるスタンスを貫き続ける3人にとってのキーパーソンとなる人物や、第一弾のヒット曲「メリーアン」が生まれるまでの話、音楽性の変化など、THE ALFEE節の効いたトークでお届けする。
THE ALFEE
ジ・アルフィー:1973年、明治学院大学キャンパスにて出会いグループを結成。翌74年8月にシングル「夏しぐれ」でデビューを果たし、83年発表のシングル「メリーアン」がデビュー9年目にして大ヒットを記録。以降、日本の音楽シーンを代表するバンドとして活躍している。87年から2018 年まで関西テレビ『大阪国際女子マラソン』のテーマソングを 32 年間(阪神淡路大震災で休止)31 曲、担当したことを“同一国際スポーツ大会のテレビ放送における同一アーティストによる最多テーマソング数”として、18 年12月24 日に行なわれた日本武道館公演でギネス世界記録に認定された。また、コンサートツアー・イベントと精力的な活動を続けており、日本のアーティストの中でもコンサート動員数が多いグループのひとつに挙げられている。コンサート通算本数は20年8月25日に行なわれた自身初の配信ライヴ『THE ALFEE 46th Birthday 夏の夢』がコンサート通算本数2776本となり、日本のバンドでコンサート実施通算本数の最多記録を更新中!
ロックに変わったのではなく、 もともと好きだったというだけ
──1974年にシングル「夏しぐれ」でデビューしたあと、約5年後の1979年にシングル「ラブレター」で再デビューされましたが、この期間はTHE ALFEEにとってどんな時間でしたか?
高見沢
「デビューするってことは自分たちのひとつの始まりなんですが、個人的にはそんなに始まっていなかったんですよね。
坂崎
「ですから、79年にキャニオンと契約するまでの期間はアマチュア時代にやるべきことをやった感じですね。」
高見沢
「そうだね。74年でデビューした時には他にもたくさんのバンドがいて、オーディションで合格しないと歌番組に出られない時代で、僕らもオーディションを受けたけど、他のバンドを見ながら“うまいいなぁ!”って素人感覚で観ちゃっていましたからね。今考えると、それってダメだよなと(笑)。それに、地方から出てきたグループは強いんですよ!」
坂崎
「みんな“ここで勝ち上がらなければテレビに出られない!”という気合いがあるのに、俺らはそれをライバルだとも思わずに“うめぇなぁ”って感心してたわけだからね。」
高見沢
「でも、僕はこのバンドにギターで入って、桜井がヴォーカルだったのに、デビューの時にはギターを弾かないでいいからハンドマイクでヴォーカルをやれって言われて。で、桜井は逆に弾けないのにギターを持てって言われ、それはやっぱりおかしいよな(笑)。当時も“うん?”と思ったけど、抵抗する力もなく、流されるままやっちゃったから、不本意なスタートではありました。
坂崎
「そこで一回挫折したから、これからは自分たちで曲を作っていかないといけないと気がついて、その流れでライヴハウスでライヴをするようになったんです。研ナオコさんやかまやつひろしさんが出演しているステージに立たせてもらって、良く言えば音楽にちゃんと向き合うことができるようになった数年間でしたね。ボツになった曲も多いけど、オリジナル曲も相当作っていましたし、再スタートに向けての悪い期間ではなかったんじゃないかな? まぁ、生活は貧乏でしたけどね。3人とも東京近郊に住んでいたし、みんな次男坊だからのんびりしていて(笑)、その性格が幸いしたんでしょうね。誰かが家業を継がないといけないとか、実家に帰らないといけないってことがあったらそこで終わっていたと思いますよ。僕らはちょっと実家に行っては、親の脛をかじっていたから(笑)。」
──オリジナル曲の制作をはじめ、ライヴハウスではMCでも場を盛り上げたり、コミカルな演出を披露していたそうで、今のTHE ALFEEにつながるものを多く作った期間だったのではないでしょうか?
高見沢
「今のTHE ALFEEにつながったというより、初めからそういう人間だったんですよ。
全員
「あははは。」
高見沢
「まぁ、そういうことを日常茶飯事でやっていたわけですよ。だから、面白いことをやろうと意識したことは一度もないんです。」
坂崎
「とにかく3人ともお笑い好きだったしね。自然の流れでしたね。」
高見沢
「そうだな。」
坂崎
「ステージに立っても僕らの曲をお客さんは知らない分けだから、その場で何か印象をつけなければいけない。だから、2曲歌わせてもらう合間にモノマネとかコントまがいなことをやってたら、そっちのほうが印象が強くなったみたいだね。
──ステージに持ち前のものを披露したら、その場が盛り上げるだけでなく活動の幅も広がっていったんですね。再デビュー後は初の野外イベントの開催や、5thアルバム『doubt,』からロック系のアレンジが増えたりと、“フォークグループ”という括りから音楽性が広がっていったと思いますが、ロックを取り入れた背景には何か想いがあったんですか?
坂崎
「それも何か狙いがあったわけじゃなくて、もともと高見沢はロックバンドをやっていて、ハードなものが得意ってことはあったね。」
桜井
「デビューしたての頃のフォークグループっていうスタイルも、当時はテクノが流行っていた時代だったから、それに逆行してアコースティックがいいんじゃないかって発想でしたからね。」
坂崎
「それが裏目に出た(笑)。」
桜井
「波に乗れなかったんだよね。それがまただんだん自分たちの得意なほうになっていっただけのことかもしれないね。」
坂崎
「最初はフォークスタイルでやっていたけど、そのうちライヴでお客さんが熱狂してくれるようになって、アンコールでお客さんが前に来て盛り上がった時に、高見沢が生ギターなのに前のほうに行っちゃってさ、当時はエレアコなんてないから誰も音が聴こえなかったこともあったな。」
高見沢
「自分だけで盛り上がってましたね。音が出ていないのに(笑)。」
坂崎
「それからだよな。熱狂するお客さんに合う曲を高見沢が作るようになって、その流れでサウンドもロック寄りになっていった。もともとレコードではドラムもキーボートも入れていたし、無理矢理ロックにした感じではなく、自分たちにとっては自然な流れでしたね。」
高見沢
「あと、よく3人でメタルのライヴに行ったよな。
桜井
「それはお前が強引に連れて行ったからだろ(笑)。」
高見沢
「まぁ、IRON MAIDENの時は俺もブルース・スプリングスティーンのほうが良かったかなってちょっと思ったけどさ(笑)。」
坂崎
「ちょうど同じ日に別の会場でブルース・スプリングスティーンがやっていたんですよ(笑)。よく僕らのサウンドがロックに変わったってよく言われますけど、もともと好きだったというだけなんです。だって、エレキ世代ですから。グループサウンズとかThe Beatlesとか、エレキが流行った時代に音楽に目覚めて、バンドを組みたいっていう気持ちがあったから、ライヴにもドラムとキーボートが入ってバンド形態になった時はやりやすかったです。」
桜井
「本当にそうだよ。それまではアコースティックにベースでチョッパーやっていたんだから(笑)。」
“気がついたらこうだった” っていうのが重なって今がある
──1983年8月に初の日本武道館公演を行なわれましたが、その時にはまだヒット曲がなかったという事実に驚きました。6月にリリースしていたシングル「メリーアン」が武道館公演後にヒットし、『第34回NHK紅白歌合戦』にも出演されましたが、第一弾のヒット曲が生まれた時はどんなお気持ちでしたか?
高見沢
「本当は「メリーアン」の前の曲でヒットするはずだったんですよ。
坂崎
「6月にリリースしたシングルが9月に入ってからジワジワと売れてきたから、ヒットまでに2カ月以上かかっているしね。目が覚めて、朝になったら突然ヒット曲が出たって感じではなかったな。」
高見沢
「で、紅白にも出られたから“これでもう10年は平気だろう”と安心していたんですけど、そしたらディレクターさんが“さぁ、高見沢、次はどうする?”って訊いてきて、“えっ、次ってまだあるんですか?” “当ったり前だろ! 一発屋で終わるのか!? 次の曲が勝負だ!!”と言われ、僕は“え~、また勝負するの!?”って(笑)。「メリーアン」以降はずっと終わりのない中間テストを受けているような感じですよ。でもその後、狙いに狙って作ったのが「星空のディスタンス」。だから、それが売れた時は嬉しかったですね。自分たちの狙いどおりチャートに入って代表曲になりましたし、「メリーアン」を越えたというのも実感しましたね。それからずっと現在に至るってことですが。」
坂崎
「でも、「メリーアン」が売れる前に武道館公演ができたっていうのは、自分たちでも“やったな”っていうのはありました。逆にヒット曲がなくても武道館に立てたから、“ライヴのみで武道館まで行けたからいいじゃん”って。」
高見沢
「会社としてはそうはいかないだろうけど、“これからはライヴで生きよう!”と密かに思ったのは確か。いろんなことをやって、あとは何をしたらいいのか分からなくもなっていたけど、自分たちが今歌いたいものを歌えば、結果がついてくるっていうのを教えてくれたのが「メリーアン」でしたね。あの時のディレクターさんには、今でも心から感謝していますよ。」
──ライヴも引き続きかなりの本数をやっていますよね。THE ALFEE は昨年12月で2,782本目のライヴを達成しましたが、これほど多くの公演を開催し続けるようになったきっかけはありますか?
高見沢
「きっかけはありません。(笑)。知らないうちに次が決まっちゃっているから。でも、本来ライヴが好きですから、それが苦とは全然思いませんよ。」
桜井
「ライヴツアーが夢だったしな。」
坂崎
「初めての武道館公演をやってからは、スタッフと一緒にライヴツアーのひな形を作ったりしたから、それが定番になっているもあるね。」
高見沢
「それとパンフも含め、大々的にコンサートグッズを作ったのは僕らが最初らしいですね。春ツアーのあと夏はイベントに出て、秋からまたツアーに出るっていうサイクルを定番化したのは80年代からでしたね。」
坂崎
「それも誰かが “嫌だ”って言っていたらやめていたかもしれないね。NOと言えない日本人だよな(笑)。」
高見沢
「まぁ、とにかく3人ともライヴは好きだからね。」
──では、最後にTHE ALFEEにとってのキーパーソンとなる人物は?
高見沢
「3人としてもそうかもしれないけど、自分で考えると吉田拓郎さんですね。拓郎さんはTHE ALFEEを早めに見つけてくれたんですよ。“お前ら絶対に売れるよ”って…まぁ、音楽以外の部分でしたけど(笑)。楽曲のほうでは81年だったかな? 当時Stars on 45っていうグループがいて、The Beatlesの曲をメドレーでつなげてLPを出していたんですね。で、ニッポン放送のディレクターの方が、坂崎がモノマネがうまいからってそれを拓郎さんでやろうって話になって。しかもTHE ALFEE 名義ではなく、“BEAT BOYS”というバンド名で拓郎さんの曲を拓郎さんのモノマネで歌った「ショック!! TAKURO23」っていう曲を作って、拓郎さんを驚かせる企画があったんです。そしたらそれを聴いた拓郎さんが非常に喜んでくれたんだけど、THE ALFEEがやっているって言っていなかったから、僕らはずっと名前を伏せたままで、しかも覆面を被っていたんですよ。」
坂崎
「覆面バンドって普通は名前を伏せるだけなのに、なぜかプロレスラーみたいに本当に覆面を被っていた(笑)。」
桜井
「マントもつけて竹下通りを歩いたよね。」
高見沢
「でも、それがヒットしたんですよ。それまでTHE ALFEEとしてオリジナル曲も出していたのに、それよりも売れた! もうそれがショックで、“BEAT BOYSの売り上げを超えなきゃいけない!”って火がつきましたね。あと、拓郎さんにはテレビにも引っ張り出されて、僕はもともとテレビが苦手だったけど、ふたりでトーク番組をやっていたんですよ。そういう何か面白いところにはいつも拓郎さんがいましたね。」
坂崎
「拓郎さんの存在は大きかったね。プロデューサーみたいな視点で見てくれていましたから。高見沢がテレビ向きだっていうのは、俺と桜井もずっと言ってたんだけど、業界の人は誰もそこに目を向けなかったから実際に引っ張り出すということはなかったんです。」
高見沢
「拓郎さんは繊細だけど大胆な部分もありますね。掴みどころがない一面もあるし、ご本人が聞いたら怒るかもしれないけど、ちょっとTHE ALFEEに似ているのかもしれないね。それは言っちゃマズいかな?(笑) “そんなわけねぇだろ!”と言われるかもしれないけど。」
桜井
「研ナオコさんにもステージを提供してもらって、ナオコさんはいつも満席のところに出ているから、ライヴの基本はあそこで体験できたと思いますね。お世話になったって言ったら、ガロだってそうだね。」
坂崎
「そうだね。本当にたくさんいるから、あちらを立てればこちらが立たずで(笑)。」
高見沢
「入った事務所が大手の芸能プロだったから、そういう方々の背中を見ていたっていうのもありますよ。」
坂崎
「僕らみたいなバンドってあんまりいないんじゃないかな? 研ナオコさんから拓郎さんまでお世話になっていて、不思議な立ち位置というか。」
高見沢
「変な癖もないしね。文句は一切言わないし、扱いやすかった(笑)。」
坂崎
「筒美京平さんに“君たちは今まで会ったフォークの人たちの中で一番素直だよ”って言われたこともありましたね。あれってダメだって意味なのかな?(笑) キーパーソンとしてひとりを挙げるなら拓郎さんですけど、本当にたくさんの方にお世話になっていますよ。」
高見沢
「拓郎さんの感覚って不思議で、前にTBSホールでの録音の時に幕に向かって僕らがお辞儀をしたら、それが“誰もいねえよ!”ってウケたらしくて、自分たちでは何もおかしくないと思っていたのに、そこを面白いと思うアンテナを持っているんですよ。人って笑わせようとして笑わせられるわけじゃないし、こっちがやったことに対して、それが良いか悪いかは見た人や聞いた人の感覚だから、自分たちでは分からないことを引き出してくれたのが拓郎さんやナオコさんなのかな?」
──THE ALFEEの音楽性にロックが加わったお話に通ずるというか、ありのままの自分たちでやってきたっていうのが筋としてあるんですね。
高見沢
「そうですね。無理して何かをしようとしたことは一度もないです。“気がついたらこうだった”っていうのが重なって今があるんでしょうね。でも、トークに関しては最初から変わらずにこの雰囲気なので(笑)、ずっと変わっていないですよ。」
取材:千々和香苗