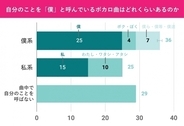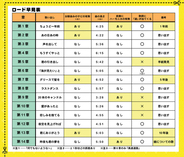※この記事は2021年6月25日発売の『Rolling Stone JAPAN vol.15』に掲載されたもの、インタビューは2月下旬に実施。
たった1枚のアルバムで、その後のギターバンドのあり方を根本から変えてしまったマイ・ブラッディ・ヴァレンタイン。幾重にもレイヤーされたフィードバック・ノイズや儚げで美しいメロディを、それまでの常識を覆すようなミックス・バランスによってまとめ上げた1991年の2ndアルバム『loveless』は、リリースから30年経った今も愛され続け、その謎めいたサウンドスケープを解明しようとする人々は後を絶たない。
彼らの旧作のストリーミング配信が解禁され、新装盤CD/LPもリイシューされた2021年はしかし、過去に何度か訪れた「マイブラ祭り」とは様子が違う。というのも、これまでメディアにはほとんど姿を現さなかったバンドの司令塔ケヴィン・シールズが、今回はいつになく積極的に取材やメディア出演に応じているのだ。バンドやその作品たちが「神格化」されることを避けようとしているのか、それとも単なる気まぐれか……? いずれにせよ、本誌も1時間半に及ぶインタビューを行うことに成功。
コロナ禍に考えていたこと
―ケヴィン、まずはご結婚おめでとうございます。
ケヴィン:どうもありがとう(笑)。
―アイルランドに移住してからもうだいぶ経ちますよね。そちらでの生活はどうですか?
ケヴィン:とても快適だよ。音楽に集中するにはもってこいの場所だ。
―それは何よりです。昨年は新型コロナウイルスの感染拡大が世界的な大流行になりましたが、どんな日々を過ごしていましたか?
ケヴィン:こんな田舎に住んでいても、その影響からは免れられなかった。都心から離れているからこそ飛行機での移動が多いのにも関わらず、それが出来なくなってしまったからね。去年の春くらいはまだ、往来が全くなくなったことをちょっとしたマジックのように感じていたんだけど、それによって病気になる人や、病床数が逼迫して大変な思いをしている人がたくさんいるわけだから、そんな悠長なことも言ってられないよね。
―日本では音楽関係者に支援が行き渡らずに社会問題になっています。イギリスはどうですか?
ケヴィン:全く同じ状態だよ。音楽関係者の状況はひどいものだ。特にUKはブレクジットの影響もあって、ミュージシャンがEU諸国に往来することに関して全く取り決めがなされぬままコロナ禍になってしまったから。1年もの間、完全に移動が止まってしまった中で、アイルランドも含めたUK周辺の音楽コミュニティは本当に疲弊している。僕らに関してラッキーだったのは、Dominoと契約して音楽の「制作段階」だったこと。

左上から時計回りにビリンダ・ブッチャー(Vo,Gt)、ケヴィン・シールズ(Vo,Gt)、コルム・オコーサク(Dr)、デビー・グッギ(Ba)(Photo = Paul Rider)
―他のメンバーたちとも会っていますか?
ケヴィン:コルム(・オコーサク)は今アイルランドに住んでいて、ビリンダ(・ブッチャー)とデビー(・グッギ)はロンドンに住んでいるのだけど、幸いにしてイングランドとアイルランドの間は共通旅行区域(コモン・トラベル・エリア)だから、ビザなしでもお互いに行き来することが出来る。まあ、いずれにせよ今はコロナで会えないのでオンラインで近況報告はしているよ。コロナさえ落ち着いてくれれば、もっと自由に、楽に行き来しながら作業も一緒にできるのだけどね。
―昨年はコロナだけでなく大統領選挙や香港デモ、BLMなど様々なことが世界中で起きていました。マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン(以下、MBV)もSNSの公式アイコンを黒くするなど、ある種の「政治的なスタンス」を明確にしていましたよね。
ケヴィン:本当にこの1年、様々なことがあったよね。僕らバンドとしては、BLMについては完全に支持する立場だった。アメリカで起きたこととはいえ、世界中の人々が考えるべき問題だとも思う。法律や社会システムの中に差別が組み込まれていることは本当に酷いことだしアンフェアだ。そこに変化をもたらそうという運動であれば、それに対して何かしらのサポートをすることがとても重要だと思っている。SNSでの意思表示はその一つだね。
それから大統領選挙のこと。トランプのような人物が現れたのは、何もアメリカだけの問題ではなくて世界中で右傾化が進んでいたことの、一つの象徴だったと思う。人々の対立や分断を利用し、それを顕在化させることで両極化が進んでいたというか。そのせいで最近のアメリカは全くもってカオス状態だったけど、一つポジティブなことが言えるとすれば、「最悪の事態はもう過ぎた」ということじゃないかな。ここから先は、例えば環境問題などもっと目を向けるべき課題に取り組むことが出来ると思っているよ。
―そういえば、つい先日ダフト・パンクが解散を発表したじゃないですか。2013年にフジロックでお会いした時、あなたが「『Random Access Memories』をよく聴いている」と言っていたことを思い出したんです。
ケヴィン:そうだったね。
―最近はどんな音楽を聴いていますか?
ケヴィン:えっと、そうだな……色々チェックはしているんだよね。1年前にようやくSpotifyを導入したので、巷で話題になっているものも聴いているんだけど……あ、アール・スウェットシャツは良かった。気になるのはやっぱりオルタナティブ・ヒップホップとかが多いのかな。そうそう、フランク・オーシャン! 彼の『Blonde』は大好きだったし、それ以降に出したシングルもすごく面白いよね。あとは、アイリッシュのちょっとヒップホップっぽいテイストのデニース・チャイラ(Denise Chaila)も気に入っているよ。
―フランク・オーシャンがお好きなのはすごく分かる気がします。
ケヴィン:今、こうやって君に尋ねられて「何が一番印象に残っているかな?」と思った時に、たまたま浮かんだのがフランク・オーシャンだっただけで、他にも色々聴いてはいるんだよ。というか「こういう話はあまりしないようにしよう」といつも思っていてさ。後で絶対に「あれも言ってなかった」「これも言い忘れた」と思って後悔するから(苦笑)。でもつい喋ってしまうね。
「シカの研究」と再始動の経緯
―ちなみに、音楽以外で今あなたが関心を持っていること、インスピレーションの源になっているものがあったら教えてもらえますか?
ケヴィン:僕らは今、こうやって自然豊かな環境で暮らしているので、まずコロナの影響で鳥が増えたんだよね。ブラックバード(クロウタドリ)って、知能的にはチンパンジーに匹敵すると言われているので、試しに餌付けをしてみたり、ちょっと呼びかけてみたりとかしているんだけど、その反応がすごく面白くて。
―そういえば以前は、「ミツバチと仲良くなった」とおっしゃっていましたよね(笑)。
ケヴィン:それと、僕らの家の周りにはシカが1600頭くらい棲んでいるのだけど、実は日本に起源を持つシカが大陸を渡ってヨーロッパまで移動してきたらしくて。現在は世界中に生息しているって知ってた?
―いえ、知らなかったです。
ケヴィン:シカの群れを眺めながら、「これってドナルド・トランプを含む今の世界の縮図のようだな」と思ったんだ。例えば、数十頭のシカがいるとする。その中にはものすごく臆病で、彼らの姿を見るとすぐに逃げてしまう連中もいれば、全く意に介せず僕らの様子を観察している連中も半分くらいいる。で、意に介さないどころかむしろこちらを威嚇してくるような連中も、ごく一部だがいるんだ。僕らはそいつらのことを「パンク・ディアー」と呼んでいるのだけど。
―はははは。
ケヴィン:そのパンク・ディアーを追い払おうとすると、逆に他の連中がパニックを起こして柵にぶつかったりしてしまうから、僕らとしても対策を考えなければならないんだけど。そういうマイノリティであるパンク・ディアーは、ハンターなどには狙われやすいんだよね。でも、そうやって一つの群れの中に様々なタイプがいないと、種として生き残っていないのかも知れない。すべてのシカがパンク・ディアーみたいだったら、群れは全滅してしまう。人間社会に置き換えてみると、例えばビビっていつも逃げてばかりいる連中もいれば、もっとオープンかつ物事をじっくり観察する連中もいるし、好戦的なパンクスもいて世界は成り立っているというか。トランプに煽動されて議事堂に乗り込むような右傾化した連中だって、その構成要素というか……僕、喋り過ぎてないかな、大丈夫?(笑)
―いえ、とても興味深いです。ニホンジカのこととかも調べたのですね。
ケヴィン:こっちにいるシカのほとんどが、日本に起源を持つことを知って「どうしてだろう?」と思ってね。すると日本にはシカがたくさん生息している島があって、ツーリストが大勢やってきて餌を与えているということも知ったよ。シカって、意思伝達のためにいろんな「音」を発するんだ。僕ら2匹の犬と暮らしているのだけど、犬とシカを鉢合わせないように柵をめぐらせ、犬のスペースを3エーカー(12平方キロメートル)くらい設けているんだ。にも関わらず、さっき話したパンク・ディアーが柵を乗り越えて犬のスペースに入ってきて、犬をけしかけたりするんだよ。その時に、犬に向かって”だけ”出す「音」というか、ちょっとメロディックな鳴き声もあるんだよ(といって、口真似をする)。
―その声にインスパイアされたサウンドも生まれるかも知れないですね。というわけで、そろそろ音楽の話をしましょうか(笑)。
ケヴィン:そうしよう(笑)。
―まず、Dominoに移籍した経緯から教えてもらえますか?
ケヴィン:ずっとレーベルは探していたんだ。他にも色々……例えばWarpとも話をしたし「面白いかな」と思ったこともあるのだけど、やっぱりDominoはオーナーと30年近く個人的な付き合いもあってさ。僕らとしてはインディ・バンドというところにすごくこだわりがあるので、そこを重視したいという姿勢を分かってくれるという意味でもDominoは僕らにとってパーフェクトなレーベルなのかなと思ったんだ。
―MBVの楽曲が一時期、サブスクから姿を消したのは、何か意図があったのですか?
ケヴィン:僕らは音楽の原盤権を持っていたけど、それをどう扱うかに関しては全てソニーUKが管理していたんだ。その契約が切れたのが、ちょうどコロナ禍と重なってしまってね。通常だったら9月くらいには戻っていたはずなんだけど、僕らがのんびりしていたので少し間が空いてしまったんだよ。特に何か、サブスクに対して思うところがあったわけじゃない。さっきも話したように、僕自身がSpotifyに登録しているし、変なこだわりを持つのは馬鹿げていることに気づいたというか。むしろ、今は(MBVも)積極的に展開すべきだと思っているよ。
ケヴィン流の作曲プロセス
―MBVの楽曲がまた気軽に聴けるようになるのは嬉しいことだなと思っています。そこで今回は過去の作品についてお聞きしたいのですが、MBVの革新的なサウンドメイキングに関しては、すでに色々なところで散々聞かれているので、今回はそもそものケヴィンの曲作りのプロセスについて、詳しく聞かせてもらえますか?
ケヴィン:そうだな、音楽のことは常に頭の中にあるのだけど、まずは「曲を作りたい」というよりは「ギターを弾きたい」というところから始まることが多い。そのために、家のそこら中にギターを置いているんだ。ただ、大抵の場合は寝る直前になって急にギターを弾きたくなるんだよね。実際に演奏を始めると8時間くらい経っていて、夜を明かすどころか昼過ぎになっていることが多い(笑)。ギターはアコースティックの場合もエレクトリックの場合もあって、その時の気持ちのままにどちらかを手に取り、ただ弾いてみる。「曲を作る」という意識は特にないのだけど、大抵そんなことを30分くらいやっていると、何かがふと浮かんでくるものがあって、それを書きとめていく感じ……。気分が乗ってくると、そのアイデアについて何日も、何週間も練る事になる。それが僕の曲作りということになるかな。チューニングをいじっている時に何かを思い浮かぶことも多いね。いずれにしても曲というのは、ギターを弾いていると向こうから勝手にやってくるから、それを捕まえ整えていく感じなんだ。
―「コードにメロディをつけていく」とか「思いついたメロディにコードをつけていく」とか、いわゆる「通常の」曲作りとは少し違うわけですね?
ケヴィン:大抵は一つか二つのコードから始まるのだけど、そのコードに乗っかっているヴォーカルメロディもほぼ同時に浮かんでくるんだよね。そこから少しずつ発展させていく……なので、メロディだけを独立に考えることはまずないかな。
―「ギターを弾きたい」って思うのは、具体的にはどんな状態なんでしょう。
ケヴィン:これは言葉で説明するのがすごく難しい、とてもストロングなフィーリングなんだよね。「何か作りたい」「何かしなきゃ」と思ってギターを手に取ってしまう。そのときに、ギターを弾く代わりに絵を描いてみようと思うこともあるんだけどね。若い頃はアートが好きで、常にスケッチブックを傍に置いていたんだ。ただ、「よし、じゃあ今日はギターを弾くのではなくて、絵を描くことにしよう」と思っても、どうしてもギターを持ってしまう(苦笑)。
―あなたが絵を描くのは初めて知りました。
ケヴィン:子供の頃は、アートの道に進みたかったんだ。ともかく、「ギターを弾きたい」というよりは「弾かずにはいられない」みたいな感覚なんだよ。「もうそろそろ寝なきゃいけないし、今から弾き始めたら明日が台無しになってしまうのは分かっている。なのに、それを止めることが出来ない」。そういう衝動だ。もちろん、テレビを見ながら何となくギターを抱えて爪弾き始めるなんてこともあるのだけど、そういう時は別にワクワクするようなアイデアは浮かんでこないんだよね。
―そういう曲作りのプロセスは、MBVの初期から基本的には変わってないですか?
ケヴィン:そうかもしれない。1988年の頃は、僕が曲を作る時には常にコルムがそばにいて、一緒に仕上げていく感じだったけど、『loveless』の頃になると僕がほぼ1人で曲を書いていたし、一方でコルムはプログラミングに夢中になっていった。僕もコルムも、曲を作り始めたばかりの頃はまだテクニック的に未熟で、作るスピードも今よりずっと遅かったかな。

Photo by Steve Gullick
―歌詞はいつもどうやって思いつくのでしょうか。
ケヴィン:通常はメロディができた段階で、3分の1か、うまくいけば半分くらい言葉も一緒に出てくるのだけど、その段階で見えている方向性に沿って言葉を整える段階がものすごく大変で。書きたいことは全て頭の中にあるのだけど、夜通し苦しむことが多い。5時間くらいそうやって頑張っていると、1時間くらいゾーンに入る時があって、そうするとあっという間に書き終わるんだけどね。
―2013年リリースの3rdアルバム『m b v』にはオルガンが主体の「if this and yes」という曲もありますが、ケヴィンは鍵盤も弾くのですか?
ケヴィン:うん。最初にキーボードで曲を書き始めたら、そのままキーボード主体の曲になる。鍵盤で書いた曲をギターに置き換えることって今までしたことがないのだけど、いつか挑戦して披露したいと思っているよ。
―同作はそれまでのアルバムに比べて、ケヴィンの「メロディメーカー」としての魅力が、より前面に打ち出されているように感じました。例えば「New You」の洗練されたメロディ、メジャー7thコードの使い方など、バート・バカラックやロジャー・ニコルスなどを彷彿とさせるのですが、この曲はどのようにして生まれたのでしょうか。
ケヴィン:確かにバート・バカラックの影響もあるし、さらに遡るとボサノヴァからの影響が、バカラックを通じて入ってきているとも思う。あと、これは奇妙に感じるかも知れないけど、プリンスの影響もあるんだよね。実は「New You」のメロディの半分は、カート・コバーンが亡くなった後に書いたものだ。僕は彼の訃報を聴いてものすごくショックを受け、しばらくそのことばかり考えていた。カートのような立場にもし自分がなったら……などと考えてしまってね。だから、ある意味でこれは「死」についての曲でもあるし、別れの曲でもある。死者への別れではなく、生者に対する死者からの別れのような。そういう死生観を歌った曲に仕上がったよ。
楽器の限界を超えた表現
―ところで『loveless』や『Isnt Anything』『m b v』には、例えばビートルズの『アンソロジー』シリーズのようにアウトテイクやデモ音源、あるいは『eps 1988-1991 and rare tracks』に収録された曲以外の未発表曲、ボツ曲なんてものも存在するのでしょうか。
ケヴィン:『loveless』に関しては、2曲くらいドラムとギターだけレコーディングしたけどそのままお蔵入りになった曲があった気がする。『m b v』でも、数曲そういう未完成のマテリアルと、あと1曲だけ「いつか発表してもいいかな?」というものがあるけど、まだラフスケッチの段階だね。そのくらいかな。
―なるほど。じゃあ『loveless 30周年デラックス・エディション』みたいなものが、今年リリースされる予定はなさそうですね?(笑)
ケヴィン:まずないだろうね、残念ながら(笑)。
―ちなみに『eps』に入っている未発表曲は、どのタイミングでレコーディングしたんですか?
ケヴィン:まず「angel」と「sugar」は1989年1月で、「good for you」と「how do you do it」は『Isnt Anything』セッション中にレコーディングした。なぜボツにしたかというと、自分のヴォーカルが気に入らなかったから。僕らの音源がボツになる大抵の理由は、自分のヴォーカルが気に入らなかったということなんだよね(苦笑)。でも、音楽的にはなかなか捨てたものじゃないし、きっと僕らのファンが喜んでくれるだろうなと思って今回入れることにした。同じような理由から、1989年1月から5月、『Isnt Anything』の最初のセッションの中から、ひょっとしたらあと2曲くらい日の目を見るものがあるかもしれない(※)。
※『eps 1988-1991 and rare tracks』(2021年版のフィジカル)に収録された2曲のシークレット・トラックのうち、1曲のことを指していると思われる。
―それは楽しみです。当時、リアルタイムでMBVの作品を追いかけていて、特に驚いたのは2作のEP『glider』から『tremolo』のサウンド面における大きな変化でした。『tremolo』があそこまでアンビエントにシフトしたのはなぜだったのでしょうか。
ケヴィン:まず『glider』制作時は、僕らバンドにとってストレンジな時期だったんだ。最も実験的な時代というか。サンプリングも多用したし、音作りに何日もかけて、だけどレコーディング自体はパパッとやってしまう。そんなやり方をしていたんだよね。『tremolo』の時は、長い間『glider』のスタジオワークに時間をかけたあとだったので、ちょっとした開放感みたいなものが出ていたのかも知れない。かつての自分たちのように、パパッと作業を進めていくやり方に戻った勢いが楽曲にも表れている気がするな。『loveless』も実は、レコーディング自体は2、3週間で終わったんだ。ただ、その後のミキシングにものすごい時間をかけたんだけどね。6週間くらいだったかな。ちょっと作り方が異例だった。
―スタジオでの時間のかけ方、レコーディングとミキシングの作業の時間の割り当てにそれぞれ違いがあったわけですね。当時不思議に思ったのは、『loveless』の中で使用されているシンセ音でした。例えば「when you sleep」や「i only said」、「to here knows when」などで使用されているあの独特のサウンドはどうやって作ったのですか?
ケヴィン:実はあれはシンセではなく、ビリンダの声やギターのフィードバック、フルートなどをサンプリングして、それを鍵盤にアサインしてピッチベンドで操作しながら弾いているんだ。だから、音作りそのものは難しくないんだよね。
―それって「swallow」のエスニックなアプローチとも通じるものがあるのでしょうか。
ケヴィン:そうかも知れない。ピッチベンド奏法そのものは、僕はずっとギターでやってきたことなのだけどね。ジャズマスターやジャガーのトレモロアームを使用することで、コードを変調させるのと発想としては一緒。なので発端はギターだけど、君の言うように民族音楽にはずっと興味があった。
―西洋音楽の要である12音階から逸脱したサウンドを、通常の楽器を使ってどう奏でるか?ということを模索する中で思いついたものというか。
ケヴィン:その通り。そういえば、以前YouTubeで色々と音楽を聴いていたら、ピッチやトーンがどんどん変化していくものすごくアヴァンギャルドな音楽を発見してさ。「なんて興味深いんだろう」と思って調べたら、実は日本の伝統音楽だったんだ。いわゆる西洋の音楽、特に鍵盤に置き換える時には全てが全音半音の中にハマらなければいけないということになってしまったけど、ヨーロッパを含めたいわゆる伝統音楽というのは、そこに当てはまらない「中間の音」がたくさんあるし、チューニングのシステムも僕らの常識とは異なるものがある。ピッチもトーンもすごく自由なんだ。それを表現したいのに、楽器には限界があって出来ないことが僕にとってはとても窮屈で。なんとか打破しようとして思いついたのがトレモロアームやピッチベントだった。僕にとってそれは、とても自由な表現方法なんだよね。
メンバーへの想いと新作の展望
―『loveless』がリリースされて今年で30年が経過したわけですが、今あのアルバムを振り返ってどのように感じていますか?
ケヴィン:「作って良かったな」と思っている(笑)。最近また再発に向けて自分でも作業をしていたのだけど、聴くたびに新しい発見があるというか。「え、こんなサウンドだったっけ?」「こんなことやってた?」みたいに驚くんだよね。すごく不思議な気持ちだけど、そんなふうに思える作品を作れたことは嬉しく誇りに思っているよ。
―今、新作の進捗状況はどんな感じなのでしょう。以前、「ブルース・スプリングスティーンのような曲が書けた」とおっしゃっていましたよね?
ケヴィン:あの曲は、自分ではアーケード・ファイアっぽいとも思ってるんだ。僕に言わせれば彼らってブルース・スプリングスティーンっぽいからさ。メロディをリフレインする感じとか、曲作りのスタイルとか共通するものを感じる。その曲を書き終えた時に、初めてその類似性に気付いたということなんだけど、でも2013年くらいの曲なので新作に入ることはまずないと思うよ。
―なるほど。2018年のライブで確か2曲くらい新曲を披露していましたよね。あの曲たちはレコーディングする予定はあります?
ケヴィン:答えは「イエス」だね。ふふふ(笑)。
―いつぐらいに発表する予定?
ケヴィン:願わくば、年内に出したいと思っている。全てがうまくいけば、だけど。
―MBVは、これまで断続的に活動をしながらも常にメンバーは変わりませんでした。それって本当に奇跡的なことだなと思うのですが、ケヴィンにとってバンドのメンバーはどんな存在なのでしょうか。
ケヴィン:まずコルムは、僕がギターを始めたばかりでコードもチューニングも何も知らず、とりあえずアンプに繋いでノイズを撒き散らかしていた頃から一緒だった。彼も「ビートを奏でる」ということが全く分からず、ただドラムをぶっ叩いている状態で(笑)、そんな時から一緒に行動を共にしている仲なんだよね。「音楽をクリエイトする」以前からの付き合いだから、その繋がりはとても強いし、今もそれが続いているのはものすごく幸運なことだと思ってる。今はもうしょっちゅう一緒にいるわけじゃないけれど、離れている時間があるからこそ新鮮味もあるし、常に新しい感覚で付き合えるのはお互いにいい状況なんじゃないかな。
デビーは1985年からの付き合いで、今はもうデビー以外のベーシストは考えられないよ。特にツアーに出ると、デビーには大事な役割があってね。バンドのダイナミクス、力関係みたいなところで彼女の存在はとても大きい。ある意味、僕らを仕切っているのはデビーなんだよ(笑)。ビリンダはまず、僕にダイナソーJr.の存在を教えてくれたのが大きい。彼女は音楽の趣味がとても良くて、歌も上手いしとにかくセンスがいいんだよな。メロディも、僕が思いついたものを彼女はすぐ完璧に理解して。彼女が歌うことでさらにいいメロディになるんだ。
―4人だからこその、特別な結びつきを側から見ていても感じます。
ケヴィン:でも、知っての通りそれが一度壊れてしまった。デビーとコルムがバンドから去って行ったのだけど、その後も友人関係は続いていたし、ロスに移住したコルムも時々僕を訪ねてくれたり、パブなどでセッションしたりしたこともあった。だから音楽人生においても、僕自身の人生においても、ずっと大事にしてきた関係だ。1995年から2007年くらいまでは、事実上の活動停止期間だったけど、その時もコルムは「いつかまた一緒にやりたいよね」って言ってくれてたんだ。「それがMBVじゃなくても、ちょっとしたプロジェクトでもいいし」って。そんなふうに友情関係が続いていたからこそ、2008年にMBVを再始動させるのも、とてもスムーズにいったんだよ。
―日本にはあなたたちのファンがたくさんいて、新作やライブを心待ちにしていますので、最後にメッセージをもらえますか?
ケヴィン:僕らがこうしてバンドを続けられているのは、もちろん聴いてくれていた人がいてこそだよ。今は本当に大変な時期だけど、これを超えた先にはまた明るい未来が待っていると僕は思っている。実を言えば、コロナ以前よりも僕自身は前向きになれているんだ。世界は振り子のように必ずリバウンドするから、これだけ酷い経験をした僕らにはきっとそれに見合った素晴らしいことが訪れるはずだからね。そしてMBVの新作は必ず作り上げる。今やっている自分たちの音楽にものすごくワクワクしているし、それを届けることを保証するよ。サンタクロースのようにね(笑)。
【コラム】マイ・ブラッディ・ヴァレンタインはなぜ日本を愛したのか?
「声高な表現をすることで、日本の人々にショックな出来事を思い起こさせたくはなかった。桜のブローチを数日身につけることで、そっと思いを示したかったんだよ」
2013年、MBVが実に22年ぶりの日本ツアーを行った時、ステージに立つケヴィン・シールズとビリンダ・ブッチャーの胸元には、小さな桜のブローチが付けられていた。これは当時、東日本大震災の復興支援活動「サクラフロントプロジェクト」に携わっていた、ケヴィンの長年の知り合いから譲り受けたものだと彼が話してくれたことを、筆者は今も時々思い出す。震災から2年、原発事故の影響を恐れて来日を控える海外アーティストがあの頃はまだ少なくなかったのだが、そのことについてどう思うか尋ねると、彼はこちらを真っ直ぐに見てこう言った。
「そんなことを心配して過ごすには、人生は短すぎるからね。僕はライブのためなら、シリアにだってイスラエルにだって行くよ。それに僕らは日本が大好きなんだ。日本が僕らによくしてくれてきた国だというのも大きな理由のひとつだね。僕がとにかく大事に思っている国、気にかけてる国はイギリス、アメリカ、そして日本の3つなんだ」

胸元に桜のブローチを付けたビリンダ・ブッチャー。2013年2月、大阪なんばHATCHにて。(Photo by Takanori Kuroda)
ケヴィン・シールズといえば、全てにおいて一切の妥協を許さない完璧主義者であり、「マスコミの前にはほとんど姿を現さない気難しい人物」というイメージが長年付き纏っていた。実際のところMBVの2ndアルバム『loveless』の制作費がレーベルの経営を傾かせただとか、1997年以降は有刺鉄線を張り巡らせた要塞のような自宅で半隠居状態だったとか、真偽が入り混じった噂話に事欠かないアーティストではある。しかし、2013年に筆者がケヴィンの密着取材をしたときに感じたのは、そうしたパブリック・イメージとは全く違う印象である。優しく繊細で、ユーモアと愛に溢れる人。そして何より、日本という国を特別に思ってくれていることは、彼の言動の端々から感じ取ることができた。
筆者が初めてケヴィンと「遭遇」したのは今から30年前、MBVが初来日を果たした1991年11月だった。東名阪でライブが行われ(好評につき東京では急遽マチネ公演も追加された)、当時大学生だった筆者は終演後、ひょんなことから楽屋に潜り込むことが出来たのだ。ライブクルーと顔見知りになった知人に連れられ、緊張で「借りてきたネコ」状態だった筆者に対し、ケヴィンもビリンダも気さくに接してくれて本当に感激したのだが、思えばその時から現在までケヴィンの「神対応」は全く変わっていない。

MBV初来日公演の終演後、ケヴィン・シールズと日本のファンが記念撮影。『loveless』Tシャツを着ているのが筆者の黒田隆憲。1991年11月、クラブチッタ川崎の楽屋にて。
2013年と2018年に来日した時も、例えばライブ終了後、会場の外に出待ちのファンがいれば、どれだけ疲れていてもバンを必ず停めて、サインや握手、記念写真など一人ひとりに対し丁寧に接していた。またツアー中のある公演では、終演後にステージから客席へと身を乗り出し、最前のファンと握手を交わしたり、ピックを配ったりしていた時もあった。筆者はこれまで様々な国でMBVのライブを観てきたが、ケヴィンがそんなことをしている姿を見るのは初めてだった。そのことを彼に伝えると、「うん、初めてだよ、そんなことしたの。自分でもどうしてだかわからないんだけど(笑)。日本でプレイするのは好きなんだ」と肩をすくめ、照れ笑いを浮かべていた姿もよく覚えている。
そういえば2018年に本誌ウェブで行なったケヴィンとの独占インタビューで、「最初に『コネクト出来た(通じ合えた)』と思えたのが、日本のオーディエンスだった。僕らと同じレベルで音楽を楽しんでくれているというか、(略)『僕らの音楽を、こんなふうに楽しんでくれたら嬉しいな』っていう目論見に、最も忠実に反応してくれたのが日本のオーディエンスだったわけ。こんなに音を馬鹿デカくしても、誰も怒らないし」と話してくれたこともあった。日本人の音楽に対するオープンな姿勢は、ケヴィンたちを深く感激させたようだ。
その一方で、同年の来日公演の際「ケヴィンたちが望むような大音量では、今回ライブが出来ないかもしれない」という情報が入ったときには、これまで見たこともないほど激怒していたという。ケヴィンの友人であり、後期コクトー・ツインズのギタリストだったタテミツヲから聞いた話だが、「ファック!」を連呼し「もう演奏はやらない」とまで言い出していたというから笑えない。結局、その問題はライブ前に解決したのだが、危うく日本に対する彼の印象が崩れるところだった。前述したように、基本的には穏やかで繊細な人物だが、それゆえに「こう」と決めたことは一切妥協しない厳しさも持ち合わせているのだ。筆者が初めて対面インタビューをしたとき、納得のいくインタビュー・スペースを確保するまで何度もダメ出しされたこともあったが(いまだにトラウマ)、それも彼の「厳しさ」の表れだったのだろう。
ともあれ、来日すれば必ず東京・秋葉原の楽器店通りをタテと共に訪れ、タテ曰く「まるでレコードのジャケ買いか、スーパーで缶詰をカゴに入れるように」ペダル・エフェクターを買い漁ることを楽しみにしているケヴィン。前掲のインタビューでも話してくれたように、日本の古典音楽(おそらく雅楽だろう)が持つサウンドに深く感銘を受けたり、自宅の周りに生息するシカについて調べながら日本に思いを馳せたりと、日本と日本人に対して深いシンパシーを感じているのは確かだろう。それは音楽に対する向き合い方だけでなく、そもそもの「気質」が似ているような気もする。MBVの活動休止中、プライマル・スクリームのサポートで何度か来日したときも、ボビー・ギレスピーたちのヤンチャな遊び方に付いていけず、チームから離れて日本の友人と食事をすることが多かったそうだ(彼はベジタリアンなので、レストランやメニュー選びにも苦労するのだが)。
数年前にニューヨークでMBVのライブを観たとき、同行した米国在住の日本人にケヴィンの印象を尋ねると、こんな答えが返ってきたこともある。
「とても神経質な話し方をするし、内にこもる人なんだろうなと思いました。質問すると『イエス』『ノー』のひと言で返してくるので、そこにこめられた重みがビリビリくるというか。この『間』に耐えられるのは限られた人、もしくは日本人くらいなんじゃないですか。アメリカ人だと、ケヴィンが黙って思考を巡らせている間、絶対に質問攻めにすると思いますよ」
子供の頃から日本の怪獣が大好きで、ヘドラやメカゴジラの絵ばかり描いていたというケヴィンは、ひょっとしたらその頃から日本と「コネクト」していたのかも知れない。
【関連記事】マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン『loveless』 ケヴィン・シールズが語る30年目の真実

マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン
新装盤CD/LP
『Isnt Anything』『loveless』
『m b v』『eps 1988-1991 and rare tracks』
発売中
国内盤:高音質UHQCD仕様/解説書付
商品詳細:https://www.beatink.com/artists/detail.php?artist_id=2581
CD購入・ストリーミング:https://fanlink.to/mbv2021

『シューゲイザー・ディスク・ガイド revised edition』
発売中
監修:黒田隆憲、佐藤一道
詳細:https://www.shinko-music.co.jp/item/pid0648528/