赤レンガの東京駅丸の内駅舎は、高層ビルに建て替えるか、保存するかの論争が昭和の時代から続いてきました。保存が実現した背景には、JR、東京都、開発業者など全てが得をする“魔術”ともいえる手法がありました。
※本記事は『知られざる国鉄遺産「エキナカ」もう一つの鉄道150年』(髙木豊著、日刊工業新聞社)の内容を再編集したものです。
1914(大正3)年竣工当時のレンガ駅舎の面影を今に残す、東京駅の丸の内駅舎。2003(平成15)年に重要文化財へ指定され、保存・復元工事を経て現在に至っていますが、かつては、これを高層ビル化する計画もありました。レンガ駅舎を保存するか、建て替えるかという論争は、近年まで尾を引いた、古くて新しい問題といえます。
竣工当時の姿に復元された東京駅丸の内駅舎。
東京駅は戦災で損傷し、1947(昭和22)年に復興工事をしたままとなっていたところ、1957(昭和32)年、「新幹線の父」と呼ばれる第4代国鉄総裁・十河信二(そごうしんじ)が地上24階建ての丸の内本屋建設の検討指示を出し、本格検討を開始しました。
“十河構想”とも呼ばれるその検討内容は、『日本鉄道技術協会誌(JREA)』(日本鉄道技術協会)の1960(昭和35)年1月号に「東京駅最終形態論」として掲載されました。執筆した国鉄技師長室調査役・馬場知巳は論文の中で、「表題はJREA誌がつけたもので、私自身これを最終案とは思っていない」とコメントしていますが、“馬場構想”と呼ぶ人もいます。
1980(昭和55)年には第8代国鉄総裁・高木文雄が東京駅将来構想として、丸の内駅舎は取り壊し、線路上空に人工地盤を張り、丸の内側35階建て、八重洲北地区に30階建て、八重洲南地区に30階建ての超高層ビル3棟を建設しようという“高木構想”を発表しています。いずれも超高層ビルへの建て替えが目的で、1958年の十河総裁時代はまだ国鉄黒字で強気の建て替え構想でしたが、高木構想は増え続ける長期債務の返済資金に充てようという苦肉の策として浮上したものです。
他方、「レンガ駅舎保存論」も1977(昭和52)年3月、東京都知事・美濃部亮吉と高木の間で合意した「東京駅と丸の内再開発構想」をきっかけに動き出します。同年10月、日本建築学会は「丸の内駅舎保存要望書」を高木に提出しています。
しかし1982(昭和57)年に「国鉄分割民営化」が答申されると、国鉄経営体そのものの解体論議が盛んになり、東京駅舎保存・復原論議どころではなくなったのです。
JR発足後から加速するレンガ駅舎保存問題足踏み状態になった東京駅レンガ駅舎保存問題が再び動き出したのは、JR発足後すぐの1987(昭和62)年4月です。運輸省、建設省、郵政省、東京都、国鉄清算事業団、JR東日本、JR東海などで構成する「東京駅周辺地区再開発連絡会議」(幹事=国土庁)が発足しました。同7月には連絡会議の下に「東京駅周辺再開発調査委員会」が設置され、東京駅舎保存問題の議論も再開されました。東京大学名誉教授・八十島義之助を委員長としたことから「八十島委員会」と通称されます。
八十島委員会は、駅舎保存に配慮しながら「日本の中枢を担う地区だが高度利用が十分なされていない」とし、周辺地区の高度利用を促す整備構想をまとめようというものです。
これと並行してJR東日本でも同年10月、専門チーム「東京駅懇談会」を設置し、東京駅の将来像の模索を始めました。メンバーは部課長の実務クラスで、レンガ駅舎保存もテーマですが、まだ民間会社として経営基盤の確立を模索している段階で、多額の費用のかかる駅舎保存については結論を先送りしていました。一方、世論は新生JRの滑り出し好調をにらみ、駅舎保存で盛り上がりをみせました。
1988(昭和63)年3月、八十島委員会は駅舎の形態保存方針とともに、保存の具体策として「駅舎上空の容積率(空中権)を“移転”する方法により実施する」という、復原費用のファイナンスまで踏み込んだ調査報告書をまとめています。つまり、未利用となっている東京駅上空の権利を売却して、財源を確保しようというものでした。

東京駅、1915年頃(画像:国立国会図書館「写真の中の明治・大正」)。
この「空中権移転」という“秘策”を講じ、東京駅のレンガ駅舎保存・復原に貢献した人物として、2代目JR東日本社長だった松田昌士が挙げられます。松田は、「500億円で東京駅の余っている容積率を買ってくれないか」と三菱地所に持ち掛け、三菱地所は「ウインウインの関係」と応じました。このことはNHKのドキュメンタリーで松田本人が語っています。
松田案によって、レンガ駅舎保存・復原は一気に進展することになったのです。
ここで松田が語っている「余っている容積率」が、東京駅の空中権のこと。
容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合で、容積率が2倍に緩和されれば、同じ敷地でも延べ床面積当たりの地価は2倍に換算できます。地価というと通常、敷地面積当たりの価格を指しますが、不動産業界では地価の高い都心再開発については延べ床面積当たりの地価を基準にします。つまり容積率が2倍になれば、地価は実質2倍になるという“魔術”とも言えるのです。開発側は容積率が緩和されたぶん、より高層なビル、より多いオフィスなどが確保でき、賃料収入を多く得られます。
現実の問題として容積率の緩和策が表面化したのは、1999(平成11)年9月、「東京駅周辺における都市基盤・誘導方針検討調査委員会」(座長=慶應義塾大学教授・依田和夫)の緊急提言を受けた形で9月28日に行われた、都知事・石原慎太郎と松田との会談です。
保存・復原の財源策も具体的に動き出します。八十島委員会の容積率移転提案を受け、東京駅のためにわざわざ法制化したのが「特例容積率適用区域制度」です。同制度は2001(平成13)年5月、歴史的建造物の未利用の容積率を活用し、建造物の保存と土地の高度利用を図ろうというもの。「大手町・丸の内・有楽町地区(大丸有地区)」の指定区域内であれば、離れていても容積率移転が可能という融通無碍の新制度です。空中権を売ったJR東日本、買った三菱地所、さらには認可した都も得をします。政官民一体の「打ち出の小づち」政策の象徴的制度として誕生したのです。

丸の内の街並み。三菱地所の牙城ともいえるエリアだ(画像:写真AC)。
翌2002(平成14)年1月、駅舎保存・復原、駅前広場整備、特例容積率適用区域制度の活用などを骨子とする報告書が、都の委員会から提出されました。これを受けて、翌月には松田の後任となった3代目JR東日本社長・大塚陸毅と石原が会談し、合意、調印します。ここに至って、駅空間創造の潜在力が法的な裏付けをもって市民権を得ることになるのです。
“魔術”は東京駅以外でも使われている石原・大塚会談の駅舎保存合意を前もって織り込んでいるような仕掛けも、まだあります。並行してレンガ駅舎の保存・復原を前提にした国の重要文化財指定の動きです。大正時代を代表する歴史的建造物で、レンガを主体とした建造物の最大規模の建築として「意匠的に優秀なもの、歴史的価値の高い」貴重な建築とした文化審議会の答申を受け、2003(平成15)年5月に重要文化財指定がなされました。
これは、首都東京のランドマーク的存在となる意味合いを込めての指定でもあり、文化財としての価値を損なわずに保存・復原工事が実施されることを前提としています。新時代の文化財のあり方を問う、歴史的転換を示すとも言えそうです。
さらに東京都は、特例容積率適用区域制度内の重要文化財について、容積率を500%アップするというプレミアムまで用意して、東京駅を厚遇しました。
東京駅レンガ駅舎の保存・復原には、さまざまな思惑が入りまじり、実現にまでこぎ着けました。そしてこの仕掛けは、「日本橋周辺の再開発」と「明治神宮外苑再開発」といった現在に至る一連の流れの源にもなっています。
















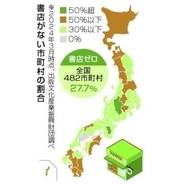




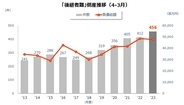
![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)
![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)









