この記事をまとめると
■インドのデリー市内を走る路線バスに乗るのは仕組みが複雑で難しい■デリー市内では2026年までにすべての路線バスをBEVバスに入れ替える計画を進めている
■日本でも運行コストを抑える意味でBEV路線バスの導入を本格的に検討する必要がある
インドで路線バスに乗るのはハードルが高い
インドの首都となるデリー首都直轄領の面積はおよそ1500平方キロメートル、人口は約1680万人となっている。ちなみに東京都は2194平方キロメートルで人口は約1420万人だ。
インドは連邦共和国制をとっており、直轄領は準国家的行政組織となり、連邦政府が直接統治している。
このデリー首都直轄領内に「オールドデリー地区」と「ニューデリー地区」が存在している。市内にはメトロと呼ばれる地下鉄(一部高架地域あり)網が張り巡らされ、さらに路線バスも走っている。メトロは日本の鉄道のようにICカードやツーリストカードも用意され、改札でタッチして構内に入り、目的地に着いたらタッチして駅を出るという乗り方なので、それほど抵抗感なく利用することができる。
ただし、地下鉄を待っていてドアが開くと、東京のような大都市での朝の通勤ラッシュの如く地元インドの人たちで車内がギュウギュウになる。筆者はそのなかに入っていく勇気がなかなかもてずに、空いている車両が来るのを待つこともある。車両の雰囲気は比較的新しく、それほど混んでいなければ快適に移動することができる。
一方の路線バスはかなりハードルが高い。以前、バスに乗ろうとして地元の人に聞いたら、そのときはスマホでQRコードを読み込んで運賃を支払うといった説明を受けた(そこでは現金は使えないと聞いた)。
ただ、街を走る路線バスを見ていると、中扉から乗車すると扉近くの席に料金収受のオジサンが座っており、ここで現金決済も可能だ。ただし問題は、どのバス停まで乗るのかを告げなくてはならない点。そこに敷居の高さを感じてしまうことが課題だ。
バスでも使えるICカードはあるのだが、作るときにはインド版の「マイナンバー」を入力しなければならないので、観光客などは基本的にカードを作ることはできないとの説明を受けた。
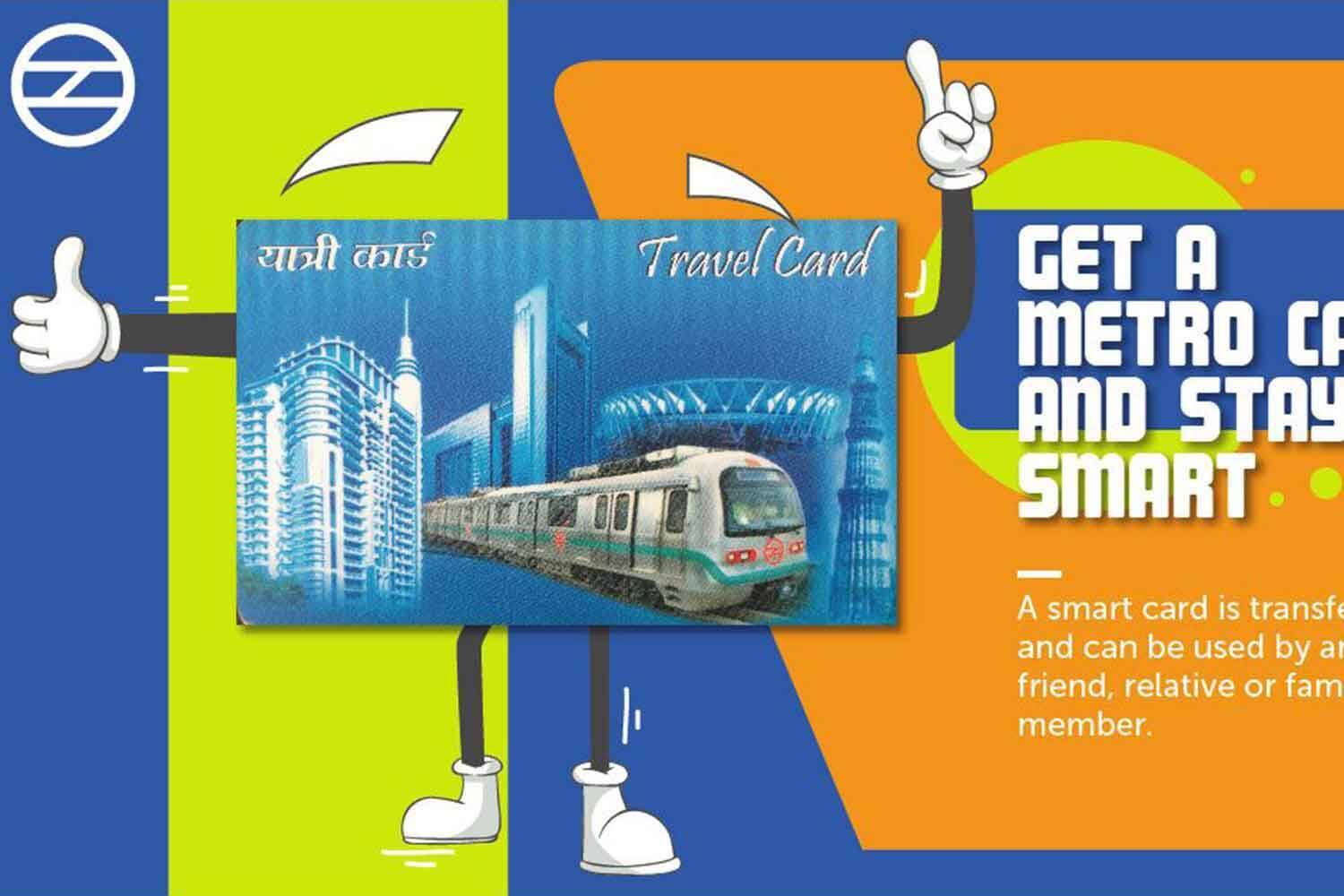
海外では路線バスがどんどんEV化
そのデリー地区の路線バスだが、公営バスでは緑色、赤色、そして青色が、DTC(デリー・トランジット・コーポレーション)とされる公営バスとなっている。緑色がエアコンなし、赤色がエアコン付き、そして青色がBEV(バッテリー電気自動車)バスとなる。このほかにも公営バスよりやや小さいオレンジ色(ほかの色もあり)などの路線バスも走っている。細かいスペックを確認することはできなかったが、これらは民営バスとなるようだ。

なお、緑色や赤色のバスだとかなりボロボロの状態の車両が多い。扉が満足に閉まらない車両も多く、オレンジ色のバスは扉を開けっぱなしで運行していることも多い。緑と赤色のバスはICE(内燃機関)車となるのだが、日本のように燃料は軽油ではなく、CNG(圧縮天然ガス)となっている。
世界的にもBEV路線バスへの変換が進んでいるのだが、インドで残っているICE路線バスはCNG仕様が一般的。軽油を燃料とするバスを使っているのは日本くらいだが、これは環境性能の高さを示しているとする話も多い。
話をデリーに戻すと、現地報道では「2026年までに、いまある2624台のCNGバスを全廃して、全面BEV路線バス化する」とのことである。ちなみにこの報道時でのDTCが保有するBEV路線バスは、1602台となっているとのこと。
2023年に訪れたときもBEV路線バスは走っていたのだが、このときはパラパラと見かける程度だった。しかし今回は、見かける路線バスの多くが青色のBEV路線バスであった。それらの多くは地元インドのタタモータースの「マルコポーロ」というBEV路線バスがいち早く導入されているので、必然的に台数がかなり多いのだが、JBMというインドのバスメーカーの「Eco-Life」という車両もそこそこ走っていた。

世界の大都市では路線バスの運行事業者が公営や公営系であることが多いので、BEV路線バスの導入もスピーディに進んでいるように見える。仮に民営だったとしても、BEV化の際に公営系として各社をひとつの事業者にまとめるなどして迅速な普及を進めているケースが多い。
日本ではディーゼルエンジンでも環境性能に優れ、急いでBEV路線バスを導入する必要はないという意見もあるが、1リッターあたりの軽油価格が東京地域平均で158.5円となっているのが実情だ。充電施設などの初期投資が必要とはなるものの、日本の場合は今後も価格上昇ありきで軽油価格の高値安定が続けば、運行コストを抑える意味で、BEV路線バスの導入を急ぐ必要があるかもしれない。
最近では多くの事業者でBEV路線バスが導入されているが、多くは数台規模が一般的で、いわば「お試し」段階となっているといえる。日本のバスメーカーがラインアップするBEVバスもかなり限定的であり、外資ブランド車ありきでお試しが進められている。

日本全国で公共交通を担うのだから「経済安全保障」の観点から、外資ブランド製バスの導入に慎重にならざるをえない部分も否定できない。
それでも、日本でも運行環境をみると、BEV路線バスを増やす必要性が高まっているのは間違いないようにも見える。外資頼みになってしまうのか、日本メーカーの動きが気になるところである。


















![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
