
残念ながら、現代の医療はすべての病を完全に治すことはできない。しかし人間は、たとえ完治する見込みがなくても「治療をやめる」という決断をすることはとても難しい生き物だと、数多くの患者の治療にあたってきた医師・里見清一氏はいう。
著書『患者と目を合わせない医者たち』から抜粋・再構成し、患者の心理状態を解説する。
「どうせ治りゃしないし、大して効きもしないのに」
戦争は始めるより止める方がはるかに難しい。ここ数年「始まった」戦争は数多いが、「終わった」のはアルメニアとアゼルバイジャンの紛争くらいか。これは援けてくれるはずのロシアが自国のことにかまけて放置し、アルメニアが一方的にやられて終わった。他の紛争は、当事者の両方に「後押し」がついていて、なかなかワンサイドゲームにはならない。旗色の悪い方も、降伏すると今までの犠牲が水泡に帰すと思ってできるだけ粘ろうとし、実際に支援によって粘れる。だから「損切り」ができない。
損切りができないのは「押している」方も同じである。それは見込み違いからだけではない。2024年6月、イスラエル軍の報道官がイスラム組織ハマスについて「ハマスは思想であり、完全に排除はできない」と述べ、壊滅は不可能という認識を示した。これに対し、イスラエル首相府が「軍は政府の方針に従え」と声明を出し、政権と軍との間で緊張が生じたと伝えられる。軍部は「勝てない」と分かっていて、ここらが潮時だと公言しているのに、「政治的な判断」が優先されてしまう。
現場感覚は実際に戦ったプロにしか身につかないらしく、軍人の方が冷静に勝算を判断できる、というのは珍しくない。
私が国立がんセンター病院(当時)に研修に行ったのは1987年12月だが、当時カナダから、「肺癌の患者には、抗癌剤治療をした方が良いか、それとも最善の緩和医療(ベスト・サポーティブ・ケア・BSC)をした方が良いか」という比較研究の論文が出たばかりで、みんなそのデータの話で持ちきりだった。BSCとはつまり、「癌をやっつけよう、抑えよう」という治療を一切せずに、対症療法に徹するのである。
結果は、ごくわずかながら化学療法により生存期間が延びる、というものだったが、そもそもそういう「研究」がされていること自体に驚いた。それまでいた大学病院では、当たり前のように化学療法が行われていた。「何もしないわけにはいかない」というのが暗黙の大前提であり、誰も「何もしないで諦める」なんて思いもよらなかった。がんセンターで「そういう治療(戦い)ばかりやっているプロたち」だけが、「そもそもやった方が良いのか」なんて考えていた。
上司の一人は、「どうして世の中の医者は、こんな治療やりたがるかなあ。
そして実際問題として、患者やその家族に対して「もうダメだから諦めよう」と説得するのは、交戦中の兵士を撤退させ、敵を倒せと熱狂する市民を落ち着かせるくらいに難しい。かつ、「何もしない」となったら、病院は一文も儲からない。戦争をやっていれば戦時経済がなんとか回るのと同様である。新薬が出れば、使わなければいけない気になる。あんなデータではどのみち無理だと「知って」いるのはプロだけである。これまた、「ゲームチェンジャー」と期待された新兵器が期待外れに終わるのと変わらない。
「こんなことならあの段階で……」
我々は、戦争の泥沼から抜け出せない当事者を嗤えない。医師で作家の久坂部羊先生は、年末に「安楽死させてくれ」と頼む神経難病の患者さんに対して、手を尽くして症状のコントロールをし、穏やかな正月を迎えさせてあげられたという経験を書かれている。
以前がんセンターで私が治療し、うまく治った肺癌患者が、別の癌になり、がんセンターで匙を投げられて私の異動先へやってきた。当時、もう少しで期待の新薬「オプジーボ」が世に出るという時期で、私はそれまでの「つなぎ」として大して期待もせずにある抗癌剤を使ったが、これが案外効き、患者は元気になった。数ヶ月してその薬の効果も切れたが、オプジーボが使えるようになったのでそちらを開始した。結果、全然効かず、患者の状態は一気に悪くなった。期待した分だけ患者も落胆し、一旦は感謝していた家族も不平がちになった。
先輩の外科医から、術後の呼吸不全の治療を頼まれた。人工呼吸器に繋いで一旦は乗り切ったが、病気は再発しどう考えてももう無理、の状況になった。だがいくらそう説明しても、家族は頑として「もう一回人工呼吸器に繋げて治療してくれ」と言い張った。先輩に相談したら、「一回助けちゃったんだろ? じゃあやらなきゃダメだ。
私が思い出すのはこんな話ばかりである。だから戦争でも博打でも、「良い時(勝っている時)に止める」のは、人間性に反するくらいの知識と決断力が不可欠で、それができる人間は稀有である。旧日本軍はミッドウェイ海戦以後負け続けたが、「なんとか敵に一太刀浴びせ、有利な条件で講和を」とずっと考えていたという。だがもし実際にどこかの戦闘で「勝って」しまっていたら、やはりそこで止められずに、「もうちょっと」とズルズル続けていたのではないだろうか。
文/里見清一
『患者と目を合わせない医者たち』(新潮新書)
里見清一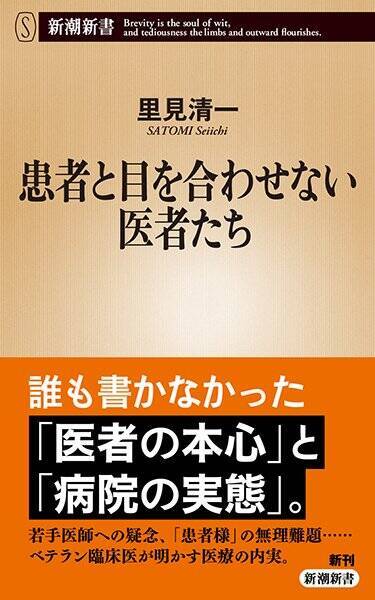




























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


