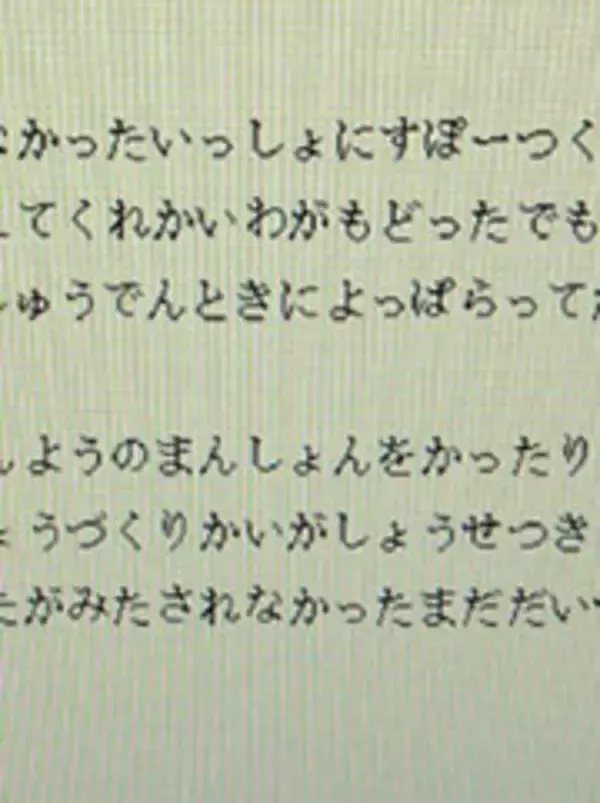
さて、今や大衆の文字通信手段といえばメール。携帯メール全盛だが、カチカチとキーを打つ様子は、なんとなくモールス通信に似ている。ひらがなを打って変換するのが基本だけれど、ひらがなにだって、よく使われる文字とそうでない文字があるはず。調べてみようではないか。ある土曜日の新聞から10の記事を選び、全てひらがなでワープロ入力。一文字ずつに切り分けて、表計算ソフトで数える。調査総数10,811字。何だかキーボードの調子が悪くなった気がする。それでは結果発表!
第1位…「い」833字(8%) 第2位…「ん」660字(6%)
第3位…「か」650字(6%) 第4位…「し」641字(6%)
この4文字だけで全体の26%。日本語の4分の1は、「い、ん、か、し」の4文字だけで表せるのである。単語を考えてみよう。
続いて、少ない方を発表。
第44位…「ー」(長音)61字(0.6%) 第45位…「む」50字(0.5%)
第46位…「へ」49字(0.5%) 第47位…「ぬ」12字(0.1%)
圧倒的に少ない「ぬ」! 「おぬしにはできぬ!」この時代劇でおなじみのセリフには「ぬ」が2つも入っているが、現代ではほとんど使われない表現。時を経て、使われなくなってきている文字なのだろう。「ぬ、へ、む、ー」の4文字だけで表せる言葉をしばし考えてみたのだが、「むへぬー」なんて、『北斗の拳』の劇中で倒れる戦士が、最期に言い残しそうな言葉しか思いつかず。
最後に、使用頻度順に並べた47文字で歌を作ってみた。冒険小説風「新いろは歌」をどうぞ。
「インカ周、辿っての苦期は世に粉(こ)なる、気(け)を白湯せすり、あれら魔持ち追ふ絵や碑、祖母輪目『ねみろー』夢(む)経ぬ」(意味:インカの周りを辿った苦しい時期は、世の中に粉となり忘れられつつあると、白湯をすすりながら感じた。あれら魔持ちを追った様子を描く絵や碑は、祖母の輪のような目にも眠いとしか映らず、夢にもでてこない)お粗末さまでした。
(R&S)
※濁点、半濁点は無視、「ゃ」など小さな文字は大きな文字として、長音は別文字として集計
























