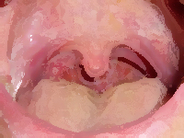24歳の頃、勤めていたリハビリテーションセンターで、手術の医療写真を撮影していた頃、患者らがリハビリの一環として取り入れていたスポーツの競技写真を撮ることになった。義足が光ったり、体と一体化してしなる姿を見て、その格好の良さに惚れ込んだのがきっかけになった。「その選手に残された機能を、いかにうまく使っているか。写真ではそれを表現したい」
清水さんは「当時、障害を持つ人を励ましたいとおこがましくも思っていたが、逆に障害を持つ人たちから『このままだったら写真のプロにはなれない。
アスリートの世界水準が高くなってきたので、選手たちは日本だけでなく、世界大会で試合する経験を積まなければメダルを狙うのは難しい。だが、選手たちには、常に資金難の問題がつきまとう。「例えば、韓国の選手たちは、健常者スポーツと同じような待遇でスポーツに取り組める環境が整えられているが、日本は違う。
まずは、健常者と障害者が一緒にスポーツできる環境を整えることが必要だ。一番の問題は、障害者のスポーツ団体は厚生労働省、健常者のスポーツ団体は文部科学省と管轄が分かれていることだという。清水さんは「いっそのこと、統一されたスポーツ省ができれば」と問題を投げかける。
「健常者の選手と比べると、障害を持つ選手たちは『恐怖』を克服している。例えば、視覚障害者水泳やスキー、サッカー、柔道などは、見えないことで頭を壁や地面にぶつけることがある。一度、目をつむってスポーツしてみれば、その怖さが分かると思う。
1994年のリレハンベルパラリンピックでは、日本人カメラマンは2人だけだったが、今大会では記者・カメラマンの数が約120人まで増えた。「たくさん報道されることで、企業の障害者スポーツの見解が変わり、サポートや協賛に繋がる。ようやく、ここまできた。それでも、まだ課題は多い」
(山下敦子)